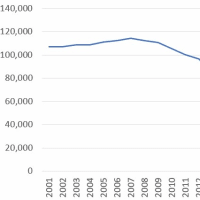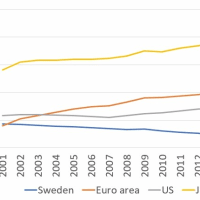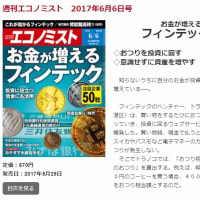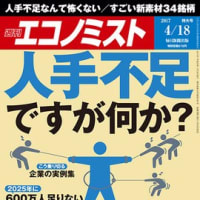スポーツというと、最近はドーピングのスキャンダルがたびたび浮上する。どこの大会でも不正をなるべく高い確率で見抜くために、努力が注がれている。
ところで、先日の朝、ラジオのニュースを聞いていたら、興味深い研究結果を紹介していた。「ドーピングにする選手は、どのようなトレーニング環境に多いのか?」という問題提起で、ドーピング行動とトレーニング環境との関連を調査したものだった。

この調査が特に焦点を置いたのは、トレーナーや監督の指導の仕方。人によって、自分の選手が成功したときや失敗したときの対応の仕方が違うが、この調査によって明らかになったのは、失敗をした選手に対して、こっぴどく批判をしたり、罰を与えたりするようなトレーナーや監督のもとでは、選手がドーピングに走る傾向が高い、ということであった。また、結果の順位ばかりを選手の評価の基準にする監督のもとでも、ドーピングをする選手は出やすい、ということだ。監督からの執拗な批判から身を守るためには、とにかく順位を上げて成功するしかない。そして、成功のためならば手段を選ばず、という雰囲気が選手の間に蔓延していくためだと考えられている。
このような環境の下では、選手たちは自らの能力を高めることの本来の目的を見失って、むしろ監督を満足させるために結果を出さなければならない、と本末転倒な考えに陥っている可能性が高い。
一方、選手がたとえ失敗しても、その努力を評価したり、良かったところを僅かでも見つけて励ましたり、その選手のミスを丁寧に指摘して、その改善にしっかりと手を貸そうとする監督やトレーナーの下では、ドーピングを行う選手は出にくい、ということだ。
――――――
確かに、納得の行く説明だと思った。それに、これはスポーツの世界だけではなく、企業の中の上司-部下の関係や、教育の現場における先生-生徒の関係にも当てはまるのではないか、と思った。
いくら努力しても結果を出さなければ意味がない、というのは様々な文脈で当てはまることかもしれない。しかし、だからといって、結果だけを評価の基準にしたり、努力したのに失敗してしまった人を罰するような環境では、まずその人間のやる気が育たない。それに、どうすれば次回はいい結果が出せるか、という冷静な思考が失われ、いい評価を受けるためであれば、どんな手段を使おうが構わない、とか、周りの者を蹴落としてまでも自分の身を守りたい、と考える者も出てくるかもしれない。それに、自分が常日頃、上司・先生の評価に神経を尖らしてピリピリと怯えている分、他の誰かが失敗するとそれをトコトン批判する、シニカルな雰囲気がその環境に蔓延することも考えられる。
なので、最初に紹介したのと同じような研究を、職場や学校環境に当てはめて、上司や先生の評価の仕方と、人間のやる気、不正行為の多寡、職場・学校イジメなどの関係を調べてみたら面白いと思う。
ところで、先日の朝、ラジオのニュースを聞いていたら、興味深い研究結果を紹介していた。「ドーピングにする選手は、どのようなトレーニング環境に多いのか?」という問題提起で、ドーピング行動とトレーニング環境との関連を調査したものだった。

この調査が特に焦点を置いたのは、トレーナーや監督の指導の仕方。人によって、自分の選手が成功したときや失敗したときの対応の仕方が違うが、この調査によって明らかになったのは、失敗をした選手に対して、こっぴどく批判をしたり、罰を与えたりするようなトレーナーや監督のもとでは、選手がドーピングに走る傾向が高い、ということであった。また、結果の順位ばかりを選手の評価の基準にする監督のもとでも、ドーピングをする選手は出やすい、ということだ。監督からの執拗な批判から身を守るためには、とにかく順位を上げて成功するしかない。そして、成功のためならば手段を選ばず、という雰囲気が選手の間に蔓延していくためだと考えられている。
このような環境の下では、選手たちは自らの能力を高めることの本来の目的を見失って、むしろ監督を満足させるために結果を出さなければならない、と本末転倒な考えに陥っている可能性が高い。
一方、選手がたとえ失敗しても、その努力を評価したり、良かったところを僅かでも見つけて励ましたり、その選手のミスを丁寧に指摘して、その改善にしっかりと手を貸そうとする監督やトレーナーの下では、ドーピングを行う選手は出にくい、ということだ。
――――――
確かに、納得の行く説明だと思った。それに、これはスポーツの世界だけではなく、企業の中の上司-部下の関係や、教育の現場における先生-生徒の関係にも当てはまるのではないか、と思った。
いくら努力しても結果を出さなければ意味がない、というのは様々な文脈で当てはまることかもしれない。しかし、だからといって、結果だけを評価の基準にしたり、努力したのに失敗してしまった人を罰するような環境では、まずその人間のやる気が育たない。それに、どうすれば次回はいい結果が出せるか、という冷静な思考が失われ、いい評価を受けるためであれば、どんな手段を使おうが構わない、とか、周りの者を蹴落としてまでも自分の身を守りたい、と考える者も出てくるかもしれない。それに、自分が常日頃、上司・先生の評価に神経を尖らしてピリピリと怯えている分、他の誰かが失敗するとそれをトコトン批判する、シニカルな雰囲気がその環境に蔓延することも考えられる。
なので、最初に紹介したのと同じような研究を、職場や学校環境に当てはめて、上司や先生の評価の仕方と、人間のやる気、不正行為の多寡、職場・学校イジメなどの関係を調べてみたら面白いと思う。