火曜日にスウェーデン議会が正式に開会された。儀式性の高いもので、国王が登場し議会を開会する。そして、その後に首相が所信表明演説を行った後、新内閣を発表する。
しかし、国会の開会に先駆けては、議会と王宮の近くにあるストール教会でミサが行われ、ストックホルム主教区の主教が説教(説法)を説くことが慣例となっている。ただ、政教分離の原則があるため、宗教色の濃いものではなく、議会の開会を前にした緊張の面持ちの議員たちに国民の期待に応えてしっかりと頑張るようにエールを送るための儀式となっている。主教の説く説教(説法)も聖書の内容に基づくものではあるが、今の社会にとって特に重要なキーワードを選んで、一般的な道徳を説くものである。
さて、国王などの来賓に続いて、議員たちが到着した。みな正装だが、中には民族衣装を身にまとっている議員もいる。やはり注目されたのは、ポピュリスト・極右政党であるスウェーデン民主党の議員だが、愛国主義や伝統をことさらに強調する党とあって、党首は自分の出身地であるブレーキンゲ地方の民族衣装を身につけて登場した。スウェーデンの伝統を守れるのは自分たちの党だけ、とでも言わんばかりだ。一方、社会民主党の女性部会の代表を務めている女性議員Nalin Pekgulはトルコのクルド地方の出身だが、彼女はクルドの民族衣装を着こなして、スウェーデンの旗を手にしながら登場した。多文化のスウェーデンを象徴するためでもあるし、スウェーデン民主党に対抗するためでもある。


このミサで、大きなハプニングがあった。主教である女性牧師による説教(説法)の途中の出来事だった。
彼女の話はこう始まった。
----------
国民から信頼を託され、議員という役目を担うことになった皆さん、おめでとう。85%の有権者、つまり600万人強のスウェーデンの人々は、私たちみんなのために良い社会を築き、素晴らしい将来を作り上げる資質を持ち備えているのはあなただと考えたからこそ、議員に選んだのです。その信頼を背負うということは偉大なことです。議員という役目は、一人で果たせるものではなく、ともに助け合いながら行っていくものです。その協同が一人ひとりの活動よりも大きな意味を持つのです。民主主義とはそうやって機能するものだと思いませんか? 政治とは、自分自身のエゴから私たちみんなに関わる物事へと視野を広げていくことです。自分の住む地域の社会に目を向け、さらにその向こうを見つめてみましょう。なぜなら、私たちは自分だけで生きているのではないのですから。私たちの役目と責任は、国家というものが規定する国境よりも大きなものです。私たちを必要としている世界があるのです。私たちの連帯、お金、そして特に私たちの視線と声を必要としている世界があるのです。
あなた方には多くの期待が掛けられています。しかし、勇気を失ってはいけません。あなた方に声の代弁を託した私たちは、傍で応援しています。民主主義とはそうやって機能するものだと思いませんか?
(中略。聖書からの一節に触れる)

すべての人間には出生地や性別、年齢に関係なく、そして、ホモセクシャルであるかどうかに関係なく、尊厳があり、同じだけの価値を持っているのだと信じている私たちは、議員となったあなた方が常に私たちと対話を持ち続け、「あなたのために何ができるだろうか?」と問い続けてくれることを期待しています。そして、そのことで社会が良い方向に動いていけば大きな喜びとなります。
昨日、ストックホルムや国内の各地では数千人の人々が集まり、声を上げました。同じ人間同士に区別を設けようとする動きに対して、反対の声を訴えたのです。「あなたには私ほどの価値はない」「あなたには私ほどの権利はない」「あなたには自由を享受しながら生きる資格はない」と主張する人種差別に対して、拒絶の気持ちを表現しました。この人種差別は、ある人がたまたま世界の別の場所で生まれたという違いだけで、人々に差別をつけようとしているのです。キリスト教を信じる者にとって、そのような差別は決してできません。人間に違いをつけることは、尊厳を犯すことです。人種差別をなくすためには、あなたたち数百人の人に議員としての役目を託すだけでは不十分です。これは、私たちみんなの役目であるからです。そして、人間としての価値を護るという闘いにおいて、誰かが声を上げなくなったり、声を封じられることがないように、石でさえ声を上げるくらい私たちみんなで頑張っていかなければなりません。そのために、神は支援の手を差し伸べてくれることでしょう。
私たちはたくさんのことを成し遂げなければなりません。そして、そのためには巧妙さと勇気と人間同士の温もりが必要です。役目に喜びを感じましょう。役目の重さを感じましょう。私たちが託した信任を実感してください。すべてのことにトライして、良いものを生かして行こうではありませんか。人間に区別をつけてはいけません。私たちを創った神の慈悲を感じましょう。
そうすることで、私たちは今を生き、将来へと歩んでいけるのです。
----------
説法のテーマは、基本的人権とすべての人々の同一価値、そして人種差別反対であった。このようなテーマについて牧師などが道徳として人々に説くのはよくあることだが、今回は、イスラム教を敵視し、外国生まれの住民の排斥を訴えるスウェーデン民主党が議席を獲得したという事実もあったので、主教はその重要性を特に強調したかったのだろう。
スウェーデン民主党の20人の議員は、この説法を最後まで聞くことなく、途中で退席してしまった。スウェーデン民主党と名指しをされたわけではないのに、「すべての人々が同じ尊厳を持っている」や「人種差別に反対」という部分が、自分たちに対する嫌がらせだと感じたのだった。

教会を後にするスウェーデン民主党の議員
また、「昨日、ストックホルムや国内の各地で人種差別に抗議する集会が開かれた」という部分に対しても、スウェーデン民主党は「一部の集会では左派の活動家が多かった」と指摘した上で「過激で暴力的な極左な活動家を擁護するつもりか!」と怒り狂ったのだった。しかし、実際には、スウェーデン民主党が議会入りを果たした国政選挙の翌日から、スウェーデン各地では極右のこの党に抗議する大規模な集会が断続的に開かれており、左派だけでなく、中道保守などの政党を支持する人も含めたスウェーデン社会を構成する幅広い人々が、基本的人権の重要性を改めて考えるキャンペーンに賛同するようになっている。主教が説法の中で触れた「昨日の集会」というのは、その一例に過ぎず、左派の活動家だけを賞賛したわけではない。むしろ、スウェーデン社会を織り成す基本的な価値観を述べたに過ぎない。
スウェーデン民主党はこれまでの活動の中で、極右というレッテルを貼られないように「自分たちは人権を尊重しているし、人種差別はしない」と主張してイメージアップに努めてきたのだが、この説法の途中に退席するという行動を通じて、ひたすら隠そうとしてきた本当のイデオロギーをむしろさらけ出すことになってしまった。スウェーデンに対する愛国主義や伝統を重んじるこの党は、スウェーデン国教会を自らのイデオロギーの拠り所の一つとしているのだが、そのまさに国教会からそっぽを向けられてしまったわけだ。サッカーの過激なフーリガンが、自分の応援するチームから「あなた達にはスタジアムで応援してほしくない」と言われたような感じだ。ただし、説法を行ったストックホルム主教区の主教は「基本的な価値を共有している限り、誰でも教会には歓迎したい」と言っており、特定の政党を追放したりするつもりはないという。
しかし、国会の開会に先駆けては、議会と王宮の近くにあるストール教会でミサが行われ、ストックホルム主教区の主教が説教(説法)を説くことが慣例となっている。ただ、政教分離の原則があるため、宗教色の濃いものではなく、議会の開会を前にした緊張の面持ちの議員たちに国民の期待に応えてしっかりと頑張るようにエールを送るための儀式となっている。主教の説く説教(説法)も聖書の内容に基づくものではあるが、今の社会にとって特に重要なキーワードを選んで、一般的な道徳を説くものである。
さて、国王などの来賓に続いて、議員たちが到着した。みな正装だが、中には民族衣装を身にまとっている議員もいる。やはり注目されたのは、ポピュリスト・極右政党であるスウェーデン民主党の議員だが、愛国主義や伝統をことさらに強調する党とあって、党首は自分の出身地であるブレーキンゲ地方の民族衣装を身につけて登場した。スウェーデンの伝統を守れるのは自分たちの党だけ、とでも言わんばかりだ。一方、社会民主党の女性部会の代表を務めている女性議員Nalin Pekgulはトルコのクルド地方の出身だが、彼女はクルドの民族衣装を着こなして、スウェーデンの旗を手にしながら登場した。多文化のスウェーデンを象徴するためでもあるし、スウェーデン民主党に対抗するためでもある。


このミサで、大きなハプニングがあった。主教である女性牧師による説教(説法)の途中の出来事だった。
彼女の話はこう始まった。
国民から信頼を託され、議員という役目を担うことになった皆さん、おめでとう。85%の有権者、つまり600万人強のスウェーデンの人々は、私たちみんなのために良い社会を築き、素晴らしい将来を作り上げる資質を持ち備えているのはあなただと考えたからこそ、議員に選んだのです。その信頼を背負うということは偉大なことです。議員という役目は、一人で果たせるものではなく、ともに助け合いながら行っていくものです。その協同が一人ひとりの活動よりも大きな意味を持つのです。民主主義とはそうやって機能するものだと思いませんか? 政治とは、自分自身のエゴから私たちみんなに関わる物事へと視野を広げていくことです。自分の住む地域の社会に目を向け、さらにその向こうを見つめてみましょう。なぜなら、私たちは自分だけで生きているのではないのですから。私たちの役目と責任は、国家というものが規定する国境よりも大きなものです。私たちを必要としている世界があるのです。私たちの連帯、お金、そして特に私たちの視線と声を必要としている世界があるのです。
あなた方には多くの期待が掛けられています。しかし、勇気を失ってはいけません。あなた方に声の代弁を託した私たちは、傍で応援しています。民主主義とはそうやって機能するものだと思いませんか?
(中略。聖書からの一節に触れる)

すべての人間には出生地や性別、年齢に関係なく、そして、ホモセクシャルであるかどうかに関係なく、尊厳があり、同じだけの価値を持っているのだと信じている私たちは、議員となったあなた方が常に私たちと対話を持ち続け、「あなたのために何ができるだろうか?」と問い続けてくれることを期待しています。そして、そのことで社会が良い方向に動いていけば大きな喜びとなります。
昨日、ストックホルムや国内の各地では数千人の人々が集まり、声を上げました。同じ人間同士に区別を設けようとする動きに対して、反対の声を訴えたのです。「あなたには私ほどの価値はない」「あなたには私ほどの権利はない」「あなたには自由を享受しながら生きる資格はない」と主張する人種差別に対して、拒絶の気持ちを表現しました。この人種差別は、ある人がたまたま世界の別の場所で生まれたという違いだけで、人々に差別をつけようとしているのです。キリスト教を信じる者にとって、そのような差別は決してできません。人間に違いをつけることは、尊厳を犯すことです。人種差別をなくすためには、あなたたち数百人の人に議員としての役目を託すだけでは不十分です。これは、私たちみんなの役目であるからです。そして、人間としての価値を護るという闘いにおいて、誰かが声を上げなくなったり、声を封じられることがないように、石でさえ声を上げるくらい私たちみんなで頑張っていかなければなりません。そのために、神は支援の手を差し伸べてくれることでしょう。
私たちはたくさんのことを成し遂げなければなりません。そして、そのためには巧妙さと勇気と人間同士の温もりが必要です。役目に喜びを感じましょう。役目の重さを感じましょう。私たちが託した信任を実感してください。すべてのことにトライして、良いものを生かして行こうではありませんか。人間に区別をつけてはいけません。私たちを創った神の慈悲を感じましょう。
そうすることで、私たちは今を生き、将来へと歩んでいけるのです。
説法のテーマは、基本的人権とすべての人々の同一価値、そして人種差別反対であった。このようなテーマについて牧師などが道徳として人々に説くのはよくあることだが、今回は、イスラム教を敵視し、外国生まれの住民の排斥を訴えるスウェーデン民主党が議席を獲得したという事実もあったので、主教はその重要性を特に強調したかったのだろう。
スウェーデン民主党の20人の議員は、この説法を最後まで聞くことなく、途中で退席してしまった。スウェーデン民主党と名指しをされたわけではないのに、「すべての人々が同じ尊厳を持っている」や「人種差別に反対」という部分が、自分たちに対する嫌がらせだと感じたのだった。

教会を後にするスウェーデン民主党の議員
また、「昨日、ストックホルムや国内の各地で人種差別に抗議する集会が開かれた」という部分に対しても、スウェーデン民主党は「一部の集会では左派の活動家が多かった」と指摘した上で「過激で暴力的な極左な活動家を擁護するつもりか!」と怒り狂ったのだった。しかし、実際には、スウェーデン民主党が議会入りを果たした国政選挙の翌日から、スウェーデン各地では極右のこの党に抗議する大規模な集会が断続的に開かれており、左派だけでなく、中道保守などの政党を支持する人も含めたスウェーデン社会を構成する幅広い人々が、基本的人権の重要性を改めて考えるキャンペーンに賛同するようになっている。主教が説法の中で触れた「昨日の集会」というのは、その一例に過ぎず、左派の活動家だけを賞賛したわけではない。むしろ、スウェーデン社会を織り成す基本的な価値観を述べたに過ぎない。
スウェーデン民主党はこれまでの活動の中で、極右というレッテルを貼られないように「自分たちは人権を尊重しているし、人種差別はしない」と主張してイメージアップに努めてきたのだが、この説法の途中に退席するという行動を通じて、ひたすら隠そうとしてきた本当のイデオロギーをむしろさらけ出すことになってしまった。スウェーデンに対する愛国主義や伝統を重んじるこの党は、スウェーデン国教会を自らのイデオロギーの拠り所の一つとしているのだが、そのまさに国教会からそっぽを向けられてしまったわけだ。サッカーの過激なフーリガンが、自分の応援するチームから「あなた達にはスタジアムで応援してほしくない」と言われたような感じだ。ただし、説法を行ったストックホルム主教区の主教は「基本的な価値を共有している限り、誰でも教会には歓迎したい」と言っており、特定の政党を追放したりするつもりはないという。










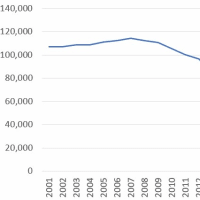
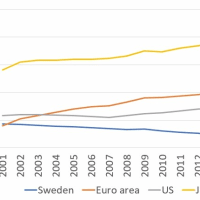
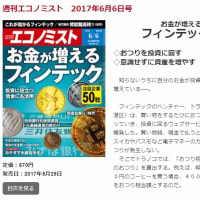
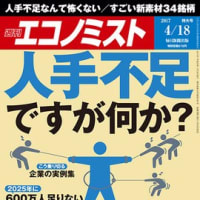






詳しいことが知りたくて、ネットで新聞を検索したのですが、どこも説教のさわりだけしか書いてなくて、不満でした。
記事、ありがとうございました。
ネットの新聞記事は最近はすぐにコメントが書けるようになっていますね。
GPなどは50以上のコメントがありました。
読んでみて驚いたのは、「政治と宗教は切り離すべきだ。こんなところで説教するのはけしからん」「お前達、彼女がなんと言ったかよく聞けよ。SDが怒るのももっともだ」「左派のデモを持ち上げるのはうざい」
そんな声がだーっと並んでいました。
SD議員20人がうちに帰ってから一生懸命に書いたのかしら。
それで詳しい内容が知りたかったのです。
この内容で席を立つのはなんとも子どもっぽい。
それを褒め称える人が沢山いるのはもっと恐いと思いました。
スウェーデン語が出来ない私にとって、スウェーデン政治を理解するのにとても役立っております。寧ろ、このブログの記事を読んで一刻も早くスウェーデン語を習得したいと思っております。
周りの友人は、スウェーデン民主党が議席を獲得したことは、とても残念だけれども、多くの人々が政治に危機感を抱いて、政治に関わろうとしている姿勢は逆に良かった、と言っております。
確かに、知らず知らずのうちに極右政権が力をつけていく方が恐ろしいと思います。
これからも更新を楽しみにしております。
どうなっているのでしょうか?
年間の受け入れ人数に制限はあるんでしょうか?
イタリアでは街の一部地域に中国人の数が増え法律や慣習を無視し、地元住民と衝突しているようですが
スウェーデンではそのようなケースにたいしてどのように対処しているのでしょうか?
日本は森林の売買と用途についての規制がなく最近になってクローズアップ現代や各紙が取り上げていました。このように、日本は制度面の整備が整っていません。スウェーデンではどのようにその辺りを上手くやったのでしょうか?
池袋北口が中国人街となり、地元ともめていると記事になっていました。窃盗グループの犯罪も増えています。
受け入れ側、移民側双方に、共生の理解が必要でしょうけれど、sweではどうアプローチしたのでしょうか?
質問ばかりですみません。
>どうなっているのでしょうか?
>年間の受け入れ人数に制限はあるんでしょうか?
まず、難民についてですが、ジュネーブ条約に基づいて審査を行い、難民認定を行うかを判断しています。この審査に時間がかかることが大きな政治問題になっています。
また、受入数についてですが、上限があるのかについては分かりません。ただ、上限があったとしても、もしある人がスウェーデンで難民申請をして、認定要件を満たす場合に、追い返すことはできないでしょう。
イラク戦争に伴い、イラクからの難民の多くがスウェーデンに受け入れられましたが、人数の増加が急激だったために、スウェーデン政府はEUの他の加盟国にも難民受け入れの責務を負うように何度も苦情を呈してきました。
また、難民認定の基準についてですが、ジュネーブ条約に基づくことにはなっているものの、近年は審査が厳しくなってきたようで、受け入れられるはずの人が強制送還されたり、家族が離れ離れになったり、といったケースもたびたび報告されるようになっており、バランスを取るのが難しいようです。
一方、難民以外の移民については、家族がすでにスウェーデンにいる場合以外は、もっぱら労働を目的にした移民になると思いますが、すでに仕事を見つけていたり、雇い主からの証明書があったり、その仕事がすでにスウェーデンにいる人にできない場合、などでなければ、労働許可証が発行されないのではないかと思います。ルールの詳細については分かりませんが、誰でもスウェーデンに移住して仕事ができる訳ではありません。
法律を地元自治体のルールなどを無視している場合は、その国に生まれた者か難民・移民であるかに関係なくきちんと取り締まる必要があるでしょう。
>受け入れ側、移民側双方に、共生の理解が必要でしょうけれど、sweではどうアプローチしたのでしょうか?
スウェーデンの一部(特に大きな都市の郊外)では、家賃が比較的安いために低所得者の人が多く集まっている地域があります。そして、これらの地域では、スウェーデンに来てから年数があまり経たず、仕事に就きにくい人も多く集まる傾向にあります。
ここでの大きな問題は、失業率や非労働力率が比較的高いために、社会との接点を失う人が増え、特に若い人の無気力が暴動などにつながるケースも発生しています。
スウェーデン生まれの人とそれ以外の人といった区別に関わらず、社会における格差拡大は、仕事を持ち、社会に貢献し、税金を納めている人と、仕事に就けず(あるいは就こうとせず)無気力化し、社会との接点を失ってしまった人との間で拡大していると、スウェーデンでは一般に考えられています。私も、その見方は的を得ていると思います。ですので、雇用をいかに増やして、労働市場を通じて、疎外された人々を社会に吸収し、社会統合を図っていくことが大きな鍵かと思います。
たとえば、製造業が盛んで失業率が比較的低い地域の自治体が、失業率の高いそのような地域の自治体と提携を結んで、労働力の移動(引越し)を促進することで雇用を増やすことに成功したといったケースもあります。また、投石や放火などの事件が頻発する地域では、児童・生徒や若者が課外活動をできる施設(学童)などを充実させたり、そこに消防士を招いて一緒にスポーツ活動をしたりすることで、事件の発生頻度が大きく減った、というケースもあります。残念ながら、良いニュースは悪いニュースほど、大きく取り上げられませんが。
>それを褒め称える人が沢山いるのはもっと恐いと思いました。
これはおそらくSDの国会議員や地方議員やサポーターですよ。選挙の1年ほど前から私も機になっていましたが、ニュース記事のコメント欄で、ひたすらSDの宣伝や主張を繰り返しています。あんまりSDとは関係ないテーマにまで口を出して、たとえば、水産資源の保全に関する記事のコメント欄にも「海の環境のことを一番大切に考えているのはSDだ」なんて書いているのを見たときには笑ってしまいました。
実際のところ、ネット上でのこのような書き込みは、SDが選挙に先駆けて重点を置いたキャンペーン方法らしく、多かれ少なかれ組織的に行われているようです。SDのpartisekreterareもいつだかのインタビューで認めていました。しかも、本名を使わずに偽名とか移民系の名前までも使っていたそうです。これも笑ってしまいます。Facebook上での「anti SD」や「anti rasism」のグループページにも彼らはちゃんと潜り込んでいます(笑)
>議席を獲得したことは、とても残念だけ
>れども、多くの人々が政治に危機感を
>抱いて、政治に関わろうとしている姿勢
>は逆に良かった、と言っております。
まさにそのとおりだと思います。様々な社会問題について政治サイドから説得力のある対策が打ち出されてこなかったという声もありますし、問題に対してちゃんと議論を重ねてきたとしても、それがSDに票を投じた人に届いていなかったということもあるかと思います。
私もヨーテボリでのデモに参加しましたが、希望はまだまだある、とそんな気分にさせられる機会でした。
スウェーデン固有の政治問題だけではなく色々な事を
考えさせられて興味深いです。
ムスリムではないけど「外国人」である私には
ルペンやスウェーデン民主党のような主張は望ましくはないし
排他性には問題を感じるけれど、その一方で互いの固有性や
文化としてどこまで尊重して許容すべきなのか…
その線引きになると、普遍的で難しい部分でもある気もします。
EU圏でのロマやブルカ問題、逆にイスラム圏での悪魔の詩や
アヤーン・ヒルシ・アリさんの騒動。中国での故宮スタバ論争や
リオエリエント論なども共通している部分はあるというか。
もし移民する側が受け入れ先の社会の倫理や価値観を共有しない…
または異なる社会観を持っている場合にそれは尊重されるべきか。
それとも教育という名目で、矯正や同化を行うのが正しいのか。
ソーシャリズムに基づいた社会と、多様性(多文化主義)とは相性
悪い部分もあるのではないか…。色々考えさせられます。
例のCMの話を読むと、スウェーデン民主党の主張は排外的愛国
主義な色が強そうだけれども、キリスト教圏でのムスリムへの
排斥は反同性愛や女性差別などの面でリベラルな思想や立場にも
非難や排斥に熱心な人が多いようにも見えますが、彼らの支持層や
台頭した社会的な土壌については、左右という括りではない
もう少し複雑な部分はないのでしょうか。
功利的な面で言えば、移民を受け入れることはその社会にとって
リターンとロスはあると思うけれど、経済的に余裕がない現状では
マイナス面の方が印象強くなってもいるのかもしれませんね…。
>または異なる社会観を持っている場合にそれは尊重されるべきか。
>それとも教育という名目で、矯正や同化を行うのが正しいのか。
価値観を完全に共有させることは無理でしょうし、そもそもスウェーデンの人同士でも様々な価値観があります。では、多様性は認めるとしてもどこで線引きをするか、という問題は、おっしゃるように容易には答えが出ませんね。しかし、いくつかの具体例を上げてみると、多くの場合はある程度、割り切って考えることができるように思います。
たとえば、文化によっては家族や親類、一族の名誉を傷つけたという理由で身内を殺す(たとえば、一族の決めた結婚相手との結婚を拒否した女性に対して)といった名誉殺人が許されているところもありますが、この場合はいくら文化の多様性とはいっても、スウェーデンでそれを認めることはできないでしょう。
体罰にしても、一部の文化や国では認められていますが、スウェーデンでは刑法で禁じられているため、いくら多文化とはいえ認められないでしょう。
また、イスラム圏の一部では、家畜のの際に独特の方法でそれを行うという慣習があるようですが、スウェーデンの動物保護法ではまず麻酔をかけてからを行うという規則になっているため、そのイスラム圏の方法に従ったを行いたい場合は、まず麻酔をかけた上で行うという妥協をしなければならないでしょう。
つまり、文化の多様性は大いに認めるけれど、それはスウェーデンの法律に抵触しない範囲内で、という線引きをすることは多くの場合に可能だと思います。
一方、線引きの難しい問題もあります。
たとえば、女性の行政職員との握手を拒んだ男性について社会的議論になったことがありましたが、彼は宗教的な規律に基づき、女性との挨拶では握手はしないというポリシーを持っていると言うし、一方、行政職員のほうは、男女平等が一つの共通的価値として捉えられているスウェーデンにおいてそのような行動を取るのは失礼だとして、両者の主張が真っ向から対立したことがありました。
また、宗教団体による保育所や学校の運営が認められてはいますが、きちんと学習指導要領に基づく教育を行うことが条件となっています。この中で問題となったのは、体育の時間を男子・女子分けて行ってもよいのか、ということでした。また、一般の公立の学校に子どもを通わせるイスラム教の親の一部には、男女共通の体育や水泳の時間は好ましくないとして、子どもを体育の授業に「宗教的な理由から」参加させない人もいるようです。では、この場合に、無理にでも出席を強制したり、男女共通の体育の時間を持つことを強制すべきか?
このようなケースでは文化の多様性という理由でどこまで許容するのかは、線引きが難しいでしょう。簡単な答えはありませんが、今すぐに抜本的な解決策を見つけ出そうとするのではなく、時間の解決を待つのも一つの手かと思います。自分の主義主張をすぐには変えようとしない彼らの世代ではなく、一生のうちの大部分もしくは全部をスウェーデン社会で過ごし、その価値観に多かれ少なかれ影響されながら育った子どもの世代は、より柔軟に社会に適応できるようになると思います。つまり、「他文化」という境界も固定的なものではなく、時代や世代間で徐々に変化していくということです。
私としては、文化の多様性に制限を設ける場合には、その根拠が「合理性」に基づくべきだと考えます。スウェーデン民主党の主張を聞いていると、彼らが様々な制限を設けたい根拠は「スウェーデン的ではない」とか「スウェーデンの伝統に反する」とか「イスラム教の教えに基づくものだから」といった漠然としたものがほとんどだと思います。これらの主張は、人々の「情緒」に訴えかけるものばかりで、ではスウェーデン的とは何なのか?とか、スウェーデンの伝統とは何なのか?などと、合理的に突き詰めて考えていくと、中身が溶けてなくなってしまうアイスクリームのようなものだと思います。
思想史には詳しくありませんが、ルネッサンスから啓蒙主義、そしてロマン主義、そして合理主義etcという時代の流れの中で、「理性」と「情緒」の間を行ったり来たりしてきた振り子が、今また「情緒」に向かって動きを強めているのかなと思います。
私は「情緒」を否定するつもりはありませんが、情緒だけにもっぱら基づいて世論を動かせばポピュリズムに流れて行きますし、情緒だけに基づいて政治的な決定を行おうとすれば、法の下の平等の侵害などのリスクを孕んでくると思います。