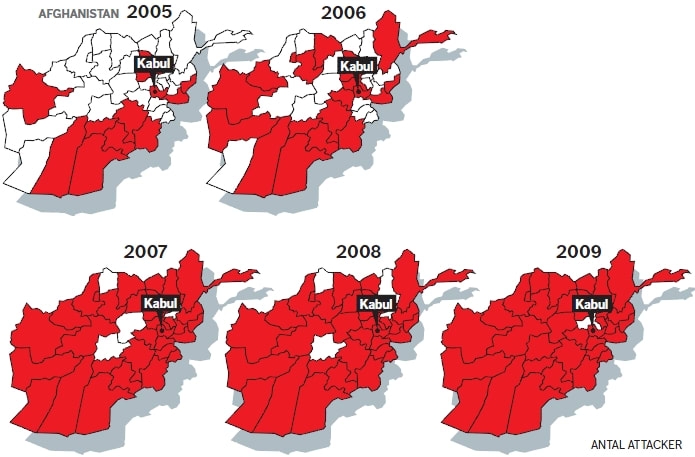スウェーデンの財政を引き続き管轄することになったボリ財務大臣は、先週火曜日に来年2011年の予算案を議会に提出した。恒例として財務省から議会までの数百メートルの道のりを予算案を抱えながら行進し、その後、議会の予算委員会で与野党が討議を行った。

後ろのウサギはどうやらあるバラエティー番組の企画らしい
私はこの日たまたまスウェーデン議会の建物を訪ねる機会があった。討議は委員会室ではなく、大きな議場を使って行われるものの、出席しているメンバーは予算委員会のメンバーがほとんどのようだ。しかし、議会のカフェテリアや議場外のスペースには新議員を含め、様々な議員が行き交っていた。物議を醸している新しい社会保険大臣も見かけた。議会の労働市場委員会の事務を担当している職員の人が言うには「新しい議員が多いから、名前を知らない議員もいっぱい見かける」と、この職員にとっても新鮮な雰囲気が漂っているようだった。

議場を出たところ
さて、2011年の予算案の中身は、9月の国政選挙に先駆けて中道保守連立与党が発表した選挙公約(マニフェスト)に基づくものだった。
たとえば、
・年金受給者のみを対象にした基礎控除額の拡大
・大学生を対象にした生活ローンの増額
・国税所得税の課税最低限の引き上げ
・エコカー補助金の対象の厳格化(これまではCO2排出を1kmあたり120g以下に抑える車が対象だったが、これからは50g以下に抑える車だけに限定する。補助金の額は4万クローナ・48万円)
・地方自治体への特別交付金
・高校職業科における実際の職場を利用した見習い制度(徒弟制)や若者向けの見習い雇用の導入
などだ。
日本でも選挙の前には「マニフェスト」という言葉が聞き飽きるくらい頻繁に使われるようにはなったが、スウェーデンの選挙との大きな違いは、スウェーデンではマニフェストに書かれた各政策分野の細かい公約が、各党の選挙キャンペーンやテレビやラジオにおける討論や「尋問」でちゃんと取り上げられ、吟味され、他の党の主張と比較される、というプロセスを経ていることだ。だから、ある程度、切磋琢磨されたものになっているし、その内容が世論にもかなりの程度、ちゃんと伝わっている。だから、その後に発表される予算案の内容も透明性を持ったものであるし、多くの人々がすでに耳にしたものばかりだ。
金融危機以降の不況から順調に脱していることを象徴するように、労働市場政策の関連予算は昨年よりも少なく抑えられることになった。これは失業者が順調に減りつつあるためだ。失業者の再教育のために大学の定員拡大を目的とした特別予算が2009年に設けられたが、これも廃止されることとなった。イメージとしては、金融危機という台風をしのぐために「家」のあらゆる「窓」に板を打ち付けていたが、それを少しずつ剥がして、正常な状態に戻している、といった感じだろうか。
また、選挙に先駆けて大きな議論となった勤労所得税額控除については、控除額のさらなる引き上げ(第5次税額控除)は見送られた。ただし、これはすでに選挙を前にした議論の中で「財政にそこまでの余裕がない」ことが次第に明らかになったため、中道保守連立政権側も経済の回復を見ながら行う、と発表していたものだった。
ちなみに、この予算案はあくまで2011年のものであるが、2012年から導入を行う予定の新しい政策についても既に触れられ、その導入がこの予算審議の時点で約束されることになった。たとえば、
・課税軽減を目的とした(株式や投資信託のための)預金口座制度の新設
・低所得の子持ち世帯のための住宅手当の増額
・子どもが生まれてから最初の30日間は、両親が同時に育児休業を取り、育児休業手当を受け取ることができるようにする(現行では、育児休業手当は両親が同時に利用することはできず、その代わり、子どもが生まれる前後に父親が10日間仕事を休んで給与の補填を受けられる制度のみがある)
・雇い主が報酬の一つとして従業員に企業の車をリースする際、エコカーであれば課税を軽減する制度
さて、この予算案に対するメディアや専門家の反応はどうか?
選挙公約(マニフェスト)のなかで約束された政策がきちんと盛り込まれたことに対しては一定の評価があるものの、それ以上の「サプライズ」に欠けるという指摘が多かったようだ。たとえば、ある日刊紙は「自動操縦スイッチがONにされた」というタイトルの社説を掲載していた。つまり、不況という嵐を抜けつつある今、再びBusiness as usualに戻っただけで、今後のスウェーデン社会を見据えた大きなビジョンに欠ける、という批判だった。現政権に基本的に賛意を示しているこの日刊紙は、この連立政権が国・地方の財政規模を対GDP比で縮小させてきたことは評価しているものの、財政のスリム化はそろそろ止めて、むしろスウェーデン社会の長期的な変革に備えるための投資に予算を積極的に使うべきだ、という趣旨の論説を展開していたのが印象的だった。
また、財務省の専門家委員会の委員長を務める経済学教授は、現政権が2007年から2010年の間に労働市場政策のうちの職業訓練(比較的短期のもの)を極端に削減したことを批判し、景気や雇用情勢が確実に回復している今、労働需給のミスマッチを防ぎ、雇用を拡大させたい産業・企業が必要な技能を持った労働者不足のために拡大を断念したり、その分野の労働者の賃金が高騰すること(いわゆるボトルネック問題)がないように、適切な内容の職業訓練を実施できるように予算をちゃんとつけるべきだと指摘していた。

上の図は、2000年から2014年までの国・地方の歳入(青線)と歳出(赤線)を示したものだ(対GDP比。2009年以降は予測)。青線、つまり歳入が徐々に下降しているのは減税措置によって税・社会保障費の対GDP比を抑える努力をしてきたためだ。グラフから分かるように、社会民主党政権の時代にも減少してきたが、2003年から2005年の間に若干リバウンドしてしまった。その後を引き継いだラインフェルト政権が勤労所得税額控除などによって対GDP比でさらに3%ポイントほど減少させた。
他方、歳出のほうは金融危機によって一時的には増えたものの、赤字の規模はわずかなものであり、来年の時点で歳入・歳出が均衡し、その後、順調に経済が回復していけば大きな黒字(青色の斜線)が生まれるものと見られている。これは、財政危機に苦しんでいる多くの先進国にとっては非常に羨ましいものだろう。近い将来に再び経済危機が襲ってくるようなことも大いにありえるものの、今の時点で言えるのは、この社会の将来はかなり明るいものだということだ。
私も、上に紹介した日刊紙の社説に賛成であり、財政規模は現在の対GDP比48%程度に安定させ、今後生まれるであろう黒字の分だけ減税をさらに行うのではなく、社会保障や教育・研究開発などへの長期的な投資に充ててほしいと思う。

後ろのウサギはどうやらあるバラエティー番組の企画らしい
私はこの日たまたまスウェーデン議会の建物を訪ねる機会があった。討議は委員会室ではなく、大きな議場を使って行われるものの、出席しているメンバーは予算委員会のメンバーがほとんどのようだ。しかし、議会のカフェテリアや議場外のスペースには新議員を含め、様々な議員が行き交っていた。物議を醸している新しい社会保険大臣も見かけた。議会の労働市場委員会の事務を担当している職員の人が言うには「新しい議員が多いから、名前を知らない議員もいっぱい見かける」と、この職員にとっても新鮮な雰囲気が漂っているようだった。

議場を出たところ
さて、2011年の予算案の中身は、9月の国政選挙に先駆けて中道保守連立与党が発表した選挙公約(マニフェスト)に基づくものだった。
たとえば、
・年金受給者のみを対象にした基礎控除額の拡大
・大学生を対象にした生活ローンの増額
・国税所得税の課税最低限の引き上げ
・エコカー補助金の対象の厳格化(これまではCO2排出を1kmあたり120g以下に抑える車が対象だったが、これからは50g以下に抑える車だけに限定する。補助金の額は4万クローナ・48万円)
・地方自治体への特別交付金
・高校職業科における実際の職場を利用した見習い制度(徒弟制)や若者向けの見習い雇用の導入
などだ。
日本でも選挙の前には「マニフェスト」という言葉が聞き飽きるくらい頻繁に使われるようにはなったが、スウェーデンの選挙との大きな違いは、スウェーデンではマニフェストに書かれた各政策分野の細かい公約が、各党の選挙キャンペーンやテレビやラジオにおける討論や「尋問」でちゃんと取り上げられ、吟味され、他の党の主張と比較される、というプロセスを経ていることだ。だから、ある程度、切磋琢磨されたものになっているし、その内容が世論にもかなりの程度、ちゃんと伝わっている。だから、その後に発表される予算案の内容も透明性を持ったものであるし、多くの人々がすでに耳にしたものばかりだ。
金融危機以降の不況から順調に脱していることを象徴するように、労働市場政策の関連予算は昨年よりも少なく抑えられることになった。これは失業者が順調に減りつつあるためだ。失業者の再教育のために大学の定員拡大を目的とした特別予算が2009年に設けられたが、これも廃止されることとなった。イメージとしては、金融危機という台風をしのぐために「家」のあらゆる「窓」に板を打ち付けていたが、それを少しずつ剥がして、正常な状態に戻している、といった感じだろうか。
また、選挙に先駆けて大きな議論となった勤労所得税額控除については、控除額のさらなる引き上げ(第5次税額控除)は見送られた。ただし、これはすでに選挙を前にした議論の中で「財政にそこまでの余裕がない」ことが次第に明らかになったため、中道保守連立政権側も経済の回復を見ながら行う、と発表していたものだった。
ちなみに、この予算案はあくまで2011年のものであるが、2012年から導入を行う予定の新しい政策についても既に触れられ、その導入がこの予算審議の時点で約束されることになった。たとえば、
・課税軽減を目的とした(株式や投資信託のための)預金口座制度の新設
・低所得の子持ち世帯のための住宅手当の増額
・子どもが生まれてから最初の30日間は、両親が同時に育児休業を取り、育児休業手当を受け取ることができるようにする(現行では、育児休業手当は両親が同時に利用することはできず、その代わり、子どもが生まれる前後に父親が10日間仕事を休んで給与の補填を受けられる制度のみがある)
・雇い主が報酬の一つとして従業員に企業の車をリースする際、エコカーであれば課税を軽減する制度
さて、この予算案に対するメディアや専門家の反応はどうか?
選挙公約(マニフェスト)のなかで約束された政策がきちんと盛り込まれたことに対しては一定の評価があるものの、それ以上の「サプライズ」に欠けるという指摘が多かったようだ。たとえば、ある日刊紙は「自動操縦スイッチがONにされた」というタイトルの社説を掲載していた。つまり、不況という嵐を抜けつつある今、再びBusiness as usualに戻っただけで、今後のスウェーデン社会を見据えた大きなビジョンに欠ける、という批判だった。現政権に基本的に賛意を示しているこの日刊紙は、この連立政権が国・地方の財政規模を対GDP比で縮小させてきたことは評価しているものの、財政のスリム化はそろそろ止めて、むしろスウェーデン社会の長期的な変革に備えるための投資に予算を積極的に使うべきだ、という趣旨の論説を展開していたのが印象的だった。
また、財務省の専門家委員会の委員長を務める経済学教授は、現政権が2007年から2010年の間に労働市場政策のうちの職業訓練(比較的短期のもの)を極端に削減したことを批判し、景気や雇用情勢が確実に回復している今、労働需給のミスマッチを防ぎ、雇用を拡大させたい産業・企業が必要な技能を持った労働者不足のために拡大を断念したり、その分野の労働者の賃金が高騰すること(いわゆるボトルネック問題)がないように、適切な内容の職業訓練を実施できるように予算をちゃんとつけるべきだと指摘していた。

上の図は、2000年から2014年までの国・地方の歳入(青線)と歳出(赤線)を示したものだ(対GDP比。2009年以降は予測)。青線、つまり歳入が徐々に下降しているのは減税措置によって税・社会保障費の対GDP比を抑える努力をしてきたためだ。グラフから分かるように、社会民主党政権の時代にも減少してきたが、2003年から2005年の間に若干リバウンドしてしまった。その後を引き継いだラインフェルト政権が勤労所得税額控除などによって対GDP比でさらに3%ポイントほど減少させた。
他方、歳出のほうは金融危機によって一時的には増えたものの、赤字の規模はわずかなものであり、来年の時点で歳入・歳出が均衡し、その後、順調に経済が回復していけば大きな黒字(青色の斜線)が生まれるものと見られている。これは、財政危機に苦しんでいる多くの先進国にとっては非常に羨ましいものだろう。近い将来に再び経済危機が襲ってくるようなことも大いにありえるものの、今の時点で言えるのは、この社会の将来はかなり明るいものだということだ。
私も、上に紹介した日刊紙の社説に賛成であり、財政規模は現在の対GDP比48%程度に安定させ、今後生まれるであろう黒字の分だけ減税をさらに行うのではなく、社会保障や教育・研究開発などへの長期的な投資に充ててほしいと思う。