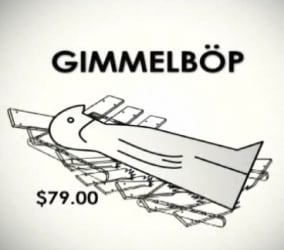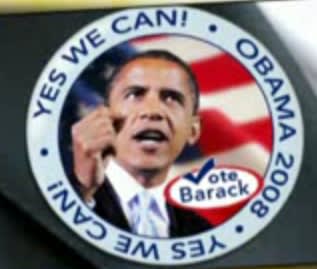アメリカ元大統領クリントンが北朝鮮を電撃訪問し、12年の禁固刑という判決を受けていたアメリカ人ジャーナリストを無事本国へ連れ帰ることに成功した。アメリカと北朝鮮の水面下での交渉の結果だが、背後にはスウェーデンの仲介があったようだ。

事実、クリントン元大統領とともにアメリカに到着した二人は、まずクリントンに謝辞を述べるとともに「在ピョンヤンのスウェーデン大使Mats Foyer(マッツ・フォイエル)にも厚く感謝したい」と述べている。
アメリカは北朝鮮と国交を持たないため、北朝鮮には大使館を開設していない。一方、スウェーデンは西側の国としては国交を持つ数少ない国の一つであり、大使館を置いている。そして、アメリカと北朝鮮の外交窓口という役割も担ってきた。
北朝鮮とスウェーデンとの関係は歴史が比較的長いようで、朝鮮戦争後、38度線の停戦ラインに非同盟中立国としてスイスとともに停戦監視団を派遣している(現在も国連部隊として数人ほどいる)。おそらく同時期に国交を結び、大使館を開設したのではないかと思う。
ヨーロッパ諸国では現在、他にイギリス、ドイツ、ポーランドが大使館を持っている。では、なぜスウェーデンの大使館がアメリカとの窓口に使われているかは謎だが、おそらく中立国という伝統のおかげや小国であることなどの理由で、北朝鮮が当初から信頼を寄せてきたためではないだろうか。(そもそも、イギリスやドイツが国交を結んだのが遅い時期であったのならば、スウェーデン以外に西側との窓口になりうる国がなかった、ということになる。)
現在は交渉の窓口だけでなく、北朝鮮内にわずかにいるアメリカ国民やカナダ・オーストラリア国民を非常時に保護・支援するといった領事館的な役割も果たしている。また、EUの国民に対しては、上に挙げたヨーロッパの3つの大使館とともに領事業務を分担している。
――――――――――
今回解放されたアメリカ人記者が北朝鮮の国境付近で逮捕されたのは、今年3月半ばのこと。二人の記者はアル・ゴア元副大統領が創設者の一人であるCurrent TVで働き、中国領内に逃れてくる脱北者を扱ったドキュメンタリー番組を作成するために撮影を行っている途中、氷の張った豆満江を渡っていたところで国境警備隊に拘束されたと言われている。
この事件が韓国のメディア経由で世界的に明るみになった直後から、アメリカ政府はスウェーデンを通じて北朝鮮とコンタクトを取ってきた。そして、3月末にはアメリカの要請でスウェーデン大使Mats Foyer(マッツ・フォイエル)が拘束された二人と実際に面会した。その後、解放に向けた努力がスウェーデンの仲介のもとで水面下で行われてきた。
今回の件について、スウェーデン外務省は「沈黙の外交の成果だ」とコメントするのみで詳細については明らかにしていない。

事実、クリントン元大統領とともにアメリカに到着した二人は、まずクリントンに謝辞を述べるとともに「在ピョンヤンのスウェーデン大使Mats Foyer(マッツ・フォイエル)にも厚く感謝したい」と述べている。
アメリカは北朝鮮と国交を持たないため、北朝鮮には大使館を開設していない。一方、スウェーデンは西側の国としては国交を持つ数少ない国の一つであり、大使館を置いている。そして、アメリカと北朝鮮の外交窓口という役割も担ってきた。
北朝鮮とスウェーデンとの関係は歴史が比較的長いようで、朝鮮戦争後、38度線の停戦ラインに非同盟中立国としてスイスとともに停戦監視団を派遣している(現在も国連部隊として数人ほどいる)。おそらく同時期に国交を結び、大使館を開設したのではないかと思う。
ヨーロッパ諸国では現在、他にイギリス、ドイツ、ポーランドが大使館を持っている。では、なぜスウェーデンの大使館がアメリカとの窓口に使われているかは謎だが、おそらく中立国という伝統のおかげや小国であることなどの理由で、北朝鮮が当初から信頼を寄せてきたためではないだろうか。(そもそも、イギリスやドイツが国交を結んだのが遅い時期であったのならば、スウェーデン以外に西側との窓口になりうる国がなかった、ということになる。)
現在は交渉の窓口だけでなく、北朝鮮内にわずかにいるアメリカ国民やカナダ・オーストラリア国民を非常時に保護・支援するといった領事館的な役割も果たしている。また、EUの国民に対しては、上に挙げたヨーロッパの3つの大使館とともに領事業務を分担している。
今回解放されたアメリカ人記者が北朝鮮の国境付近で逮捕されたのは、今年3月半ばのこと。二人の記者はアル・ゴア元副大統領が創設者の一人であるCurrent TVで働き、中国領内に逃れてくる脱北者を扱ったドキュメンタリー番組を作成するために撮影を行っている途中、氷の張った豆満江を渡っていたところで国境警備隊に拘束されたと言われている。
この事件が韓国のメディア経由で世界的に明るみになった直後から、アメリカ政府はスウェーデンを通じて北朝鮮とコンタクトを取ってきた。そして、3月末にはアメリカの要請でスウェーデン大使Mats Foyer(マッツ・フォイエル)が拘束された二人と実際に面会した。その後、解放に向けた努力がスウェーデンの仲介のもとで水面下で行われてきた。
今回の件について、スウェーデン外務省は「沈黙の外交の成果だ」とコメントするのみで詳細については明らかにしていない。