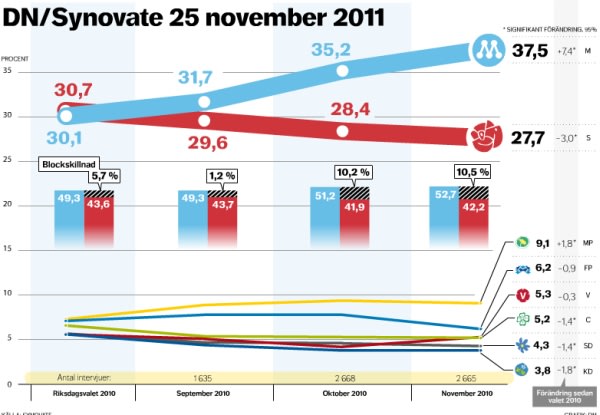チュニジアから始まったアラブ諸国の民主化運動 の波は、エジプトのムバラク政権 を倒し、そして今、リビアのカダフィ政権 を追い詰めている。民主化勢力を積極的に後押し すべきなのだが、EUもアメリカも時として明確な立場表明をためらってきた。スウェーデンのカール・ビルト外相 も、リビアにおける暴力行使を批判するコメントをしたものの「重要なのは、カダフィ政権側を支持するのか、民主化デモ側を支持するのか、ということではなく、秩序と安定性を維持するように働きかけることだ」 と発言したために、大きな非難を浴びていた。この発言は2月22日頃のことだったが、両者が対等な立場にあるならまだしも、一方の側が圧倒的な武力によって、もう片方の側を無差別に殺害している状況においては、カダフィ政権をしっかりと非難すべきだっただろう。 VIDEO
ヨーロッパ諸国の政治家のなかには、ムバラク政権やカダフィ政権と
深い親交 を持ってきたがために、今ごろ
気まずい思いをしている人々 もたくさんいる。相手が本国で人権を踏みにじっている独裁政権であることを知りながら、彼らと仲良くすることで経済的な恩恵に与ってきた閣僚がフランスなどで辞任したし、カダフィの個人パーティーに招かれてパフォーマンスを披露した歌手なども、彼との親交を後悔している。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの学長も辞任した。さんざん良い思いをしておいて、
相手が負け馬だと分かった途端に手を切る というのも、非常に情けない話だ。
VIDEO
同様に気まずい思いをしているのは
スウェーデン もだ。というのも、チュニジアに対しては30年にわたって、またエジプトに対しては過去10年ほどのあいだ
武器輸出 を行ってきたからだ。
一般に、武器輸出についてはスウェーデンでもこれまで激しく議論されてきた。スウェーデンは非同盟中立を保つために
国防軍の武装・兵器の供給は自ら行う という方針を長い間とってきた。戦闘機から戦車、駆逐艦や潜水艦に至るまで自国で開発・生産するわけだが、スウェーデンの国防軍の需要を満たすだけの数を生産していたのでは
規模の経済 が働かず、高額の研究開発投資のもとが取れない。だから、どうしても
生産量を増やすために外国輸出の道を探ろう という考えになってしまう(それでも過去20年ほど外国から既製品を調達するケースがかなり増えてはいる)。
確かにスウェーデンは、国連やEUの禁輸制裁などは当然ながら遵守しているし、
紛争当事国や内戦中の国、人権侵害などを行なう独裁国などには武器輸出は行わない 、などのガイドラインを自主的に設けている。しかし、問題なのは、果たして
そのガイドラインがきちんと守られているのか 、ということだ。
武器輸出のコントロールを行っているのは、国の行政機関である
戦略的製品検査庁(ISP) および議会に設けられ、国政政党すべての代表者からなる
輸出監督委員会(EKR) だ。しかし、そのようなコントロール制度にもかかわらず、
チュニジア、エジプト、サウジアラビア、バーレーン、オマーン、パキスタン のような独裁国や人権侵害の懸念がある国々に武器輸出が行われてきた。
また、
タイでクーデター が発生し軍部が政権を掌握した数年前にも、戦闘機の入札で他の国が入札参加を差し控える中、スウェーデンが戦闘機輸出の手続きを進め、スウェーデン国内でも大きな議論となったことはこのブログでも書いた(結局スウェーデンの
多目的戦闘機JAS-39 が入札を勝ち取り現在12機の輸出プロセスが進められている)。
<過去の記事>
2007-10-18: Aj aj aj… 軍事クーデターのタイへ戦闘機を輸出か・・・
2007-10-20: ビルト外相:「最終決定は民主選挙を待ってから」
だから、
アラブ・中東の問題国に武器輸出 を行ってきたことに対しては、スウェーデン国内でも1月以降、非難の声がさらに強まっている。しかし、それに対するラインフェルト首相のコメントが情けなかった。訪問先の小学校の小学生から、スウェーデンが世界平和を掲げる一方で問題のある国に武器輸出を行っていることの矛盾を問われたとき、彼は
「相手がいくら気に入らない政府でも対話を持つことは必要」 と、あたかも
武器輸出が問題国との対話の一つの手段である かのような答え方をしたのだった。
それに比べたら、
戦略的製品検査庁の長官 による反論はまだマシだった。彼は、過去5年間のエジプトへの武器輸出の総額は2000万クローナ(2.6億円)、チュニジアへは870万クローナ(1.1億円)に過ぎない、と前置きをした上で、武器輸出と言っても
エジプトへは競技射撃用の弾薬と軍事訓練用の装備 であり、また
チュニジアへは対空機関砲・対空ミサイル・防空レーダーや小銃に取り付ける照準や弾薬 であると指摘したのだった。彼が言いたかったのは、機関銃や爆弾、榴弾などをスウェーデンが輸出しているのではなく、よって
「スウェーデン製の兵器が民主化を求める人々の殺害に使われている」というのは間違いだ 、ということだった。さらに、
人権侵害の恐れがある国への武器輸出 と言っても、一般に海賊やテロリストの活動を航空機や艦艇によって監視するシステムなどが多く、それが自国の一般市民に対する抑圧に使われることはなく、戦略的製品検査庁や輸出監督委員会もこの点をしっかり認識したうえで輸出に対してゴーサインを出してきたのだ、と説明したのだった。
スウェーデンでは、この後もメディア上で様々な議論がNPOや行政機関、政治家などの間で交わされたが、さて、この
戦略的製品検査庁の長官の言い分 はどう評価できるのだろうか? 本当に、
市民の人権を侵害する恐れがある武器 と
そうではない武器 と明確に線引きして、
後者のみを独裁国に輸出する ということが可能なのだろうか? 軍事訓練用の装備は明らかに軍隊の強化を図るものだし、小銃に取り付ける照準だって軍隊や公安警察がデモ隊の封じ込みに使うことは可能だ。
防空システムにしても、それが民衆に直接使われる恐れは小さいものの、例えばリビアに対しては国連においてこの2週間ほどのあいだ、飛行禁止区域を設定することでカダフィ政権が空から民主化勢力を攻撃することを阻止する措置の是非が議論されてきたが、それに実効力を持たせるためにはNATOなどの戦闘機による上空監視が不可欠であり、そのためにはまずリビアの防空基地を叩く必要があるという。スウェーデンは制裁のあるリビアに対しては武器輸出を行ってこなかったものの、もしチュニジアやエジプトなどに対して同様の飛行禁止区域設定が必要となっていた場合に、スウェーデン製の対空ミサイルや防空砲がその障害となっていた可能性さえある。だから、線引きは非常に難しいといわざるを得ない。
スウェーデンは外交方針として
諸外国の民主化や人権擁護を支援する立場 をとっている。だから、そうではない国への武器輸出は、どのような形をとろうが、いくら額が小さかろうが、やはり
ダブル・スタンダード と認識せざるを得ない。それでももし、そのようないかがわしい国への輸出なしにはスウェーデンの軍需産業が成り立たない、というのであれば、いっそのこと解体していくべきだろう。
ちなみにスウェーデン製の兵器は、アメリカにも輸出され、それが国際法に照らしてもその正当性が疑われるイラク戦争で使われているし、戦闘機がハンガリーやチェコなどに輸出されるときには、スウェーデン政府に代わって売り込みを担当してきた
外国エージェント が多額のお金を使って相手国の官僚や政治家に賄賂を支払っていたことが、スウェーデン・テレビなどのスクープによって明るみに出ている。武器輸出においては常に汚い取引が付きまとう。スウェーデン経済に占める軍需産業の割合はたかが知れているのだから、そのようなことにいつまでも手を染め続ける必要はないだろうに。