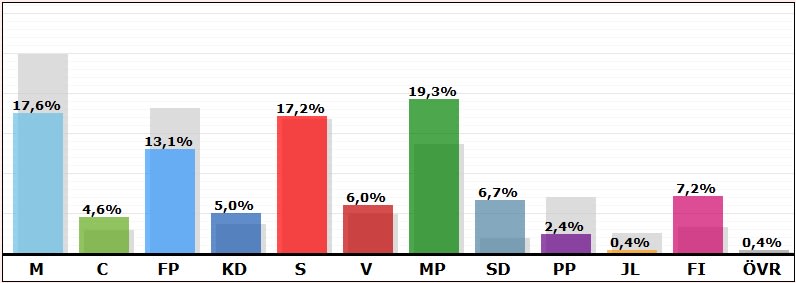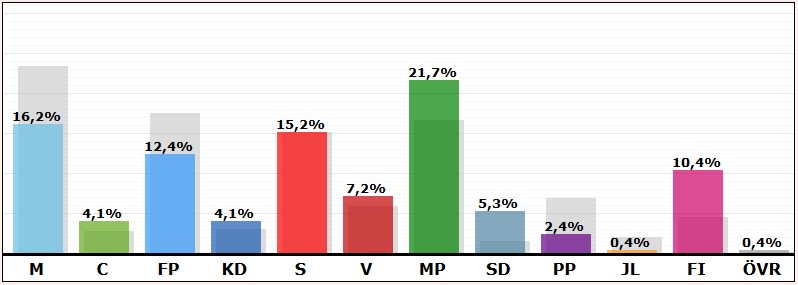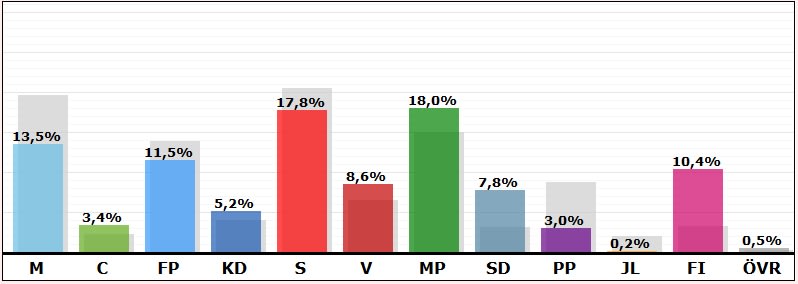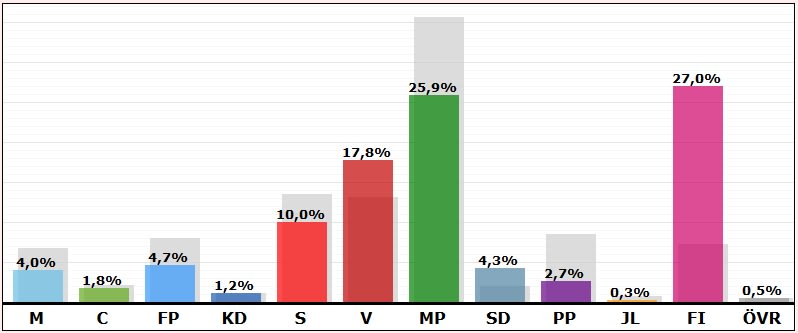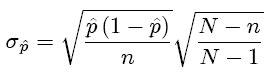欧州議会選挙の投票日である5月25日。前日の午前中まで日本に滞在し、飛行機でスウェーデンへ戻ってきたばかりなので眠くてしょうがないが、この日は朝からアドレナリン全開。
この日は朝7時半から会場設営。会場は小学校の教室だ。
スウェーデンにおける今回の欧州議会選挙では、スウェーデンから20人の議員を選んで、EUの立法府の一つである欧州議会に送り出すわけであるが、この選挙では大選挙区・比例代表制が適用されている。つまり、スウェーデン全体を一つの選挙区とし、スウェーデン全体の得票率に応じて20議席を比例的に各政党に配分し、各政党はあらかじめ決めておいた候補者リストの上位から当選者を選んでいくのである(有権者が特定の個人を選んで繰り上げ当選させる制度も補完的にはある)。
投票のマネージメントは各コミューン(市)の選挙管理委員会が管轄しており、それぞれのコミューンをいくつの投票区に分けるかは一任されている。例えば、ストックホルム市は大きいので537の投票区があるが、私が今回、投票立会人として仕事をした市は38の投票区に分かれていた。スウェーデン全体で見ると、合わせて5837の投票区が存在する。
私が仕事をするのは、そのうちの1つだ。ただ、投票所として使われるこの小学校は、その周りにある他の2つの投票区の投票所にもなっており、別々の教室が使われているので、投票しに訪れた有権者が、自分がどの教室に行けば良いかがすぐ分かるように張り紙をすることが、会場設営の重要な仕事だ。
投票所となっている教室には、投票立会人が座る机と椅子を用意し、それから投票者のために台と衝立を設置する。そして、教室の入口には、各党の投票用紙を置く。スウェーデンの投票では、自分が票を投じたい党の投票用紙を一枚選び、指定された封筒に入れて封をした上で投票箱に入れる。

開場時間の朝8時になった。眩しい太陽が学校の校庭を照らし、今にでも外に飛び出したい気分だ。しかし、投票所には誰も来ない。数分ほどして心配になり、外に出てみたら、学校の入口にはそれでも数人いたが、それは投票しに来た人ではなく、各党の党員やサポーターだ。投票しに来た人に投票所の入り口で自分の党の投票用紙を配ることで、有権者に最後のアピールをするためだ。そのような形でのキャンペーンは投票日当日でも認められている。果たして、投票の直前に党員から笑顔で投票用紙をもらったからといって、その党に票を入れようと決心する人がどれくらいいるのか分からないが、スウェーデンでは投票日当日の一つの光景として定着している。

左派・右派それぞれのサポーター
各党の党員・サポーターのほうが投票しに来る有権者よりも多いなんて!と他の投票立会人と笑い合ってしまったが、それでも8時10分頃になるとポツリポツリと有権者が現れ始めた。
一つの投票所で働く投票立会人は全部で7人、うち1人は代表で1人が副代表。この7人が朝7時半から夜9時まで交代で作業する。投票所には常に少なくとも4人(うち1人は代表か副代表)がいるようにシフトが組まれている。
4人のうち、2人は机に座る。1人は有権者に身分証明書を提示させ、選挙人名簿に名前があるかをチェック。選挙人名簿は住民背番号順になっているので、探すのは難しくない。名簿に名前があれば、もう1人が有権者から投票用紙の入った封筒を受け取り、投票箱に入れる。有権者が自分で票を投じるわけではない。この時、封筒に投票用紙が2枚入っていないかをチェック。私たちの投票所では今回の選挙で2人ほどそういう人がいたので、初めからやり直すよう指示した。

3人目は、教室の入り口に立って、やって来る有権者に投票の仕方を説明したり、投票用紙を入れる封筒を配ったりする。よくあるのは、自分がどの投票区に属するのかがわからない人。有権者には選挙管理委員会から事前に投票カードが送られており、そこには投票区の番号が書いてあるので、それを見ればすぐ分かる。しかし、投票カードを持参せずに投票所へやってくる人もたくさんいる。投票日当日の投票であれば、投票カードがなくても身分証明書だけで投票ができるからだ。本人が自分の投票区を覚えていればよいが、そうでなければ大変だ。既に書いたように、投票所として使われているこの学校は、3つの投票区の投票所となっているため、それぞれの教室を順に訪ねて、選挙人名簿に名前があるかどうかを確認する。どこにもなければ、市の選挙管理委員会に電話で問い合わせることになる。
4人目は、期日前投票で投じられた票の確認を担当する。期日前投票は投票日の18日前から全国で始まるが、自分の属する投票区に関係なく、全国の期日前投票所で投票ができる。期日前投票所は市役所や図書館など公的機関の建物のほか、人がよく集るショッピングセンターや駅、さらに大学などにも設けられている。そこで投じられた票が仕分けされ、その有権者が属している投票区の投票所に、投票日当日に配達されるのだ。もちろん、直前に投票された期日前投票は仕分けが間に合わないだろうし、実は、投票日当日にも開いている期日前投票所が全国に幾つかあり、投票区に関係なく投票できるので、そういう票は投票所には届けられず、即日開票でもカウントされない。その代わり、後ほど行われる数え直しの時にカウントされる。
さて、期日前投票の票が配達されるのは朝10時。それぞれの票は指定された封筒に入れられているわけだが、その封筒はさらに別の封筒に入れられており、ここでは有権者の個人が特定できるようになっている。そのため、期日前投票の票が本当にこの投票所に属しているのかどうかが確認できる。もし間違った投票所に届けられていれば、ミスとして選挙管理委員会に報告しなければならない。
期日前投票の票は、有権者個人の特定ができる封筒から取り出して無名化し、最終的に投票箱へ入れ、即日開票で一緒にカウントするわけだが、無名化し投票箱へ入れるのは、投票がすべて終わってからなのである。何故かと言うと、投票日当日に後悔票を投じることができるからなのだ。つまり、期日前投票を済ませたけれど、その後、気が変わったために別の党に入れるという人だ。そのような行為は、投票日当日に自分の属する投票所で可能だ。もし、そういう人がいれば、その人の期日前投票は無効にして、カウントしないようにするわけだ。
(長くなりそうなので、続きは次回)
この日は朝7時半から会場設営。会場は小学校の教室だ。
スウェーデンにおける今回の欧州議会選挙では、スウェーデンから20人の議員を選んで、EUの立法府の一つである欧州議会に送り出すわけであるが、この選挙では大選挙区・比例代表制が適用されている。つまり、スウェーデン全体を一つの選挙区とし、スウェーデン全体の得票率に応じて20議席を比例的に各政党に配分し、各政党はあらかじめ決めておいた候補者リストの上位から当選者を選んでいくのである(有権者が特定の個人を選んで繰り上げ当選させる制度も補完的にはある)。
投票のマネージメントは各コミューン(市)の選挙管理委員会が管轄しており、それぞれのコミューンをいくつの投票区に分けるかは一任されている。例えば、ストックホルム市は大きいので537の投票区があるが、私が今回、投票立会人として仕事をした市は38の投票区に分かれていた。スウェーデン全体で見ると、合わせて5837の投票区が存在する。
私が仕事をするのは、そのうちの1つだ。ただ、投票所として使われるこの小学校は、その周りにある他の2つの投票区の投票所にもなっており、別々の教室が使われているので、投票しに訪れた有権者が、自分がどの教室に行けば良いかがすぐ分かるように張り紙をすることが、会場設営の重要な仕事だ。
投票所となっている教室には、投票立会人が座る机と椅子を用意し、それから投票者のために台と衝立を設置する。そして、教室の入口には、各党の投票用紙を置く。スウェーデンの投票では、自分が票を投じたい党の投票用紙を一枚選び、指定された封筒に入れて封をした上で投票箱に入れる。

※ ※ ※ ※ ※
開場時間の朝8時になった。眩しい太陽が学校の校庭を照らし、今にでも外に飛び出したい気分だ。しかし、投票所には誰も来ない。数分ほどして心配になり、外に出てみたら、学校の入口にはそれでも数人いたが、それは投票しに来た人ではなく、各党の党員やサポーターだ。投票しに来た人に投票所の入り口で自分の党の投票用紙を配ることで、有権者に最後のアピールをするためだ。そのような形でのキャンペーンは投票日当日でも認められている。果たして、投票の直前に党員から笑顔で投票用紙をもらったからといって、その党に票を入れようと決心する人がどれくらいいるのか分からないが、スウェーデンでは投票日当日の一つの光景として定着している。

左派・右派それぞれのサポーター
各党の党員・サポーターのほうが投票しに来る有権者よりも多いなんて!と他の投票立会人と笑い合ってしまったが、それでも8時10分頃になるとポツリポツリと有権者が現れ始めた。
一つの投票所で働く投票立会人は全部で7人、うち1人は代表で1人が副代表。この7人が朝7時半から夜9時まで交代で作業する。投票所には常に少なくとも4人(うち1人は代表か副代表)がいるようにシフトが組まれている。
4人のうち、2人は机に座る。1人は有権者に身分証明書を提示させ、選挙人名簿に名前があるかをチェック。選挙人名簿は住民背番号順になっているので、探すのは難しくない。名簿に名前があれば、もう1人が有権者から投票用紙の入った封筒を受け取り、投票箱に入れる。有権者が自分で票を投じるわけではない。この時、封筒に投票用紙が2枚入っていないかをチェック。私たちの投票所では今回の選挙で2人ほどそういう人がいたので、初めからやり直すよう指示した。

3人目は、教室の入り口に立って、やって来る有権者に投票の仕方を説明したり、投票用紙を入れる封筒を配ったりする。よくあるのは、自分がどの投票区に属するのかがわからない人。有権者には選挙管理委員会から事前に投票カードが送られており、そこには投票区の番号が書いてあるので、それを見ればすぐ分かる。しかし、投票カードを持参せずに投票所へやってくる人もたくさんいる。投票日当日の投票であれば、投票カードがなくても身分証明書だけで投票ができるからだ。本人が自分の投票区を覚えていればよいが、そうでなければ大変だ。既に書いたように、投票所として使われているこの学校は、3つの投票区の投票所となっているため、それぞれの教室を順に訪ねて、選挙人名簿に名前があるかどうかを確認する。どこにもなければ、市の選挙管理委員会に電話で問い合わせることになる。
4人目は、期日前投票で投じられた票の確認を担当する。期日前投票は投票日の18日前から全国で始まるが、自分の属する投票区に関係なく、全国の期日前投票所で投票ができる。期日前投票所は市役所や図書館など公的機関の建物のほか、人がよく集るショッピングセンターや駅、さらに大学などにも設けられている。そこで投じられた票が仕分けされ、その有権者が属している投票区の投票所に、投票日当日に配達されるのだ。もちろん、直前に投票された期日前投票は仕分けが間に合わないだろうし、実は、投票日当日にも開いている期日前投票所が全国に幾つかあり、投票区に関係なく投票できるので、そういう票は投票所には届けられず、即日開票でもカウントされない。その代わり、後ほど行われる数え直しの時にカウントされる。
さて、期日前投票の票が配達されるのは朝10時。それぞれの票は指定された封筒に入れられているわけだが、その封筒はさらに別の封筒に入れられており、ここでは有権者の個人が特定できるようになっている。そのため、期日前投票の票が本当にこの投票所に属しているのかどうかが確認できる。もし間違った投票所に届けられていれば、ミスとして選挙管理委員会に報告しなければならない。
期日前投票の票は、有権者個人の特定ができる封筒から取り出して無名化し、最終的に投票箱へ入れ、即日開票で一緒にカウントするわけだが、無名化し投票箱へ入れるのは、投票がすべて終わってからなのである。何故かと言うと、投票日当日に後悔票を投じることができるからなのだ。つまり、期日前投票を済ませたけれど、その後、気が変わったために別の党に入れるという人だ。そのような行為は、投票日当日に自分の属する投票所で可能だ。もし、そういう人がいれば、その人の期日前投票は無効にして、カウントしないようにするわけだ。
(長くなりそうなので、続きは次回)