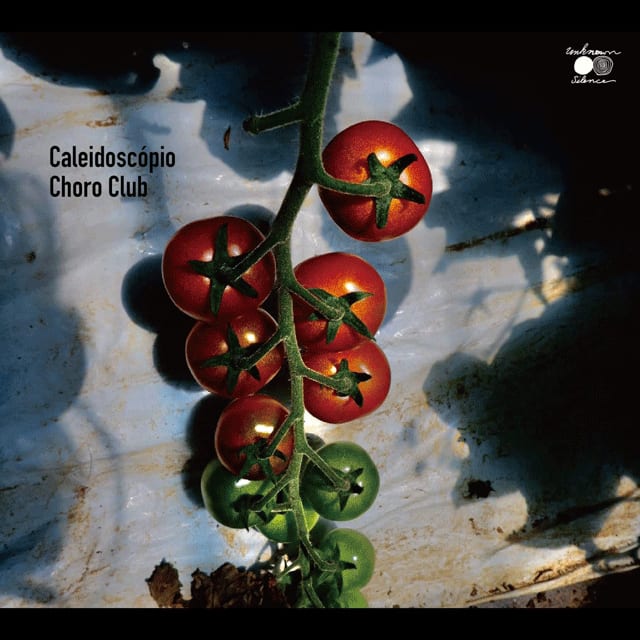自宅の水槽の「蓮」は花が今年2本目の蕾をつけた。水槽の中の蓮根を植える土は田んぼの土が良いと言われる、今はジョイフル本田で販売しているのでその土を使う、今年は初めて2本目の蓮の花である。
水面から高く伸びた花茎に咲く、ピンクや白、黄色の美しい花で、朝に開き昼に閉じる開閉運動を数日繰り返し、やがて散ります。泥の中から清らかな花を咲かせることから「清らかな心」や「神聖」を象徴する花とされ、仏教とも深く結びついています。花後には実の入った花托(かたく)が蜂の巣のように見えることが名前の由来です。蓮は植物のなかでも、もっとも古いもののひとつです。
調べると何と驚くことに、およそ1億4000万年前に、すでに地球上に存在していたといわれています勿論縄文人も見たのであろう。

又別名「蓮の実」形が良く似てるためじょーろの先の部分を指している。
仏教画では、よく仏陀が蓮の花の上に座っている姿が描かれています。これを蓮華座(れんげざ)と言うそうです、蓮の花は、泥水のような池の中から真直ぐに茎を伸ばし、その先に華麗な花を咲かせます。池から出てきても泥に汚れることはありません。このことから蓮の花は清らかさの象徴と考えられ、仏教では神聖な花とされてきました。また、泥を肉体に、蓮の花を浄化された魂に見立てたという説もあります。

翌日仕事依頼で文京区まで出かけた。11時頃の待ち合わせではあるが現場には到着したが駐車場が見当たらない。現場より若干離れた所に空きの駐車場を見つけ駐車した。
場所は文京区は有名な根岸時神社が近くにあり、現地調査を早めに切り上げ帰りは根岸時神社詣でを試ようと思った。

現場に到着するとクライアントから連絡あり1時間程遅れるので下見および現場の調査を始める、寸法等を計測し、打ち合わせを含め粗1時間30分ほどで終了するが此の時期外でも待機は暑く、随分補給は充分した。
予定通り根岸神社参拝に見学する、一般的には上野東照宮、湯島天満宮、神田神社、根岸神社訪問が良きコースになっていると言われるが、東京に25歳から会社に勤務しているが此の4社は一度も参拝した事がない。

先ずは神田神社(かんだじんじゃ)は、730年創建、創建1300年の節目を迎えるという非常に歴史の長い神社になります。730年、出雲系の氏族が当地に入植し、大己貴命を祖神として祀ったことがこの神社の始まり。935年に平将門の乱で敗死した平将門の首が京都より当地に持ち去られ、当社の近くに葬られました。14世紀後半に疫病が流行した際は平将門の祟りであるとして供養が行われ、彼は相殿神として祀られました。
続いて湯島天満宮(ゆしまてんまぐう)は、日本の最高学府・東京大学に程近い場所に鎮座する、言わずと知れた学問の神様『菅原道真(天神様)』をお祀りする神社。458年に雄略天皇の勅命で創建されたと伝えられる神社。1355年に菅原道真公を勧請しました。徳川家康の江戸入府以来、徳川家の信仰を集め、多くの学者や文人が訪れました。
有名な上野東照宮は、1627 年創建の東京都台東区上野公園に鎮座する神社です。江戸時代末期の戦いや、関東大震災、また先の世界大戦の中にも奇跡的に被害も受けず倒壊することなく残っている江戸時代初期の建築物として、国の重要文化財に指定されています。
以上の3社はその内に訪れようと思った。

今回は根津神社(ねづじんじゃ)は、文京区根津の地にあって、根津権現とも呼ばれる神社。
およそ1900年ほど前、日本武尊(やまとたけるのみこと)が創建したと伝えられています。東京十社の一つであり、災害や東京大空襲にも全ての社殿が焼失を免れた強運の神社とされています。

江戸時代初期の建築になる本殿や拝殿、楼門、唐門、透塀などは国の重要文化財に指定されており、春はつつじも有名な神社です。御祭神は、須佐之男命(スサノオノミコト)、大山咋命(オオヤマクイノミコト)、誉田別命(ホンダワケノミコト)で、相殿神は大国主命(オオクニヌシノミコト)と菅原道真公。今から千九百年余の昔日本武尊が東夷征定の途次、武神須佐之男命の御神徳を仰ぎ千駄木の地に創祀したと伝えられる古社で、文明年間(1469~87)には太田道灌が社殿を奉建しています。
駐車場が根津神社の裏側に位置したので裏から入り、山道を歩くと根津神社 千本鳥居根津神社が若い世代を中心に人気となったのが、摂社である乙女稲荷神社の千本鳥居です。有名な花はつつじ苑の奥、境内の西をずらりと朱色の鳥居が連なります。

3杯形式があるそうです、根津神社の千本鳥居は北から南へ抜ける形で鳥居をくぐるとご利益があると言われていますが、鳥居をくぐる際には、鳥居の手前で一礼し、神様の通り道である鳥居の真ん中を避けて左右どちらかの端からくぐるようにしましょう。帰る際も同様に、一礼してから鳥居の端をくぐり、神社の方向に向き直って一礼するのが正しい作法だそうです。

また此の地は当時イギリスから帰国した夏目漱石が、奇しくも鴎外の住んだ同じ家に引っ越してきた。彼も神社に来てはこの石に座り、作品の構想を練ったという。「吾輩はねこである」はまさにこの時期に発表された作品だ。
又当時友人正岡子規の入谷宅にも訪ねていたのであろう。この石が「文豪の石」と呼ばれている。この二人が住んだ家は現在犬山市の明治の館に移築されている。
最近此の様な神社の経営が大変資金不足で危機である様で、コンビニより多いと言われる神社が多く、土地を売って住宅に変えていたり、支那人に売ってしまっているそうである、神奈川の児玉神社(神奈川県藤沢市江の島にある日露戦争で活躍した明治時代の軍人・児玉源太郎を祀った神社である)も売買されたと聞くが事実かは不明である、実に嘆かわしきことでもある。
確かに江戸から文明開化から大統和戦争敗戦後の日本は実に情けない国になってしまった様で特に英国のウィンストン・チャーチル から誘惑され米国のドワイト・D・アイゼンハワーが日本との戦争を仕組まれたとも言われる、勿論日本は今だに独立国家ではない様です?

「千本鳥居」と言えば、京都の伏見稲荷大社が有名ですが、「ミニマムでもよいから千本鳥居」を体感したいなら、こちらがお手軽かと思いました。ちなみに日本語の千本はたくさんという意味です。
そこから入り口の随分立派な楼門(ろうもん)とは、寺社建築で用いられる二階建ての門の形式を指します。また拝殿は撮影禁止のため入り口唐門付近から撮影しました。

江戸幕府と言うより徳川家との影響が強く五代将軍徳川綱吉は兄綱重の子綱豊(六代将軍家宣)を養嗣子と定めると、家宣の産土神である根津神社にその屋敷地を献納、世に天下普請と言われる大造営を行こなったと言われる。時間を作りじっくり考察する価値はある様に思う。ブラボー!