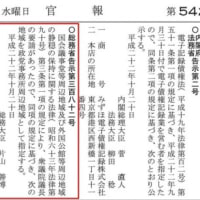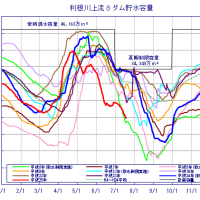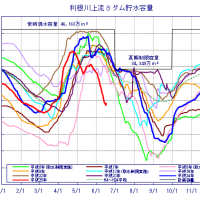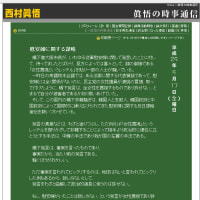故紙と古紙は、現代日本語ではバイスバーサ(vice versa)である。故紙の方が用例としては古く、古紙は表記の簡素化として(画数が少ない)、1956年頃の国語審議会や新聞業界の話合い以降、徐々に採用が進んだらしい。1969年のJISに「故紙」が初めて登場したが、79年版で「古(故)紙」となり、98年版で「古紙」となった。また通産省の統計で故紙が古紙に変わったのは1988年である。だから最近では古紙の用例が一般的になった(故紙も残っている)。
古紙の用例の登場はよく分からないが、昭和初期にはあったようだ。
さて元来は故紙のはずだが、これは反故紙の略記だろうか(多分そうだろうと思うが、自信はない)。反故にした紙とは、書き損じ、何らかの理由でだめにした紙ということで、まっさらの新品の紙と対比される。実は、「新紙」という語は広辞苑には載っていた。古紙と新紙なら、まことに対比がよろしいが、古紙の説明は「古い紙」とある(広辞苑など)。これでは意味が特定しにくい。「古い」とは、要するに「反故」と同義のような気もする。
話が曖昧でしょうがないが、反故とは、紙に下書きしたり、または書き損ね、あるいは修正の書き直しを別にする事などで、それまでは新しかった紙を「古い」ものとしてしまうことだと説明できる。
「故紙」には、使用して(しかも保存対象でない不要の)ゴミ(反故)にした(けど、なんらかの再利用のために取ってある)というニュアンスが込められている。「古紙」は、もっぱらリサイクル用語っぽく、再生紙の原料としての回収紙というニュアンスが込められている。裏を再利用する(ために取ってある)紙は、「故紙」が相応しい。同音異義語は使いづらいだろうけどね。
関連文献:「故紙と古紙」(財)古紙再生促進センター『会報』第29巻第4号、2003.7.31、pp.14-15.
#結論は逆っぽいけどね↑

古紙の用例の登場はよく分からないが、昭和初期にはあったようだ。
さて元来は故紙のはずだが、これは反故紙の略記だろうか(多分そうだろうと思うが、自信はない)。反故にした紙とは、書き損じ、何らかの理由でだめにした紙ということで、まっさらの新品の紙と対比される。実は、「新紙」という語は広辞苑には載っていた。古紙と新紙なら、まことに対比がよろしいが、古紙の説明は「古い紙」とある(広辞苑など)。これでは意味が特定しにくい。「古い」とは、要するに「反故」と同義のような気もする。
話が曖昧でしょうがないが、反故とは、紙に下書きしたり、または書き損ね、あるいは修正の書き直しを別にする事などで、それまでは新しかった紙を「古い」ものとしてしまうことだと説明できる。
「故紙」には、使用して(しかも保存対象でない不要の)ゴミ(反故)にした(けど、なんらかの再利用のために取ってある)というニュアンスが込められている。「古紙」は、もっぱらリサイクル用語っぽく、再生紙の原料としての回収紙というニュアンスが込められている。裏を再利用する(ために取ってある)紙は、「故紙」が相応しい。同音異義語は使いづらいだろうけどね。
関連文献:「故紙と古紙」(財)古紙再生促進センター『会報』第29巻第4号、2003.7.31、pp.14-15.
#結論は逆っぽいけどね↑