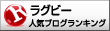1970年の大阪といえば万博(万国博覧会)だ。大阪市内とはいっても阪急電車の天六(天神橋六丁目)駅から比較的近くの場所に住んでいたこともあって、50回以上千里まで通い、めでたく(でもないか)全パビリオンを制覇した(ことは何の自慢にもならない)。83万人が入場した日には、家に帰るのが深夜なったことなどいろんな思い出がある。
さて、同じ頃の大阪では音楽ファンにとってメモリアルな出来事があった。万博の開幕に遅れること2週間、FM大阪が開局したのだ。本放送開始前から試験電波が発射されていて、開局を心待ちにしていたことを覚えている。それまでのFM放送はクラシック音楽中心のNHK-FMだけだったから、音楽ファンにとっては楽しめる音楽の幅がぐんと拡がった。それこそ、1日の番組表が頭の中に入ってしまうくらいに家に居ればずーっとラジオを聴いているような毎日だった。短波ラジオで海外からの電波をキャッチすること(いわゆるBCL)に熱中し始めたのもちょうどこのころ。
FM放送はAM放送に比べると音質が良くて雑音が少ないことから、音楽専門放送とも言われるくらいに音楽番組が充実していた。先の「初ECMの苦い想い出」でも書いたように、ジャズもかなり頻繁に耳にすることができたのだ。もっともFM大阪のジングル自体が4ビートジャズだったわけだが。最近の民放FMはじっくりと音楽を聴かせてくれる番組が減っているように感じる。今一番充実している音楽番組はラジオ深夜便の「ロマンティック・コンサート」ではないかと思ったりもする。
それはさておき、専門の番組ではなくても、時にとんでもないジャズがかかることもあったのが当時のFM放送の面白さ。例えばここで紹介するスタンリー・タレンタインの「ソルト・ソング」みたいな7分の曲がオンエアされたりする。ふと耳に飛び込んできたテナーサックスの音色。最初はゆったりとしたテーマだったのが、途中からテンポアップして白熱のソロとなり、気がつくと聴いている方も興奮の坩堝の中に居たのだった。何という曲で誰が演奏しているのだろう? 曲が終わった後に耳に飛び込んできたのがテナー・サックス奏者の名前とミルトン・ナシメント(ブラジル人)の名曲だったというわけ。
とはいっても、スタンリー・タレンタインのこともミルトン・ナシメントのことも知らなかった当時の私。すぐにレコード店に走ることもなく時は過ぎていったのだが、この演奏を耳にしたときの興奮だけはずっと記憶にとどめていた。そして、5年ほど経ち1980年代に入ったある日、ついにこの曲が入ったレコードを手にする。耳にしたのは、CTIレーベルから出ている『ソルト・ソング』のタイトルナンバーだったわけだ。
◆スタンリー・タレンタインの魅力とは
ジョン・コルトレーンやソニー・ロリンズといった両巨頭を筆頭に「猛者」がひしめくテナー・サックス界にあって、スタンリー・タレンタインは地味な存在かも知れない。また、70年代当時に大ヒットしたCCR(クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル)の「雨を見たかい?」をカバーするなどしたことからシリアスな(?)ジャズファンからは軽く見られていた面もあったのではないだろうか。
しかし、レコードを入手してタイトル曲以外も聴いてみると、タレンタインには他のサックス奏者にない大きな魅力があることに気づいた。それは、サム・テイラーに通じる(と書くと怒られそうだが)ソウルフルな歌心。これに尽きると思う。とくに、「アイ・トールド・ジーザズ」のようなゴスペルタッチの曲でそのことが顕著となる。「ソルト・ソング」のようなブラジルMPBの名曲でもけして泥臭くはならずに洗練された感覚で演奏できることも驚き。心の底から歌うことが好きな演奏家ということになるのかも知れない。
このアルバムには、タレンタインの他にもエリック・ゲイル(ちょっと大人しめ?)やリチャード・ティーも参加していていい味を出している。『ツァラトゥストラ』で一世を風靡したエウミール・デオダートのストリングス・アレンジもなかなか刺激的だ。タレンタインの他の作品は持っていないが、この1枚だけでも十分に満足できる内容に仕上がっている。
ジャズの歴史を振り返ってみると、その黄金時代は1930年代のスウィング・ジャズの時代。「スウィング」が社会現象となり、ボールルームやラジオを通じて大衆的な人気を勝ち得ていたのはおそらくこの時代だろう。それが、ダンスを失うことによりファン層が狭まったのがモダンジャズの時代。さらに、モードジャズからフリージャズへと先鋭化していく過程でコアなジャズファンもついて行けなくなった。踊れる要素だけでなく「歌」までも失ってしまったら、あとは死を待つのみ...
ここでエポックメイキングな出来事となったのは、1967年のコルトレーンの死ではないだろうか。ソ連崩壊のような現象がジャズ界に起こったのかも知れない。音楽ファンの支持という意味で死にかけていたジャズが「歌」を取り戻すことで復活を遂げる。その流れがロックビートや電気楽器の導入への道を拓き、新しいジャズを産み出す方向付けとなった。というのはもちろん手前勝手な妄想。
残念ながら、コルトレーンが亡くなったとき、私はまだジャズファンではなかった。仮に知っていたって10代の少年にはそんな時代の流れを感じ取る力があるはずもない。コルトレーンの死を前後して、ジャズを取り巻く雰囲気がどのように変わっていったのかをぜひ先輩諸氏にお聞きしたいところ。「ロックやエレキなんて」という辛口のご意見ばかりだったら耳が痛いが。70年代からジャズを聴き始めた私のような世代の人間とはジェネレーションギャップがあるのではないかと思っている。
◆CTIレーベルのジャズの魅力
70年代当時のジャズファンはどうしても、「自分たちは特別な存在」という意識を持ちたがる人が多かったように思う。ジャズ喫茶にしても、「エレキやロックはお断り」というお店があったし、『ヘッドハンターズ』やチャーリー・パーカーの演奏で有名な「ドナ・リー」をカバーした『ジャコ・パストリアスの肖像』のような「問題作」出る都度に、「認める」「認めない」の論争が巻き起こっていたように思う。
そんな中で、クロスオーバー/フュージョン(この言葉は個人的には好きではないのだが)がブームとなる5年以上も前に新しいサウンドを産み出していたCTIレーベルのレコードも批判の矢面に立つ場面が多かったように思う。ポピュラリティを勝ち得たことで「あんなのはジャズではない」といったような。でも、このレコードのように歌心に溢れる堂々たる演奏に真剣に耳を傾けたらそんなことも言っていられなくなるはずだ。もっとも真剣に聴かなくても、ちゃんと心の中にまで入り込んできてくれる音楽だけど。
「ソルト・ソング」のようなブラジル音楽にも確かな目配りがあるCTIレーベルにはそんな作品がたくさんある。また、ジャンルを問わず多くのミュージシャン達を魅了し続けているミルトン・ナシメントの音楽の素晴らしさについては、場を改めてじっくり書いてみたい。
デューク・エリントンの「音楽にはよい音楽と悪い音楽の2つしかない」というのは至極名言で、音楽を前にして、フュージョンだのジャズだのとフィルターをかけてしまうのは、とてももったいない聴き方のように思われる。
◆Stanley Turrentine “Salt Song”
1) Gibraltar (Freddie Hubbard)
2) I Told Jesus (Traditional adapted by Stanley Turrentine)
3) Salt Song (Milton Nascimento)
4) I Gaven’t Got Anything Better To Go (P.Vance / L.Pockriss)
5) Strom (Stanley Turrentine)
Stanley Turrentine : Tenor Sax
Ron Carter : Bass
Billy Cobham : Drums
Airto Moreira : Drums & Percussion
Eumir Deodado : Keyboards
Horace Parlan : Keyboards
Richard Tee : Keyboards
Eric Gale : Guitar
Recorded July, September 1971 at Van Gelder Studios
Produced by Creed Taylor