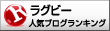マイルス・デイヴィスはジャズ入門者にとって避けて通れない最重要ミュージシャンの一人。最初に聴くべきアルバムとして挙げられるのはオリジナル・クインテット時代のマラソン・セッション(4枚)の中からの1枚になるだろう。そこから『カインド・オブ・ブルー』以降に行ってもいいし、『マイルストーンズ』や『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』へと時代を遡っていくのもいい。
でも、レアケースだが、時と場合によっては70年代以降の電化サウンドがマイルスとの最初の出逢いだったりすることもある。私にとって最初のマイルス体験は、1974年にリリースされた『ビッグ・ファン』だった。歴史的な名盤『ビッチズ・ブリュー』の陰に隠れて注目度も低いが、最初に耳にしたときのことはよく覚えている。
当時、民放FM局で夜の11時からの毎日30分間、CBSソニーレコード(米国のコロンビアレーベル)の新譜レコードを紹介する番組がオンエアされていた。番組名は「ミュージック・スコープ」でDJはケン田島さん。オープニングの7拍子の曲(デイブ・ブルーベックの「アンスクエア・ダンス」)がとくに印象に残っている。その番組から流れてきたのが新譜の『ビッグ・ファン』に収録されていた「グレイト・エクスペクテイションズ」だった。
これがなかなか刺激的だった。というのも、シタールやタンブーラといったインド音楽の楽器が使われていたから。ラヴィ・シャンカールが来日したことで、インド音楽に興味を持っていた頃だったことも大きかったように思う。2枚組LPのはずなのに、何故かこの曲ばかりが他の番組でも流されていた。他の曲で記憶にあるのは油井正一さんの『アスペクト・イン・ジャズ』で紹介された「ロンリー・ファイア」くらいで、「ゴー・アヘッド・ジョン」と「イフェ」の面白さを知ったのはもう少し後のことだ。
当然、興味は『ビッグ・ファン』(の購入)に向かうのだが、ダブルアルバム(2枚組)5000円也ということで手が届かず涙を呑んだ。とにかく世紀の傑作と謳われた『ビッチズ・ブリュー』やライブ盤などマイルスの70年代の諸作品は、ダブルアルバムが多くて手が出なかったのだ。そこで仕方なく手にしたアルバムが『イン・ア・サイレント・ウェイ』だった。
果たしてどんな音が飛び出すのだろうかとレコード盤に針を下ろした時に、終生忘れ得ぬ、後にも先にもこれ1回だけという希有の体験をすることになるから面白い。冒頭に飛び出したオルガン(ジョー・ザヴィヌル)のサウンドに不意を突かれ、短いギターのあとにトニー・ウィリアムスがハイハットで刻む軽快な16ビートのリズムが出てきた瞬間、全身に鳥肌が立ってしまったのだ。音楽を聴いていてこんなに気持ちよくていいのだろうか?と思ったくらい。
その後、場面を少しずつ変えながらマイルス、マクラフリン、ウェイン・ショーターのソロが続き、曲はフェイドアウトして終了かと思った瞬間、再びオルガンの音が聞かれ前半部分がリピートされる。ここで再び最初の興奮が蘇りさらに快適な時間が続く。曲が完全に終わった後、そのままB面には行かずに、もう一度A面の最初から聴き直したことを今でもはっきり覚えている。これでA面の Shhh/Peaceful の虜となり、最初の興奮を思い出したいがために何度も何度もターンテーブルに載っけた。というのはウソでトニーの刻むリズムに乗ってソロをとるマイルス他のプレイにすっかり引き込まれたというのが真相。
そんな風に何度も針を下ろしたA面とは対照的に、看板の “In A Silent Way” が入ったB面は当時あまり聴かなかった。後に、エレピで呪文のように唱えられる3小節周期のなだらかな下降系の和音が気になりだしてB面も聴くようになるのだが。B面もA面にヒントを得たかのような作り方で、面白いレコードだなと思いつつも、その生まれた背景にまで興味を抱くまでには至らなかった。

◆レコード誕生にまつわる驚きの舞台裏
時は少し流れて、このアルバムの制作過程には衝撃の事実があったことを知る。マイルスの専属プロデューサーだったテオ・マセロはインタビューで多くの録音テープにハサミを入れて編集したと語っているのだが、その最高レベルの成功例がこの作品だったのだ。1983年に刊行されたイアン・カー著の『マイルス物語』(小山さち子訳)に、このアルバムの録音からレコード完成に至るまでのプロセスが明かされていたのだ。
初参加にもかかわらずこのセッションで重要な役割を担ったジョン・マクラフリンのプレーをマイルスはそれまで一度も聴いていなかった。そして、「イン・ア・サイレント・ウェイ」の作曲者のザヴィヌルの参加も偶然の徒のような出来事だったのだ。朝にマイルスから電話がかかってきて、「今日はレコーディングをやるから遊びにきたらどうだ。」と誘われ、「ついでにいくつか曲を持って来いよ。」と言われた。著者は「マクラフリンのアンサンブルへの追加がほんの思いつきだとしたら、ザヴィヌルの参加は何かの間違いとしか思えなかった。」と書いている。
セッション終了から編集完了に至るまでのプロセスが、また驚愕の事実の連続だった。
(1) セッション終了後にマイルスとテオ・マセロの元には約2時間分の音楽が残った。
(2) マセロはそれをアルバム片面40分ずつ、計80分の音楽に落とした。
(3) その段階でマイルスが編集作業に加わり、片面を9分そこそこまで短縮し、「これで1枚だ。」と明言。
(4) これではアルバム半面にも満たないので、二人はセクションの一部を繰り返して時間の問題を解決した。
ある意味、姑息な手段により1枚のレコードができたわけだが、これが思わぬ大成功を導くことになるから面白い。結果論から言えば、映画では当たり前の作業(大胆なカットや前後の入れ替えと挿入)を音楽に適用してもおかしくはない。でも、クラシックに限らず、音楽の場合はどうしても「連続性が正」で「編集や多重録音は邪道」というイメージを持たれやすい。グレン・グールドのような音楽の作り方はあくまでも例外的とされていたような印象がある。
◆コンプリート・セッションのリリースでさらなる驚愕の事実が明らかに
時はさらに流れて、『イン・ア・サイレント・ウェイ』のコンプリートセッション(3枚組CD)が2001年に発売される。ここで、殆どすべてのことがあからさまになるわけだが、さらなる衝撃を受けることになる。
問題のシーンは2枚目のCDの後半に収録されている。さして魅力的とは思えないテーマに導かれて曲(Shhh/Peaceful)は始まる。ここから約20分間(イアン・カーの著書で明かされた40分の半分だが?)は、冒頭のテーマが橋渡し役となる形で、聴いたことがある場面と初めて聴く場面とが断片的に現れるといった構成。
なにやら、ロック(EL&P)や電子音楽(冨田勲)にも改作されて多くの音楽ファンのハートを掴んだムソルグスキーの『展覧会の絵』をイメージさせるような構成だが、テーマは「プロムナード」のような魅力には欠ける。そもそも曲全体がだらだらと流れている印象が強い。めでたく本採用となったマイルスやショーターのソロなど魅力的な場面はあっても、冗長という言葉がしっくりくるような仕上がりだ。
こんな事実を知ってしまうと、よけいにテオ・マセロとマイルスの二人による天才的な仕事ぶりに感嘆するしかない。確かにテープを繋いだ編集の痕跡は残っていても、一分の隙もない引き締まった内容の音楽に変貌を遂げているのだ。リズムをトニー・ウィリアムスが刻むハイハットのみにしたことも曲の統一感を高めることに大きく寄与している。
余談ながら、『コンプリート・セッション』の3枚組でもっとも魅力的な演奏が聴かれるのは、実は1枚目の『イン・ア・サイレント・ウェイ』よりも前の時期に行われたセッション。体調面で絶好調だったマイルスはもちろんのこと、ウェイン・ショーターも惚れ惚れするようなソロを聴かせてくれる。それをトニー・ウィリアムスのタイトで自由闊達なドラミングが支えている。ひとつ問題があるとすれば、この素晴らしい演奏をいったいどんな形で売ればいいのだろうか?ということになるだろう。
レコード原盤のライナーノーツに強調されている “NEW DIRECTION” の文字に象徴されるように、『イン・ア・サイレント・ウェイ』はマイルスの音楽作りに新たな方向性をもたらした重要作品だ。その後のマイルスの変貌ぶりの原点と考えれば、『ビッチズ・ブリュー』よりも大きな価値があるとも言える。そんな作品に「ダブルアルバム」の壁に拒まれたとはいえ、偶然接することができたことは、今にして思えばとても幸運なことだったと思う。
◆Miles Davis "In A Silent Wayl"
1) Shhh / Peaceful (Miles Davis)
2) In A Silent Way (Josef Zawinul)
3) It's About That Time (Miles Davis)
Miles Davis : Trumpet
Herbie Hancock : Electric Piano
Chick Corea : Electric Piano
Wayne Shorter : Soprano Sax
Dave Holland ; Bass
Josef Zawinul : Electric Piano & Organ
John McLaughlin : Guitar
Tony Williams : Drums
Recorded at Columbia Studio, NYC, February 18th, 1969
Produced by Teo Macero