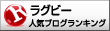今でこそジャズなくしては生きてはいけない身になってしまっているのだが、なかなか馴染むことができなかった音楽が、実はジャズだった。ピアソラは中学に上がる前に聴いていたのだから、ジャズにだって親しめたはずなのに何故だろう。
でも、偶然の徒によりもたらされた音との出逢いが、一夜にしてそんな私を熱狂的なジャズファンに変えてしまうのだから人生はわからない。70年代から本格的に音楽を聴き始めた私にとって、ラジオは最高の友達だった。とくに夜の静寂に流れてくる音楽には心に深く印象を刻みつけたものが多かったのだ。
深夜のラジオ番組の魅力のひとつは、時間の制約なしに音楽をたっぷりと聴かせてくれるところ。現在はKBS京都に名を変えて放送を続けている近畿放送に「ミュージック・オン・ステージ」というオールナイトの音楽番組があった。曜日によってジャンルが変わり、日曜日の深夜はジャズ。
翌日の授業や部活に差し支えるから滅多に聴くこともなかったのだが、受験勉強で夜更かしをしたとき、偶然にダイヤルがそこに合ってしまった。「今夜はジャズか...」ということで、数分後には心地よい眠りにつけるはずだった。
しかしながら、ラジオから流れてくるヴァイブラフォンの音色がとても心地よく、心の奥底までごくごく自然に染みこんでいく。ジャズを聴いていてこんな心地よい気持ちになったのは生まれて初めて。結局その夜は眠れなくなってしまい、LP2枚分の音楽にしっかりつきあってしまった。
そんな夜の静寂にラジオから流れてきたのはMJQ(モダン・ジャズ・カルテット)の『ユーロピアン・コンサート』に収録された音楽だった。ジャズ史上最強のコンボの誕生から5年余りの音楽を集大成した名盤としても名高く、当時は2枚に分けて発売されていた。写真の赤い部分を黄色に変えたものがVol.2というわけ。このアルバムは音がよいことでも評判を呼んでいる。このことは後に彼らの最高作とされる『フォンテッサ』を聴いたときに痛感させられることになる。
もちろんそんな能書きは後から知った話。その夜はあくまでも「音楽が先(ミュージック・ファースト)」だった。さらに言うと、その夜の主役は魅惑のヴァイブラフォン奏者で、名はミルト・ジャクソン。他の演奏者達のことはさっぱり覚えていない。ジョン・ルイスが実に味わい深いピアノを弾く人だと認識するまでにもかなりの時間がかかっている。
だから、私を素晴らしきジャズの世界(底なし沼とも言える)に導いてくれたのはMJQに間違いないが、ミルト・ジャクソンその人ということになる。それも、本当に無理のないごく自然な形で。
素晴らしい音楽といえば、コンサートホールやライブスポットといった「設定された場所」での出逢いがイメージされがち。でも、それが街中でも、風呂場でも、ベッドの中でもいいわけだ。特別なオーディオ装置から流れてくる必要もない。むしろ、まったく(音楽に対して)無防備な状態のときに勝手に耳に飛び込んできて、気がついたらそんな音の虜になってしまった自分が居る、といった形こそが最高の出逢い方と言えるのではないだろうか。
そういった意味からすると、スイッチを捻り、ダイヤルを回すだけで予期せぬ出逢いの場を提供してくれるラジオこそが最高のメディアではないかと思う。様々な形で忘れ得ぬ音と出逢ってきているが、印象深いものの多くはラジオからというのも十分に頷けるのだ。
◆The Modern Jazz Quartet "European Consert"
1) Django (John Lewis)
2) Bluesology (Milt Jackson)
3) I Should Care (S,.Kahn, A.Stordahl & P.Weston)
4) L Ronde (John Lewis)
5) I Remember Clifford (Benny Golson)
6) Festival Sketch (John Lewis)
7) Vandome (John Lewis)
8) Odd Against Tomorrow (John Lewis)
9) Pyramid (Ray Brown)
10) It Don’t Mean A Thing (Duke Ellington)
11) Skating In Central Park (John Lewis & Judy Spence)
12) The Cylinder (Milt Jackson)
13) 'Round Midnight (B.Hanighen, C.Williams & T.Monk)
14) Bag's Groove (Milt Jackson)
15) I'll Remember April (Gene de Poul, P.Raye & P.Johnson)
John Lewis : Piano
Milt Jackson : Vibraphon
Percy Heath : Bass
Connie Kay : Drums
Recorded in Scandinavia in April, 1960