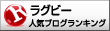勤務先が(国技館のある)両国のため、浴衣姿の力士達とは日常的に遭遇する。駅の周りにはちゃんこ料理店も多く、細い路地だが「横綱横町」があったりして、ここは相撲の町そのもの。
しかし、そんな場所に週5回は通っているのに、力士が浴衣を脱いだ姿を生で見たことはない。なんてことはない、そもそも国技館で相撲を観たことがないのだ。
しかし、つい先日、ひょんなことから力士の肉体の素晴らしさを知ることになった。場所は国技館ではなく、国技館のすぐ近くにある土俵のあるお店。京都の学会に出席するために来日した先生をもてなすためにセレクトしたお店。土俵上では相撲に因んだ様々なパフォーマンスが行われていたなかで、「力士」も「物まね」などで活躍していたのだった。
件の力士だが、身体は小さく(といってもプロップ体型だが)どのレベルまで上がった人かは不明。でも、身のこなしを観ていると、どこかの部屋に入門していたことは間違いない。引き締まった肉体の美しさもさることながら、身体(とくに膝などの下半身)の柔らかさが際立っていた。なるほど、淀みなく相撲の型を決めるためには、柔軟な肉体を持っていなければならないわけだ。そうでなければ、座った状態で満足に歩くことも出来ないだろう。
ここで、ふと思った。相撲選手も鍛え抜かれた肉体を持つアスリートだということ。だいいち、150キロを超えるような身体でありながら、激しくぶつかりあい、動き回ることが出来ること自体、常人には想像も及ばない世界なので。
本題に入る。ほんのちょっとした力士(経験者かもしれない)の身のこなしを見るに付け、ラグビー選手は果たしてアスリートなのだろうか?という疑問が沸いてきた。確かに、試合になれば80分間走り回るスタミナが必要だし、タックルやブレイクダウンなどの局面では当然身体も張る。世間一般的には間違いなく運動選手だろう。
しかし、100mを10秒台で走るとか、とびきりアスリートがラグビー界には何人居るだろうか。パワーはもとより、身体の柔軟性だって、力士には適わないのではないだろうか。見た目だが、総じてラグビー選手の身体は硬いような印象を受ける。それだけが原因ではないにしても、故障者が多かったり、タックルの姿勢が高かったりするのを見ているとそう思ってしまう。
日本でもアスリートの宝庫となっている野球にしても、イチローのようにウォーミングアップを見ただけでも柔軟な身体を持っていることははっきり分かる。ラグビーは何度も見ているはずなのに、「身体が柔らかそう」とか「身のこなしが軽そう」という選手を殆ど見かけないのが寂しい。もちろん、わざわざそれを見せる必要もない訳だが、ちょっとしたところから垣間見ることもできるのが選手の身体能力。
では、なぜアスリートなのか。日本のラグビーの人気を高めるためには、「この選手のプレーを観たい」というファンを増やすことが重要であり、その答えがアスリートによる魅力的なプレーではないかと考えているから。
五輪競技となったセブンズは、トップアスリート達の眼をラグビーに向けさせるために格好の武器になるはずだった。しかしながら、アスリートをラグビーに呼び込む作戦は殆ど成功していない(ようにみえてしまう)現実を考えると、なかなか道は険しそうだ。
しかし、そんな場所に週5回は通っているのに、力士が浴衣を脱いだ姿を生で見たことはない。なんてことはない、そもそも国技館で相撲を観たことがないのだ。
しかし、つい先日、ひょんなことから力士の肉体の素晴らしさを知ることになった。場所は国技館ではなく、国技館のすぐ近くにある土俵のあるお店。京都の学会に出席するために来日した先生をもてなすためにセレクトしたお店。土俵上では相撲に因んだ様々なパフォーマンスが行われていたなかで、「力士」も「物まね」などで活躍していたのだった。
件の力士だが、身体は小さく(といってもプロップ体型だが)どのレベルまで上がった人かは不明。でも、身のこなしを観ていると、どこかの部屋に入門していたことは間違いない。引き締まった肉体の美しさもさることながら、身体(とくに膝などの下半身)の柔らかさが際立っていた。なるほど、淀みなく相撲の型を決めるためには、柔軟な肉体を持っていなければならないわけだ。そうでなければ、座った状態で満足に歩くことも出来ないだろう。
ここで、ふと思った。相撲選手も鍛え抜かれた肉体を持つアスリートだということ。だいいち、150キロを超えるような身体でありながら、激しくぶつかりあい、動き回ることが出来ること自体、常人には想像も及ばない世界なので。
本題に入る。ほんのちょっとした力士(経験者かもしれない)の身のこなしを見るに付け、ラグビー選手は果たしてアスリートなのだろうか?という疑問が沸いてきた。確かに、試合になれば80分間走り回るスタミナが必要だし、タックルやブレイクダウンなどの局面では当然身体も張る。世間一般的には間違いなく運動選手だろう。
しかし、100mを10秒台で走るとか、とびきりアスリートがラグビー界には何人居るだろうか。パワーはもとより、身体の柔軟性だって、力士には適わないのではないだろうか。見た目だが、総じてラグビー選手の身体は硬いような印象を受ける。それだけが原因ではないにしても、故障者が多かったり、タックルの姿勢が高かったりするのを見ているとそう思ってしまう。
日本でもアスリートの宝庫となっている野球にしても、イチローのようにウォーミングアップを見ただけでも柔軟な身体を持っていることははっきり分かる。ラグビーは何度も見ているはずなのに、「身体が柔らかそう」とか「身のこなしが軽そう」という選手を殆ど見かけないのが寂しい。もちろん、わざわざそれを見せる必要もない訳だが、ちょっとしたところから垣間見ることもできるのが選手の身体能力。
では、なぜアスリートなのか。日本のラグビーの人気を高めるためには、「この選手のプレーを観たい」というファンを増やすことが重要であり、その答えがアスリートによる魅力的なプレーではないかと考えているから。
五輪競技となったセブンズは、トップアスリート達の眼をラグビーに向けさせるために格好の武器になるはずだった。しかしながら、アスリートをラグビーに呼び込む作戦は殆ど成功していない(ようにみえてしまう)現実を考えると、なかなか道は険しそうだ。