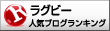ブラジル出身の歌姫、フローラ・プリムは私がほぼリアルタイムで追いかけている大切なミュージシャンのひとり。最初の出逢いがサンタナの『ウェルカム』だから、もう40年も経っていることになる。彼女名義のアルバムはすべて手元にあり、今はひたすら新譜を待つ状態なのだが、とびきりの1枚は最初に手にしたこの『ストーリーズ・トゥ・テル』。とても、幸運な出逢いだった。
(フローラ・プリムは本来フローラ・プリンと呼ぶべきかもしれない。Antonio Carlos Jobimが「アントニオ・カルロス・ジョビン」なのと同じ。でも、我が最愛の人を「プリン」ちゃんと呼ぶのはちょっと忍びないので、ここではプリムとしておこう。)
フローラと初めて「逢った」のは上でも書いたように、ゲスト参加したサンタナの『ウェルカム』だった。地味な役割ながら同じく『不死蝶』にも参加している。また、同じ頃にはチック・コリア&RTF(Return To Forever)のメンバーの一員として来日公演も果たしている。しかしながら、「カモメのRTF」として多くのファンの心を掴んだアルバムを手にすることもなく、その頃はとくに気になる人という訳でもなかった。
しかしながら、ひょんなことから「ぞっこん」になってしまうから面白い。それもサンタナのお陰。当時のサンタナは『不死蝶』をリリースした後、なかなか新しいレコードを出してくれない。欲求不満のような状態に陥っていたときにレコード店で見かけたのが、発売されたばかりの『ストーリーズ・トゥ・テル』だった。もしレコードの帯に「サンタナ」の文字が踊っていなかったら、今もフローラは「RTFに参加した一風変わったヴォーカリスト」のままだったと思う。
ところが、頼みのサンタナは1曲のみの参加で、しかも昔のワイルドなサンタナではなくなっている。当初はなんだかがっかりだなぁという気分でレコードに針を下ろしていた。でも、このアルバムの主役はあくまでもフローラなのだ。初な少年にはちょっと刺激的なジャケットを眺めながら聴いているうちに、いつしかフローラの歌声の虜になっている自分が居たのだった。
このアルバムにはサンタナの他にも個性的なミュージシャン達が名を連ねている。ジョージ・デューク(キーボードとシンセサイザー)、アール・クルー(ギター)、アイルト・モレイラ(フローラの夫君、パーカッション)、キング・エリソン(コンガ)を基軸(?)として、曲ごとに少しずつメンバーが替わる。ところが、クレジットが最高レベルにわかりにくい。「曲Aと曲BにはXとYとZが参加している。ただし、曲BにはYは参加していない...」といった具合。省スペースを目指していたのだろうが、それならば普通に1曲ずつ参加メンバーを表記してくれたほうがよっぽどすっきりする。ちなみに、こんなクレジットを見たのはこのアルバムが最初で最後となった。
肝心なメンバーの話に戻る。ベースはロン・カーターとミロスラフ・ヴィトウスが弾き分ける形。後者にとっては貴重なエレキ・ベース時代の記録とも言える。そういえば、ギターとベースが一体化した文字通りのベースギターを駆使して、『マジカル・シェパード』というアルバムを出したのもこの頃だ。ソロイストはジョージ・デューク(シンセ)やサンタナの他にはラウル・ジ・ソウザ(トロンボーン)とオスカル・カストロ・ネヴェスが主だったところ。
そして収録曲だが、ACジョビン、エドゥ・ロボ、ミルトン・ナシメントといったブラジルの定番作曲家達の作品がある一方で、マッコイ・タイナーやジョージ・デューク、そしてヴィトウスの曲も入っているといった具合。メンバーや曲のことをあれこれ書いているだけでも、とりとめのない作品のように見えてしまう。とても1枚のレコードの中で仲良く同居できるような雰囲気は、文字からは伝わってこない。
ところが、レコードを聴いていると、様々なタイプの曲が一連の流れの中で調和して耳に入ってくるから面白い。そう、この異種混合のブレンド感覚こそがフローラの魅力だということに気づく。中心は10曲中6曲を占めるブラジル人の手になる曲なのだが、そこにヴィトウスが参加したシンセ多用の宇宙志向の曲があり、またそれが絶妙なスパイスにもなっている。最初は馴染めなかったサンタナとヴィトウスとフローラが共演した作品(シルバー・スウォード)も、何度か聴いているうちに味わいが出てくると言った感じ。
しかし、この曲のハイライトはなんと言ってもA面2曲目のジャジーな「サーチ・フォー・ピース」だと思う。マッコイ・タイナーが書いた美しい曲にフローラが詩を付けたしっとり系の感動的なトラック。ここで、アコースティックピアノを弾いているのは意外にもジョージ・デュークで、ソロがまた味わい深い。どうしても甘ったるさを感じさせるシンセのサウンドとのギャップに悩んでしまうくらいだ。名手ロン・カーターのサポートもツボを心得ていて、総合的に見てもフローラのベストではないだろうかという想いが聴く都度に強くなっていく。
フローラの歌の特徴は、6オクターブにも及ぶ音域を駆使した器楽的な唱法。しかし、この「奇声」とも捉えられかねない声こそがフローラの敬遠される要素となったかもしれず、また、フローラ自身の声を痛めることにもなったのではないだろうか。フローラは2001年に俊英ピアニストのクリスチャン・ジェイコブを得てリリースした「パーペチュアル・エモーション」でも「サーチ・フォー・ピース」を録音しているが、デリケートな歌唱の魅力は断然こちらの録音の方が上なのでそんなことを考えてしまう。
フローラが70年代に残したアルバムは全部で9枚ある。ベートーヴェンの交響曲のように9つの性格を持つといってもいいくらいに、どれもが個性がキラキラしていて魅力的だ。しかし、私的ベストはこの『ストーリーズ・トゥ・テル』で次点は最後の『キャリー・オン』になる。いずれにせよ、チック・コリア&RTFに参加したことで知られるヴォーカリストで終わらせてしまうのは惜しい。80年代以降のアイルト・モレイラとタッグを組んだ作品群など充実している。
終生の恋人という私的感情は別にしても、「再評価」があってしかるべきヴォーカリストではないかという想いを捨てきれないでいる。
◆Flora Purim “Stories To Tell’”
1) Stories To Tell (Vitous-Purim-Coppola)
2) Search For Peace (Tyner-Purim)
3) Casa Forte (Edu Lobo)
4) Insensatez (Jobim-De Moraes)
5) Mountain Train (Hood-Purim)
6) To Say Goodbye (Lobo-Hall)
7) Silver Sword (Miroslav Vitous)
8) Vera Cruz (Nascimento-Hall)
9) O Cantador (Filho-Motta)
/ I Just Want To Be Here (Purim-Duke-Errison-Moreira-Vitous)
Flora Purim : Vocal
George Duke : Keyboards & Synthesizers
Larry Dunlop : Piano
Earl Klugh : Guitar
Oscar Castro Neves ; Guitar
Carlos Santana : Guitar
Ernie Hood : Zither
Ron Cartar : Bass
Miroslav Vitous : Bass & Synthsizers
Airto Moreira : Drums & Percussion
King Errisson : Congas
Raul de Souza : Trombone solo
Oscar Brasher : Flugelhorn
George Bohanon : Trombone
Hadley Caliman : Flute, Alto Flute
Recorded at Berkeley CA, May & July 1974
Produced by Orrin Keepnews