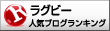『カフェ・コン・レチェ』で(ひっそりとではあるが)高らかに「アフロ・ペルー・ジャズ宣言」を行い、ジャズワールドへと羽ばたいたリッチー・セーロン。どこか(アフロ・ペルー・ジャズの存在を世界にアピールするといったような)使命感も漂う少し肩に力が入った実質的なデビュー作(*)に比べると、第2作はセーロン自身がやりたいことを鏤めた自画像のような作品といえる。
(*)リッチー・セーロンは1982年に処女作となるアフロ・ペルー・ジャズのLP ”Portraits In Black & White” をリリースしている。同作品は、2007年に “Landologia” (Songosaurus 724786) として復刻された。
さて、リッチー・セーロンは永らく年齢不詳の人だった。女性アーティストの場合は、生年(月日)を明らかにしないことはお約束ごとみたいなものだが、男性アーティストの場合は珍しい。とくに深い理由はあったのだろうか。手がかりは母親がピアノ好きのブラジル人であり、幼少時代に子守歌代わりにジョビンの音楽を聴いていること、ジミ・ヘンドリックスやサンタナのギターサウンドに魅せられたこと、80年代前半にチャブーカ・グランダに逢っていることなどを総合すると、50年代前半の生まれではないかと推測していた。ちなみに父親はユダヤ系のアメリカ人で音楽的な素養は持ち合わせていなかったようだ。
しかし、ひょんなことからリッチー・セーロンの生年月日が判明した。ネット上で見つかったバイオグラフィーに1954年12月生まれと記載されていたのだ。だから、この作品は42歳になる前にリリースされたことになる。10年遡ってリリースされた処女作がフュージョンカラーが強い作品であることを考えると、その後10年を経たジャズのスタイルの変貌を “Café Con Leche” を通じて考察することも面白いと思う。そのことについては追って触れてみることにしたい。
♪ジミ・ヘンドリックスとアフロ・キューバン・ジャズの幸福な結婚
ギターが「ナスカの地上絵」になった素敵なジャケットが目を引くこの作品。リッチー・セーロンはギターフリークだったが、米国で音楽と同時にウェブ・デザインを学んだアーティストでもある。そんなセーロンの最大のアイドルはジミ・ヘンドリックスだった。おそらく20世紀の音楽シーンで10本の指に入る偉大な音楽のひとり。リッチー・セーロンは、そのジミの音楽をいつの日かラテンジャズスタイルでやってみたいという強い願望を持っていた。
しかし、この「構想」に対して異を唱える人はいても賛同する人は皆無だったようだ。「そんなのうまくいくわけない。」と言った周囲の反対を押し切って「結婚」に踏み切ったのだが、結果はこのアルバムのハイライトをなす2つの作品として収録されることになった。オープニングを飾る「ファイアー」はチャチャチャで、そして、4曲目の「パープル・ヘイズ」はソン・モントゥーノとして見事にアフロ・キューバン系のラテンジャズ作品として鳴り響く。ギタリストの「どうだ!」という誇らしげな顔が目に浮かぶようだ。
思い起こせば、サンタナはジミヘンに憧れてブルース・バンドを結成し、ラテンロックの金字塔を打ち立てた。サンタナの例を挙げるまでもなく、ラテンビートでもチャチャなどのアフロ・キューバン系の4つで刻まれるリズムはロックビートとの相性は悪くない。世間一般的にはかけ離れた存在だったジミヘンのロックギターとラテン・ジャズは、セーロンの頭の中ではけして異質なものではなく、一体化されていたことになる。もちろん、サンタナに勇気づけられた部分もあったことだろう。
♪ラテン・ジャズの地平線をさらに南へと拡げる様々な試み
衝撃的な「ジミヘン」に隠れがちだが、この作品は「アフロ・ペルー」に留まらない様々な試みが満載の野心作となっている。2曲目の「メレンバップ」はドミニカ共和国のメレンゲのリズムに乗って、ビバップでお馴染みのフレーズが繰り出される(ジャズファンなら)むふふの作品。9曲目の「サンバ・トレーン」はサンバとコルトレーンの合体で、リッチー・セーロンの盟友ジョージ・ガゾーンが印象的なソロを聴かせてくれる。もちろん、リッチー自身ももう一つの母国ブラジルへの熱い想いを込めてアコースティック・ギターソロを披露する。
10曲目のエリントン・ナンバー「イン・ア・センチメンタル・ムード」ではタンゴで郷愁を誘い、11曲目にはアコーディオンが大活躍するコロンビアのヴァジェナートを登場させる。さらに12曲目の「ミッション・マリネラ」は「スパイ大作戦」のテーマをもじったような5拍子のマリネラ。そういえば、TVドラマ「ミッション・インポッシブル」の音楽を担当したラロ・シフリンも南米アルゼンチンの出身だった。ここでは海岸の音楽マリネラの特徴のひとつとなっているブラスバンドを入れることも忘れていない。
♪魅力溢れる共演者達
録音場所やメンバーが異なる3つのセッションが混在した『カフェ・コン・レチェ』に比べると、「固定メンバー」で演奏されている『ナスカ・ラインズ』は、バラエティに富んだ内容にもかかわらず落ち着いて愉しめる作品に仕上がっている。『チルカーノ』のリーダー、ホセ・ルイス・マデュエニョがキーボードを担当し、ベースもリーダーと同郷のオスカル・スタニャロ。ただし、ドラマーにはアレックス・アクーニャ(ここではパーカッションを担当)ではなく、キューバ出身の達人イグナシオ・ベローアを起用したのはジミヘン作品を録音することを念頭に置いたからだろう。
第1作目で「アフロ・ペルー・ジャズ宣言」を行い、第2作目で自身のルーツと目指す音楽を思う存分披露したリッチー・セーロンは、第3作目でいよいよ自らが思い描く「サウス・アメリカン・ジャズ」のスタイルを完成へと導くことになる。
RICHIE ZELLON “THE NAZCA LINES” (Songosaurus 724773) -1996-
1) Fire (Jimi Hendrix) – cha-cha/Cuba -
2) Merenbop (Richie Zellon) -merengue/Dominican Repubric-
3) The Wind Cries Jimi (Richie Zellon)
4) Purple Haze (Jimi Hendrix) –son-montuno/Cuba
5) The Wind Keeps Crying Jimi (Richie Zellon)
6) The Nazca Lines (Richie Zellon) -festejo/Peru-
7) Bromeliad Prelude (Richie Zellon)
8) Dance of The Bromeliad (Richie Zellon) –lando/Peru-
9) Sambatrane (Richie Zellon) –bossa-samba/Brazil
10) In A Sentimental Mood (Duke Ellington) -tango/Argentina-
11) The Moon Over Medellin (Richie Zellon) –vallenato/Colombia-
12) Mission Marinera (Richie Zellon) –marinera/Peru-
13) Johnny Chango (Richie Zellon) –festejo/Peru-
14) Dance of The Bromeliad (short version)
Richie Zellon : Guitars (Peru)
George Garzone : Tenor & Soprano Sax (USA)
Jose Luis Madueno : Piano (Peru)
Oscar Stagnaro : Bass (Peru)
Ignacio Berroa : Drums & Timbales (Cuba)
Alex Acuna : Congas, Bongos, Timbales, Cajon & Shekere (Peru)
Eddie Marshall : Flute, Bass Clarinet & Baritone Sax (USA)
Paul Butcher : Trumpet (USA)
Dan Jordan : Tenor Sax (USA)
Hamilton Sanchez : Baritone Sax (USA?)
John Allred : Tuba (USA)
Recorded at “The Studio”, Orland, Florida, January 1996
Produced by Richie Zellon