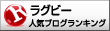2015年3月2日は日本のラグビー界にとって重要な1日になったではないだろうか。2019年に日本で開催されることが決まっているラグビーW杯の開催場所が決まったのだが、この日初めてラグビーファン以外の人が日本で世界3大イベントのひとつに数えられる国際大会が開催されることを知ることになったかもしれないから。
普通なら日本で開催されることが決まったときが一番盛り上がるはずだ。2002年のサッカーのW杯がそうだし、2020年の東京五輪もそう。ラグビーがそうならなかったのは、このスポーツが日本でおかれている地位を率直に反映したものだが、ラグビーファンとしては残念という他ない。しかし、たとえどんな形であれ、「2019もある」ということが多くの人のメモリーにインプットされたはずと思うと、「会場決定」というイベントも意味があった。あとは、ラグビー関係者が頑張るしかない。
当日の会場決定の発表はインターネットのストリーミングで観ていたが、実はハラハラどきどきだった。ポイントは1点、私的には日本一のラグビー場だと思っている熊谷ラグビー場がセレクトされるかどうかに尽きた。よもや権威筋がラグビー場としての機能が整った熊谷を外すことはないと思っていたが、発表を前にして日本側と主催者側(ワールドラグビー)の間に会場数についての意見の食い違いがあることが発覚する。12会場を前提に15の候補地を決めた日本側に対し、主催者側は予算負担の増加を懸念して10会場に絞りたいという意向を示した。
仮に10会場となると、競技場としてはまったく問題がない熊谷も収容人数で見劣りがするから外れる可能性が高くなる。発表前の15会場の紹介を見るに付け、そんな不安が現実的なものとなっていった。そして、いよいよ発表。札幌の次に釜石がコールされ、次がもし仙台だったら熊谷はアウトだなと覚悟した。しかし、発表者が熊谷をコールする前にアシスタントの女性が「クマガ~ヤ」と呟いてしまう。まだ早いよとの制止にもダメ押しで「クマガ~ヤ」だから笑ってしまった。緊張が一気に解けたというよりも何だか拍子抜けだが、無事熊谷が選ばれたことで安堵した。あとで出てきた話では、熊谷は当落線上で10なら確実にアウトだったということらしい。
選ばれた12会場のうち、「ラグビー場」の名前が付くのは、新設の釜石を含めて3つだけだ。だから熊谷が選ばれないのはおかしいと思い、観戦の度に署名もしていたわけだが、少しは役に立ったのかも知れないと思うと嬉しい。
しかし、では何故熊谷なのだろうか。アクセス面で評判が芳しくないことは百も承知だ。私自身は埼玉県民なのでマイカーで1時間あれば行けるが、それも理由にはならない。永年ラグビー観戦を続けていて、ラグビーの醍醐味を味わうという意味で熊谷が最高の場所だと感じていること。そのことが熊谷を日本一のラグビー場だと感じさせる理由のすべてということになる。もちろん日本全国のスタジアムを隈無く回ったことはないので日本一ではないかも知れないが、少なく見積もっても日本最高のひとつではないかと思っている。

◆ラグビー観戦のベストポジションはどこか
ラグビー観戦で観客席に座るときにいつも迷うのはどこに座って観戦するかといいうこと。ピッチ上で起こっていることを実感したいなら絶体に前だと思う。それもせいぜいシートの3列目くらいまで。選手の身体の大きさを実感しながら、プレーごとに変わっていく表情を見ているだけでも迫真に迫る思いがする。それが、1列1列と後ろに下がるにつれて選手達から発せられるオーラのようなものが確実に薄れていき、10列目くらいになってしまうとピッチの上は既に別世界のような感覚になってしまうから不思議だ。
しかし、前の方での観戦には大きな問題がある。選手目線(選手の感覚)でラグビーを観ると言うことは、全体の組織的な動きが選手に被ってしまうので見えなくなってしまうことと同じ。戦術に根ざした組織の戦いになっているラグビーではこれも致命的だ。その解決策として、中央ではなく22mライン付近の前の方で観る方法がある。確かにこれだと組織的な動きは見えやすくなる。しかし、当然のことながら遠い反対サイドのプレーは分かり辛い。
分身の術が使えない以上、永遠に答えが出そうにない中で、結局はHWL付近のスタンドの10列目くらいのところに座るというのが(ベストではないが)ベターということに落ち着きそうだ。そうなってくるとあとはラグビー場のスタンドの構造に委ねるしかない。そう気づいたとき、「ベストの競技場はどこか?」ということで出た答えが、実は一番たくさん来ている熊谷ラグビー場ではないかということになったのだった。

◆なぜ熊谷ラグビー場は最高なのか
熊谷ラグビー場のスタンドの設計はかなりユニークと言える。それを一番感じるのはメインスタンドの緩めに付けられた勾配。上で書いた話ではないが、ピッチまでの距離と全体の見えやすさを考えるとスタンドの勾配はきつめにした方が有利だと思う。ジュビロ磐田のスタジアムは特別としても、秩父宮もメインスタンドもそうなっている。そして、勾配に関しては、おそらく三ツ沢球技場が見やすさの面でベストだと思う。
しかし、勾配がきつめの場合にも問題がある。それはスタンドがセパレートされた感じになり、競技場全体の一体感が失われがちになること。あくまでも私的な感覚なのだが、ピッチ上はよく見えても観客席が見渡せなくなることにその原因があるのではないかと考えられる。もちろん、それでいいと言う人の方が多いと思うが、プレーの一つ一つに対する観客のリアクションを感じることも生観戦の醍醐味のひとつだと思っているので、そんな感情を抱いてしまう。「熱気」はピッチ上からだけでなく、スタンドの中からも発するわけでそれをしっかりと感じたい。
そんなことを思った時、熊谷のスタンドの緩めに付けられた勾配こそが「一体感」を感じさせてくれるという意味でベストではないかと(今更だが)気づいた。例えば中央席のエリアの端の方に座っても、反対サイドのリアクションがしっかりと伝わってくるのが熊谷のよさだと思う。ノーサイドの精神は、ピッチ上だけでなく、スタンドの観客席でも感じたいもの。だから、世界最高峰のラグビーが一部だけでの熊谷で開催されることになったことを率直に喜びたい。
W杯の会場に選ばれたことで、今後熊谷ラグビー場は最大3万人規模まで観客席を増やすことが決まったようだ。また、屋根も増設されることだろう。初秋は猛暑で冬は赤城おろしの冷風に悩まされてきたファンとしては嬉しい。しかし、屋根付きになるとどうしても閉塞感が出てしまうことも気になる。上で書いたような熊谷固有といってもいい良さが失われないような形での改修を期待したい。

 | 田中史朗と堀江翔太が日本代表に欠かせない本当の理由 ~最強ジャパン・戦術分析~ (ラグビー魂BOOKS-1) |
| 斉藤 健仁 | |
| ガイドワークス |