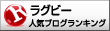1970年代の前半に限定、アルバムで言うと1作目の『デビュー』から6作目の『不死蝶』までではあるけれど、熱烈なサンタナファンであったことに変わりない。とくにリアルタイムで接した4作目の『キャラヴァンサライ』から『不死蝶』までのレコードは何回も聴いている。
しかし、「哀愁のヨーロッパ」が入った『アミーゴス』で熱が冷めてしまい、それから長い長い年月が経っていた。そんな「オールドファン」を冬眠状態から目覚めさせてくれたのがNHKラジオ深夜便の「ロマンティック・コンサート」だった。サンタナ特集で取り上げられた「エヴィル・ウェイズ」(1作目の収録)がとっても格好良く心に響いたのだった。
それ以来、懺悔の気持ちで「ビフォア・キャラヴァンサライ」の3作を聴き直し、そしてデビュー前の『ジ・アーリー・サンフランシスコ・イヤーズ』と銘打たれた3枚組のCDボックスも手に入れてしまった。1968年のフィルモアでのライブと1969年のスタジオ録音を収めたアンソロジー集で、「サンタナ・ブルース・バンド」と名乗っていた頃の最初期の演奏を聴くことができる。
正直、今までいったい何を聴いてきたのだろうかというくらいに新たな発見がいくつもあってすっかり参ってしまっている。でも気がつかないでいるよりはいいかなとも思った。カルロス・サンタナは官能のギタリストである以上に才能に溢れたグレイトなミュージシャンだったことを認識できたので。
もちろん、「エヴィル・ウェイズ」がズシリと心に響いたのはそれなりの下地が出来ていたから。1980年代に出逢ってからずっと追いかけているポンチョ・サンチェスはティト・プエンテからラテンジャズの王位を継承したコンガ奏者だが、根っこにはロックンロールやR&B(リズム&ブルース)がある人。マンボやサルサやアフロ・キューバンジャズに接する過程でブーガルーやグアヒーラ(レイ・バレット曰く、ラテンのブルース)に親しんできたことも大きい。
こうして改めて60年代後半から70年代中盤までのサンタナの音楽を聴き込んでみると、確かに頂点は『キャラヴァンサライ』かも知れないが、最高作は『不死蝶』だという結論に至った。その辺りのことは追って書くとして、いま殆ど毎日のように聴いている曲がある。ジョン・マクラフリンと共作の『魂の兄弟達』のオープニングを飾るジョン・コルトレーンの「至上の愛」。サンタナとマクラフリンがギタープレイを通じてお互いの主張をぶつけ合いながらも、最後は美しいハーモニーを奏でて終わる感動の作品。当初は宗教臭く聞こえるという理由で敬遠気味だったのがウソのように親しんでいることが不思議ではある。
サンタナ&マクラフリン・バージョンの「至上の愛」は(厳かな雰囲気で始まる)コルトレーンのオリジナル作品(原典版)とはうって変わって、2人のギタリストのバトルを中心に据えたある種喧噪の下に始まる。「原典版」に親しんでいた人は、まずここで勘弁してくれになったかも知れない。続いて登場するのはダグ・ローチのベース。落ち着いた雰囲気でグルーブ感もありなかなかよいのだが、「エレキベースは勘弁」という人はここで投了だったかも。コルトレーンが吹いた精緻なテーマはラリー・ヤングがオルガンで丁寧に心を込めてなぞる。このため、有名なフレーズが全編にわたって残像のように響き渡るフラッシュバックのような効果がある。こうしてみても、「メインディッシュ」が登場するまででも既に内容の濃い作品に仕上がっているわけだ。
そして、いよいよサンタナとマクラフリンによりギターバトルが始まる。先行するのはサンタナより5歳年長のマクラフリン。とっかかりはお互いの主張を朗々と語り合う8小節ずつの交換になっている。そんな対話も熱を帯びてきて4小節ずつの交換へと2人の距離感が縮まる。そして、いつしかサンタナが仕掛けてマクラフリンが受け応える形となった2小節交換のステージへと進む。白熱したアイデアの交換は遂に1小節にまで縮まり、最高潮に達したところで「共演」となる。ここが、この演奏で最高にスリリングであり感動的な瞬間。
2人の徐々に間合いを詰めていく絶妙なやりとりを野球のキャッチボールに例えてみるのも面白い。最初は遠投でお互いの肩の強さや球筋を確かめる。それぞれのクセがわかったところで2人は徐々に間隔を詰めていき、最後は肩を組んで仲良く終了。サンタナが投げるクセ球系のボールをしっかりと受け止めて次にボールが投げ返しやすいように丁寧に返すマクラフリン。2人が野球選手だったらそんな楽しいキャッチボールができたに違いない。マクラフリンの技量だけでなく、懐の深さと優しさなくしてこの平和なバトルは成立しなかっただろう。
時にサンタナ(1947年生まれ)は20代半ばで、マクラフリン(1942年生まれ)は30歳を越えたばかり。ラリー・ヤングはマクラフリンより2年年上で、ダグ・ローチも20代半ばだ。そんな演奏者達の年齢からは想像できないくらいに、成熟を感じさせる世界が創り上げられていることには驚きを禁じ得ない。一聴した限りではカオスのような印象を与えるオープニングも、実は2人が辿り着くべき調和の世界ではなかったのかなと捉えてみたくもなる。

毎日のようにこの若き2人による「至上の愛」を聴いてみると、やはりコルトレーンの演奏も聴かないわけにはいかなくなる。CDは持っていないのでジャズを聴き始めた頃に購入したレコードに針を下ろした。購入してから40年くらい経っているのに盤面はピカピカでノイズも殆どないから十分に聴ける。ジャズ史に残る不滅のマスターピースは精緻でズシリと重く響く。サンタナとマクラフリンの演奏は1曲目のみを取り上げているが、原典版だと通して聴きたくなってしまうところはさながら4楽章構成のシンフォニーの趣がある。
参加メンバーでは、やはりエルヴィン・ジョーンズのドラミングが圧巻。たったひとりでポリリズムを刻んでいることなど、なにゆえに「神様」と讃えられているのかがよく分かる。私感だが、名ドラマーに共通して言えることは、ドラムをスティックで叩いているのではなく、楽器を魔法の杖で鳴らしているというふうにしか聞こえないこと。本当に不思議なのだがそんな印象を受けてしまう最右翼がこの人だと思う。4曲目で素晴らしいソロを聴かせてくれるジミー・ギャリソンの演奏も含蓄がある。このレコードもこれから時々聴くことになるだろう。
断絶の時代にこそ必要なのが対話と相互理解。ここで音楽が果たす役割は大きいと思う。なぜなら、自分の琴線に触れる音楽を創り、演奏する人達と仲良くなれない理由を見つけるのは難しいはずだから。サンタナはメキシコ出身でマクラフリンは英国出身。共演するミュージシャンも様々なバックグラウンドを持つ。サンタナとマクラフリンの演奏をギター奏法や音楽の創り方だけで論じるのはもったいないと思う。意見や主義主張が違っても、対話により相互理解が出来る。2人が中心となって展開する感動的な演奏にそんな奥義を感じる。
 | 魂の兄弟たち (紙ジャケット仕様) |
| カルロス・サンタナ,マハビシュヌ・ジョン・マクラグリン | |
| Sony Music Direct |