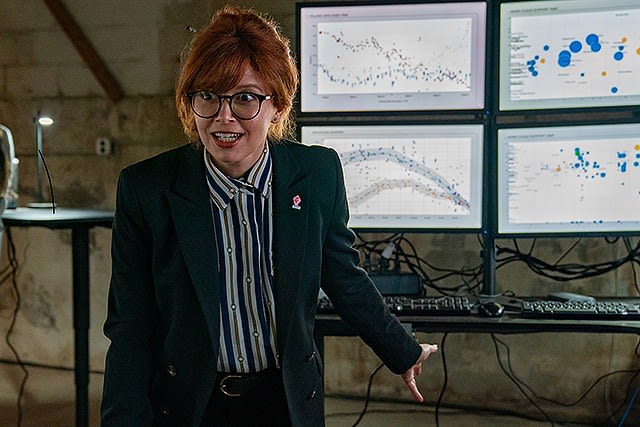映画「ベルファスト」を映画館で観てきました。

映画「ベルファスト」は、監督兼俳優のケネス・ブラナーが幼少期に北アイランドに住んでいた時の思い出を綴る作品である。アカデミー賞の発表の前にとりあえず観てみた。その後、脚本賞を受賞でいいオチどころだった。
モノクロ映画であるが、最初だけカラー映像で北アイランドにあるベルファストを俯瞰する。日本でいえば、下町の長屋の風景みたいなものかなあ。映画が始まり、住人たちが仲良く暮らす平和な風景をモノクロ映像で映し出した後に、プロテスタントの連中が大暴れしだす。ごく普通のベルファストに住む家族が、キリスト教のプロテスタントとカトリックの騒乱に巻き込まれる。ロンドンに出稼ぎに行っている大工の父親の勧めで、引っ越そうとするけど、名残惜しさで家族みんなが戸惑うストーリーだ。

作品的に飛び抜けて良いとは思えなかった。いわゆる5点満点で4点の感動しかない。とにかく、宗教って面倒くさいなあ、嫌だな。そう思わせる映画である。クリスマスを祝った後で、神社や寺に初詣する日本人はある意味、宗教が染み付いていない。欧米や中東諸国はこのあたりが違う。自分はいわゆる「アカ嫌い」だけど、宗教についてはマルクスの「宗教はアヘン」という考え方を支持する。
主人公のバディ少年がかわいい。舞台となる1969年の自分よりもすこし小さい。ここでは祖父が病床についている話で、ちょうど自分の祖父、母方の祖母が亡くなった年で、設定に親近感が湧く。映画を観ながら、同じころ自分はどうだったんだろうと思い起こす。
⒈町を出たくなかったのに
カトリック教徒を狙い撃ちにするプロテスタントの暴徒が大暴れする。学園紛争の出来の悪いアカ学生みたいだ。祖父母の時代から住み着いている北アイルランドのベルファストにいても良いのかと思う。ロンドンに大工の出稼ぎに出ている父親は家も提供するよと雇い主に言われて、母親に相談する。父母いずれも子どもの頃から住み着くこの地を離れたくない。母親はロンドンに行ったら、アイルランド訛りをバカにされるとばかりに絶対イヤだとごねる。父親は無理じいはしない。少年も泣いてごねる。

それなのに、暴徒の動きは止まらず、ついに母親も呆れかえるのだ。そんな心境の変化を起こさせる宗教のいやらしさが顕著に表現される。
⒉サンダーバード
観ていて楽しいのが、バディ少年を取り巻くオタク文化だ。1960年前後生まれは、大塚英志に言わせれば日本ではオタク第一世代だ。自分もそうだ。1958年にマガジン、サンデーが発行され、TVが普及され1963年にはアニメの鉄腕アトムが始まる。オタク文化は日本だけの世界だと思ったら、そうでもなさそうだ。1966年NHKで始まった英国発のサンダーバードには興奮した。人形劇とは思えぬリアル感、サンダーバード1号から5号やジェットモグラなどの補助的な救助機は夢があふれていた。
サンダーバードのご兄弟が着る制服と帽子をクリスマスプレゼントでもらったバディ少年が身につけるシーンがある。この制服は日本では売っているのを見たことがない。うらやましいなあと思った。
あとは、「チキチキバンバン」の実写場面が映る場面、ここもカラー映像になる。これって当時の東京で、至る所でポスターを見た。でも観ていないんだよなあ。海にむかって崖から飛び込んでもうダメと思った瞬間に、クルマが浮かび上がる。幼児から見て興奮するシーンを家族で楽しむ。いい感じだなあ。

⒊おもしろいおばあさん
バディ少年には祖父母がいる。特におばあちゃんが個性あふれる。毒舌で自分の思い通りに生きている。自分には、青島幸男の「意地悪ばあさん」に思えた。

でも、ラストでつぶやくのがいい感じだ。それにしても、エンディングロールでジュディディンチの名前を見て驚いた。さすがの貫禄である。

映画「ベルファスト」は、監督兼俳優のケネス・ブラナーが幼少期に北アイランドに住んでいた時の思い出を綴る作品である。アカデミー賞の発表の前にとりあえず観てみた。その後、脚本賞を受賞でいいオチどころだった。
モノクロ映画であるが、最初だけカラー映像で北アイランドにあるベルファストを俯瞰する。日本でいえば、下町の長屋の風景みたいなものかなあ。映画が始まり、住人たちが仲良く暮らす平和な風景をモノクロ映像で映し出した後に、プロテスタントの連中が大暴れしだす。ごく普通のベルファストに住む家族が、キリスト教のプロテスタントとカトリックの騒乱に巻き込まれる。ロンドンに出稼ぎに行っている大工の父親の勧めで、引っ越そうとするけど、名残惜しさで家族みんなが戸惑うストーリーだ。

作品的に飛び抜けて良いとは思えなかった。いわゆる5点満点で4点の感動しかない。とにかく、宗教って面倒くさいなあ、嫌だな。そう思わせる映画である。クリスマスを祝った後で、神社や寺に初詣する日本人はある意味、宗教が染み付いていない。欧米や中東諸国はこのあたりが違う。自分はいわゆる「アカ嫌い」だけど、宗教についてはマルクスの「宗教はアヘン」という考え方を支持する。
主人公のバディ少年がかわいい。舞台となる1969年の自分よりもすこし小さい。ここでは祖父が病床についている話で、ちょうど自分の祖父、母方の祖母が亡くなった年で、設定に親近感が湧く。映画を観ながら、同じころ自分はどうだったんだろうと思い起こす。
⒈町を出たくなかったのに
カトリック教徒を狙い撃ちにするプロテスタントの暴徒が大暴れする。学園紛争の出来の悪いアカ学生みたいだ。祖父母の時代から住み着いている北アイルランドのベルファストにいても良いのかと思う。ロンドンに大工の出稼ぎに出ている父親は家も提供するよと雇い主に言われて、母親に相談する。父母いずれも子どもの頃から住み着くこの地を離れたくない。母親はロンドンに行ったら、アイルランド訛りをバカにされるとばかりに絶対イヤだとごねる。父親は無理じいはしない。少年も泣いてごねる。

それなのに、暴徒の動きは止まらず、ついに母親も呆れかえるのだ。そんな心境の変化を起こさせる宗教のいやらしさが顕著に表現される。
⒉サンダーバード
観ていて楽しいのが、バディ少年を取り巻くオタク文化だ。1960年前後生まれは、大塚英志に言わせれば日本ではオタク第一世代だ。自分もそうだ。1958年にマガジン、サンデーが発行され、TVが普及され1963年にはアニメの鉄腕アトムが始まる。オタク文化は日本だけの世界だと思ったら、そうでもなさそうだ。1966年NHKで始まった英国発のサンダーバードには興奮した。人形劇とは思えぬリアル感、サンダーバード1号から5号やジェットモグラなどの補助的な救助機は夢があふれていた。
サンダーバードのご兄弟が着る制服と帽子をクリスマスプレゼントでもらったバディ少年が身につけるシーンがある。この制服は日本では売っているのを見たことがない。うらやましいなあと思った。
あとは、「チキチキバンバン」の実写場面が映る場面、ここもカラー映像になる。これって当時の東京で、至る所でポスターを見た。でも観ていないんだよなあ。海にむかって崖から飛び込んでもうダメと思った瞬間に、クルマが浮かび上がる。幼児から見て興奮するシーンを家族で楽しむ。いい感じだなあ。

⒊おもしろいおばあさん
バディ少年には祖父母がいる。特におばあちゃんが個性あふれる。毒舌で自分の思い通りに生きている。自分には、青島幸男の「意地悪ばあさん」に思えた。

でも、ラストでつぶやくのがいい感じだ。それにしても、エンディングロールでジュディディンチの名前を見て驚いた。さすがの貫禄である。