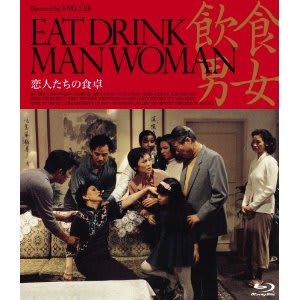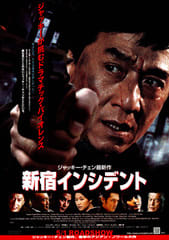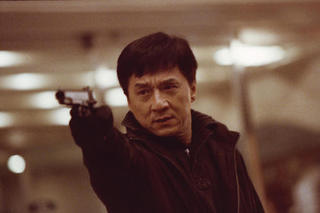映画「危険な関係」は2012年の中国映画である。
「危険な関係」は、フランスの作家ラクロが18世紀後半のフランス貴族の社交界を舞台に描いた文芸小説である。プレイボーイの子爵と策略家の侯爵夫人が貞淑な人妻を恋愛ゲームに巻き込んでいく。
これまで何度も映画化されてきた。もっとも有名なのは若くして亡くなった名優ジェラール・フィリップとジャンヌモロー共演の1959年版である。それを1930年代の魔都上海に舞台を移し、チャン・ツィイー とセシリア・チャンの中国の美人女優に韓国の男優スターチャン・ドンゴンを組み合わせる。
華美な美術が際立ち、当時世界の最先端の都市だった上海を美しく描いている。

1931年の上海。莫大な資産を持つ富裕層はパーティに明け暮れ、享楽的な生活を送っていた。女性実業家のジユ(セシリア・チャン)と裕福なプレイボーイのイーファン(チャン・ドンゴン)は、人の心を弄ぶ悪だくみを繰り返していた。自分を捨てた男が、年端もいかない少女と婚約したことが許せないジユは、イーファンに少女を寝取るよう持ち掛ける。

しかし百戦錬磨のイーファンは、別の女性に目をつける。亡夫の意志を継いで奉仕活動をしている、貞淑な未亡人・フェンユー(チャン・ツィイー)だ。イーファンがフェンユーをベッドに誘うことができればジユはイーファンのものに、失敗したらイーファンの土地がジユのものになるという、淫らで恐ろしい賭けを始める2人。野心家のジユはすべてを意のままに操ろうとし、イーファンはそんな彼女を支配することに欲望を燃やす。2人の悪魔的な企みに、フェンユーは弄ばれていく。3人の間で繰り広げられる愛の駆け引きの先には、衝撃的な結末が待ち受けていた……。 (作品情報より)
フランス版との配役の比較
ジェラール・フィリップ→チャン・ドンゴン
ジャンヌモロー →セシリア・チャン

フランス版では倦怠期に入った夫婦を演じていた。お互いの浮気を認め合う夫婦だけど、本気にはならないルールを持っている。ジェラールは少女に手を出し、ジャンヌはその恋人を誘惑する。今回夫婦の設定ではないが、手を出す相手は一緒だ。
アネット・ヴァディム(人妻)→チャン・ツィイー(富豪の未亡人)
ジェラールフィリップもチャンドンゴンも本気で惚れてしまう相手だ。ここでは、セシリアチャンとチャンドンゴンは夫婦ではなく、社交界の遊び仲間だ。チャン・ツィイーを落としたら、セシリアはチャンドンゴンのものになるというゲームを始める。難攻不落なのに、一旦落としたら女性の方が一気にテンションが上がる。

若干設定は違うが、ストーリー的には中国版の方がおもしろい。
チャン・ツィイー(フェンユー)が恋の炎を呼び覚まされ、情熱的な女に変貌していく。プレイボーイとわかっていながら、徐々に男に狂う。そしてチャンドンゴン(イーファン)を完全に信頼する。でもイーファンはジユの操り人形だ。この悪女ぶりがゾクゾクさせる。
だましだまされの構図が複雑だが、何より悪女なのはセシリアチャンだ。
現代香港映画を代表する美女が、顔つきからするとおそらくは実生活でもやってそうな悪だくみを仕組む。
セシリアチャンの妖艶さが増してきた印象を受ける。女の色気はやはり30過ぎに出る。

フランス版では、悪事をはたらくジャンヌモローには最後に最悪の結末が待っていた。この場面には驚いた。この映画でははたしてどうなるのか
「危険な関係」は、フランスの作家ラクロが18世紀後半のフランス貴族の社交界を舞台に描いた文芸小説である。プレイボーイの子爵と策略家の侯爵夫人が貞淑な人妻を恋愛ゲームに巻き込んでいく。
これまで何度も映画化されてきた。もっとも有名なのは若くして亡くなった名優ジェラール・フィリップとジャンヌモロー共演の1959年版である。それを1930年代の魔都上海に舞台を移し、チャン・ツィイー とセシリア・チャンの中国の美人女優に韓国の男優スターチャン・ドンゴンを組み合わせる。
華美な美術が際立ち、当時世界の最先端の都市だった上海を美しく描いている。

1931年の上海。莫大な資産を持つ富裕層はパーティに明け暮れ、享楽的な生活を送っていた。女性実業家のジユ(セシリア・チャン)と裕福なプレイボーイのイーファン(チャン・ドンゴン)は、人の心を弄ぶ悪だくみを繰り返していた。自分を捨てた男が、年端もいかない少女と婚約したことが許せないジユは、イーファンに少女を寝取るよう持ち掛ける。

しかし百戦錬磨のイーファンは、別の女性に目をつける。亡夫の意志を継いで奉仕活動をしている、貞淑な未亡人・フェンユー(チャン・ツィイー)だ。イーファンがフェンユーをベッドに誘うことができればジユはイーファンのものに、失敗したらイーファンの土地がジユのものになるという、淫らで恐ろしい賭けを始める2人。野心家のジユはすべてを意のままに操ろうとし、イーファンはそんな彼女を支配することに欲望を燃やす。2人の悪魔的な企みに、フェンユーは弄ばれていく。3人の間で繰り広げられる愛の駆け引きの先には、衝撃的な結末が待ち受けていた……。 (作品情報より)
フランス版との配役の比較
ジェラール・フィリップ→チャン・ドンゴン
ジャンヌモロー →セシリア・チャン

フランス版では倦怠期に入った夫婦を演じていた。お互いの浮気を認め合う夫婦だけど、本気にはならないルールを持っている。ジェラールは少女に手を出し、ジャンヌはその恋人を誘惑する。今回夫婦の設定ではないが、手を出す相手は一緒だ。
アネット・ヴァディム(人妻)→チャン・ツィイー(富豪の未亡人)
ジェラールフィリップもチャンドンゴンも本気で惚れてしまう相手だ。ここでは、セシリアチャンとチャンドンゴンは夫婦ではなく、社交界の遊び仲間だ。チャン・ツィイーを落としたら、セシリアはチャンドンゴンのものになるというゲームを始める。難攻不落なのに、一旦落としたら女性の方が一気にテンションが上がる。

若干設定は違うが、ストーリー的には中国版の方がおもしろい。
チャン・ツィイー(フェンユー)が恋の炎を呼び覚まされ、情熱的な女に変貌していく。プレイボーイとわかっていながら、徐々に男に狂う。そしてチャンドンゴン(イーファン)を完全に信頼する。でもイーファンはジユの操り人形だ。この悪女ぶりがゾクゾクさせる。
だましだまされの構図が複雑だが、何より悪女なのはセシリアチャンだ。
現代香港映画を代表する美女が、顔つきからするとおそらくは実生活でもやってそうな悪だくみを仕組む。
セシリアチャンの妖艶さが増してきた印象を受ける。女の色気はやはり30過ぎに出る。

フランス版では、悪事をはたらくジャンヌモローには最後に最悪の結末が待っていた。この場面には驚いた。この映画でははたしてどうなるのか