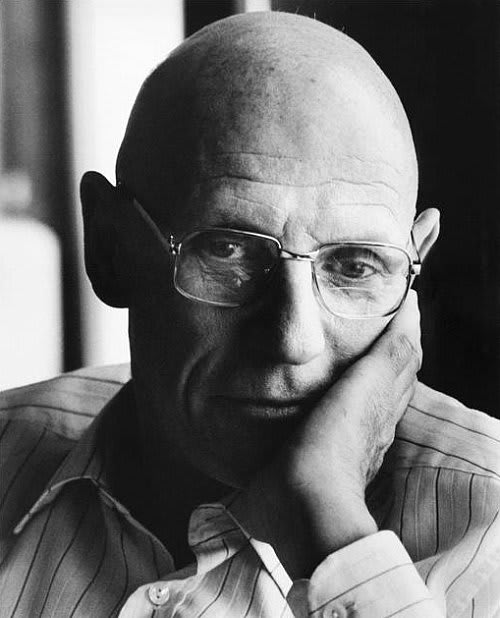★ ヒキガエルが多い。玄関の前の植えこみの間によく坐りこんでいる。敷地の中だけでなく、前の道にも這い出ている。
ひと気ない下り坂を降りきって家まで20メートルほどの道の真中に、ヒキガエルが一匹坐りこんでいたことがある。道は狭いが車が時折通る。
「何してんだ、そんなところで」
と私はヒキガエルの傍らに立ちどまって声をかけた。声も出さなければ動きもしないが、生きていることは気配でわかる。傷ついても衰えてもいない。
「車にひかれるぞ」
私は靴の先で軽く触れてみた。だが動き出す様子はなかった。道路のそのあたりがもしかすると古池の岸のお気に入りの場所だったのかもしれない。悠然と落ち着き払ってアスファルトの上に坐りこんでいる。
「悪いけど池はもうなくなったんだ」
私はかがみこんで片方の足の先をつまんで、道端の斜面になった芝生の上にそっと下ろした。つまみ上げても体をもがきもしなかったし、芝生の上に置いても驚いた様子はなかった。ゆっくりと斜面を這い登ってゆく。
★ 決して美しい容姿ではないけれども、それは複雑で精巧な自ら動く物質であり、確率的には本来ありうべからざる奇蹟の組み合わせ、良き混沌からの美しい偶然の産物だ、と私は心の中で言う。
暗い芝生の斜面を這い登ってゆくヒキガエルを眺めながら、まわりの、背後の、頭上の暗く静まり返った空間が、かすかに、だが決して乱脈ではないリズムをもって震えるのが、感じられるように思った。この空間は良き空間だ。原子を、生物を、意識を、私と呼ばれるものを滲み出したのだから。
<日野啓三『Living Zero』(集英社1987)>
★
生死のあわいにあればなつかしく候
みなみなまぼろしのえにしなり
おん身の勤行に殉ずるにあらず ひとえにわたくしのかなしみに殉ずるにあれば 道行のえにしはまぼろしふかくして一期の闇のなかなりし
ひともわれもいのちの臨終(いまわ) かくばかりかなしきゆえに けむり立つ雪炎の海をゆくごとくなれど われよりふかく死なんとする鳥の眸(め)に遭えり
はたまたその海の割るるときあらわれて 地(つち)の低きところを這う虫に逢えるなり
この虫の死にざまに添わんとするときようやくにして われもまたにんげんのいちいんなりしや かかるいのちのごとくなればこの世とはわが世のみにて われもおん身も ひとりのきわみの世をあいはてるべく なつかしきかな
いまひとたびにんげんに生まるるべしや 生類のみやこはいずくなりや
わが祖(おや)は草の親 四季の風を司り 魚(うお)の祭りを祀りたまえども 生類の邑(むら)はすでになし かりそめならず今生の刻をゆくに わが眸(まみ)ふかき雪なりしかな(石牟礼道子『天の魚』)
<真木悠介『時間の比較社会学』(岩波現代文庫2003)より引用>
★ 死はわたしたちを、「宗教」と名のつくものであってもなくても、その死の時に信じていたもののところで永劫に立ち停まらせる。プリオシン海岸を発掘する背の高い学者は、生きている者の世界の「科学」のパラダイムやエピステーメーがどう変わろうと、彼の信ずる科学の証明を永劫に発掘しつづける。鳥捕りの人の、主義といわず思想といわずただ行われる生活の信仰もそうだ。
★ それでもジョバンニはどこでも降りない。銀河鉄道のそれぞれの乗客たちが、それぞれの「ほんとうの天上」の存在するところで降りてしまうのに、いちばんおしまいまで旅をつづけるジョバンニは、地上におりてくる。
★ ひとつの宗教を信じることは、いつか旅のどこかに、自分を迎え入れてくれる降車駅をあらかじめ予約しておくことだ。ジョバンニの切符には行く先がない。ただ「どこまでも行ける切符」だ。
<真木悠介『自我の起源 愛とエゴイズムの動物社会学』“補論2”(岩波現代文庫2008)>