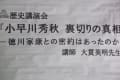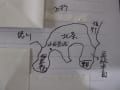平成28年10月9・10日(日・月) 体育の日が月曜日で、三連休の後半の2日間、
福島県相馬市に行ってきた。
義父が亡くなり、義母に名義替えをする手続きで、主人が戸籍謄本を取り寄せた際、福島から北海道に開拓に来て移り住んだという話は聞いていたが、義父の父母の詳しい住所が分かったので、今回、是非とも行ってみたいというので、行ってきた。
それというのも、北海道に移り住んだ時に、このお父様は、自分の敷地に、この生まれ故郷の中村神社の「妙見様」を分社して、神社を建てたという。そして、義母が嫁いだ際には、この父親から「一度本家の神社にお参りに行って来い」と言われ、今回行った「相馬中村神社」に何十年も前に拝みに行ったという。
それでは、順を追って、載せていく。
まずは、朝7時に家を出て、圏央道に乗り、東北道に乗って、郡山市中田町へ。そこが義父の父母が生まれた場所。二人は近所同士で結婚した。







近くに、相馬小高神社(そうまおだかじんじゃ)相馬馬追の元祖の神社だそうです。





元々は、源頼朝が、藤原三代と戦い、勝ったことで、相馬氏が受け継いだ土地で、この小高神社は相馬氏が建てた神社で、その後、江戸時代に相馬中村神社に移っていったということだ。
いわき市のビジネスホテルで泊をとり、つぎの日に、福島の海岸沿いを北上して、相馬市に入る。その間、事故のあった原子力発電所の付近を通ったが、大震災から5年も経っているけど、まだ「避難区域」が続いていて、高速道路は通っているけど、脇の道には入れないように、鉄杭等が、そこかしこに立っていた。道路には、何箇所にも、放射能の測定値が提示され、実際行ってみないと、こういうことって、知らないし、分からないなと感じた。
そして、妙見様が祀っていある「相馬中村神社」へ。馬追で有名なだけあって、入口には、白馬がいた。















帰りは、羽生サービスエリアで休憩、江戸時代の街並みが再現されているという。



父母に
妙見様の
影見たり
秋しぐれ
中村神社は
先祖の思い
福島県相馬市に行ってきた。
義父が亡くなり、義母に名義替えをする手続きで、主人が戸籍謄本を取り寄せた際、福島から北海道に開拓に来て移り住んだという話は聞いていたが、義父の父母の詳しい住所が分かったので、今回、是非とも行ってみたいというので、行ってきた。
それというのも、北海道に移り住んだ時に、このお父様は、自分の敷地に、この生まれ故郷の中村神社の「妙見様」を分社して、神社を建てたという。そして、義母が嫁いだ際には、この父親から「一度本家の神社にお参りに行って来い」と言われ、今回行った「相馬中村神社」に何十年も前に拝みに行ったという。
それでは、順を追って、載せていく。
まずは、朝7時に家を出て、圏央道に乗り、東北道に乗って、郡山市中田町へ。そこが義父の父母が生まれた場所。二人は近所同士で結婚した。







近くに、相馬小高神社(そうまおだかじんじゃ)相馬馬追の元祖の神社だそうです。





元々は、源頼朝が、藤原三代と戦い、勝ったことで、相馬氏が受け継いだ土地で、この小高神社は相馬氏が建てた神社で、その後、江戸時代に相馬中村神社に移っていったということだ。
いわき市のビジネスホテルで泊をとり、つぎの日に、福島の海岸沿いを北上して、相馬市に入る。その間、事故のあった原子力発電所の付近を通ったが、大震災から5年も経っているけど、まだ「避難区域」が続いていて、高速道路は通っているけど、脇の道には入れないように、鉄杭等が、そこかしこに立っていた。道路には、何箇所にも、放射能の測定値が提示され、実際行ってみないと、こういうことって、知らないし、分からないなと感じた。
そして、妙見様が祀っていある「相馬中村神社」へ。馬追で有名なだけあって、入口には、白馬がいた。















帰りは、羽生サービスエリアで休憩、江戸時代の街並みが再現されているという。



父母に
妙見様の
影見たり
秋しぐれ
中村神社は
先祖の思い