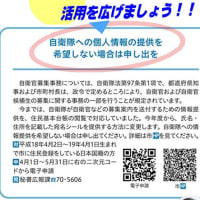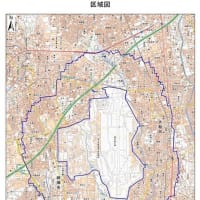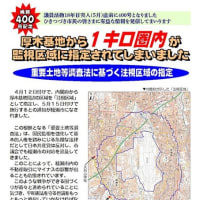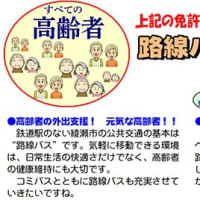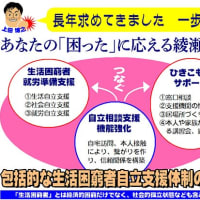相模原の教育を考える市民の会の会報第20号を読んでいましたら、「 いじめは「撲滅すべき」なのか」という貴重なご意見に接することができました。この視点はとても大切で、“いじめ”を社会的制裁によって「撲滅」させるのではなく、いじめは『だれの心にもある。だからこそ、自分を含めたみんなで解決していく』という視点が必要ではないのか、という提起です。
私は常にこの視点に立ち返るため、このブログに残したいと思い、著者の篠崎先生とコンタクトをとらさせていただき、ここへの転載のご許可をいただきました。
どうぞ、ご一読ください。
いじめは「撲滅すべき」なのか
篠崎 修
去る11月16日、市教委・市主催による「いじめフォーラム」(シンポジウム)が行われました。基調講演、小学校と中学校の取り組み、シンポジウム、そして若干の意見交換というプログラムでした。
その中でいくつか気になったことがあります。一つはある中学校での「生徒主体による『いじめ撲滅』の取り組み」報告でした。いじめ防止のための生徒(会)活動の一環として、全校・学年集会における「無言入場」と「無言退場」・・・。もちろん「騒がしい」より静かな行動の方が、と一般論としては理解します。
しかし「無言入退場」がなぜ良いことなのか、それがどこで「いじめ防止」につながっているのかが全く見えませんでした。このことが果たして多数の生徒の本当の要求・願いに立脚したものなのだろうか。一つ間違うと典型的な管理教育に陥るのではないのか。しかもそれが「生徒主体で実行されている」となると、さらに気になってしまうのです。さらに言えば、これは教師の必要と要求で、生徒に「させている」のではないのか、という疑念も生じます。生徒の視点や視野を広げるような支援が、見えないからなのかもしれません。
また、ある部活動では「みんなが元気に、相手の目を見てあいさつしよう」と申し合わせ実行しているといいます。これも一見良いことのように見えます。しかし本当にそうなのでしょうか? そういう元気な子もいれば、性格的にあるいはいろんな理由から、できない子だっているのです。こういう子への配慮がどれくらいできているのかどうか(そこをこそ、子どもたちに問いかけ考えさせる大人・教師の指導の中身)が、実はいじめ問題の根本にあると考えています。
■いじめ撲滅論への違和感
一人のシンポジストの「この場に違和感を感じる。(いじめが起きない条件があるとするなら)どの子も、弱くても安心してそこにいられる場であり、ありのままの自分でいられる場ではないのか」との発言が印象に残りました。
私はこの発言と中学校の取り組みにかかわって、以下の3点を会場から述べました。
1.いじめを「撲滅する」という表現の背景には、「いじめをする子は悪い子→悪い子には制裁を加えて反省させる→それでも直さなければ排除する」という考えがある。
それでは「いじめ」る子はだれからもケアされない。
2.「いじめる子」には、その子自身が傷ついてきた歴史があるはず。それを無視して制裁を加えても解決しないばかりか、その子自身の、自ら反省する機会も、成長発達する権利をも奪いとってしまうことになる。
3.いじめは「撲滅」ではなくて、子ども主体でみんなで考え、討論して解決していくこと。大人の役目は、その子どもたちの活動を、多様な見方考え方や視点などを示したりして、励まし支援していくことではないのか、と考える。
中学校の報告に感じる疑問を象徴する言葉が、まさに「いじめ撲滅」論に立っていることでした。発表した生徒さんは「いじめは『撲滅する』で良いと思います」と確信を持って言い切っていました。ここに私は改めて、教育の「怖さ」を思います。
■いじめの根っこは誰の心にもある
そんな中でも救いは2つありました。1つは先のシンポジストの発言。もう1つは、私の発言に対して助言者が「撲滅論」の問題点を指摘してくれたからです。
その一つとして「いじめ撲滅論の背景には『自分はいじめをしない正義の立場の人』という思い込みに陥る危険性がある。そうではなくて、いじめは『だれの心にもある。だからこそ、自分を含めたみんなで解決していく』という視点が必要ではないのか」という趣旨のコメントでした。この助言者は、さらに言葉を選びつつ「この中学校での実践を鵜呑みにしないでほしい」とも付け加えました。
この助言者の指摘は、私にとって目からうろこでした。一般的に大人も子どもも、普通の市民感覚として単純に「いじめる子は悪い。悪いから制裁を」という価値判断を支持したくなりがちです。しかしこの考え方を克服し、「子どもは間違いやトラブルを重ねながら、学び成長していく存在である。その時こそ、大人が背中を押してやること」という子ども観が広く理解され、支持されることが、本当の意味で「市民・大人も含めたいじめ克服」の展望を開くことになるのではないのか、と考えます。
■子どもの力を信頼しよう
最後にひとつのエビソードを紹介します。
相模原市とNPOによる協働事業=生活困窮家庭の中学生への学習支援(「中3勉強会」)の夏合宿が実施されました。ブルーベリー狩り・バーベキュー・星の観察などの活動がぎっしりと詰まった2泊3日。その中でも2日目の夜の「語り場」は、この合宿のメインプログラムです。
中学生と大学生が、静かに語り始める。家族のこと、友だちのこと、学校のこと・・・・・・そのどれもが胸を締め付けられるような話です。「こんなにも重たい現実を引きずりながら、それでも懸命に健気に生きている」中学生。かつて中学生だった大学生も、長い間ずっと心の奥に封印してきた思いを語ります。
今年は、少し前まで「いじめ・いじめられの関係」にあった3人の女子が、平和的に本音を語り合い、「和解する」という場面がありました。全く予想だにしなかったことでした。
中学生たちは「学習する場」に、様々な問題も持ち込みます。どんな話題でも丁寧に、時には忍耐強く耳を傾けてくれる大学生ボランティアとの出会いは、衝撃的な体験でしょう。彼らにとって「初めて自分の話を真剣に聞いてもらえた」と実感したのかも知れません。「みんなが真剣に聞いてくれる」と確信が持てるから、安心しつつちょっと勇気を出して自分を語ることができたのでしょう。
子どもは、問題を解決していく力を本来的に持っているのです。そのことを見事に示してくれる場面でした。
庶民いじめの悪政を変えたい
という方は、応援クリックを
お願いいたします。