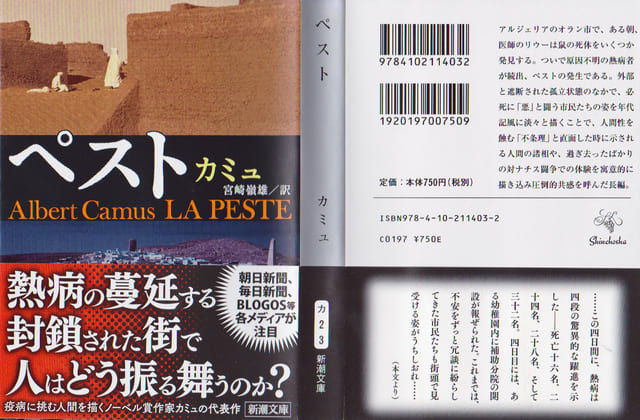
新型コロナ禍で「ステイホーム」のゴールデンウィーク中、カミュ著『ペスト』を読んだ。学生時代に一度読んでいるので、今回が二度目になる。長くなるが(何しろ458ページもの大作だから)忘れないうちに、以下にこの小説のあらましを記しておく。
致死率が30~60%以上というペストと、新型コロナウイルス肺炎(日本人の致死率は3.7%程度)とは比べものにならないが、この時期に読むと、やはり納得するところが多い、今回はそんな箇所を中心に引用させていただく。なお朝日新聞のサイト「好書好日」には、
新潮社によると、『ペスト』は2月以降で15万4千部を増刷し、累計発行部数は104万部になった。ペストにより封鎖された街で、伝染病の恐ろしさや人間性を脅かす不条理と闘う人々を描く。フランスやイタリア、英国でもベストセラーになっているという。
舞台は当時フランス領だったアルジェリアの港町・オラン県(本書では「オラン市」と表記されている)。なおカミュはアルジェリアの生まれである。小説はこんな書き出しで始まる。《この記録の主題をなす奇異な事件は、194*年、オランに起こった》《4月16日の朝、医師ベルナール・リウーは、診察室から出かけようとして、階段口のまんなかで一匹の死んだ鼠につまずいた》。
鼠の死骸はどんどん増えていく。《4月28日には報知通信社は約8,000匹の鼠が拾集されたことを報じ、市中の不安は頂点に達した》。4月16日に鼠の死骸を片付けたリウーのアパートの門番は、28日に発症した。《熱は39度5分で、頸部(けいぶ)のリンパ腺と四肢が腫脹(しゅちょう)し、脇腹に黒っぽい斑点が2つ広がりかけていた》。4月30日、救急車の中で門番は死んだ。
リウーはペストを疑い、保健委員会を招集してもらうが、医師会長のリシャールは、検査結果を待つべきだと主張した。《リシャールが最後にこういった―「つまりわれわれは、この病があたかもペストであるかのごとくふるまうという責任を負わねばならぬわけです」この言いまわしは熱烈な賛意をもって迎えられた》。翌日の新聞の扱いは小さく、県庁も目立たない場所に貼り紙をする程度の注意喚起にとどまった。
しかしその後も死者の数は毎日16人、24人、28人、32人と増え続ける。リウーは思い切って県知事に電話をかけた。知事は「(アルジェリア)総督府の命令を仰ぐことにしましょう」と答える。数日後、総督府から公電が届く。「ペストチクタルコトヲセンゲンシ シヲヘイサセヨ」。つまりオラン県の「ロックダウン(封鎖)」が命じられたのだ。オラン県には城壁が巡らされていたのだろう、封鎖はまたたく間に行われた。
《ペストは、彼らを閑散な身の上にし、陰鬱な市内を堂々めぐりするより仕方がなくさせ、そして来る日も来る日も空(むな)しい追憶の遊戯にふけらせたのである》《実際、まさにこの追放感こそ、われわれの心に常住宿されていたあの空虚であり、あの明確な感情の動き―過去にさかのぼり、あるいは逆に時間の歩みを早めようとする不条理な願いであり、あの突き刺すような追憶の矢であった》。
そんな中、キリスト教イエズス会の司祭・パヌルー神父は説教をする。《この説教はある人々に、それまではおぼろげであった観念、すなわち自分たちは何か知らない罪を犯した罰として、想像を絶した監禁状態に服させられているのだという観念を、一層はっきりと感じさせたのである》。
タルーは、旅行でオランを訪ね、ロックダウンで帰れなくなった男である。《タルーは、ペストに冒された町における1日のかなり精密な描写を試み、それによってこの夏の市民たちの仕事と生活について1つの的確な観念を提供している―「誰も、酔っ払い以外には笑うものはない」と、タルーはいっている。「そして、酔っ払いたちは笑いすぎる」》。
タルーは志願者による保健隊を組織することをリウーに提案し、リウーは協力する。パヌルー神父も、保健隊に協力することになった。いっぽうでリウーの医師仲間のカステルは、血清の製造に全力を尽くす。カステルは海外でペストの症例を見た経験があった。なお医療従事者は、基本的に血清により安全を保証されていた。
《8月の半ばというこの時期には、ペストがいっさいをおおい尽くしたといってよかった。もうこのときには個人の運命というものは存在せず、ただペストという集団的な史実と、すべての者がともにしたさまざまの感情があるばかりであった。その最も大きなものは、恐怖と反抗がそれに含まれていることも加えて、別離と追放の感情であった》。
《市民たちは事の成り行きに甘んじて歩調を合わせ、世間の言葉を借りれば、みずから適応していったのであるが、それというのも、そのほかにはやりようがなかったからである。彼らはまだ当然のことながら、不幸と苦痛との態度をとっていたが、しかしその痛みはもう感じていなかった。それに、たとえば医師リウーなどはそう考えていたのであるが、まさにそれが不幸というものであり、そして絶望に慣れることは絶望そのものよりもさらに悪いのである》。
《記憶もなく、希望もなく、彼らはただ現在のなかに腰をすえていた。実際のところ、すべてが彼らにとって現在となっていたのである。これもいっておかねばならぬが、ペストはすべての者から、恋愛と、さらに友情の能力さえも奪ってしまった。なぜなら、愛は幾らかの未来を要求するものであり、しかもわれわれにとってはもはや刻々の瞬間しか存在しなかったからである》。
こんな印象的なシーンも登場する。ある日、タルーは友人とオペラ見学に行く。その最後のクライマックスの場面で、道化師役が舞台の上でペストに倒れる。《最初はあたかも儀式が終わって教会から、あるいは弔問を済まして死者の部屋から出て来るときのように黙々として、婦人たちはスカートの裾を引き上げ、頭をたれて出て行き、男たちは連れの女に肘を貸しながら、補助椅子にぶっつからないように気をつけてやっていた。しかし、次第に人々の動きは急激になり、ささやきは叫びに変り、群衆は出口に殺到して押し合い、最後にはわめきながらもみ合いをはじめた》。
《舞台の上には、関節の自由を失った道化師役の扮装をしたペスト、そして観覧席には、椅子の赤いクッションの上に置き忘れられた扇子や、引きずっているレースというかたちで横たわっている、不要になったいっさいの贅沢》。
パヌルー神父は保健隊に入ってから、疫病に接する最前線で働いた。2回目の説教も、ある大風の日に行った。しかしその後神父にはペストと思われる症状が出たが、医者を呼ぶことを拒み、世を去った。
12月末になって、ようやくペストの最初の退潮のきざしが現れる。《病疫のこの突然の退潮は思いがけないことではあったが、しかし市民たちは、そうあわてて喜ぼうとしなかった。今日まで過ぎ去った幾月かは、彼らの解放の願いを増大させながらも、一方また用心深さというものを彼らに教え、病疫の近々における終息などますます当てにしないように習慣づけていたのである》。
《統計は下降していたのである。健康の時代が、大っぴらに希望はされなくても、しかも、ひそかに期待されていたという1つの徴(しるし)は、市民たちがもうこのときから、ペストの終息後どんなふうに生活が再編成されるかということについて、無関心めいた口ぶりながらも、進んで話すようになったことである》。
1月25日、ついに当局はペストの終息を宣言し、2月のある晴れた明け方、ついに門は開かれた。祝賀の花火を聞きながら、リウーはこの物語を書き綴ろうと決心する(つまり、この小説『ペスト』の書き手はリウーだったということが明かされる)。リウーは、決してペストの終息を手放しで喜んではいない。なぜならリウーは以下のことを知っていたからである。
《ペスト菌は決して死ぬことも消滅することもないものであり、数十年の間、家具や下着類のなかに眠りつつ生存することができ、部屋や穴倉やトランクやハンカチや反古(ほご)のなかに、しんぼう強く待ち続けていて、そしておそらくはいつか、人間に不幸と教訓をもたらすために、ペストが再びその鼠どもを呼びさまし、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに差し向ける日が来るであろうということを》。
私の学生時代には、おそらく何日もかけて読んだのだろうが、今回は1日でこの小説を読み終えることができた。毎日毎日、本を読んでいるので、自然と早く読む技術が身についたのだろう。
カミュの文章は翻訳で読んでも名文であることがうかがえたが、最初の創元社版『ペスト』 (訳者は新潮文庫版と同じ宮崎嶺雄氏=明治生まれの故人)の刊行が昭和25年だったので、翻訳が固いというか古い。若い読者はその点を覚悟して読んでいただきたい。
なお『ペスト』のあらすじは、こちらのサイトに出ているし、中条省平氏(NHK「100分de名著」講師)の書評は松森重博さんのブログに出ているので、ぜひ参考にしていただきたい。
致死率が30~60%以上というペストと、新型コロナウイルス肺炎(日本人の致死率は3.7%程度)とは比べものにならないが、この時期に読むと、やはり納得するところが多い、今回はそんな箇所を中心に引用させていただく。なお朝日新聞のサイト「好書好日」には、
新潮社によると、『ペスト』は2月以降で15万4千部を増刷し、累計発行部数は104万部になった。ペストにより封鎖された街で、伝染病の恐ろしさや人間性を脅かす不条理と闘う人々を描く。フランスやイタリア、英国でもベストセラーになっているという。
舞台は当時フランス領だったアルジェリアの港町・オラン県(本書では「オラン市」と表記されている)。なおカミュはアルジェリアの生まれである。小説はこんな書き出しで始まる。《この記録の主題をなす奇異な事件は、194*年、オランに起こった》《4月16日の朝、医師ベルナール・リウーは、診察室から出かけようとして、階段口のまんなかで一匹の死んだ鼠につまずいた》。
鼠の死骸はどんどん増えていく。《4月28日には報知通信社は約8,000匹の鼠が拾集されたことを報じ、市中の不安は頂点に達した》。4月16日に鼠の死骸を片付けたリウーのアパートの門番は、28日に発症した。《熱は39度5分で、頸部(けいぶ)のリンパ腺と四肢が腫脹(しゅちょう)し、脇腹に黒っぽい斑点が2つ広がりかけていた》。4月30日、救急車の中で門番は死んだ。
リウーはペストを疑い、保健委員会を招集してもらうが、医師会長のリシャールは、検査結果を待つべきだと主張した。《リシャールが最後にこういった―「つまりわれわれは、この病があたかもペストであるかのごとくふるまうという責任を負わねばならぬわけです」この言いまわしは熱烈な賛意をもって迎えられた》。翌日の新聞の扱いは小さく、県庁も目立たない場所に貼り紙をする程度の注意喚起にとどまった。
しかしその後も死者の数は毎日16人、24人、28人、32人と増え続ける。リウーは思い切って県知事に電話をかけた。知事は「(アルジェリア)総督府の命令を仰ぐことにしましょう」と答える。数日後、総督府から公電が届く。「ペストチクタルコトヲセンゲンシ シヲヘイサセヨ」。つまりオラン県の「ロックダウン(封鎖)」が命じられたのだ。オラン県には城壁が巡らされていたのだろう、封鎖はまたたく間に行われた。
《ペストは、彼らを閑散な身の上にし、陰鬱な市内を堂々めぐりするより仕方がなくさせ、そして来る日も来る日も空(むな)しい追憶の遊戯にふけらせたのである》《実際、まさにこの追放感こそ、われわれの心に常住宿されていたあの空虚であり、あの明確な感情の動き―過去にさかのぼり、あるいは逆に時間の歩みを早めようとする不条理な願いであり、あの突き刺すような追憶の矢であった》。
そんな中、キリスト教イエズス会の司祭・パヌルー神父は説教をする。《この説教はある人々に、それまではおぼろげであった観念、すなわち自分たちは何か知らない罪を犯した罰として、想像を絶した監禁状態に服させられているのだという観念を、一層はっきりと感じさせたのである》。
タルーは、旅行でオランを訪ね、ロックダウンで帰れなくなった男である。《タルーは、ペストに冒された町における1日のかなり精密な描写を試み、それによってこの夏の市民たちの仕事と生活について1つの的確な観念を提供している―「誰も、酔っ払い以外には笑うものはない」と、タルーはいっている。「そして、酔っ払いたちは笑いすぎる」》。
タルーは志願者による保健隊を組織することをリウーに提案し、リウーは協力する。パヌルー神父も、保健隊に協力することになった。いっぽうでリウーの医師仲間のカステルは、血清の製造に全力を尽くす。カステルは海外でペストの症例を見た経験があった。なお医療従事者は、基本的に血清により安全を保証されていた。
《8月の半ばというこの時期には、ペストがいっさいをおおい尽くしたといってよかった。もうこのときには個人の運命というものは存在せず、ただペストという集団的な史実と、すべての者がともにしたさまざまの感情があるばかりであった。その最も大きなものは、恐怖と反抗がそれに含まれていることも加えて、別離と追放の感情であった》。
《市民たちは事の成り行きに甘んじて歩調を合わせ、世間の言葉を借りれば、みずから適応していったのであるが、それというのも、そのほかにはやりようがなかったからである。彼らはまだ当然のことながら、不幸と苦痛との態度をとっていたが、しかしその痛みはもう感じていなかった。それに、たとえば医師リウーなどはそう考えていたのであるが、まさにそれが不幸というものであり、そして絶望に慣れることは絶望そのものよりもさらに悪いのである》。
《記憶もなく、希望もなく、彼らはただ現在のなかに腰をすえていた。実際のところ、すべてが彼らにとって現在となっていたのである。これもいっておかねばならぬが、ペストはすべての者から、恋愛と、さらに友情の能力さえも奪ってしまった。なぜなら、愛は幾らかの未来を要求するものであり、しかもわれわれにとってはもはや刻々の瞬間しか存在しなかったからである》。
こんな印象的なシーンも登場する。ある日、タルーは友人とオペラ見学に行く。その最後のクライマックスの場面で、道化師役が舞台の上でペストに倒れる。《最初はあたかも儀式が終わって教会から、あるいは弔問を済まして死者の部屋から出て来るときのように黙々として、婦人たちはスカートの裾を引き上げ、頭をたれて出て行き、男たちは連れの女に肘を貸しながら、補助椅子にぶっつからないように気をつけてやっていた。しかし、次第に人々の動きは急激になり、ささやきは叫びに変り、群衆は出口に殺到して押し合い、最後にはわめきながらもみ合いをはじめた》。
《舞台の上には、関節の自由を失った道化師役の扮装をしたペスト、そして観覧席には、椅子の赤いクッションの上に置き忘れられた扇子や、引きずっているレースというかたちで横たわっている、不要になったいっさいの贅沢》。
パヌルー神父は保健隊に入ってから、疫病に接する最前線で働いた。2回目の説教も、ある大風の日に行った。しかしその後神父にはペストと思われる症状が出たが、医者を呼ぶことを拒み、世を去った。
12月末になって、ようやくペストの最初の退潮のきざしが現れる。《病疫のこの突然の退潮は思いがけないことではあったが、しかし市民たちは、そうあわてて喜ぼうとしなかった。今日まで過ぎ去った幾月かは、彼らの解放の願いを増大させながらも、一方また用心深さというものを彼らに教え、病疫の近々における終息などますます当てにしないように習慣づけていたのである》。
《統計は下降していたのである。健康の時代が、大っぴらに希望はされなくても、しかも、ひそかに期待されていたという1つの徴(しるし)は、市民たちがもうこのときから、ペストの終息後どんなふうに生活が再編成されるかということについて、無関心めいた口ぶりながらも、進んで話すようになったことである》。
1月25日、ついに当局はペストの終息を宣言し、2月のある晴れた明け方、ついに門は開かれた。祝賀の花火を聞きながら、リウーはこの物語を書き綴ろうと決心する(つまり、この小説『ペスト』の書き手はリウーだったということが明かされる)。リウーは、決してペストの終息を手放しで喜んではいない。なぜならリウーは以下のことを知っていたからである。
《ペスト菌は決して死ぬことも消滅することもないものであり、数十年の間、家具や下着類のなかに眠りつつ生存することができ、部屋や穴倉やトランクやハンカチや反古(ほご)のなかに、しんぼう強く待ち続けていて、そしておそらくはいつか、人間に不幸と教訓をもたらすために、ペストが再びその鼠どもを呼びさまし、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに差し向ける日が来るであろうということを》。
私の学生時代には、おそらく何日もかけて読んだのだろうが、今回は1日でこの小説を読み終えることができた。毎日毎日、本を読んでいるので、自然と早く読む技術が身についたのだろう。
カミュの文章は翻訳で読んでも名文であることがうかがえたが、最初の創元社版『ペスト』 (訳者は新潮文庫版と同じ宮崎嶺雄氏=明治生まれの故人)の刊行が昭和25年だったので、翻訳が固いというか古い。若い読者はその点を覚悟して読んでいただきたい。
なお『ペスト』のあらすじは、こちらのサイトに出ているし、中条省平氏(NHK「100分de名著」講師)の書評は松森重博さんのブログに出ているので、ぜひ参考にしていただきたい。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます