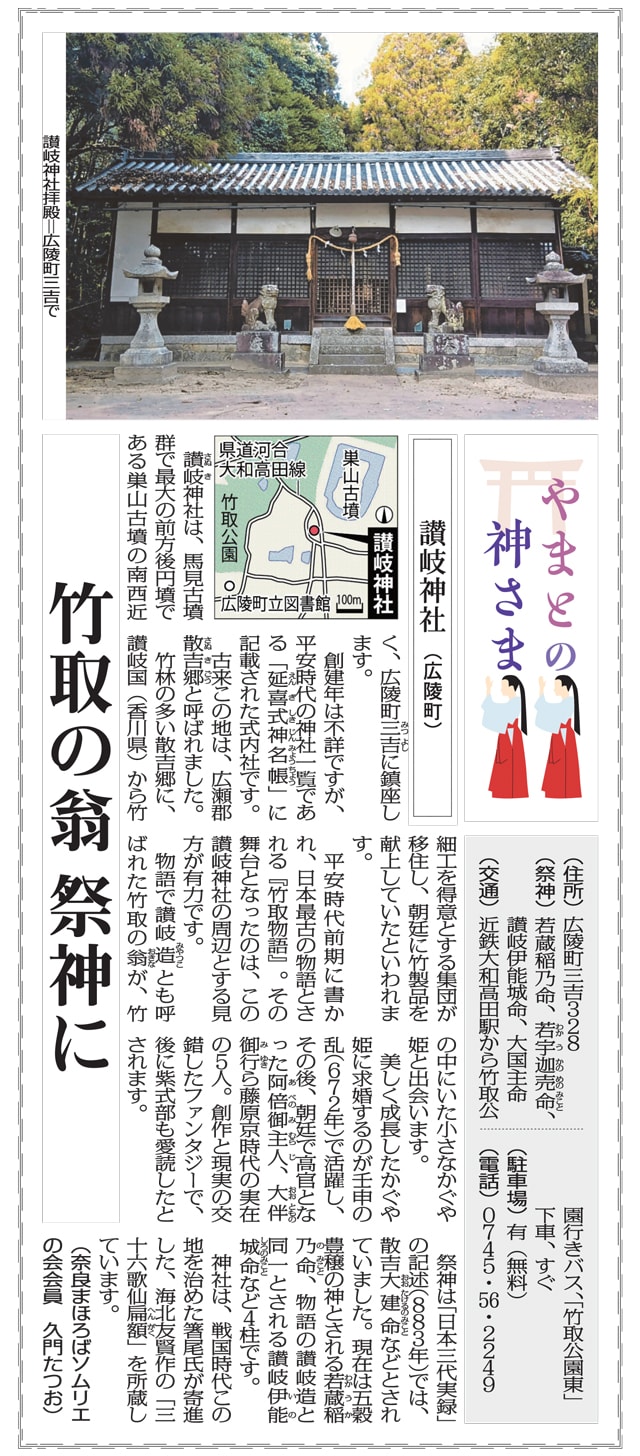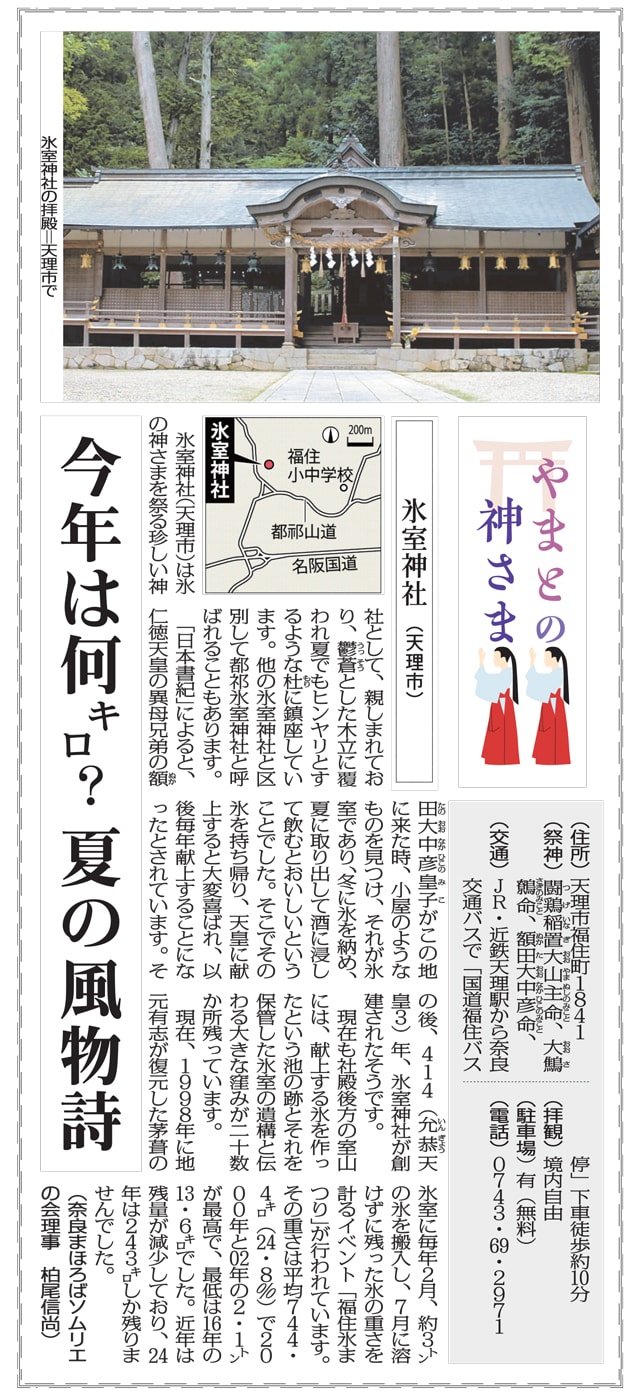NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「やまとの神さま」を連載している。先週(2025.6.5)掲載されたのは、〈「源氏再興へ」常陸に源流/鹿島神社(香芝市)〉、執筆されたのは、同会会員で生駒郡平群町にお住まいの喜多村英夫さんだった。
喜多村さんは平群町をはじめ奈良県西部の神社や史跡に精通されているので、当会としては、大いに助かっている。では、以下に全文を紹介する。
「源氏再興へ」常陸に源流/鹿島神社(香芝市)
近鉄下田駅の北にある神社で、祭神は茨城県の鹿島神宮と同じ武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)です。香芝の地名は当社の「カシマ」に由来するともいわれます。
「結鎮座(けっちんざ)文書」(後述)によりますと、1172年、源義朝(みなもとのよしとも)の家臣の鎌田小次郎政光(かまたこじろうまさみつ)が、常陸の国鹿島神宮の分霊を勧請したのが始まりです。
平治の乱(1159年)で平清盛に敗れた源義朝一行は、知多で殺害されましたが、政光は逃れて常陸国の鹿島にたどり着き、鹿島神宮で源氏再興の願掛けをしました。満願の日の夜、夢に老人が出てきて、西の方に行けば願いがかなうと言われ、旅に出ます。
鹿島の風景に似た下田に至り、祠(ほこら)を建てて鹿島神宮の神を祭ったのが始まりと伝えられます。当初はやや南の地にあり、鎌田という地名も残ります。
ここには古くから、氏子の宮座として「結鎮座」があり、現在も継承されています。神社に奉仕し、祭礼を行ってきた集団で、座の組織や年中行事などを記した「結鎮座文書」(県指定文化財)が伝わり、村や宮座の構造を知る貴重な史料となっています。
毎年1月26日に行われる渡御(とぎょ)行事は、宮座の上十人衆が輪番で務める頭屋宅に、鹿島神社のご神霊を迎える行事です。昨年の秋祭りでは「下田だんじり」が約60年ぶりに曳行(えいこう)されました。(奈良まほろばソムリエの会会員 喜多村英夫)
(住 所)香芝市下田西1の9の3
(祭 神)武甕槌大神
(交 通)近鉄下田駅からすぐ、JR香芝駅から徒歩約5分
(拝 観)境内自由
(駐車場)有(無料)
(電 話)0745・78・7535

喜多村さんは平群町をはじめ奈良県西部の神社や史跡に精通されているので、当会としては、大いに助かっている。では、以下に全文を紹介する。
「源氏再興へ」常陸に源流/鹿島神社(香芝市)
近鉄下田駅の北にある神社で、祭神は茨城県の鹿島神宮と同じ武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)です。香芝の地名は当社の「カシマ」に由来するともいわれます。
「結鎮座(けっちんざ)文書」(後述)によりますと、1172年、源義朝(みなもとのよしとも)の家臣の鎌田小次郎政光(かまたこじろうまさみつ)が、常陸の国鹿島神宮の分霊を勧請したのが始まりです。
平治の乱(1159年)で平清盛に敗れた源義朝一行は、知多で殺害されましたが、政光は逃れて常陸国の鹿島にたどり着き、鹿島神宮で源氏再興の願掛けをしました。満願の日の夜、夢に老人が出てきて、西の方に行けば願いがかなうと言われ、旅に出ます。
鹿島の風景に似た下田に至り、祠(ほこら)を建てて鹿島神宮の神を祭ったのが始まりと伝えられます。当初はやや南の地にあり、鎌田という地名も残ります。
ここには古くから、氏子の宮座として「結鎮座」があり、現在も継承されています。神社に奉仕し、祭礼を行ってきた集団で、座の組織や年中行事などを記した「結鎮座文書」(県指定文化財)が伝わり、村や宮座の構造を知る貴重な史料となっています。
毎年1月26日に行われる渡御(とぎょ)行事は、宮座の上十人衆が輪番で務める頭屋宅に、鹿島神社のご神霊を迎える行事です。昨年の秋祭りでは「下田だんじり」が約60年ぶりに曳行(えいこう)されました。(奈良まほろばソムリエの会会員 喜多村英夫)
(住 所)香芝市下田西1の9の3
(祭 神)武甕槌大神
(交 通)近鉄下田駅からすぐ、JR香芝駅から徒歩約5分
(拝 観)境内自由
(駐車場)有(無料)
(電 話)0745・78・7535