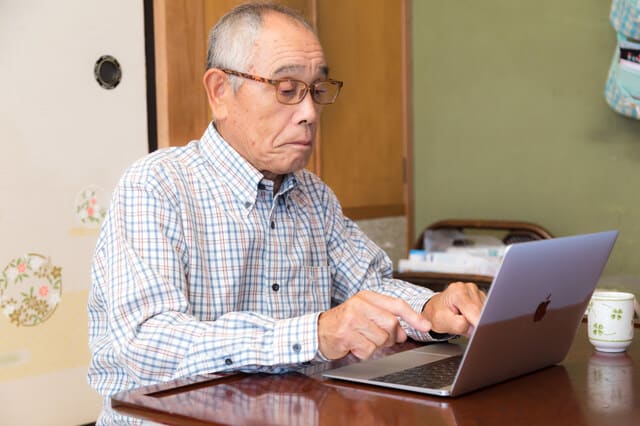奈良新聞「明風清音」欄に、月1~2回、寄稿している。昨日(2025.6.19)掲載されたのは〈「奥明日香さらら」の軌跡〉、店主の坂本博子さんのご著書『もちつもたれつ栢森 それでもやっぱりここが好き』の紹介である。
※写真は「さらら膳」(2,200円 お店のHPより)。以前は2,500円だったが、値下がりしていた!
同店の15周年を機に出版を決意され、昨年12月に刊行された。私はお店が開店した年(2008年)の11月1日に訪ね、当ブログで紹介した。その後、私の知人も何人か、ブログを見てお店を訪ねている。では、記事全文を紹介する。
「奥明日香さらら」の軌跡
明日香村栢森(かやのもり)で農家レストラン「ふるさとの食 奥明日香さらら」を運営される坂本博子さんが、『もちつもたれつ栢森 それでもやっぱりここが好き』(税別1500円)を自費出版された。
サイト「本屋とほん」には、〈2008年に明日香村栢森にて「奥明日香さらら」を開店した店主によるエッセイ集。開業から現在にいたるまでの日々を、心を込めた文章で綴(つづ)っています。博子さん語録や繋(つな)がりのある人たちによる寄稿文、座談会も収録されており、さまざまな角度からその魅力を知ることができる1冊です〉とある。
店名は、持統天皇の即位前の名「鸕野讃良(うののさらら)皇女」にちなんでいる。天皇は在位中、奥明日香から芋峠を越えて宮滝の吉野離宮へ、31回も足を運んだと言われる。
本書は、さららの歴史を振り返った1章、坂本さんのブログから抜粋された2章、ご縁のある方の文章を載せた3章、巻末にはさらら隊(支援者たち)による座談会や年表などがつく。まさに名物「さらら膳」のように、おいしくて体に良いものをギュギュッと凝縮した一冊である。以下、私の目に止まったところを1、2章から抜粋する。
▼「さらら膳」が誕生
2002年、村役場主導で奥明日香(稲渕、栢森、入谷)の活性化事業がスタート。03年には「加工グループさらら」が発足し、地元食材を使った「さらら膳」を考案する。
〈03年に立ち上がった「加工グループさらら」の活動と共にあった5年間。私にとって、体力的にも精神的にもしんどいことのほうが多かったこの5年がなければ、「奥明日香さらら」は産まれてもいなかったし、この5年があったからこそ、「奥明日香さらら」は今も存在しているのだと思います〉(本書から抜粋、以下同様)。
近隣の地区委員、各種団体の代表者、役場職員たちが参加して、さらら膳の試食会が開かれた。その時の感想は〈「こんなもん、昨日も一昨日も家で食べたわ、ここは草(山菜)食べさせるんか?」「ちゃんとした料理人も置かずに、失敗したら格好が悪いで」「もっとボリュームのあるものでないと食べた気がせんわ」「味が薄い、何食べてるかわからんわ」エトセトラ、エトセトラ。こんな風にぼろくそに言われても、妙に自信がありました。試食会で感想を言ってもらっても、「何にも知らんおっちゃんたちやなあ。現代人は薄味を好むねん」と全然参考にしない私(笑)〉。
本書では「なにくそ精神」とお書きだが、坂本さんのベースには、このような負けじ魂とポジティブ思考があるようだ。
▼空き家を購入し、事業開始
5年間の準備期間を経て、事業化することになった。空き家の購入と改修費用は、約2000万円。資金は自己資金のほか一部は、ご友人とお姉さんから借りた。〈何かに、背中を押されていたんだと思います。突拍子もないことをしでかそうとしている私を、「しゃないなあ~」と思ってくれた何かに力を借りることができたんだと思います〉。
▼「人生の楽園」に出演
主婦が地域おこしの延長でお店を開業したことは、大きな話題となった。〈明日香村には遺跡発掘などの取材のため、マスコミの方々が常に村内でネタ探しをしておられ、よく取材していただきました。(中略)取材を受けるという行為は、モチベーションアップにつながります。こちらからアプローチしたことは一度もないのですが、オープン以来、ずっと続いてくれています〉。
新聞・雑誌はもちろん、11年には、「人生の楽園」(テレビ朝日系)にも出演された。
▼「住民が生活しながら守る」
坂本さんは、30年以上前の役場職員のこんなひと言が、今も心に刻まれているという。〈坂本さん、美しい景観を残すためには、その地域を国や県が保護することもひとつの手段やけど、地域住民が生活をしながら守っていくことも大切やねん。ここをそんな風に残したいねん〉。本書のご注文は、奥明日香さらら(電)0744-54-5005。
なお本書の出版を記念して、坂本さんは7月4日(金)14時頃~20時、「きまぐれ古本市in吉野・上市」(清谷堂書店主催)でトークをされる。テーマは「歳を重ねる」、場所は旧渡邊呉服店(吉野上市郵便局前・吉野町上市193-1(電)080-4449-6406)。
ぜひ足をお運びください!(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)

※写真は「さらら膳」(2,200円 お店のHPより)。以前は2,500円だったが、値下がりしていた!
同店の15周年を機に出版を決意され、昨年12月に刊行された。私はお店が開店した年(2008年)の11月1日に訪ね、当ブログで紹介した。その後、私の知人も何人か、ブログを見てお店を訪ねている。では、記事全文を紹介する。
「奥明日香さらら」の軌跡
明日香村栢森(かやのもり)で農家レストラン「ふるさとの食 奥明日香さらら」を運営される坂本博子さんが、『もちつもたれつ栢森 それでもやっぱりここが好き』(税別1500円)を自費出版された。
サイト「本屋とほん」には、〈2008年に明日香村栢森にて「奥明日香さらら」を開店した店主によるエッセイ集。開業から現在にいたるまでの日々を、心を込めた文章で綴(つづ)っています。博子さん語録や繋(つな)がりのある人たちによる寄稿文、座談会も収録されており、さまざまな角度からその魅力を知ることができる1冊です〉とある。
店名は、持統天皇の即位前の名「鸕野讃良(うののさらら)皇女」にちなんでいる。天皇は在位中、奥明日香から芋峠を越えて宮滝の吉野離宮へ、31回も足を運んだと言われる。
本書は、さららの歴史を振り返った1章、坂本さんのブログから抜粋された2章、ご縁のある方の文章を載せた3章、巻末にはさらら隊(支援者たち)による座談会や年表などがつく。まさに名物「さらら膳」のように、おいしくて体に良いものをギュギュッと凝縮した一冊である。以下、私の目に止まったところを1、2章から抜粋する。
▼「さらら膳」が誕生
2002年、村役場主導で奥明日香(稲渕、栢森、入谷)の活性化事業がスタート。03年には「加工グループさらら」が発足し、地元食材を使った「さらら膳」を考案する。
〈03年に立ち上がった「加工グループさらら」の活動と共にあった5年間。私にとって、体力的にも精神的にもしんどいことのほうが多かったこの5年がなければ、「奥明日香さらら」は産まれてもいなかったし、この5年があったからこそ、「奥明日香さらら」は今も存在しているのだと思います〉(本書から抜粋、以下同様)。
近隣の地区委員、各種団体の代表者、役場職員たちが参加して、さらら膳の試食会が開かれた。その時の感想は〈「こんなもん、昨日も一昨日も家で食べたわ、ここは草(山菜)食べさせるんか?」「ちゃんとした料理人も置かずに、失敗したら格好が悪いで」「もっとボリュームのあるものでないと食べた気がせんわ」「味が薄い、何食べてるかわからんわ」エトセトラ、エトセトラ。こんな風にぼろくそに言われても、妙に自信がありました。試食会で感想を言ってもらっても、「何にも知らんおっちゃんたちやなあ。現代人は薄味を好むねん」と全然参考にしない私(笑)〉。
本書では「なにくそ精神」とお書きだが、坂本さんのベースには、このような負けじ魂とポジティブ思考があるようだ。
▼空き家を購入し、事業開始
5年間の準備期間を経て、事業化することになった。空き家の購入と改修費用は、約2000万円。資金は自己資金のほか一部は、ご友人とお姉さんから借りた。〈何かに、背中を押されていたんだと思います。突拍子もないことをしでかそうとしている私を、「しゃないなあ~」と思ってくれた何かに力を借りることができたんだと思います〉。
▼「人生の楽園」に出演
主婦が地域おこしの延長でお店を開業したことは、大きな話題となった。〈明日香村には遺跡発掘などの取材のため、マスコミの方々が常に村内でネタ探しをしておられ、よく取材していただきました。(中略)取材を受けるという行為は、モチベーションアップにつながります。こちらからアプローチしたことは一度もないのですが、オープン以来、ずっと続いてくれています〉。
新聞・雑誌はもちろん、11年には、「人生の楽園」(テレビ朝日系)にも出演された。
▼「住民が生活しながら守る」
坂本さんは、30年以上前の役場職員のこんなひと言が、今も心に刻まれているという。〈坂本さん、美しい景観を残すためには、その地域を国や県が保護することもひとつの手段やけど、地域住民が生活をしながら守っていくことも大切やねん。ここをそんな風に残したいねん〉。本書のご注文は、奥明日香さらら(電)0744-54-5005。
なお本書の出版を記念して、坂本さんは7月4日(金)14時頃~20時、「きまぐれ古本市in吉野・上市」(清谷堂書店主催)でトークをされる。テーマは「歳を重ねる」、場所は旧渡邊呉服店(吉野上市郵便局前・吉野町上市193-1(電)080-4449-6406)。
ぜひ足をお運びください!(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)