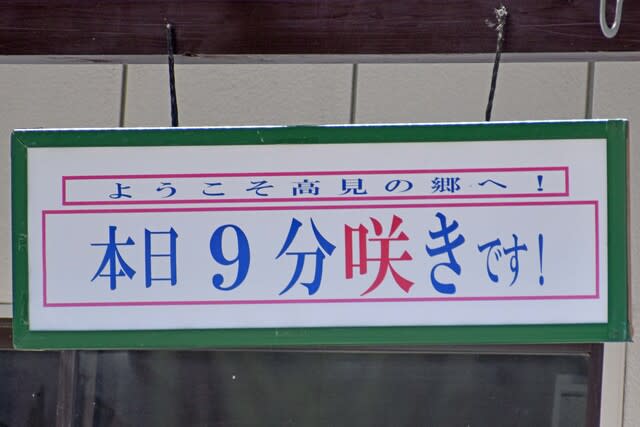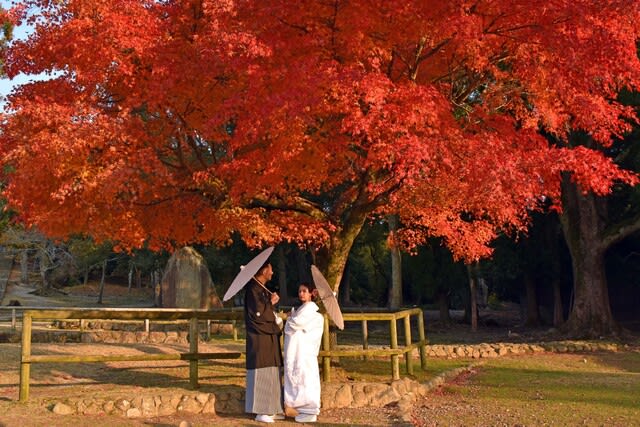五月晴れの今日(2025.5.3)正午から、平城宮跡で、「平城京天平行列」を見物してきた。県知事が「予算をつけない」としたが、平城京天平行列の会(旧平城京天平祭実行委員会)が中心になって、この行事を継続している。秋にも、「東大寺参詣」(秋の天平行列)を行うそうだ(11月3日開催予定)。

まずは、聖武天皇が登場

両陛下の前で、お子たちが舞を舞った
かつては奈良時代に即位したすべての天皇・皇后が行列していたが、この日は聖武天皇・光明皇后だけ。それでも衛士隊の行進や、女性貴族・子どもさんの行列もあり、結構楽しめた。

朱雀門前で整列。これは以前にはなかったシーンだ!

光明皇后は、やはりきれいな女性が扮していた


行列の参加者が少ない分、観客も少なかったので、写真を撮るには有り難い。今まで、なかなか正面からのショットは撮れなかった。
春の陽ざしを浴びながら、楽しく写真を撮り回った。GW後半は、5月5日(月・祝)までは、天気も良さそうだ。皆さんは、どんなGWをお過ごしですか?

まずは、聖武天皇が登場

両陛下の前で、お子たちが舞を舞った
かつては奈良時代に即位したすべての天皇・皇后が行列していたが、この日は聖武天皇・光明皇后だけ。それでも衛士隊の行進や、女性貴族・子どもさんの行列もあり、結構楽しめた。

朱雀門前で整列。これは以前にはなかったシーンだ!

光明皇后は、やはりきれいな女性が扮していた


行列の参加者が少ない分、観客も少なかったので、写真を撮るには有り難い。今まで、なかなか正面からのショットは撮れなかった。
春の陽ざしを浴びながら、楽しく写真を撮り回った。GW後半は、5月5日(月・祝)までは、天気も良さそうだ。皆さんは、どんなGWをお過ごしですか?