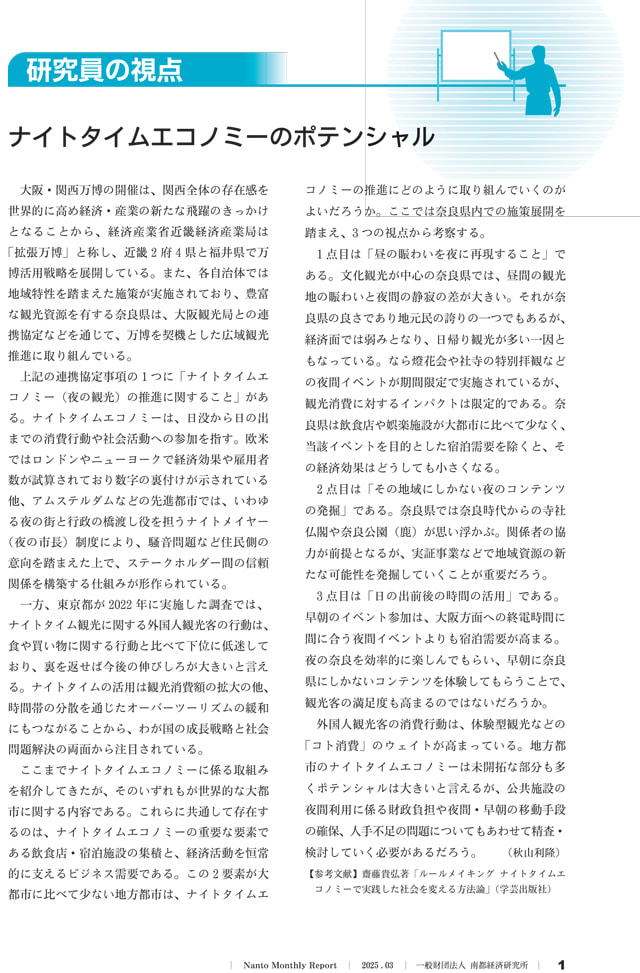藤丸正明さん(株式会社地域活性局 代表取締役)が、ご自身のFacebookに「外資のホテルに関して一言 言わせて」という文章を投稿されていた。よく掘り下げた内容だし、それに対するコメントも興味深いので抜粋して、ここに紹介させていただく。まずは藤丸さんの投稿。
※トップ写真は、ぱくたそ(著作権フリーの写真素材サイト)から拝借した
外資のホテルに関して一言 言わせて(藤丸正明さん)
奈良に多くの外資系ホテルが参入しています。ならまち地域に1人でも多くの人を呼び込みたい私としては、多くの宿泊施設を回ります。地元資本のホテルの方は基本的に協力的で、やりとりも丁寧にしてくださいます。
一方で、外資系のホテルは全てがそうだとは言いませんが、ならまちを知らない担当者が、一度は付き合いで出てきても、2度目はメールも返事がなく、電話してもいませんで、終わります。
一方で、行政は宿泊施設を誘致したがります。奈良は全国で最も宿泊者数が少ないとか、奈良市は全国の県庁所在地の中で最も別途数が少ないとか、色々と言われています。
でも、立ち止まって考えて欲しいことは、他のほとんどの地域は外から宿泊施設を誘致するような事ではなく、地元資本が大きくなることを目的に行政運営して、今の宿泊客数とかベッド数があると思います。
地元資本が納税した税金が、県外の外資系資本のホテル誘致に使われて、結果として地元資本の競争相手を作っていくと言うのは、地獄絵図ではないかと思います。
私の会社は創業時にレンタサイクルをやっていましたが、奈良市役所がすぐ近所でモバイク事業を始めたことで、レンタサイクルは辞めざるを得なくなりました。ただ、嫌がらせで、モバイクもやがて撤退しました。
観光の世界はこう言う謎の外勢力の優遇をすることで、地域の観光力の平易化(弱体化?)を結果として進めてしまっている現状があります。地元資本を支援して納税額を伸ばすことが行政の基本だと思いますが、そうなっていない奈良の現状は想像以上に悲惨だと思います。
これに対して、猿渡晴子さん(Freelance Licensed Guide)から、こんなコメントが入った。
地元資本の支援、大事だと思います。どのくらいの規模の宿泊者を受け入れるのかなどスイスのある観光地は住民が全てを話し合いで決めています。一般車の乗り入れを制限しており、町中で走っている小さな道に適応した電気自動車は全て地元の会社(というか製造所?)が作ったものです。
実際にはよその地域から出来合いのもの買えば安く調達できるだそうですが、住民の方々はそれを良しとしていません。そうして地域の産業を守りひいては住民の生活を守り、住民が納得して観光業と共存できるようにしているようです。
日本もそろそろ学んで、安易な外資の取り込みによる現地経済の疲弊と将来的な産業の縮小(廃業)を避ける方向でいかないと日本の、そして日本人の生活が成り立たなくなると思います。
これに対する藤丸さんのコメントは、
日本って外資に都合よく刈り取られていますよね。スイスって地理的環境を補うための人間力を磨き上げている印象があります。あと、いま、日本って政治家任せで、市民って議論に参加できるような仕組みも感覚もないですよね。住民自治になっていないのもまた課題ですね。
金田充史さん(ゲストハウス はる きたまち オーナー)も、途中から参戦された。
1862年に、既に旅館営業を開始していたのにも拘わらず、2013年に閉館した奈良市の旅館経営者からの見解です。因みに、また宿泊施設をやっとります。今はゲストハウスだけど。平成になって、更に阪神淡路大震災後、かなり旅行の環境が変わった感がします。
ただ、不況になればアウトドアが流行りますが、阪神淡路後もアウトドアが急増して、旅館に泊まって旅行をすると云う様式が変化しました。で、その後はどうなったかと云うと、今度はホテルに泊まってになって、旅館は、全国的に一部の施設を除いて、淘汰の時代に入ります。巨大温泉旅館の廃墟が林立して、今の社会問題に続く事態になったのも、ここがスタートです。
で、奈良はどうかと云うと、高度規制・容積率・建ぺい率の数値が、建築する視点では極端に悪く、超低層階しか建築出来ないので、他の地域の施設からすれば、思いっ切り見劣りがして、宿泊施設として認識されなくなったと云うのが1つ有ります。
その為に、奈良市は平成10年に、旧・三井ガーデンホテルの土地を含む、JR奈良駅西側のみ、高度規制は40m・容積率は400%・建ぺい率200%と、土地規制の大幅緩和をして建築させた訳ですが、それでも大阪・京都と比較すれば見劣りし、旧・三井ガーデンホテルは赤字のまま撤退となりました(=現在はホテル日航奈良)。
で、旧来の店舗は、そのまま何の恩恵も有りません。自分たちでナンとかしろってだけ。民間事業者ですから、当たり前な訳ですけど、今は奈良市だけで宿泊を考える時代でも無く、大阪や京都、神戸と云った近畿圏内での宿泊需要に取って変わられました。
つまり、大阪や京都で泊まっても、交通手段の利便性が非常に良くなり、奈良市で泊まる必要が無い訳です。既に昭和時代に、修学旅行の京都2泊が主流になったのが、それを物語っています。
その上、旧来なら奈良で泊まって、早朝に出発すると云うコースも有りましたが、京奈和道路が出来た為に、夕刻に奈良市を出発して京都泊まりと云うコースに変更されてしまいました。
交通の利便性、特に道路については、こうした事態になる傾向で、実際、白浜も、地元資本の旅館が激減して、湯快リゾートとカラカミ観光になっています。隣町の椿温泉は廃墟になりましたね。
ただ、非常に残念な事に、こうした事態に対して、当事者の旅館団体は、単に指を咥えてオウンゴール状態。これでは勝てるものも勝てない訳で、これは第一に、大阪や京都に勝てる様な施設を建設するだけの、土地のポテンシャルを持たせなかった奈良県の土木行政に、問題の根源が有ります。今はそれが奈良市に移り、もっと無能な職員がオペレーションする様になり、更に条件が悪くなっています。
ただ1つ言えるのは、この土地のポテンシャルで進出するホテル群は、他府県の施設と比較して、非常にチンケなもんになっています。その為に稼げずに、グループとして、いわばお荷物となっている訳です。
そんなホテルに、マトモな支配人や料理長が来る事も無く、人的ポテンシャルも最低となり、藤丸さんの仰る、なんにも知らない…、と云う事態になる訳です。つまり、奈良と云う土地が、そこまでのポテンシャルしか無くて、今の時代に合う宿泊施設が、事実上建てさせて貰えないと云う訳ですね。
これに対する藤丸正明さんのコメント。
宿泊を増やすことは同時に高さ規制にメスを入れないといけないというのが結論ですね。それをせずに補助金頼みで行くのはちょっと違うような思います。もっとも、高い建物が乱立するのも問題だとは思うので、何かやり方を考えるべきですよね。
高さ規制を守らないと、古都の景観がだいなしになる。自治体がホテル誘致を進めると、県外や海外の資本を導入することになり、地元の宿泊施設がダメージを受ける。「あちらを立てれば、こちらが立たず」というジレンマに悩まされている、というのが奈良の観光行政なのだ。
しかし宿泊施設が不足しているのは、厳然たる事実である。「ホテルフジタ奈良」の跡地がマンションになると聞いてガッカリしたが、地元の既存施設と共存共栄できる宿泊施設の誘致を望みたい。
※6/17追記 当ブログに金田充史さんから、コメントをいただきましたので、以下に紹介させていただきます。金田さん、ありがとうございました。
民間の競合原理 (金田充史) 2025-06-16 14:26:21
この問題は、「あちらが立てばこちらが・・」になるのは当たり前な訳です。つまり、役所が両立を考えようとした事自体が、そもそも誤っています。また、付和雷同した様に、役所の見解で「ホテルが建たない」って合唱したプレスも、根源を見ていないと判断していますし、その考え方は、未だに変わっておりません。10年以上前に、この鉃田さんのブログに書かせて頂いたのも記憶しています。
他府県資本が入って、地元資本が疲弊するのは、何も宿泊施設だけでは無くて、全国的に起こっている事案です。商店街の空洞化も、郊外の全国資本の進出が要因の1つですし、パチンコ産業も、大資本になって、商店街のパチンコ屋さんの大半が消えています。
ただ、そうは言っても、大資本に負けない経営をされているビジネスホテルや旅館も存在しているのも事実。香川県の「川六」さんや、和歌山の「かつうら御苑」さんなどは、その最右翼かと。両社の社長氏は仲良しです。
両社の体制を外野ですけど、見ていたら、まずは人材ですね。人材に勝るものはありません。長年やっていたからこその人材が揃い、中央資本に負けない経営が出来ています。逆に、中央資本が、新規での採用にしかならず、サービス基準が一定化しないと云う事態にもなる訳で、ここが、藤丸氏の言う、「地域の事がわからない」につながる事だと感じます。
中央資本だとて、その中の社員さんが、当該地域の地元に対して、どれだけリスペクトしているかと云う点に注目すれば良く解る事です。中央資本だとて、地元の人間と、フェイストゥフェイスになれば、ちゃんと情報も入りますし、また、一緒にと云う事態にもなる訳で、一時期、そうした時期も有りましたし、そういう人材の人も出て来ました。
ただ、この数年で進出の外資に限定すれば、そういう人は出て来ないですね。外資でも、営業しているのは外国では無く、同じ日本国内の地域です。お客様に地域に来て貰う為なら、外資も地元も有りません。そこら辺りが、外国人の支配人が居たら、肌感覚の違いが出てしまう原因とでも云う事になる気がします。また、日本人でも、都市部だけでしか居なかったら、そういう感覚ってわからないでしょう。
ただ、これもスキルの問題やと思いますけど、私が奈良県のダントツ№1と思っているホテルの元支配人は、地元を一生懸命研究されていましたね。また、県庁が、喉から手が出る位欲しいランクのお客様を大量にお持ちでした。また、そうした方々をお連れして、滝坂の道や山の辺をご案内されていました。これが真のホテルだと思い、感服した次第です。
中央資本か地元資本かと云う点も大切ですけど、進出した以上、どれだけ地元と一緒に・・って事や無いでしょうかねぇ。それだけの人的ポテンシャルを持った人が、ちゃんと奈良に来てくれるのか、また、中央資本がどこまで奈良県に対してリスペクトしているのか、そこがポイントの気がします。
※トップ写真は、ぱくたそ(著作権フリーの写真素材サイト)から拝借した
外資のホテルに関して一言 言わせて(藤丸正明さん)
奈良に多くの外資系ホテルが参入しています。ならまち地域に1人でも多くの人を呼び込みたい私としては、多くの宿泊施設を回ります。地元資本のホテルの方は基本的に協力的で、やりとりも丁寧にしてくださいます。
一方で、外資系のホテルは全てがそうだとは言いませんが、ならまちを知らない担当者が、一度は付き合いで出てきても、2度目はメールも返事がなく、電話してもいませんで、終わります。
一方で、行政は宿泊施設を誘致したがります。奈良は全国で最も宿泊者数が少ないとか、奈良市は全国の県庁所在地の中で最も別途数が少ないとか、色々と言われています。
でも、立ち止まって考えて欲しいことは、他のほとんどの地域は外から宿泊施設を誘致するような事ではなく、地元資本が大きくなることを目的に行政運営して、今の宿泊客数とかベッド数があると思います。
地元資本が納税した税金が、県外の外資系資本のホテル誘致に使われて、結果として地元資本の競争相手を作っていくと言うのは、地獄絵図ではないかと思います。
私の会社は創業時にレンタサイクルをやっていましたが、奈良市役所がすぐ近所でモバイク事業を始めたことで、レンタサイクルは辞めざるを得なくなりました。ただ、嫌がらせで、モバイクもやがて撤退しました。
観光の世界はこう言う謎の外勢力の優遇をすることで、地域の観光力の平易化(弱体化?)を結果として進めてしまっている現状があります。地元資本を支援して納税額を伸ばすことが行政の基本だと思いますが、そうなっていない奈良の現状は想像以上に悲惨だと思います。
これに対して、猿渡晴子さん(Freelance Licensed Guide)から、こんなコメントが入った。
地元資本の支援、大事だと思います。どのくらいの規模の宿泊者を受け入れるのかなどスイスのある観光地は住民が全てを話し合いで決めています。一般車の乗り入れを制限しており、町中で走っている小さな道に適応した電気自動車は全て地元の会社(というか製造所?)が作ったものです。
実際にはよその地域から出来合いのもの買えば安く調達できるだそうですが、住民の方々はそれを良しとしていません。そうして地域の産業を守りひいては住民の生活を守り、住民が納得して観光業と共存できるようにしているようです。
日本もそろそろ学んで、安易な外資の取り込みによる現地経済の疲弊と将来的な産業の縮小(廃業)を避ける方向でいかないと日本の、そして日本人の生活が成り立たなくなると思います。
これに対する藤丸さんのコメントは、
日本って外資に都合よく刈り取られていますよね。スイスって地理的環境を補うための人間力を磨き上げている印象があります。あと、いま、日本って政治家任せで、市民って議論に参加できるような仕組みも感覚もないですよね。住民自治になっていないのもまた課題ですね。
金田充史さん(ゲストハウス はる きたまち オーナー)も、途中から参戦された。
1862年に、既に旅館営業を開始していたのにも拘わらず、2013年に閉館した奈良市の旅館経営者からの見解です。因みに、また宿泊施設をやっとります。今はゲストハウスだけど。平成になって、更に阪神淡路大震災後、かなり旅行の環境が変わった感がします。
ただ、不況になればアウトドアが流行りますが、阪神淡路後もアウトドアが急増して、旅館に泊まって旅行をすると云う様式が変化しました。で、その後はどうなったかと云うと、今度はホテルに泊まってになって、旅館は、全国的に一部の施設を除いて、淘汰の時代に入ります。巨大温泉旅館の廃墟が林立して、今の社会問題に続く事態になったのも、ここがスタートです。
で、奈良はどうかと云うと、高度規制・容積率・建ぺい率の数値が、建築する視点では極端に悪く、超低層階しか建築出来ないので、他の地域の施設からすれば、思いっ切り見劣りがして、宿泊施設として認識されなくなったと云うのが1つ有ります。
その為に、奈良市は平成10年に、旧・三井ガーデンホテルの土地を含む、JR奈良駅西側のみ、高度規制は40m・容積率は400%・建ぺい率200%と、土地規制の大幅緩和をして建築させた訳ですが、それでも大阪・京都と比較すれば見劣りし、旧・三井ガーデンホテルは赤字のまま撤退となりました(=現在はホテル日航奈良)。
で、旧来の店舗は、そのまま何の恩恵も有りません。自分たちでナンとかしろってだけ。民間事業者ですから、当たり前な訳ですけど、今は奈良市だけで宿泊を考える時代でも無く、大阪や京都、神戸と云った近畿圏内での宿泊需要に取って変わられました。
つまり、大阪や京都で泊まっても、交通手段の利便性が非常に良くなり、奈良市で泊まる必要が無い訳です。既に昭和時代に、修学旅行の京都2泊が主流になったのが、それを物語っています。
その上、旧来なら奈良で泊まって、早朝に出発すると云うコースも有りましたが、京奈和道路が出来た為に、夕刻に奈良市を出発して京都泊まりと云うコースに変更されてしまいました。
交通の利便性、特に道路については、こうした事態になる傾向で、実際、白浜も、地元資本の旅館が激減して、湯快リゾートとカラカミ観光になっています。隣町の椿温泉は廃墟になりましたね。
ただ、非常に残念な事に、こうした事態に対して、当事者の旅館団体は、単に指を咥えてオウンゴール状態。これでは勝てるものも勝てない訳で、これは第一に、大阪や京都に勝てる様な施設を建設するだけの、土地のポテンシャルを持たせなかった奈良県の土木行政に、問題の根源が有ります。今はそれが奈良市に移り、もっと無能な職員がオペレーションする様になり、更に条件が悪くなっています。
ただ1つ言えるのは、この土地のポテンシャルで進出するホテル群は、他府県の施設と比較して、非常にチンケなもんになっています。その為に稼げずに、グループとして、いわばお荷物となっている訳です。
そんなホテルに、マトモな支配人や料理長が来る事も無く、人的ポテンシャルも最低となり、藤丸さんの仰る、なんにも知らない…、と云う事態になる訳です。つまり、奈良と云う土地が、そこまでのポテンシャルしか無くて、今の時代に合う宿泊施設が、事実上建てさせて貰えないと云う訳ですね。
これに対する藤丸正明さんのコメント。
宿泊を増やすことは同時に高さ規制にメスを入れないといけないというのが結論ですね。それをせずに補助金頼みで行くのはちょっと違うような思います。もっとも、高い建物が乱立するのも問題だとは思うので、何かやり方を考えるべきですよね。
高さ規制を守らないと、古都の景観がだいなしになる。自治体がホテル誘致を進めると、県外や海外の資本を導入することになり、地元の宿泊施設がダメージを受ける。「あちらを立てれば、こちらが立たず」というジレンマに悩まされている、というのが奈良の観光行政なのだ。
しかし宿泊施設が不足しているのは、厳然たる事実である。「ホテルフジタ奈良」の跡地がマンションになると聞いてガッカリしたが、地元の既存施設と共存共栄できる宿泊施設の誘致を望みたい。
※6/17追記 当ブログに金田充史さんから、コメントをいただきましたので、以下に紹介させていただきます。金田さん、ありがとうございました。
民間の競合原理 (金田充史) 2025-06-16 14:26:21
この問題は、「あちらが立てばこちらが・・」になるのは当たり前な訳です。つまり、役所が両立を考えようとした事自体が、そもそも誤っています。また、付和雷同した様に、役所の見解で「ホテルが建たない」って合唱したプレスも、根源を見ていないと判断していますし、その考え方は、未だに変わっておりません。10年以上前に、この鉃田さんのブログに書かせて頂いたのも記憶しています。
他府県資本が入って、地元資本が疲弊するのは、何も宿泊施設だけでは無くて、全国的に起こっている事案です。商店街の空洞化も、郊外の全国資本の進出が要因の1つですし、パチンコ産業も、大資本になって、商店街のパチンコ屋さんの大半が消えています。
ただ、そうは言っても、大資本に負けない経営をされているビジネスホテルや旅館も存在しているのも事実。香川県の「川六」さんや、和歌山の「かつうら御苑」さんなどは、その最右翼かと。両社の社長氏は仲良しです。
両社の体制を外野ですけど、見ていたら、まずは人材ですね。人材に勝るものはありません。長年やっていたからこその人材が揃い、中央資本に負けない経営が出来ています。逆に、中央資本が、新規での採用にしかならず、サービス基準が一定化しないと云う事態にもなる訳で、ここが、藤丸氏の言う、「地域の事がわからない」につながる事だと感じます。
中央資本だとて、その中の社員さんが、当該地域の地元に対して、どれだけリスペクトしているかと云う点に注目すれば良く解る事です。中央資本だとて、地元の人間と、フェイストゥフェイスになれば、ちゃんと情報も入りますし、また、一緒にと云う事態にもなる訳で、一時期、そうした時期も有りましたし、そういう人材の人も出て来ました。
ただ、この数年で進出の外資に限定すれば、そういう人は出て来ないですね。外資でも、営業しているのは外国では無く、同じ日本国内の地域です。お客様に地域に来て貰う為なら、外資も地元も有りません。そこら辺りが、外国人の支配人が居たら、肌感覚の違いが出てしまう原因とでも云う事になる気がします。また、日本人でも、都市部だけでしか居なかったら、そういう感覚ってわからないでしょう。
ただ、これもスキルの問題やと思いますけど、私が奈良県のダントツ№1と思っているホテルの元支配人は、地元を一生懸命研究されていましたね。また、県庁が、喉から手が出る位欲しいランクのお客様を大量にお持ちでした。また、そうした方々をお連れして、滝坂の道や山の辺をご案内されていました。これが真のホテルだと思い、感服した次第です。
中央資本か地元資本かと云う点も大切ですけど、進出した以上、どれだけ地元と一緒に・・って事や無いでしょうかねぇ。それだけの人的ポテンシャルを持った人が、ちゃんと奈良に来てくれるのか、また、中央資本がどこまで奈良県に対してリスペクトしているのか、そこがポイントの気がします。