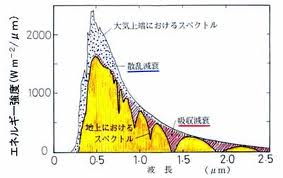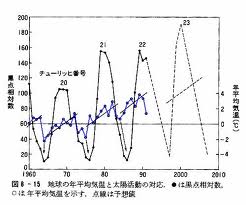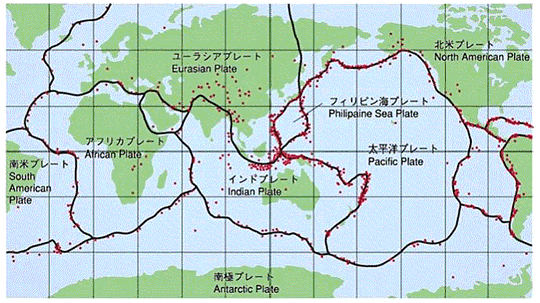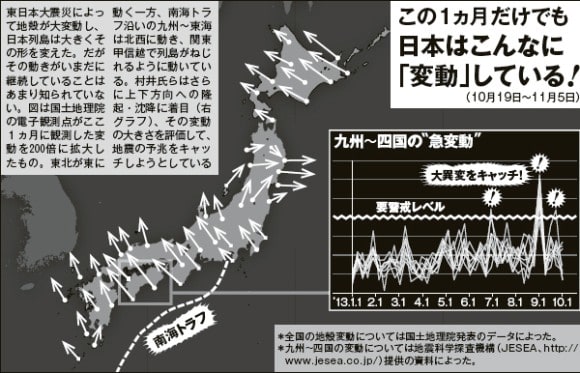’13-11-25投稿
既報歴代首相の脱原発発言を収集してその骨子を整理しました。【追加】での引例(小泉発言)のように、「最終処分場を造れなかったのは住民の反対(があったから)だ。こんなことに莫大(ばくだい)な資金とエネルギーを使うなら、国民が協力できるような、自然を資源にしたさまざまなエネルギーのために使った方がいい、というのが私の主張だ。大きな岐路だ。
原発ゼロの方針を出せば、必ずある人が良い案を作ってくれる。内閣に原発ゼロに賛同する識者を集め、専門家の知恵を借りて結論を尊重して進める」ことを期待していますが、
問題点として、「再生(可能)エネルギーの比率を上げ、原発比率を落とすという方向性において小泉元首相と違うところはない原発ゼロに至るまでの時間や手法、費用の捻出先などの具体論がなければ、単なるスローガンに過ぎない」との見解もあり、
現状、既報 再生可能なエネルギーに係る記載(その25:日本とドイツのエネルギー関係データの比較)(2013-10-31)によれば、
再生可能エネルギーの割合は、
日本1.6% ?VS ドイツ20.3%
技術的には、劣っていない?と思われるのに、はかばかしくない普及率から、当面、再生エネには頼れない現状。
個人的には、「塵も積もれば山となる」ことを期して、再生エネの普及に対して、再生可能エネルギーによる発電量がどのように、現状の1.6%からどのくらい増加推移しているか掲示板、等での「見える化」によって国民がわかるようなシステムがほしいところです。
既報今までの「再生可能なエネルギーに係る投稿」の整理('11-5-21~'12-2-29)に記載しましたように、
10数年前、技術的に優位に立っていたわが国の再生可能なエネルギー技術は量産化技術の立ち遅れ、恵まれない気象条件、島国のためヨーロッパなどと比べて電力の融通性に欠けること、原子力関連への偏重予算に加えて、大手電力会社になどによる発電事業者への電力買取拒否などから、および、ドイツ、中国などに後塵を浴びている現状から、再生可能なエネルギーの進展に係る積極的な政策誘導的な支援の成果すら見えません。
なぜそのようになったのか?を議論して、結論を出して、ドイツのように着実に普及させて、挽回することが必要と思われます。
ドレスデン情報ファイル
http://www3.ocn.ne.jp/~elbe/kiso/atomdata04.html
ドイツのエネルギー関係データ
電力に占める再生可能エネルギーの割合
まえがきが長くなりましたが、
個人的には、丘陵を利用した小規模水力発電、排他的経済水域を利用した海上風車などは立地、気象条件さえ満たせば、政策補助、開発予算次第では分散型として有望か?
分散型として最適な太陽光発電はコストが高すぎるので、部品の製造コストの低減および取り付けコストが安くなるシースルー、フレキシブルな薄膜タイプの画期的な開発推進が期待されます。
水力発電に再び脚光、小水力発電の現状および問題点について調べました。
水力発電に再び脚光、工場や農地で「小水力発電」
「水力発電と聞くと山間にある大規模なダムを想像しがちで、これまでは環境破壊の代表のように考えられてきた。ところが固定価格買取制度の対象に入ったことをきっかけに、河川や工業・農業用水路などを活用した「小水力発電」が注目を集め、全国各地で小規模な設備の導入が進み始めた。
本来であれば水力発電は化石燃料に依存しない再生可能エネルギーの代表格のはずだが、大規模なダム式や火力・原子力発電を必要とする揚水式が主流のため、再生可能エネルギーに分類されないことが多い(図1)。もともとは自然な水の流れを生かした発電方法であり、一定規模以下の発電設備であれば固定価格買取制度の対象として認められる。・・・
特に注目を集めているのが発電規模の小さい「小水力発電」と呼ばれるもので、通常は発電能力が200kW未満の場合を指す。この小水力発電のコストや効率性を太陽光発電と比較して
水の流れは安定、発電量も落ちない
最新の太陽光パネルの発電能力は面積が1平方メートルあたりで150W程度である。仮に150kWの発電能力を実現するには、1000平方メートル分の太陽光パネルが必要になる計算だ。これに対して200kW以下の小水力発電に必要な水車の大きさは直径1メートル以下のものが多く、収容する建物も小規模で済む(図2)。・・・
発電設備の形態が違うので単純な比較はできないものの、太陽光発電よりも用地は小さくて十分だろう。特に河川に近くて水を大量に使う工場や農地に向いている。
では実際にかかる建設費や期待できる発電量はどうなのか。環境省が分析した結果では、1kWhの電力を作るコストは太陽光発電よりも低い(図3)。その最大の要因は天候による影響が小さいことにある。
太陽光や風力の場合は、1kWの発電能力があっても、実際に得られる電力量は平均すると1割~2割程度まで落ちてしまう。これに対して小水力発電では水量や落差によって決まり、平均して7割程度の発電効率(設備利用率)を維持することができる。水の流れは雨の影響などはあるものの、太陽の日射量や風の強さほどには大きく変動しない。
発電効率が7割ならば10年で元をとれる
最大の問題点は建設費と運転維持費の高さである。固定価格買取制度における見積もりでは、発電能力が200kW未満の小水力発電の場合、建設費は1kWあたり100万円で、太陽光発電の2倍以上になる。運転維持費も年間で7万5000円/kWと他の発電方法を大きく上回る(図4)。
仮に100kWの小水力発電を実現させるとなると、建設費で1億円、運転維持費で毎年750万円かかる。もちろんこの費用を前提に買取価格が決められているため、他の発電方法と比べて決して不利ということはない。
200kW未満の場合の買取価格は税引き後で34円/kWhに設定されている。発電効率が平均的な7割と想定すると、100kWの発電設備で年間に約60万kWhの電力を作り出すことができ、2000万円程度の収益を見込める。10年間で建設費と運転維持費を十分にカバーして元をとれる計算が成り立つ。
あとは水量や落差によって決まる発電効率の高い場所を選ぶことである。もし発電効率が5割まで下がってしまうと、採算が合うまでに15年以上かかり、買取期間の20年のうちにコストを回収できないおそれもある。設備を導入する前に入念な設計が必要だ。
図4 発電方法別に定められた固定買取価格。出典:資源エネルギー庁
・・・」という。
参考情報:
日本列島エネルギー改造計画(16)長野:
小水力発電で全国トップ、市民参加型の太陽光発電所も拡大中
「日本最長の信濃川が流れる長野県では水力発電が盛んで、中でも「小水力発電」の導入量は全国で第1位である。県内の電力需要の2割以上を満たし、大規模な水力発電と合わせると6割近くに達する。2020年までには太陽光発電も大幅に増やして自給率をほぼ100%に高める計画だ。[石田雅也,スマートジャパン]・・・」
続きを読む>>
関連投稿:
土砂災害に係る記載(提案:洪水と渇水対策に中規模水力発電ダム増設を)
(2012-07-12)
別報の今までの「再生可能なエネルギーに係る投稿」の整理で記載した再生可能な発電(小規模水力発電)より規模の大きい、かつ、大規模ダム(設置位置;引用下図)より規模の小さいダム発電と治水を兼ねた一石二鳥の「中規模ダム」の建設が立地条件、経済性、生態系への影響には多少目をつぶっても望まれます。
⇒各所の各発電方式実績が現状の1.6%(16000ppm)に対して、何ppm増加させているのか?の見える化の積み重ねが重要かと思われます。