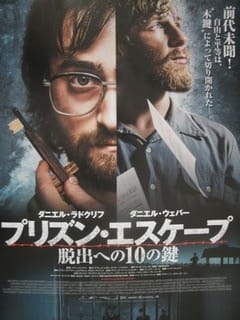原題:『攀登者』 英題:『The Climbers』
監督:ダニエル・リー
脚本:ダニエル・リー/ア・ライ
撮影:トニー・チャン
出演:ウー・ジン/チャン・ツィイー/チャン・イー/ジン・ボーラン/フー・ゴー/ジャッキー・チェン
2019年/中国
史実よりも優先される「メロドラマ」について
日中合作の『オーバーエベレスト 陰謀の氷壁』(ユー・フェイ監督 2019年)を観て後悔したばかりだったが、本作は1960年に北稜からのチョモランマ登頂に世界で初めて成功し、15年後の1975年に再び挑戦する中国の登山隊の実話が元になっているということで観に行ったのだが、相変わらずだった。
やはり気になるのは隊員たちがしているゴーグルで、さすがに隊長のファン・ウージョウは立派なゴーグルを身につけており、中にはサングラスで済ませている者もいるのだが、酷いのは気象チームを率いるシェイ・インで、やはりチャン・ツィイーが演じているためなのかサングラスさえ身につけていないのである。
そのシェイ・インが急に吐血して体調を崩し、何と彼女は肺水腫だったという設定で、写真家として雇われたリー・グオリャンはマルファン症候群を患っており、もう史実よりも「メロドラマ」が優先されていて事実はどうだったのか何が何だか訳が分からず、現実ではあり得ない派手な遭難シーンを堪能するしか楽しみようがないように思う。