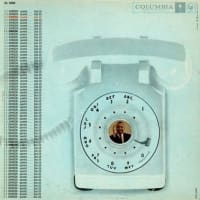拒絶の歴史(69)
ぼくらはまだまだ未完成の学生でもあった。
近くの場所に新しく作られる美術館のデザインの公募があった。ぼくらの教師はちょうど良い機会なので生徒全員に応募してみろ、と言った。それで、ぼくらは頭を悩ませ、いくつもの線を書いては消した。斬新なデザインが望まれており、実際に建築まで行けるか判断する際には、建築士が手を加えるそうである。
その前に、小学生部門、中学生、高校生、大学生、有資格者という段階があった。若ければ若いほどファンタジーに傾き、大人になると空想の飛躍はなくなり実際的な形体になった。それをミックスして後世に残るものにするようだった。それぞれの段階でトップ3が決められ表彰される模様で、ぼくらは学んだ過程を計る機会として活用することにした。
それで授業が終わり、バイトも片付けた後、ぼくは部屋にこもって線を引いた。外部の設計を考え、それに似合った内部のことも考えた。正解がなく、ただ無から作り出すクリエイトの力を試すことは、疲れると同時に爽快感もあった。だが、そればかりにこだわっていると夢の中でもそのことに追い回されている自分がいた。
時間はいくらあっても足りなかったが締め切りがある以上、未完成なものでも仕方がなかった。言い訳でもあるがそれは事実であった。それを教師にいったん見せいくらかアドバイスをもらい、手直しに時間を費やした。そこは経験者の意見でもあったのだろうぼくらの問題はいくらか解決に向かった。
生徒全員のものをまとめてその事務局まで送られた。送られてから、もうそのことは一切忘れてしまった。いつものようにバイトをして、いつものように休日にはサッカーの練習の相手をした。たまに上田先輩の父に呼ばれて、食事をおごってもらうこともあった。ぼくは遠く離れた彼の息子の代役でもあり、また材木を売ることから不動産に手を伸ばした彼の現状と、ぼくの大学生からの意見を交換することもその機会には含まれていた。企業は優秀な人材を確保することに必死になっていた時代であった。それは小さな会社であるならなお更だった。
先日、上田さんの学園祭で会ったときの彼の現況をぼくは彼の父に報告した。父は芸術など形が不明瞭なことに息子が傾斜していることを不安がっていた。しかし、彼の写真や絵画を見た自分はその実力を誉めた。ぼくが誉めたからといって暖かな未来が待っているとも思えないが、そのことは父の表情からよりいっそう理解することができた。こうしてある人を起点に人間関係が膨らんでいった。ぼくは高校時代に体力を使って、山から木材を運ぶバイトをした。そのことはぼくの後輩にも引き継がれており、バイトができない練習の忙しいラグビー部のつかの間の金銭の取得の機会であり、その小さな穴から社会を見るチャンスでもあった。ぼくらはあまりにも運動に傾きがちで、世間というものを知らないで過ごしてしまう恐れがあった。先輩の家の仕事を手伝うことにより、そこは守られた範囲であったが、社会の成り立ちの最初のページが開かれた。
ぼくは注がれるままにビールを飲み干し、息子への愛情と心配の言葉を同じように呑み込んだ。いくつかの問題は解決し、いくつかの問題はそのまま放って置かれた。
ある日、もう忘れてしまった公募の結果が教師の口から告げられた。結果として、ぼくの友人でもあった斉藤という女性の仕事が大学生部門の第三位に選ばれた。賞状といくらかの賞金が彼女に与えられる予定だった。ぼくは幹事になり彼女のお祝いを企画した。ぼくは自分のことのように喜んでいたが、すべての人がそうではなかったと後で知ることになる。そこには嫉妬や羨望の気持ちがあったのだろう。
ぼくは自分の作業にかけた数日が無になってしまうことを悲しいとは思わずに、むしろ潔く感じていた。いつもいつもそう簡単に認められる世の中ではないのだ。認められようが無視されようが、ぼくの可能性が直ぐに変わる訳でもなかった。ただ地道に実力がつくことを求めていた。
ぼくは、ある店で乾杯の合図を叫んでいる。ビールは無数にあり何かのきっかけがあれば盛り上がることのできる年代なのだ。彼女は幸先の良いスタートを切ったが、これからの勉強を考えればそれが有利に働くのか、不利になるのかは誰にも分からなかった。ただ、彼女の発想の良さと問題に対する適用力があることは、確かに立派に証明できた。
彼女は前に立って、自分の功績を恥ずかしがるような言葉を述べた。拍手や冷やかしの言葉があったが、その後その建物がどのように作られ、誰の仕事を推すのかは分からなかった。
ぼくも前に出て最後の言葉を言いその会は終わった。結局のところ騒ぐことが与えられたことと、一致して学ぶことを教えられたようだった。だが、多くの仕事はひとりの時間が求められ、そこで右往左往する過程の結果なのだろう。
ぼくは斉藤さんの荷物を担ぎ、彼女を途中まで送った。ビールの飲みすぎでか彼女の言葉は聞きづらかった。ぼくは暗くなった空き地に自分の創造した建物が建っていることをイメージしようとしたが、それはあまりにも非現実的に思えた。
ぼくらはまだまだ未完成の学生でもあった。
近くの場所に新しく作られる美術館のデザインの公募があった。ぼくらの教師はちょうど良い機会なので生徒全員に応募してみろ、と言った。それで、ぼくらは頭を悩ませ、いくつもの線を書いては消した。斬新なデザインが望まれており、実際に建築まで行けるか判断する際には、建築士が手を加えるそうである。
その前に、小学生部門、中学生、高校生、大学生、有資格者という段階があった。若ければ若いほどファンタジーに傾き、大人になると空想の飛躍はなくなり実際的な形体になった。それをミックスして後世に残るものにするようだった。それぞれの段階でトップ3が決められ表彰される模様で、ぼくらは学んだ過程を計る機会として活用することにした。
それで授業が終わり、バイトも片付けた後、ぼくは部屋にこもって線を引いた。外部の設計を考え、それに似合った内部のことも考えた。正解がなく、ただ無から作り出すクリエイトの力を試すことは、疲れると同時に爽快感もあった。だが、そればかりにこだわっていると夢の中でもそのことに追い回されている自分がいた。
時間はいくらあっても足りなかったが締め切りがある以上、未完成なものでも仕方がなかった。言い訳でもあるがそれは事実であった。それを教師にいったん見せいくらかアドバイスをもらい、手直しに時間を費やした。そこは経験者の意見でもあったのだろうぼくらの問題はいくらか解決に向かった。
生徒全員のものをまとめてその事務局まで送られた。送られてから、もうそのことは一切忘れてしまった。いつものようにバイトをして、いつものように休日にはサッカーの練習の相手をした。たまに上田先輩の父に呼ばれて、食事をおごってもらうこともあった。ぼくは遠く離れた彼の息子の代役でもあり、また材木を売ることから不動産に手を伸ばした彼の現状と、ぼくの大学生からの意見を交換することもその機会には含まれていた。企業は優秀な人材を確保することに必死になっていた時代であった。それは小さな会社であるならなお更だった。
先日、上田さんの学園祭で会ったときの彼の現況をぼくは彼の父に報告した。父は芸術など形が不明瞭なことに息子が傾斜していることを不安がっていた。しかし、彼の写真や絵画を見た自分はその実力を誉めた。ぼくが誉めたからといって暖かな未来が待っているとも思えないが、そのことは父の表情からよりいっそう理解することができた。こうしてある人を起点に人間関係が膨らんでいった。ぼくは高校時代に体力を使って、山から木材を運ぶバイトをした。そのことはぼくの後輩にも引き継がれており、バイトができない練習の忙しいラグビー部のつかの間の金銭の取得の機会であり、その小さな穴から社会を見るチャンスでもあった。ぼくらはあまりにも運動に傾きがちで、世間というものを知らないで過ごしてしまう恐れがあった。先輩の家の仕事を手伝うことにより、そこは守られた範囲であったが、社会の成り立ちの最初のページが開かれた。
ぼくは注がれるままにビールを飲み干し、息子への愛情と心配の言葉を同じように呑み込んだ。いくつかの問題は解決し、いくつかの問題はそのまま放って置かれた。
ある日、もう忘れてしまった公募の結果が教師の口から告げられた。結果として、ぼくの友人でもあった斉藤という女性の仕事が大学生部門の第三位に選ばれた。賞状といくらかの賞金が彼女に与えられる予定だった。ぼくは幹事になり彼女のお祝いを企画した。ぼくは自分のことのように喜んでいたが、すべての人がそうではなかったと後で知ることになる。そこには嫉妬や羨望の気持ちがあったのだろう。
ぼくは自分の作業にかけた数日が無になってしまうことを悲しいとは思わずに、むしろ潔く感じていた。いつもいつもそう簡単に認められる世の中ではないのだ。認められようが無視されようが、ぼくの可能性が直ぐに変わる訳でもなかった。ただ地道に実力がつくことを求めていた。
ぼくは、ある店で乾杯の合図を叫んでいる。ビールは無数にあり何かのきっかけがあれば盛り上がることのできる年代なのだ。彼女は幸先の良いスタートを切ったが、これからの勉強を考えればそれが有利に働くのか、不利になるのかは誰にも分からなかった。ただ、彼女の発想の良さと問題に対する適用力があることは、確かに立派に証明できた。
彼女は前に立って、自分の功績を恥ずかしがるような言葉を述べた。拍手や冷やかしの言葉があったが、その後その建物がどのように作られ、誰の仕事を推すのかは分からなかった。
ぼくも前に出て最後の言葉を言いその会は終わった。結局のところ騒ぐことが与えられたことと、一致して学ぶことを教えられたようだった。だが、多くの仕事はひとりの時間が求められ、そこで右往左往する過程の結果なのだろう。
ぼくは斉藤さんの荷物を担ぎ、彼女を途中まで送った。ビールの飲みすぎでか彼女の言葉は聞きづらかった。ぼくは暗くなった空き地に自分の創造した建物が建っていることをイメージしようとしたが、それはあまりにも非現実的に思えた。