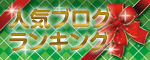おもな街道には一里ごとに一里塚が設けられ、旅人の役に立った。一里塚に植えられたのは榎がほとんどで、残りは松などであった。
この一里塚が制定されたのは、江戸初期・徳川秀忠の時代で、慶長九年(1604年)から十年の歳月を掛けて完成された。
一里塚設置の指揮に当たったのは、大久保長安(ながやす)。武田氏の家臣から、家康の家臣となった人物で、祖父は春日神社の猿楽師だったという。
特に経理面で非常に優秀だったらしく、家康にも重用され、勘定奉行から老中まで昇進し、佐渡金山統括の任にも就いている。
一里塚に植える樹木に榎が選ばれたのは、選定に窮した長安が秀忠に問うたところ、「松とは異な木にせよ」と言われ、「異な木」と「榎」を聞き間違えて榎を選定したとの逸話が残されている。話としては面白いが、優秀な能吏である長安がそんな重要なことを聞き間違える訳がない。街道に多く植えられた松とは別の種にしろと指示されたのは事実かもしれないが、榎を選定したのは、長安の考えであろう。
一里塚は現代でいうと道の駅、あるいは高速のサービスエリアみたいなもので、旅人の目標となるだけでなく、茶屋などが設けられ、休憩することもできた。
その江戸時代のものが今に現存しているというのは、すごいことではないだろうか。
笠寺の一里塚

↓ よろしかったら、クリックお願いします。
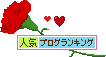
人気ブログランキングへ

にほんブログ村
和風ブログ・サイトランキング
この一里塚が制定されたのは、江戸初期・徳川秀忠の時代で、慶長九年(1604年)から十年の歳月を掛けて完成された。
一里塚設置の指揮に当たったのは、大久保長安(ながやす)。武田氏の家臣から、家康の家臣となった人物で、祖父は春日神社の猿楽師だったという。
特に経理面で非常に優秀だったらしく、家康にも重用され、勘定奉行から老中まで昇進し、佐渡金山統括の任にも就いている。
一里塚に植える樹木に榎が選ばれたのは、選定に窮した長安が秀忠に問うたところ、「松とは異な木にせよ」と言われ、「異な木」と「榎」を聞き間違えて榎を選定したとの逸話が残されている。話としては面白いが、優秀な能吏である長安がそんな重要なことを聞き間違える訳がない。街道に多く植えられた松とは別の種にしろと指示されたのは事実かもしれないが、榎を選定したのは、長安の考えであろう。
一里塚は現代でいうと道の駅、あるいは高速のサービスエリアみたいなもので、旅人の目標となるだけでなく、茶屋などが設けられ、休憩することもできた。
その江戸時代のものが今に現存しているというのは、すごいことではないだろうか。
笠寺の一里塚

↓ よろしかったら、クリックお願いします。
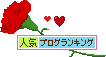
人気ブログランキングへ
にほんブログ村
和風ブログ・サイトランキング