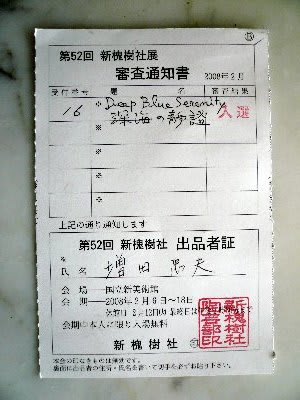8月8日(金)
今日は北京オリンピック開会式。
北京まで行って見物するほどの元気は無いが
今夜は涼しい部屋でビールを片手にTVと云うのは楽しみだ。
それまで今日は特に予定無し。
そこで今年も「芸術の秋」に上野の森の何処かの美術展に
ミスターマスダは出展しようと計画している。
色々試行錯誤している途中経過を御紹介したい。
春先から構想を練ってこの程 焼上がったが
狙いどうりの仕上がりではなく応募作品にはならないだろう。

漸く釉掛けが終わり本焼を待つばかり。
少し自信を持っている。
焼き上がり次第で入選は可能だ。
窯出しが待たれる。


このオブジェはモックアップ。
この形から色々構想を広げていった。

その結果この様なフォルムに辿り着いた。
どのような釉薬で仕上げるか まだ決めていない。
黒を基調に何か変化を付けるか?
夜 ベッドに寝転んで色々考えるのも陶芸の楽しみの一つだ。

9月になり親愛なる弊ブログの御愛読者に
美術展の御案内が出来れば嬉しい限りだ。
今日は北京オリンピック開会式。
北京まで行って見物するほどの元気は無いが
今夜は涼しい部屋でビールを片手にTVと云うのは楽しみだ。
それまで今日は特に予定無し。
そこで今年も「芸術の秋」に上野の森の何処かの美術展に
ミスターマスダは出展しようと計画している。
色々試行錯誤している途中経過を御紹介したい。
春先から構想を練ってこの程 焼上がったが
狙いどうりの仕上がりではなく応募作品にはならないだろう。

漸く釉掛けが終わり本焼を待つばかり。
少し自信を持っている。
焼き上がり次第で入選は可能だ。
窯出しが待たれる。


このオブジェはモックアップ。
この形から色々構想を広げていった。

その結果この様なフォルムに辿り着いた。
どのような釉薬で仕上げるか まだ決めていない。
黒を基調に何か変化を付けるか?
夜 ベッドに寝転んで色々考えるのも陶芸の楽しみの一つだ。

9月になり親愛なる弊ブログの御愛読者に
美術展の御案内が出来れば嬉しい限りだ。