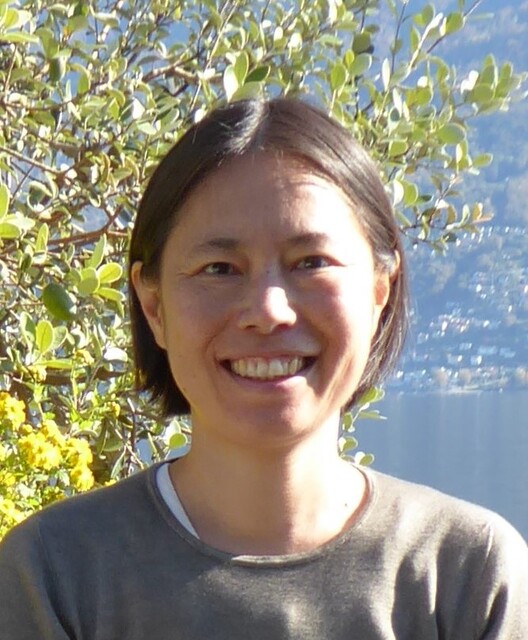スイスの建設業界は昨年も今年も不景気知らず、職人は猫の手も借りたいほどだという声を良く耳にします。理由は、現在金利が低いこともありますが、省エネ改修助成政策の効果が大きいようです。スイスの省エネ改修補助制度は、過去3年間にも力が入れられてきましたが、2010年より一新。シンプルになり、レベルアップして再スタートしました。助成期間は2019年まで、10年間という継続性が頼もしいです。その補助額と概要は全国一様に以下の通りです。
① 建物省エネ改修助成制度
開口部
ガラスU値 0.7W/㎡KあるいはMinergie®モジュール認証を受けた製品
開口部面積1㎡あたり70フラン(約6300円)
外気および地下2m以内に接する屋根・外壁・床
U値 0.2W/㎡KあるいはMinergie®モジュール認証を受けた製品
断熱材1㎡あたり40フラン(約3600円)
無暖房空間に接する外壁・天井・床、地下2m以下に接する外壁と床
U値 0.25W/㎡KあるいはMinergie®モジュール認証を受けた製品
断熱材1㎡あたり15フラン(約1350円)
費用の30%が補助額の目安で、対象は住宅に限らず暖房している建物全般。外壁・窓・屋根のうちの、1部位でも助成対象になります。ただし日本のように1つの窓だけ、とか一面の壁だけの改修は対象にならなりません。
②2010年から新しくなった点
2009年までの制度と比べて比べて変わった点がいくつかあります。まず、昨年までは改修後U値が0.23でも補助金がでましたが、今年からは0.20以下が条件になりました。それから、以前は外壁と窓など2部位以上を同時改修することが補助条件でしたが、現在の制度では部分改修でも補助が出ます。これは省エネ改修への投資と税控除効果を数年に分散させたい、という施主の希望を反映させています。
また財源とその規模も変わりました。建物省エネ助成プログラムには、国の灯油へのCO2税の収入の一部から年180億円が、それに加えて州から72~90億円が出資。合計すると計252~270億円になります。そのうち、上記の省エネ改修の補助に用いられるのは、国からの120億円。残りの国からの60億円や州の72~90億円は、下記の州ごとの建物省エネ助成プログラムに用いられます。
(註:CO2税は灯油100ℓあたり9フラン(800円)のCO2税が課税されている。)
この建物省エネ改修助成制度により、州と国はCO2排出量を年220万トン削減することを目指しています。これは計算すると、現在のスイスのCO2排出量の約4~5%程度です。(そんなものかと思いましたが。)もちろん建物分野では、省エネ改修以外にも、断熱の規制基準強化や熱源交換により、これ以上のCO2削減が実施されていくでしょう。
③州ごとの建物省エネ助成プログラム
さて、上記の省エネ改修助成制度は国が全額を出資しているもので、それ加えて、州ごとに建物の省エネ助成プログラムがあります(統一した方が良いと思いますが、そこは何分、地方分権スイスのこだわりで・・)。その助成メニューには、建物の総合的な省エネ改修やMinergie®改修・新築、再生可能熱源の導入やエネルギー証明書作成などが含まれています。州ごとの助成メニューについては、国と州は半々を出資しています。例えば、トゥールガウ州では、省エネ改修について次のような助成を追加で行っています。
●エネルギー性能証明に基く総合改修へのボーナス
スイスの建物エネルギー性能証明は、躯体の断熱性能と、家電・設備・熱源を含む一次エネルギー消費量の2項目について、A~Gクラスに分けて表示するもの。総合改修後にエネルギー証明書の効率クラスがC以上(新築の規制基準並の断熱性能)を達成すると、上記助成に追加のボーナスが出る。
一世帯・二世帯住宅 5000フラン (45万円)
3世帯以上の集合住宅 2500フラン/世帯 (22.5万円)
非住宅建築 10フラン/ 暖房面積㎡ (900円)
●総合改修によるMinergie®やMinergie-P®へのボーナス
ミネルギーはスイスの任意認証で、より高度な省エネ基準。ミネルギー改修には高額な補助金がでるため、通常の建物省エネプログラムの助成金と合わせてはもらえない。熱回収付き換気を条件とするMinergie®改修の数は多くなく、現在1260棟。技術的にも難易度の高いMinergie‐P®改修は、まだ23棟しかない。
Minergie® 基準への改修
一世帯・二世帯住宅 25000フラン (225万円)
3世帯以上の集合住宅 15000フラン(135万円)+一世帯につき6000フラン(54万円)
非住宅建築 15000フラン(135万円)+暖房面積一㎡につき30フラン(2700円)
Minergie-P®基準への改修
一世帯・二世帯住宅 37000フラン (333万円)
3世帯以上の集合住宅 35000フラン(315万円)+一世帯につき6000フラン(54万円)
非住宅建築 35000フラン(315万円)+暖房面積一㎡につき30フラン(2700円)
④施主を導く「エネルギー性能証明のアドバイス報告書」
また、国と州は、市民に省エネ改修を考えるにあたり、まずは「建物エネルギー性能証明・アドバイス報告書版」を作成することを推薦しています。エネルギー性能証明に付属するこの報告書は、施主に成功する、効率の良い省エネ改修の総合計画を具体的にアドバイスします。内容は、建物の躯体・設備の現状認識、エネルギー性能評価、改修対策とその効果、対策別の省エネ効果とコスト表示、補助金利用の情報、実施計画(対策の優先順位、組み合わせ、推薦事項)などです。作成は、州から認定を受けた中立のアドバイザーが行います。
ほとんどの施主は、何年かに分けて段階的に省エネ改修を実施していきますから、初めに総合計画を持つことが欠かせません。そのため、トゥールガウ州では施主に対して、アドバイス報告書の作成に補助を出しています。 金額的には報告書付き証明書の3分2もの価格を補助。州が中立の専門家によるアドバイス報告書をいかに重要とみなしているかがわかります。
●アドバイス報告書付きの建物エネルギー性能証明への助成
一世帯・二世帯住宅 1000フラン(9万円)
集合住宅・三世帯住宅 1500フラン(13.5万円)
非住宅建築 2000フラン(18万円)
⑤改修にも熱エネルギーの規制基準がある
助成の話とは関係がありませんが、これらの助成制度の前提にあるのが、改修時の熱エネルギー消費量の規制基準です。新築だけでなく、改修でも規制基準があります。改修の建設許可を得るためには、熱計算により規制基準をクリアしていることを証明するか、あるいは改修部分のU値を守ることが義務付けられています。
総合改修時の熱エネルギー消費量の規制基準は、新築の規制基準+25%とされています。新築の規制基準は住宅ですと、暖房給湯熱需要量が48kWh/㎡年(SIA 380/1の計算手法)です。
また改修時のU値規制値は、外気および2m以内の地下に触れる部分では、外壁・床・屋根・天井が0.25、窓・ドア1.3(窓の前にラジエーターがある場合は1.0)です。このレベルの省エネ改修は改修の際の義務であるため、助成の対象にはなりません。だったら30%の補助が出るU値0.20の改修にしよう、と思いますよね。