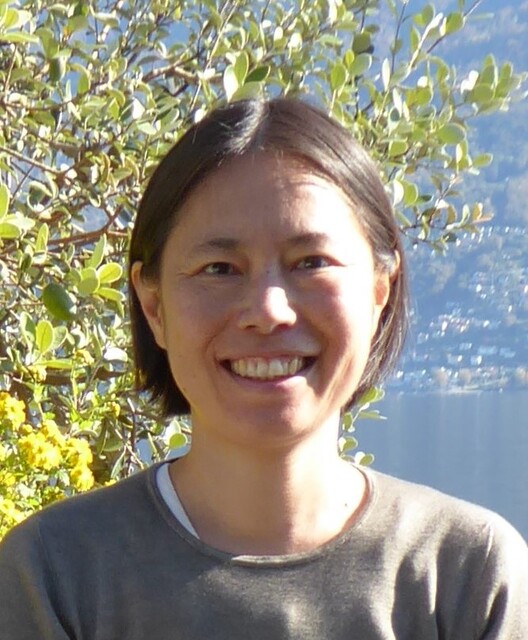スイスでは建物の省エネ改修がエネルギー・気候政策の大きな柱であり、数年来の補助金プログラムのおかげで省エネ改修がブームになっていることは、これまでにも紹介しました。そんな中、近年、実用化された技術が木造プレファブパネル構法による集合住宅のファザード改修です。
先日のブログで報告したプラスエネルギーハウスのシンポジウムで、このシステムを導入している木造会社Erne社のプレゼンを聞きました。
それによりますと:まず、建物のファザードをレーザー測定器でスキャンし、そこから直接に図面を起こし、3-Dモデルを作る。その後、省エネ改修用ソフトウェアを用いてライフサイクルの視点からエネルギー消費の改良を行なってゆく。それを元に壁ごとの木造パネル構造をコンピュータが計算。そのデータを木造工場に送り、自動切削機で木材をカット。最後に大工が工場で組み立てて外壁パネルを作る、という工程だそうです。
外壁パネルの中には、断熱材や機械換気のダクトなども含まれており、現場ではファザードに固定するだけ。現場での施工期間が極端に短くなるため、住みながらの改修でも住人への負担が少なくなります。非常に精度が高い施工を行うことができるのも特徴です。デジタル化、自動化の差こそあれ、このような木造プレファブパネル構法を用いた集合住宅の省エネ改修の例は、スイスでは少しずつ増えてきています。
いち早くこの技術を用いて省エネ改修を実施してきたのが、スイスの有名なソーラー建築家、ベアット・ケンプフェンさんです。
例えばケンプフェンさんが手がけたチューリッヒ市にあるセガンティー二通りの集合住宅(写真下)。省エネ改修によりミネルギー・P基準の省エネ・気密性能を満たし、熱エネルギー需要量を-90%!それにソーラー温水器と光発電を加えることでゼロ暖房エネルギー建築を達成しています。暖房・給湯・換気に必要とするエネルギーを自給する建物という意味です。

セガンティー二通りの集合住宅は、1954年築の賃貸住宅です。構造壁はレンガの二重壁で、とても良質、頑丈だったそうです。もともとは灯油暖房で、年に210kWh/㎡年の熱エネルギーを消費していました。2009年に実施された総合改修では、以下の工事が行われました。
・ 外壁・屋根・地下の断熱を強化。
・ 外壁に断熱や換気配管を内蔵した木造プレファブパネルを設置して断熱・気密改修。改修後のU値は0.12。
・ 浴室とキッチンを総改修。
・ 居間の増築。ベランダだった部分に居間に広げ、大きな窓を設けた。
・ 窓を省エネ性の高い製品に交換し、南窓を拡張、パッシブソーラー獲得を増やした。
・ 新しいファザードの外側に、躯体とは別構造の大きなベランダを設置。
・ 木造プレファブパネル構法による屋上階の増築で一世帯を増築、家賃収入を増やした。
・ 熱回収型の機械換気設備を設置。
・ 熱源設備の交換。暖房はソーラー温水器と地熱ヒートポンプの組み合わせによる温水暖房。
・ ヒートポンプと換気に必用な電力は屋根材一体型の光発電パネルでまかなう。
セガンティー二通りの集合住宅の改修後の熱エネルギー需要量は、26kWh/㎡年。家賃収入は倍増したそうです!
この冬に見学に行ってきましたが、広々とした明るい居間とテラスが気持ちよく、真冬でもとても快適になった、と住人の方は話していました。外観はすっかり変わりましたが、室内には50年代の懐かしさも残っており、魅力的な住宅です。
この建物は、プレファブによる省エネ改修に関する国の研究プロジェクトや、IEA(国際エネルギー機関)の研究プロジェクト「ソーラーリノベーション」にも参加している、パイオニア的な事例です。下記のサイトでは、建築家ケンプフェンさんのプレゼン資料がダウンロードできます。改修前の状態、工事の様子や図面が間近に見られます。 http://www.novatlantis.ch/fileadmin/downloads/veranstaltungen/Bauforum_4Nov09_Referat_Kaempfen.pdf
コンクリートやレンガの家でも、木を使って断熱改修できる、木造建築の活躍できる場所は、スイスにもまだまだ沢山ありそうです!
★写真は盛岡市のエネルギーアドバイザーの長土居正弘さんにご提供頂きました。