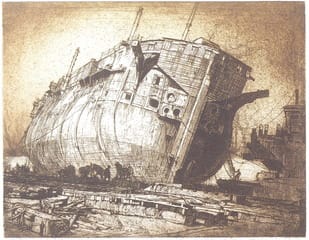一昨日、多磨霊園・神代植物園・深大寺を探索した日の夜、夕食時に胃の下部なのか十二指腸の辺りなのか、突然に痛み出し夕食はお茶だけにして早寝をした。初めは昼間のカレーの香辛料の刺激が強烈だったのかと思ったが、発症の時間から考えて違うようだ。
昨日は用心をしてアルコールは控えて就寝した。しかし本日になっても胃のあたりがむかむかして落ち着かない。市販の胃薬が効いているのか、下痢はしていないが‥。
本日は約10キロの歩行をしたのみ。帰宅後はおとなしくベッドへ潜り込み、連休前に購入した土門拳の「風貌/私の美学」を読む。
文章のプロ顔負け、否、文筆家以上の文章の達人である。
「風貌」という、いわゆる著名人の風貌を収めた写真集に掲載された対象の人物を撮影したときのエピソードが綴られている。人物の性格まで身近に見るように活写されている。文庫本わずか2ページに足りない量で簡潔にまとめられている。対象をカメラを撮影する目線で凝視し抜き、文章として後日まとめられるほど凝視し続けたことを証明しているようなものである。
同時にその人物を通して、歌舞伎・文楽・彫刻・陶芸への好奇心が旺盛に湧いているのがわかる。
風景写真雑感、これなどは写真が芸術としての、美としての成立の根源に迫る迫力がある文章だと思う。
「自分の主体的な、人間的な撮影動機、エモーションというものが加わらない限りは、風景を撮ってもそれは単に絵はがきである。」「概念的に知っているだけではダメだ。‥知るということは深く知るということである。‥胸を広げてモノの突っかかってくる方向へ胸を広げて立ち向かってみるのである。」「松林の風景も、松がはえている大地、土台を抜きにしては一本の松といえども、地上に生えているのとして成立しないのである。苔は松の根方にはえて、その滑らかな光を反射させているだろう。周囲にはタンポポがはえて、黄色い小ちゃな花を咲かせているかもしれない。‥松・苔・タンポポの三つのモノを写しこまなくても環境を出せないというものではない。心中に深く感ずるならば、その存在の影響は画面のどこかに出ないということはない。」
肉声として私に向かって響いてくるものがある。迫ってくる力がある。体験に基づく強さがある。
私はかなり以前、市民講座でモノクロの写真を習った。しばらくその先生を囲む写真愛好家のグループに付き合った。しかし当時はまたフィルムだったので、フィルム代、暗室、引伸機、現像紙代や時間のかかる事態に直面し、継続をあきらめた。しかし石元泰博の写真のようなモノクロの世界をしり、とても勉強になったことを覚えている。
土門拳の仏像のシリーズなどはこの石元泰博の方向性や私が通った講座の講師の志向とは違うが、それでもモノクロの豊穣な世界をより広げてくれた。風景に対する土門拳の言葉は、写真に限らず、風景画にも当てはまる。ただし写真と絵画では構図のあり方も風景を捕らえる技術的なものは当然、レンズと人の目、フィルムと筆という決定的な違いによる差が当然あるのだが。時間の捉え方も違うと思う。
モノを深く知る、肉薄する、凝視をするということの迫力を教えてくれるエッセイだと思った。
最後に、報道写真家として出発し、脳出血などの影響で現場での取材が制限される中、古寺巡礼などの風景写真を行った土門拳だが、1968年の羽田事件では、半身不随の病身を押して現場での写真を撮影した。私などは当時現場に行きたかったが行けなかった高校生活をしていた。2年後くらいに土門拳の写真集を見て、ニュース映像とは比較にならぬその迫力に圧倒された記憶がある。このエッセイ集では「デモ取材と古寺巡礼」という題で、氏の考えが述べられている。
「報道写真家としては、今日ただ今の社会的現実に取り組むのも、ならや京都の古典文化や伝統に取り組むのも、‥僕には同じことに思える。前者が西洋医学の対症療法ならば、後者は漢方医学の持久療法ぐらいの違いがあるだけで、何も問題意識に本質的な違いはない。‥今の日本は問題が多すぎる。医者ならば、急患が多すぎるというところである。ベトナム、沖縄、核禁、公害、物価と問題は山積している。1970年もすぐそこ。報道写真家としての僕も、今日ただ今のアクチュアリティのある問題と取り組んで、現場の目撃者として火柱の立つような告発なり、発言を行いたい」
途中割愛した「日本民族の怒り」などのことばなどは私にはどうしようもない違和感や深い溝を感じるが、しかし土門拳という人の中で、デモと仏像がこのようにつながっていたのか、ということを知り、私の心の今と大きく重なりうれしかった。
昨日は用心をしてアルコールは控えて就寝した。しかし本日になっても胃のあたりがむかむかして落ち着かない。市販の胃薬が効いているのか、下痢はしていないが‥。
本日は約10キロの歩行をしたのみ。帰宅後はおとなしくベッドへ潜り込み、連休前に購入した土門拳の「風貌/私の美学」を読む。
文章のプロ顔負け、否、文筆家以上の文章の達人である。
「風貌」という、いわゆる著名人の風貌を収めた写真集に掲載された対象の人物を撮影したときのエピソードが綴られている。人物の性格まで身近に見るように活写されている。文庫本わずか2ページに足りない量で簡潔にまとめられている。対象をカメラを撮影する目線で凝視し抜き、文章として後日まとめられるほど凝視し続けたことを証明しているようなものである。
同時にその人物を通して、歌舞伎・文楽・彫刻・陶芸への好奇心が旺盛に湧いているのがわかる。
風景写真雑感、これなどは写真が芸術としての、美としての成立の根源に迫る迫力がある文章だと思う。
「自分の主体的な、人間的な撮影動機、エモーションというものが加わらない限りは、風景を撮ってもそれは単に絵はがきである。」「概念的に知っているだけではダメだ。‥知るということは深く知るということである。‥胸を広げてモノの突っかかってくる方向へ胸を広げて立ち向かってみるのである。」「松林の風景も、松がはえている大地、土台を抜きにしては一本の松といえども、地上に生えているのとして成立しないのである。苔は松の根方にはえて、その滑らかな光を反射させているだろう。周囲にはタンポポがはえて、黄色い小ちゃな花を咲かせているかもしれない。‥松・苔・タンポポの三つのモノを写しこまなくても環境を出せないというものではない。心中に深く感ずるならば、その存在の影響は画面のどこかに出ないということはない。」
肉声として私に向かって響いてくるものがある。迫ってくる力がある。体験に基づく強さがある。
私はかなり以前、市民講座でモノクロの写真を習った。しばらくその先生を囲む写真愛好家のグループに付き合った。しかし当時はまたフィルムだったので、フィルム代、暗室、引伸機、現像紙代や時間のかかる事態に直面し、継続をあきらめた。しかし石元泰博の写真のようなモノクロの世界をしり、とても勉強になったことを覚えている。
土門拳の仏像のシリーズなどはこの石元泰博の方向性や私が通った講座の講師の志向とは違うが、それでもモノクロの豊穣な世界をより広げてくれた。風景に対する土門拳の言葉は、写真に限らず、風景画にも当てはまる。ただし写真と絵画では構図のあり方も風景を捕らえる技術的なものは当然、レンズと人の目、フィルムと筆という決定的な違いによる差が当然あるのだが。時間の捉え方も違うと思う。
モノを深く知る、肉薄する、凝視をするということの迫力を教えてくれるエッセイだと思った。
最後に、報道写真家として出発し、脳出血などの影響で現場での取材が制限される中、古寺巡礼などの風景写真を行った土門拳だが、1968年の羽田事件では、半身不随の病身を押して現場での写真を撮影した。私などは当時現場に行きたかったが行けなかった高校生活をしていた。2年後くらいに土門拳の写真集を見て、ニュース映像とは比較にならぬその迫力に圧倒された記憶がある。このエッセイ集では「デモ取材と古寺巡礼」という題で、氏の考えが述べられている。
「報道写真家としては、今日ただ今の社会的現実に取り組むのも、ならや京都の古典文化や伝統に取り組むのも、‥僕には同じことに思える。前者が西洋医学の対症療法ならば、後者は漢方医学の持久療法ぐらいの違いがあるだけで、何も問題意識に本質的な違いはない。‥今の日本は問題が多すぎる。医者ならば、急患が多すぎるというところである。ベトナム、沖縄、核禁、公害、物価と問題は山積している。1970年もすぐそこ。報道写真家としての僕も、今日ただ今のアクチュアリティのある問題と取り組んで、現場の目撃者として火柱の立つような告発なり、発言を行いたい」
途中割愛した「日本民族の怒り」などのことばなどは私にはどうしようもない違和感や深い溝を感じるが、しかし土門拳という人の中で、デモと仏像がこのようにつながっていたのか、ということを知り、私の心の今と大きく重なりうれしかった。














 さてルオーは「郊外のキリスト」「ピエロ」「赤鼻のクラウン」「裁判所のキリスト」が展示されていた。私の好みは「郊外のキリスト」(上掲)。私の好きなルオーの緑・明るい青が現れない絵の中ではもっとも好きな絵である。
さてルオーは「郊外のキリスト」「ピエロ」「赤鼻のクラウン」「裁判所のキリスト」が展示されていた。私の好みは「郊外のキリスト」(上掲)。私の好きなルオーの緑・明るい青が現れない絵の中ではもっとも好きな絵である。