「ちはやふる」(漫画:末次由紀)1~5巻を読んだ。
第2回マンガ大賞2009受賞作品。
競技かるた・小倉百人一首に懸けた青春!
感想。
①百人一首、やりてぇー!
②かるた部の約3名、ビジュアルがちょっと雑過ぎやしないか。
③ずっと出ずっぱりの太一、やっと出て来た詩暢にまで負けるのか。(カバーの話)
囲碁とか将棋とか、昔からの地味な競技漫画が出て来たと思ったら、
まさかの“かるた”まで!?(しかも、少女漫画)
やっぱり地味ではあるけれど、懐かしくて面白い。巻末の巫山戯たオマケ漫画も好き。
末次由紀も懐かしいなぁ~。
他作品も割りと多く読んでいるけれど、(「白羽根」「黒羽根」シリーズは泣ける!)
某超人気バスケ漫画構図盗用事件からは、とんとご無沙汰。盛り返したかな??
★★★★☆
実は、何を隠そう、私も競技かるたの経験者である。
と言っても、北海道地域限定らしい“下の句かるた”の方であるが。
なので、上の句は全く解りません。ちんぷんかんぷんです。
私の町では、毎年冬に2回、子ども会百人一首大会が開催されていて、
低学年の部(小1~小5?)と高学年の部(小6~中3?)に分けられ、
多くの生徒が参加し、青春を謳歌(?)する。
本作のかるたとは若干違い、読みも下の句、取りも下の句。
主に3対3の団体戦で、百首全てを相手チームと半分ずつ分け、
更に、突き(5枚)・中堅(15枚)・守備(30枚)の3つに分ける。
相手の守備・中堅・突きと向かい合う形で座り、
自分と正面の相手の枠分の札しか取ることが出来ない。
札が少なくなると、中堅が真っ先に抜けることになり、色々とラクであることから、
私の定位置★(最悪)
いや、実力から見ても、私が一番戦力外だったのだけど。
やはり“畳の上の格闘技”と言われているだけあり、試合中はあちこちで札が飛ぶ!
取り方は割りと自由で(両手取りは駄目)、
私の場合、右札は右手、左札は左手の中指で「トン!」と取る。
枚数が減ると、横に払ったりも。(あちこちの壁にブチ当たる)
が、物凄い人もいて、マジで「ゴッ!!」 という大きな音が会場に響くことも。
つーか、同じチームの友人N(♀)がそうだったんだけど・・。
指の骨、イッたんじゃないか?!という程の力強さ。物凄く恐い。
まぁ、そういう人とも札を取り合うので、試合後の手はボロボロ。
腫れたり流血することも。
・・・・あ、ちなみに。
取り札は紙製ではありません。
北海道限定の、木の厚い板です。(だから、物凄い音が響き合うのだ)
それと試合中、大声を張り上げるチームもあるけれど、
気合いと威嚇を表した、畳を叩く行為がここでは一般的。
まぁ、詳細はこちらやこちらを適当に。(大まかなルールや札が載っている)
勿論、自分の腕だけでなく、読手が誰になるのかも勝敗に大きく関わってくる。
ウチの地区は読手がいなかったので、様々な読手の録音テープを使って練習をしていた。
読手のいる地区は、当然その人ばかりで練習する訳なので、
試合時、その読手に当たれば絶大な強さを発揮するが、外れたらそうでもなかったり。
好みこそあれ、あらゆる読手のクセを広範囲に知ることが出来ていたので、
コレはコレで良かったのかも??(テープ内容を半分覚えかけるけど・・)
そんなこんなで、
一度、小さな大会の低学年の部で優勝したことがある。
決勝で当たったチームは物凄く強くて、練習でも殆ど勝てたことがなくて、
正直、自分たちにも周囲にも最初から勝敗は見えていたと思う。
でも、やっぱりここまで来たなら勝ちたくて、必死で食らい付いていったら、
1枚差で逆転優勝!!
やっぱり百人一首は楽しいなぁ~♪
優勝賞品の図書券(+@)貰えて嬉しいなぁ~♪(本音はソコか)
その時のチーム(守備のN・中堅の私・突きのH)は、その後解散してしまったけれど、
出来れば高学年の部でも、このまま3人で続けて行きたかった。
いい所までいけそうな気がした。
でも途中から、「したい」と言ってきた友人Mが入って来て、
仲も良かったから、自然とM(♀)よりH(♂)が弾かれることになって、
ちょっとした喧嘩別れで終わってしまった。
私とはずっと同じクラスでもあったので、学校ではそれなりに話したし、
中学からはぶっちゃけ、NやMとよりも仲良かったくらいなのだけど、
かるたの練習には、それから一度も顔を出して貰えることなく終わってしまった。
彼の前では、“かるた”という言葉がタブーとなった。
私とNは、「同じチームでかるたしよう」と最初から決めて動いていたけれど、
Hの場合は組む相手が最初からいなく、助っ人感覚でここに入って来てくれたのだ。
同級生とはいえ、女のチームに入るというのは、当時はかなり勇気がいったはず。
実力あるHの存在は、私たちには有り難かったけれど、内心では、
「女のチームなんて、やっぱり嫌なんじゃないだろうか」
「いつか、『抜けたい』と言い出すんじゃないだろうか」と不安だった。
だから、Mが入る時、
「ウチらは女子同士で組むから、Hも男子同士で組みなよ」とサラリと言ってしまえた。
私的には、Hの背中を押して上げているつもりだった。
でも、そんなことなかったんだね。
Hにとっては、メンバーは私とNの2人だけで、
他に組むメンバーなんて、後にも先にも誰一人いなかったんだ。
まさか最後まで「抜けたくない」と抵抗してくれるとは思わなかったよ。
Mを入れた新チームは、勿論楽しかったけれど、
やっぱりHがいた旧チームの方が、実力だけでなく、チームワークが良かったように思う。
私の定位置だった中堅を初心者のMに譲り、
Hが長年務めてきた突きのポジションに回って、初めてその大変さを知った。
Hが今までどれだけチームを支えてきたのか、改めてその凄さを知った。
作中での原田先生の言葉が、今では胸に突き刺さる。
「子供はさ どんなに強くても かるたが好きでも 友達がいないと続けられないんだ」
千早から、それぞれ仕方なく離れてしまった新と太一より、
Hから、2人で離れてしまった私とNの方が、何倍も酷いように思う。
ごめんね、H。
Hから大好きなかるたを奪っちゃってごめん。
第2回マンガ大賞2009受賞作品。
競技かるた・小倉百人一首に懸けた青春!
感想。
①百人一首、やりてぇー!
②かるた部の約3名、ビジュアルがちょっと雑過ぎやしないか。
③ずっと出ずっぱりの太一、やっと出て来た詩暢にまで負けるのか。(カバーの話)
囲碁とか将棋とか、昔からの地味な競技漫画が出て来たと思ったら、
まさかの“かるた”まで!?(しかも、少女漫画)
やっぱり地味ではあるけれど、懐かしくて面白い。巻末の巫山戯たオマケ漫画も好き。
末次由紀も懐かしいなぁ~。
他作品も割りと多く読んでいるけれど、(「白羽根」「黒羽根」シリーズは泣ける!)
某超人気バスケ漫画構図盗用事件からは、とんとご無沙汰。盛り返したかな??
★★★★☆
実は、何を隠そう、私も競技かるたの経験者である。
と言っても、北海道地域限定らしい“下の句かるた”の方であるが。
なので、上の句は全く解りません。ちんぷんかんぷんです。
私の町では、毎年冬に2回、子ども会百人一首大会が開催されていて、
低学年の部(小1~小5?)と高学年の部(小6~中3?)に分けられ、
多くの生徒が参加し、青春を謳歌(?)する。
本作のかるたとは若干違い、読みも下の句、取りも下の句。
主に3対3の団体戦で、百首全てを相手チームと半分ずつ分け、
更に、突き(5枚)・中堅(15枚)・守備(30枚)の3つに分ける。
相手の守備・中堅・突きと向かい合う形で座り、
自分と正面の相手の枠分の札しか取ることが出来ない。
札が少なくなると、中堅が真っ先に抜けることになり、色々とラクであることから、
私の定位置★(最悪)
いや、実力から見ても、私が一番戦力外だったのだけど。
やはり“畳の上の格闘技”と言われているだけあり、試合中はあちこちで札が飛ぶ!
取り方は割りと自由で(両手取りは駄目)、
私の場合、右札は右手、左札は左手の中指で「トン!」と取る。
枚数が減ると、横に払ったりも。(あちこちの壁にブチ当たる)
が、物凄い人もいて、マジで「ゴッ!!」 という大きな音が会場に響くことも。
つーか、同じチームの友人N(♀)がそうだったんだけど・・。
指の骨、イッたんじゃないか?!という程の力強さ。物凄く恐い。
まぁ、そういう人とも札を取り合うので、試合後の手はボロボロ。
腫れたり流血することも。
・・・・あ、ちなみに。
取り札は紙製ではありません。
北海道限定の、木の厚い板です。(だから、物凄い音が響き合うのだ)
それと試合中、大声を張り上げるチームもあるけれど、
気合いと威嚇を表した、畳を叩く行為がここでは一般的。
まぁ、詳細はこちらやこちらを適当に。(大まかなルールや札が載っている)
勿論、自分の腕だけでなく、読手が誰になるのかも勝敗に大きく関わってくる。
ウチの地区は読手がいなかったので、様々な読手の録音テープを使って練習をしていた。
読手のいる地区は、当然その人ばかりで練習する訳なので、
試合時、その読手に当たれば絶大な強さを発揮するが、外れたらそうでもなかったり。
好みこそあれ、あらゆる読手のクセを広範囲に知ることが出来ていたので、
コレはコレで良かったのかも??(テープ内容を半分覚えかけるけど・・)
そんなこんなで、
一度、小さな大会の低学年の部で優勝したことがある。
決勝で当たったチームは物凄く強くて、練習でも殆ど勝てたことがなくて、
正直、自分たちにも周囲にも最初から勝敗は見えていたと思う。
でも、やっぱりここまで来たなら勝ちたくて、必死で食らい付いていったら、
1枚差で逆転優勝!!
やっぱり百人一首は楽しいなぁ~♪
優勝賞品の図書券(+@)貰えて嬉しいなぁ~♪(本音はソコか)
その時のチーム(守備のN・中堅の私・突きのH)は、その後解散してしまったけれど、
出来れば高学年の部でも、このまま3人で続けて行きたかった。
いい所までいけそうな気がした。
でも途中から、「したい」と言ってきた友人Mが入って来て、
仲も良かったから、自然とM(♀)よりH(♂)が弾かれることになって、
ちょっとした喧嘩別れで終わってしまった。
私とはずっと同じクラスでもあったので、学校ではそれなりに話したし、
中学からはぶっちゃけ、NやMとよりも仲良かったくらいなのだけど、
かるたの練習には、それから一度も顔を出して貰えることなく終わってしまった。
彼の前では、“かるた”という言葉がタブーとなった。
私とNは、「同じチームでかるたしよう」と最初から決めて動いていたけれど、
Hの場合は組む相手が最初からいなく、助っ人感覚でここに入って来てくれたのだ。
同級生とはいえ、女のチームに入るというのは、当時はかなり勇気がいったはず。
実力あるHの存在は、私たちには有り難かったけれど、内心では、
「女のチームなんて、やっぱり嫌なんじゃないだろうか」
「いつか、『抜けたい』と言い出すんじゃないだろうか」と不安だった。
だから、Mが入る時、
「ウチらは女子同士で組むから、Hも男子同士で組みなよ」とサラリと言ってしまえた。
私的には、Hの背中を押して上げているつもりだった。
でも、そんなことなかったんだね。
Hにとっては、メンバーは私とNの2人だけで、
他に組むメンバーなんて、後にも先にも誰一人いなかったんだ。
まさか最後まで「抜けたくない」と抵抗してくれるとは思わなかったよ。
Mを入れた新チームは、勿論楽しかったけれど、
やっぱりHがいた旧チームの方が、実力だけでなく、チームワークが良かったように思う。
私の定位置だった中堅を初心者のMに譲り、
Hが長年務めてきた突きのポジションに回って、初めてその大変さを知った。
Hが今までどれだけチームを支えてきたのか、改めてその凄さを知った。
作中での原田先生の言葉が、今では胸に突き刺さる。
「子供はさ どんなに強くても かるたが好きでも 友達がいないと続けられないんだ」
千早から、それぞれ仕方なく離れてしまった新と太一より、
Hから、2人で離れてしまった私とNの方が、何倍も酷いように思う。
ごめんね、H。
Hから大好きなかるたを奪っちゃってごめん。












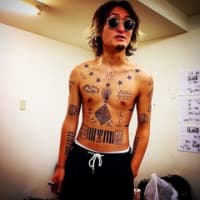







どうして北海道で発達したのか? 雪で閉ざされた期間が長く室内競技が盛んだったのかな。
私の方こそ驚きました。
「百人一首漫画がある」と話題で、わくわくして読んでみたら、
「な、何ィーッ!コレが百人一首だったのーッ?!」みたいな。(面白いけど)
で、簡単に調べてみたら、北海道限定と判明した訳で・・。
この漫画を読んで驚いた道産子は少なくないハズ・・。
何故、取り札が紙ではなく木の板なのかは、
北海道の開拓者にとって紙は高価で木板は豊富にあったから、とのことですが、
下の句かるたそのものの発祥や由来はよく解っていないそうです。残念。
本州・・というか、一般的なのが“上の句かるた”の方だったなんて、
やっぱりちょっと寂しいですね・・。
下の句かるたの方が絶対簡単だから、もっと普及して欲しいものです。
読みが上の句、取りが下の句なんて、全然わっかんねーよ!!(紙札は小さいし!)
はじめまして。natsuと申します。
私も下の句かるたやってました!
漫画大賞で知って最近ちはやふるを読んで懐かしくなり検索していたら辿りつきました。
私の地元でも下の句かるたは盛んで小中学生の地区大会がありました。結構チーム数もあり、地域ごとのチーム名がありました。うちの地区では中堅が5枚ではりが40枚がオーソドックスでした。
小学校高学年の時、地区大会で4位になったことがあります。ずっとはりをやっていてその時の負けた試合の時のことは未だによく覚えています。
そのあとは教えてくださっていた方々の体調が悪くなり、練習会も自然消滅してしまいましたが、中学生になっても小学校の練習に顔を出し細々と続けていました。高校からは地元から遠い高校に進学し下宿するようになり、教えてくださった方々も亡くなってしまい、かるたからは全く遠ざかりました。
下の句かるたはすごく好きだったのでちはやふるを読んでうらやましく思いました。うちは結構ドライだったので。サナダさんのかるた仲間のお話もなんかいいなあと思ってうらやましかったです。そういうときのなんとも言えない気持ちってずっと残りますよね。
小学生当時の練習相手の中学生のお兄さん方は高校生になって大人の全道大会の3位とかになった人たちででした。自分の方がたくさん札を持っているのに全然取れなくて、ばんばん畳を叩く迫力に気おされて悔しくて泣きそうになりながらやってました。それでも必死に集中してやっていたことが懐かしいです。
私は20代半ばなのですが周りの同年代の人たちは下の句かるた自体を知らない人が多くさみしいです。経験者の方を見つけられてうれしかったです。
下の句かるたはとっつきやすいですし、音になる前の音を聞く緊張感や瞬発力は本場の百人一首と同じですし、この漫画を機にやる人が増えてくれるとうれしいですね。私も機会があったらまたやりたいです。
自分の話を長々と失礼いたしました。
初めまして、こんばんはー。
まさかの下の句かるた経験者でありましたか!同士を見つけられて、私も嬉しいです!
地域ごとのチーム名はこちらにもありましたが、 その他に大会用のチーム名も自由に作れまして、
明らかに巫山戯ているというか、主催のオジサンたちを困らすような 早口言葉的な長い名前も多くて、
色んな意味で面白かったですねぇ。
それにしても、40枚って多くないですか?!30枚でも多いのに・・。
いくらそれが一般的だからって、やっぱりバランス悪いと思うなぁ。
2人共が5枚ずつってのもね。うーむ。
こちらの地域では、流石に大人大会で入賞する程の逸材はいませんでした。
かるたは飽くまでも「イベント」や「趣味」の一つというか。 しかも、冬(休み中)だけでしたし。
毎日毎週・・だったら嫌になってたかもですけど、
やっぱり季節なんて関係なしにやっていたかったですね。
高校は、割りと近くの所に入った所為か、かるた大会はありました。
でも、初心者ばかりだったので、てんで話にならなくてつまらなかったです。
クラス代表を決める予選(?)だって、私一人VS残り全員でも余裕でしたもん。
なので大会は、経験者である地元の先輩ばかりに。強い。
そんなだからか、行事縮小に引っ掛かり、あっという間に消えちゃいました。笑
友人Hもねぇ~、今は何をしているのやら。
噂では、ヲタクでひきこもりなニートを経て、フリーターになっているとか。笑
別にかるたが原因とは思わないけど・・、ガッカリですよ!笑
今は本当にかるたから離れてしまっているので、昔程取れないでしょうけど、
まだまだ札は覚えているので、またしたいです!
大会とか、ちょっと見てみたいかも。