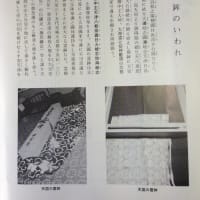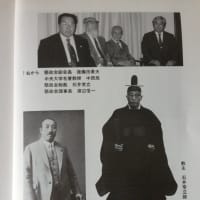「福島&復興」について掲載されていた。
以下、参考にして欲しい。
◎避難したことありますか?
・大雨と台風で避難は2回しました。動物がたくさんいて、どこの避難所もペットの受け入れができず、車の中か、義実家の選択に。義理の母は動物が好きではなく、ためらいましたがそれしかありませんでした。自宅に被害はありませんでしたが、雨のたび恐怖です。長期避難となればストレスや苦痛は計り知れないと思います。福島の方々は今も多くの方がそういう状況にあると知り、1日でもはやく皆さんが幸せに暮らせる日がきてほしいと思っています。
・東日本大震災被災者です。避難所はいっぱいだったこともあり避難しておりません。築浅のマンション住まいであったため、余震におびえながら家族全員で川の字になって一夜を過ごしました。自宅で何とかなる方は他の方を優先すべきだと思いました。アウトドアが趣味だったため、ポリタンクやカセットコンロ、寝袋、ランタンなど、とても役立ちました。また会社では必ず非常食セットを支給してくれており、とても助かっています。
・西日本豪雨の時に浸水被害にあい、自宅2階に取り残されました。飼っている犬と小鳥を連れての避難は無理との判断からです。結果論で言えば命は助かりましたが、家ごと流された可能性もあったわ
・うちの親は80代ですが、地震や水害などの災害で家がつぶれてなくなるようなことがあったら避難せず家と一緒に最期を迎えたい、この年になって全てをなくしてまで生きていたくないと言っていま
・当時福島第1原発から4kmのところに住んでいました。今も避難生活です。様子を見に行くと新しい建物が建ち田舎とは思えない箱物がたくさん造られています。一方で心理的には復興は30%ぐらいで
・テレビで東日本大震災の悲惨な情景を見ていましたので、私なりに出来ることを探しに2012年から毎年東北の被災地に行っています。12年に福島の小名浜で1人のおばあさんに会い、「こうやって現状
・ALPS処理水はめどが立ちましたが、肝心の廃炉問題はロードマップから遅れに遅れ、中間貯蔵施設の問題もある。パーセントでは言い表せないところがあります。ただ一時期増えていた暴走族の類い
◎福島県からの避難者はいまだ2万7000人超、東日本大震災から今年で11年
今も避難生活を続ける被災者は、これまでの11年をどう受け止めているのか。福島県から避難している2人に聞いた。
・家族7人で東京へ 帰還困難区域の自宅に戻った20分
松崎真希子さん(56)。夫(56)とその両親、長女(30)、次女(28)、長男(26)の7人家族。現在は夫とその両親と東京都板橋区に在住。介護福祉士として働いている。
松崎真希子さんは震災時、家族7人で自宅のある福島県浪江町から東京に暮らす夫の姉妹の元へ避難した。その後、板橋区の都営成増団地に暮らし、現在は購入した一軒家に夫とその両親と住んでいる。11年前に学生だった子どもたちは、東京で就職した。浪江町の自宅近辺は帰還困難区域に指定され、今も住むことはできない。
2011年4月中旬、浪江町の自宅周辺がバリケードで封鎖されると聞いた松崎さんは、夫とともに一度、自宅に戻った。
「雨がっぱを二重に着て、足にも靴の上からビニール袋を二重に履き、ゴーグルとマスクをして、頭にはシャワーキャップをかぶって、手袋もして。30分以内なら大丈夫とうわさに聞いたので、大事なものだけ取りに行こうと思いました。でも、いざ行くと何が大事なのか分からない。銀行関係の書類とか子どものものを持って、20分くらいで出ました」
現在、自宅の周りには緑が生い茂って、家が木々に埋もれているような状態だ。一方、帰還困難区域を除くエリアでは復興に向けた建設工事が進んでいる。昨年、松崎さんはお墓参りの際、「道の駅なみえ」を見た。
「子どもが通っていた小学校、中学校も取り壊されていますし、新しい建物が建って、景観はすっかり変わっています。私の知っている浪江町ではないですね。11年間は生活するのに一生懸命で、あっという間でした。ただ、まだ浪江町から住民票を移してはいないんです。長年住んだ家の住所が消えてしまいますし、なんとなく負けたような気がするというか。移したくて移すわけでもないのに、と思うんですね。夫は長男なので、お墓は守らないといけないと思っています」
・30年以上住んだ自宅を更地に 失った終のすみか
今里雅之さん(75)。現在は横浜市で妻(73)と暮らす。神奈川県内および近郊に避難している人たちをつなぐ「かながわ東北ふるさと・つなぐ会」の会長を務める。
今里雅之さんは原発事故の直後、妻とともに福島県富岡町から横浜市の長女の元へ避難した。長女が引っ越し予定だったマンションに仮住まいのつもりで住み始め、現在に至る。
「すぐに帰れると思っていたんですよ。双葉町で建設会社に勤めていて、『原子力明るい未来のエネルギー』という看板をいつも見ていました。そういう安全神話の中で生活していたので、『まさか』でした」
富岡町の自宅は居住制限区域だったが、2017年4月1日、避難指示が解除された。環境省による被災建物の解体除染は期限があるので、自宅の解体を決めた。
「年に何度か家を見に行きましたが、窓が割れていて、ネズミの死骸があったり、動物の荒らした跡があったり。泥棒が入った様子もありました。昔は庭で藤やブルーベリーを育てるのが楽しみだったんです。その庭もジャングルみたいになっていて。家も街も住める環境ではないので、このタイミングで壊すしかないなと。終のすみかのつもりでしたから、切なくてね。取り壊しの途中はとても見に行けなくて、更地になってから行きました」
取り壊し後は自宅跡地の管理が重荷になっているという。除草などもしなくてはならないし、減免されていた固定資産税が2021年度から満額負担となる。
「帰る選択肢を捨てたわけじゃない。帰るか帰らないか、気持ちは半々です。避難当初は孤立感が大きく、そんな中で私も妻も体調を崩し、通院する生活になりました。みんなあちこちに分散してしまって、寂しいと思うんですね。だから、避難者の人たちが集う機会を継続的に作っています」
◎『復興完了』への道のりは?
最短でも100年後
福島第1原発の敷地 再利用の可能性(日本原子力学会の報告書による)
福島からの避難者が全国に2.6万人
◎復興の現在地、識者はどう見る
・関谷直也さん
東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター准教授/東日本大震災・原子力災害伝承館上級研究員
Q.復興完了とは、どういう状態ですか?
東京電力福島第1原発事故による原子力災害において、その被害の過程は長期に及びました。震災前と同じ状態に戻ることは困難です。「復興」を、震災前と同じ状態に戻るという意味で捉えるならば、復興が完了するということは「ない」と思います。被害の様相が固まり、復旧をどう組み立てるかが見えるまでさえ、数年かかりました。数年間、状況が定まらない間に人々は各方面に避難し、多くの人が避難先で生計を立て、生活を営んでいます。
新しくできた商業施設も、小中学校でさえも、震災前と同じ人口規模を前提にしているわけではありませんし、被害を受けた人全員が戻ってくることを前提にしているわけではありません。ただ、移住されている方もいます。2011年以前のコミュニティ、つながりを大切にしつつも、震災前とは異なる、新しい地域のビジョンや未来像を作り、それに進んでいくことが復興なのだろうと思います。
Q.地域の未来像を描く上での課題は?
福島県の災害被害は非常に多様で、帰還の時期もそれぞれの地域で異なります。一言で「被災」と言っても、災害に対して共通の経験を持つことができないということが当初からの課題としてあると思います。
自然災害に限っても、津波の大きな被害を受けた南相馬市、浪江町、富岡町、相馬市、いわき市のほか、地震の大きな被害を受けた地域、須賀川のように地震による土砂災害が発生した地域など様々です。これに、避難指示区域とそうではない区域、放射性物質の飛散によって大きな経済的被害を受けた地域・業種もあれば、会津のように全く放射性物質による汚染はなくても、風評被害によって農業・観光業が大きな影響を受けた地域などもあります。また、区域外でも多くの人が避難しました。どこを軸として語るかによって復興の現在地は変わってくると思います。
Q.福島の復興のために、できることは?
まずは知ることだと思います。一度でも構わないので、訪問して、目で見て、「福島県」を体験してほしいと思います。原発事故や処理水のことを知ることも必要ですが、住民や地域に関わる人の思いに触れること、色んな場所を訪れてこの地域ならではの魅力を知ることも大切だと思います。この10年間、道路が開通し、人が住めるようになり、コンビニやスーパーができ、電車が通り、飲食店や居酒屋が再開してきました。こういった小さなことが、本当に大きなニュースだったりします。行ってみて、話をすることで、放射線量の数値や農家の考えなどを意識できるようになり、復興を後押しするのではないでしょうか。
一度、途切れてしまった、人とモノの流れを新たに再構築することこそ、この地域の復興そのものだと思います。