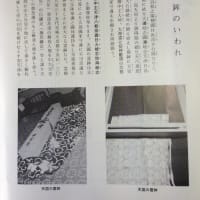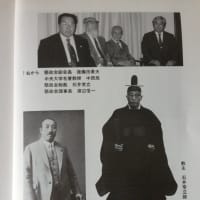◎首都=二上の大宮のあった場所について
ウエツフミには、王朝の首都は「二上(ふたのぼり)の大宮」であると書かれています。
通説では、これは現在の高千穂町であろうと解釈しています。
ただし、ひとつ不思議なのは、王族が船を使って旅をするときは、必ず臼杵から出航しており、逆に旅先から高千穂に帰るときは、臼杵に上陸⇒大野の宮(現在の豊後大野市)⇒直入の宮(現在の竹田市)を経由して、「二上(ふたのぼり)の大宮」に入っていることです。
つまり現在の国道57号線沿いに、高千穂に向かっているのです。 (下記の地図参照)
地元の人ならほぼ全員が納得するはずですが、竹田と高千穂の間には祖母山という険しい山が横たわり、ケモノミチのような登山道しかありません。
大名行列が越えられるような広くて平坦な道路は、現在でも存在しないのです。
にもかかわらず、なぜ、船を延岡あたりに着けなかったのでしょうか?
このことから、「二上(ふたのぼり)の大宮」とは、高千穂のことではなく、「祖母山の北側にあったのではないか?」と考えるようになりました。
高千穂町には、三田井一族という人たちが住んでおり、現在も「三田井」という地名で残っていますが、この人たちは大分県側の緒方町から出た大神氏=緒方一族の末裔なのです。しかもこの人たちが「岩戸神楽」を伝える中心勢力でした。お神楽も大分県側で創られた可能性が高いのです。
(ちなみに、812年大神惟基が高千穂の天岩戸神社を再興しています。)
さて、ニニギの命はここ大分の地から全国に巡幸して、日本列島をほぼ勢力範囲に治めました。
といっても、実際に書かれているのは「○○地方を訪れて盛大なもてなしを受けた」という程度で、そこにどんな交渉があったのか?あるいは戦闘があったのか?は、全く分かりません。
ただし、ニニギの孫の初代・ウガヤフキアエズが即位したときには、全国を統治する体制がほぼ固まったようで、各地に建(タケル)と呼ばれる領主が置かれました。
この配置を見る限り、九州を中心に西日本はほぼ現在の都道府県の単位と一致します。
近畿から東については、とびとびでしか国が存在していませんが、これは実際にそうだったようです。
つまり、まだこの時代には人口がそこまで多くなかったと考えられます。
そして、ウガヤ王朝は、北海道と沖縄を除く、ほぼ日本全国を掌握していたことが分かります。(後代になって北海道と沖縄も王国に組み込まれてゆきます)