社員教育というのは、どんな会社でも持っている課題でしょう。
弊社でもいろんな研修系のセミナーを開催されており、葬儀社の社員の方が参加されるのもよく目にしています。
もちろん、こういった研修プログラムに参加し、基本的な考え方やマナー、意識の向上を狙うことはよいと思います。
ただ、私は社員教育はマーケティング活動を通じての方がより効果が高いと考えています。
葬儀でいえば、「葬儀1件を受注することがどれだけ大変か」ということを感じてもらうこと、それが大事なのです。
どうしても葬儀というものは受身的になってしまいがちのもの、だからこそ仕事を”こなし”てしまいがちです。
そういう姿勢で仕事に取り組んでいる人が、基本的な考え方を学んだとしても改善されるとはいえないでしょう。
しかし、例えば「とにかくポスティングを2,000枚やってこい!!」といってとにかくやらせる。その中でたまたま見てもらった人が一人会員になってくれた、葬儀につながった。
そういった自分の苦労が受注に直結することで、一件の葬儀に対する取組姿勢が変わってきます。
現場の動きに物足りなさを感じる方は、研修もよいと思いますが、まずはポスティングやドアコールなどの実践により、1件の重みを感じてもらうことからはじめてはいかがでしょうか。
弊社でもいろんな研修系のセミナーを開催されており、葬儀社の社員の方が参加されるのもよく目にしています。
もちろん、こういった研修プログラムに参加し、基本的な考え方やマナー、意識の向上を狙うことはよいと思います。
ただ、私は社員教育はマーケティング活動を通じての方がより効果が高いと考えています。
葬儀でいえば、「葬儀1件を受注することがどれだけ大変か」ということを感じてもらうこと、それが大事なのです。
どうしても葬儀というものは受身的になってしまいがちのもの、だからこそ仕事を”こなし”てしまいがちです。
そういう姿勢で仕事に取り組んでいる人が、基本的な考え方を学んだとしても改善されるとはいえないでしょう。
しかし、例えば「とにかくポスティングを2,000枚やってこい!!」といってとにかくやらせる。その中でたまたま見てもらった人が一人会員になってくれた、葬儀につながった。
そういった自分の苦労が受注に直結することで、一件の葬儀に対する取組姿勢が変わってきます。
現場の動きに物足りなさを感じる方は、研修もよいと思いますが、まずはポスティングやドアコールなどの実践により、1件の重みを感じてもらうことからはじめてはいかがでしょうか。
社長の仕事は資金繰りと人材採用だと前回述べました。
しかし、そうはいっても規模的には、社長自身が現場の第一線に立ち、営業、打ち合わせ、葬儀のフォローに入らなければならないこともしばしばあると思います。
人員が少ないうちは現場に出て、徐々に大きくなれば現場から離れ、最初に述べたような仕事に力を注いでいくことと思います。
このときに注意しなければならないこと、それは「現場に口を出さないこと」です。
理由は何か。それは現場社員のモチベーションの低下にあります。
確かに昔は現場に出ていたので、現場を見なくともある程度の予測は付くのでしょう。ですが、急に単価が下がってきたように、葬儀の内容は急速に変化しつつあります。
その中で、現場を見ない状況で、社長が「あーしろ、こーしろ」というと、現場レベルでは非効率になること、お客様にとって不具合のことがよくあります。
社長は現場を見なくなったのであれば、なるべく現場は責任者に一任し、それ以外の社長にしか出来ない仕事に全力を注いだ方が、会社は上手く廻る。
いろんな会社を見ていると、そのように感じます。
しかし、そうはいっても規模的には、社長自身が現場の第一線に立ち、営業、打ち合わせ、葬儀のフォローに入らなければならないこともしばしばあると思います。
人員が少ないうちは現場に出て、徐々に大きくなれば現場から離れ、最初に述べたような仕事に力を注いでいくことと思います。
このときに注意しなければならないこと、それは「現場に口を出さないこと」です。
理由は何か。それは現場社員のモチベーションの低下にあります。
確かに昔は現場に出ていたので、現場を見なくともある程度の予測は付くのでしょう。ですが、急に単価が下がってきたように、葬儀の内容は急速に変化しつつあります。
その中で、現場を見ない状況で、社長が「あーしろ、こーしろ」というと、現場レベルでは非効率になること、お客様にとって不具合のことがよくあります。
社長は現場を見なくなったのであれば、なるべく現場は責任者に一任し、それ以外の社長にしか出来ない仕事に全力を注いだ方が、会社は上手く廻る。
いろんな会社を見ていると、そのように感じます。
今日お伺いした支援先は、お付き合いしてまだ3ヶ月目です。
ただ、すでに社長が変わり始めました。
それは、「数字に対する意識の向上」です。
この3ヶ月の間で、目標を設定することの意味、利益を出すことの意味、そのために戦い方があるのだということ、それらの意識がぐっと高まりました。
私は、社長の仕事は人材採用と資金繰り、要は数値管理であると考えています。
社長が数字に強く、厳しくなればなるほど、会社は強くなると思っています。
では、どのようにして社長が3ヶ月で変わることが出来たのか。
それは、「ただ売上を紙に記入してもらった。」それだけです。
これまではまったくといっていいほど、どんぶり勘定の売上。
葬儀ごとにどれだけの利益が生まれ、月毎にどれだけの利益が生まれているのかがまったく把握できていませんでした。
そのため、
「とにかく今年の1月からの全施行について、葬儀費用、料理費用、供物関連費用、返礼品費用を洗い出してください。それを紙に記入してください。」
とお伝えしました。
最初はしぶしぶやっていたそうです。めんどくさいと。
しかし、途中から自分が思っていたよりも利益が出ていなかったことや、利益が出ている葬儀の形がわかっていくにつれて、どんどん面白くなっていったそうです。
今では、つけずにはいられないとのこと。
一旦、面白くなってしまえばこれからも続いていくでしょう。利益率ももっともっと良くなっていくはずです。
もし、数字に疎い・・・とお考えの方がいれば、ぜひ一度試してみてください。
ただ、すでに社長が変わり始めました。
それは、「数字に対する意識の向上」です。
この3ヶ月の間で、目標を設定することの意味、利益を出すことの意味、そのために戦い方があるのだということ、それらの意識がぐっと高まりました。
私は、社長の仕事は人材採用と資金繰り、要は数値管理であると考えています。
社長が数字に強く、厳しくなればなるほど、会社は強くなると思っています。
では、どのようにして社長が3ヶ月で変わることが出来たのか。
それは、「ただ売上を紙に記入してもらった。」それだけです。
これまではまったくといっていいほど、どんぶり勘定の売上。
葬儀ごとにどれだけの利益が生まれ、月毎にどれだけの利益が生まれているのかがまったく把握できていませんでした。
そのため、
「とにかく今年の1月からの全施行について、葬儀費用、料理費用、供物関連費用、返礼品費用を洗い出してください。それを紙に記入してください。」
とお伝えしました。
最初はしぶしぶやっていたそうです。めんどくさいと。
しかし、途中から自分が思っていたよりも利益が出ていなかったことや、利益が出ている葬儀の形がわかっていくにつれて、どんどん面白くなっていったそうです。
今では、つけずにはいられないとのこと。
一旦、面白くなってしまえばこれからも続いていくでしょう。利益率ももっともっと良くなっていくはずです。
もし、数字に疎い・・・とお考えの方がいれば、ぜひ一度試してみてください。
今日お会いした方は、1ホールで年間350件弱の施行、そして10分圏内においてはシェアが4割近くと高い数字を示していました。
2年ほど前から同じような数字を維持しているという状態です。そして売上でいえば今年もしっかりと伸ばしています。
数字を見ると、非常にいい数字です。ただこの数字を経営者がどのように捉えるかで、その先に進んでいくところが変わっていくと思います。
現状に満足するか、危機感を持つか。
満足する要素はあります。件数は横ばいで売上は上がっていますから、それだけで満足しようと思えばできます。
ただ、今日お会いした社長は、この状況に危機感を持っておられました。
現状の売上アップは単価アップによるもの。件数が一定ということは、お客様の支持率は変わっていないということです。
今の売上アップは一時的なもので、このままでは必ず下がる、そうお考えでした。
本日お話をしてみて、さらに社長はそういった意識が高まったようでした。
危機感が生まれると、それが必ず行動に移されると思います。
その結果は、良い方向に必ずいくと私は思います。
今後の動向に期待してみていきたいと思います。
2年ほど前から同じような数字を維持しているという状態です。そして売上でいえば今年もしっかりと伸ばしています。
数字を見ると、非常にいい数字です。ただこの数字を経営者がどのように捉えるかで、その先に進んでいくところが変わっていくと思います。
現状に満足するか、危機感を持つか。
満足する要素はあります。件数は横ばいで売上は上がっていますから、それだけで満足しようと思えばできます。
ただ、今日お会いした社長は、この状況に危機感を持っておられました。
現状の売上アップは単価アップによるもの。件数が一定ということは、お客様の支持率は変わっていないということです。
今の売上アップは一時的なもので、このままでは必ず下がる、そうお考えでした。
本日お話をしてみて、さらに社長はそういった意識が高まったようでした。
危機感が生まれると、それが必ず行動に移されると思います。
その結果は、良い方向に必ずいくと私は思います。
今後の動向に期待してみていきたいと思います。
業績アップの一番簡単な方法に「目標数字だけを見続ける」というものがあります。
先日お伺いした支援先のことです。今年の1月からお付き合いがスタートしたその葬儀社様と最初にやったことは、目標設定からでした。
とりあえず目標を決めましょう。今の延長ではなく、「ここまでやりたい!」という大きな目標を、と。
そして立てた目標とは昨対150%に達する目標でした。
その目標をグラフ化し、事務所内に張り出し。月毎に実績を記入していきます。
先日お伺いして、7月までの数字を確認。
目標対比で見ると90%強という数字でした。しかし、実は昨年実績との比較をすると、135%で推移していました。
社長もいつも目標を見ていたので、この数字には驚いていました。
社長はいつの間にか、150%の目標が当たり前となっており、そのための行動を自然としていたのです。
これまでのやり方では絶対に到達しない数字を設定したからこそ、行動が変わり、そして売上アップにつながったということです。
ぜひ一度、現状の延長ではない高い目標設定をしてみてください。
先日お伺いした支援先のことです。今年の1月からお付き合いがスタートしたその葬儀社様と最初にやったことは、目標設定からでした。
とりあえず目標を決めましょう。今の延長ではなく、「ここまでやりたい!」という大きな目標を、と。
そして立てた目標とは昨対150%に達する目標でした。
その目標をグラフ化し、事務所内に張り出し。月毎に実績を記入していきます。
先日お伺いして、7月までの数字を確認。
目標対比で見ると90%強という数字でした。しかし、実は昨年実績との比較をすると、135%で推移していました。
社長もいつも目標を見ていたので、この数字には驚いていました。
社長はいつの間にか、150%の目標が当たり前となっており、そのための行動を自然としていたのです。
これまでのやり方では絶対に到達しない数字を設定したからこそ、行動が変わり、そして売上アップにつながったということです。
ぜひ一度、現状の延長ではない高い目標設定をしてみてください。
今日は3つの会館を持つ葬儀社様の支援。
3月決算のその会社は、4月、5月、6月と好調を維持し、昨対120%の推移を達成していました。
しかし、7月に入ると急激な減少、結果として4月ー7月の数字は昨年とほぼ同等の数字になってしまいました。
そこで、昨年の売上の推移を見直してみました。
また売上だけではなく、販促費の内訳、月別推移を見てみると面白い関係が見えたのです。
昨年の売上高ベスト3の月と、販促費のベスト3が一致しているのです。
葬儀社にとって売上とは、人が亡くなられてはじめてできるもの、販促費との関係性というのは、一見見えづらいようにも思えます。
しかし、実際には関係があるのだと感じています。
もちろん今回の数字だけでは100%とはいえませんが、少なからずこの販促費と売上の比例関係は他の会社でも見て取れるのです。
つまり、葬儀社にとっても販促費とは、売上をつくるための投資なのだといえます。売上が下がり、利益が下がり、そのために経費削減をする。
一番最初に削られてしまいがちな販促費ですが、これを削ってしまうとさらに売上が悪くなるという悪循環がそこには待っているのです。
ぜひ、売上アップ、件数アップのために積極的な販促活動を行っていただきたいと思います。
3月決算のその会社は、4月、5月、6月と好調を維持し、昨対120%の推移を達成していました。
しかし、7月に入ると急激な減少、結果として4月ー7月の数字は昨年とほぼ同等の数字になってしまいました。
そこで、昨年の売上の推移を見直してみました。
また売上だけではなく、販促費の内訳、月別推移を見てみると面白い関係が見えたのです。
昨年の売上高ベスト3の月と、販促費のベスト3が一致しているのです。
葬儀社にとって売上とは、人が亡くなられてはじめてできるもの、販促費との関係性というのは、一見見えづらいようにも思えます。
しかし、実際には関係があるのだと感じています。
もちろん今回の数字だけでは100%とはいえませんが、少なからずこの販促費と売上の比例関係は他の会社でも見て取れるのです。
つまり、葬儀社にとっても販促費とは、売上をつくるための投資なのだといえます。売上が下がり、利益が下がり、そのために経費削減をする。
一番最初に削られてしまいがちな販促費ですが、これを削ってしまうとさらに売上が悪くなるという悪循環がそこには待っているのです。
ぜひ、売上アップ、件数アップのために積極的な販促活動を行っていただきたいと思います。
3年後、5年後はどうなっているかわからない。
確かに私もそう思います。景気によっても最適な商品のカタチは変わってくるでしょう。
だからといって先のことを考えないことは、暗闇の中を何の目印もなく闇雲に歩き続けているもの。偶然光のある出口に出られればよいですが、そうでなければ大変なことになります。
3年後、5年後の流行、それを100%当てることはできませんが、そんな時代だから勝ち残る企業のカタチはしっかりとわかっています。
それは利益重視の経営。借入金の額を押さえること。これに尽きます。
当たり前のことですが、意外にこれができていないのです。
特に葬儀業界の場合は会館を建てる際に、大きな借入金が発生します。
少し前、銀行がまだ積極的にお金を貸していた時代に会館を建てた企業は、今その返済に苦しんでいます。
一方、そんな時代でも、徹底して賃貸、居ぬき物件を中心に展開していた企業は、今非常に好調です。
借金が少なく、利益があれば、その分攻めることが出来るからです。
これからの経営は、攻めることのできる余地をどれだけ残すか、どれだけ作り上げることが出来るかがポイントになるといえます。
確かに私もそう思います。景気によっても最適な商品のカタチは変わってくるでしょう。
だからといって先のことを考えないことは、暗闇の中を何の目印もなく闇雲に歩き続けているもの。偶然光のある出口に出られればよいですが、そうでなければ大変なことになります。
3年後、5年後の流行、それを100%当てることはできませんが、そんな時代だから勝ち残る企業のカタチはしっかりとわかっています。
それは利益重視の経営。借入金の額を押さえること。これに尽きます。
当たり前のことですが、意外にこれができていないのです。
特に葬儀業界の場合は会館を建てる際に、大きな借入金が発生します。
少し前、銀行がまだ積極的にお金を貸していた時代に会館を建てた企業は、今その返済に苦しんでいます。
一方、そんな時代でも、徹底して賃貸、居ぬき物件を中心に展開していた企業は、今非常に好調です。
借金が少なく、利益があれば、その分攻めることが出来るからです。
これからの経営は、攻めることのできる余地をどれだけ残すか、どれだけ作り上げることが出来るかがポイントになるといえます。
原油価格上昇、原材料の高騰、そしてそれに伴う消費者の買い控え・・・
景気の波はプラスではないことだけは間違いなくいえます。
そんな中でも、私の付き合い先では悪くても昨対100%、いいところでは140%の数字を維持しています。
これも業界の特性なのか、比較的まだまだ葬儀業界には景気の波は押し寄せていないのかもしれません。
様々な業種のコンサルティングを行っている船井総研ですから、葬儀業界以外の情報が入ってきます。
そして、今大事なことは業績を上げるということではなく、「業績を下げない」事だといいます。
縮小するマーケットの中で業績を下げないことは、相対的には業績アップにもつながります。
さらに業績を下げないために必要なこと、それは利益管理、マネジメント体制にあるといえます。
利益に厳しくなること、そして中身を見直すこと。
さらに組織内の役割を明確にして仕事の分担をはっきりさせること。
葬儀業界を見てみると、まだまだやることは多くあります。
まだ業界としては右肩下がりではないために、業績アップが実現できる業界です。
しかし、今から業績を下げないためのマネジメント体制、利益管理を行っている会社は、これから5年、10年と強く行き続けるのだと思います。
景気の波はプラスではないことだけは間違いなくいえます。
そんな中でも、私の付き合い先では悪くても昨対100%、いいところでは140%の数字を維持しています。
これも業界の特性なのか、比較的まだまだ葬儀業界には景気の波は押し寄せていないのかもしれません。
様々な業種のコンサルティングを行っている船井総研ですから、葬儀業界以外の情報が入ってきます。
そして、今大事なことは業績を上げるということではなく、「業績を下げない」事だといいます。
縮小するマーケットの中で業績を下げないことは、相対的には業績アップにもつながります。
さらに業績を下げないために必要なこと、それは利益管理、マネジメント体制にあるといえます。
利益に厳しくなること、そして中身を見直すこと。
さらに組織内の役割を明確にして仕事の分担をはっきりさせること。
葬儀業界を見てみると、まだまだやることは多くあります。
まだ業界としては右肩下がりではないために、業績アップが実現できる業界です。
しかし、今から業績を下げないためのマネジメント体制、利益管理を行っている会社は、これから5年、10年と強く行き続けるのだと思います。











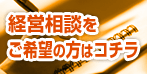





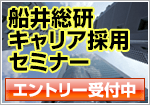
 詳細はバナーをクリック>>>
詳細はバナーをクリック>>>



