だいぶ日が空いてしまいました。
前回の日記では、
目標設定は高めに設定するほうがよい、それは業績を上げることが目的であり目標を達成することが目的ではないから
ということでした。
今回は、その理由の②として、「発想の転換を行うため」ということについて書きたいと思います。
例えば、設定した目標の数字が110%という場合、この数字は現状の仕事でも何とか頑張れば達成できるものではないかと思います。
ですが、設定した目標が150%という数字の場合、これはなかなか現状の仕事だけでは達成が難しい数字です。
そうなったときに初めて「違う方法で何か売上をあげる方法はないか・・・」
ということを考えるようになります。
こうやって違う方向からビジネスの可能性を考えることが非常に大事なのです。
「現状維持は衰退」
といいます。同じことだけをずっとやっていても、いずれ企業は衰退してしまいます。
かといって、現状の仕事も忙しいのでなかなか次のことを考える時間も見つからないのではないでしょうか。
だからこそ150%の目標達成という一見無理な数字を設定することで、新しいことを
考えること事態を「必要なこと」にしてしまうのです。
そうすることで、会社はまた一歩上のレベルに行くことが出来るのだと思います。
*************************
ちょっと知りたい、聞いてみたい!
船井総合研究所 前田亮への無料経営相談はこちら↓
ryomaeda@funaisouken.co.jp
*************************
前回の日記では、
目標設定は高めに設定するほうがよい、それは業績を上げることが目的であり目標を達成することが目的ではないから
ということでした。
今回は、その理由の②として、「発想の転換を行うため」ということについて書きたいと思います。
例えば、設定した目標の数字が110%という場合、この数字は現状の仕事でも何とか頑張れば達成できるものではないかと思います。
ですが、設定した目標が150%という数字の場合、これはなかなか現状の仕事だけでは達成が難しい数字です。
そうなったときに初めて「違う方法で何か売上をあげる方法はないか・・・」
ということを考えるようになります。
こうやって違う方向からビジネスの可能性を考えることが非常に大事なのです。
「現状維持は衰退」
といいます。同じことだけをずっとやっていても、いずれ企業は衰退してしまいます。
かといって、現状の仕事も忙しいのでなかなか次のことを考える時間も見つからないのではないでしょうか。
だからこそ150%の目標達成という一見無理な数字を設定することで、新しいことを
考えること事態を「必要なこと」にしてしまうのです。
そうすることで、会社はまた一歩上のレベルに行くことが出来るのだと思います。
*************************
ちょっと知りたい、聞いてみたい!
船井総合研究所 前田亮への無料経営相談はこちら↓
ryomaeda@funaisouken.co.jp
*************************
お付き合いを始める最初の段階として、目標設定を必ずするようにしています。
どれだけの売上を上げたいのか、件数をやりたいのか、そして単価設定はいくらになるのか、といった部分を落とし込んでいきます。
そのときの目標設定金額のたて方ですが、私は『実現不可能』な目標設定をすることをお勧めしています。
理由としては、
①業績を上げることが目的であり、目標を達成することが目的ではないから。
②発想の転換を行うため
①については、例えばマラソンをイメージしてもらうとわかるのですが、マラソンはゴールの距離を考えて、ペースの配分をすると思います。
ですから、ハーフマラソンを走っている途中で、いきなり距離をフルマラソンに変えてしまえば、その人は走りきることはできないでしょう。
売上目標も私は同じではないかと思っています。
例えば、9000万の売上の会社が目標を1億円と設定する。
すると自然と1億円を目指して走るようになる。がんばって何とか1億円達成!!
ですが1億5千万円となると難しいのではないかと思っています。
ですが、例えば2億円を目標にした場合、1億円というのは”通過点”でとなるため、1億円達成時の疲労具合は変わってくるのです。
1億5千万円も通過点ですから、達成の可能性はあります。
110%の目標を設定して、120%の達成をする。
150%の目標を設定して、90%の達成をする。
実はこの2つを比較すると
110%×120%=132%
150%×90%=135%
つまり、売上額のアップとしては後者の方が高くなります。
もちろん「達成感が必要だ!!」という考え方もありますので、後者の考え方が絶対正しいとは思っていません。
ただ、私は後者の目標設定をお勧めするようにしています。
長くなりましたので、理由の②は次回に。
*************************
ちょっと知りたい、聞いてみたい!
船井総合研究所 前田亮への無料経営相談はこちら↓
ryomaeda@funaisouken.co.jp
*************************
どれだけの売上を上げたいのか、件数をやりたいのか、そして単価設定はいくらになるのか、といった部分を落とし込んでいきます。
そのときの目標設定金額のたて方ですが、私は『実現不可能』な目標設定をすることをお勧めしています。
理由としては、
①業績を上げることが目的であり、目標を達成することが目的ではないから。
②発想の転換を行うため
①については、例えばマラソンをイメージしてもらうとわかるのですが、マラソンはゴールの距離を考えて、ペースの配分をすると思います。
ですから、ハーフマラソンを走っている途中で、いきなり距離をフルマラソンに変えてしまえば、その人は走りきることはできないでしょう。
売上目標も私は同じではないかと思っています。
例えば、9000万の売上の会社が目標を1億円と設定する。
すると自然と1億円を目指して走るようになる。がんばって何とか1億円達成!!
ですが1億5千万円となると難しいのではないかと思っています。
ですが、例えば2億円を目標にした場合、1億円というのは”通過点”でとなるため、1億円達成時の疲労具合は変わってくるのです。
1億5千万円も通過点ですから、達成の可能性はあります。
110%の目標を設定して、120%の達成をする。
150%の目標を設定して、90%の達成をする。
実はこの2つを比較すると
110%×120%=132%
150%×90%=135%
つまり、売上額のアップとしては後者の方が高くなります。
もちろん「達成感が必要だ!!」という考え方もありますので、後者の考え方が絶対正しいとは思っていません。
ただ、私は後者の目標設定をお勧めするようにしています。
長くなりましたので、理由の②は次回に。
*************************
ちょっと知りたい、聞いてみたい!
船井総合研究所 前田亮への無料経営相談はこちら↓
ryomaeda@funaisouken.co.jp
*************************
ご支援先が好調です。
今日4月から10月までの売上を見たら、昨対120%で推移していました。
昨年の1年間も大きな成長をした会社なので、今、まさに破竹の勢いです。
さて、その会社、売上はさることながら粗利益率の向上が目を見張ります。
売上が成長しながらも粗利益率も5%ほど上昇。
経費が一定であれば、営業利益率がそのまま5%上がるわけですから、すばらしい数字です。
この「粗利益率の向上」、やったことはごく単純です。
それは、「数字を出すこと」。それだけです。
具体的には、
①月毎に
②葬儀の基本料金、供花、返礼品、料理、ドリンクの5分野に分解
しただけです。
こうやって売上を分解して集計すると、どこにどれだけの売上があるかがわかります。
当然それぞれの粗利益率に違いもあります。
これら5分野の組み合わせを変えることで粗利益率は変わるんです。
いや、供花や返礼品、料理はお客様の数によって決まるものだから無理だろう・・・。
そう思うかもしれませんが、実際に変わるんです。
問題意識が発生すれば、自然とそこに解決策を考えようと工夫が働きます。
その工夫を実行すれば、確実に変化は生まれます。
それが結果の違いに現れます。
さて、数字はしっかりチェックされていますでしょうか?
*************************
ちょっと知りたい、聞いてみたい!
船井総合研究所 前田亮への無料経営相談はこちら↓
ryomaeda@funaisouken.co.jp
*************************
今日4月から10月までの売上を見たら、昨対120%で推移していました。
昨年の1年間も大きな成長をした会社なので、今、まさに破竹の勢いです。
さて、その会社、売上はさることながら粗利益率の向上が目を見張ります。
売上が成長しながらも粗利益率も5%ほど上昇。
経費が一定であれば、営業利益率がそのまま5%上がるわけですから、すばらしい数字です。
この「粗利益率の向上」、やったことはごく単純です。
それは、「数字を出すこと」。それだけです。
具体的には、
①月毎に
②葬儀の基本料金、供花、返礼品、料理、ドリンクの5分野に分解
しただけです。
こうやって売上を分解して集計すると、どこにどれだけの売上があるかがわかります。
当然それぞれの粗利益率に違いもあります。
これら5分野の組み合わせを変えることで粗利益率は変わるんです。
いや、供花や返礼品、料理はお客様の数によって決まるものだから無理だろう・・・。
そう思うかもしれませんが、実際に変わるんです。
問題意識が発生すれば、自然とそこに解決策を考えようと工夫が働きます。
その工夫を実行すれば、確実に変化は生まれます。
それが結果の違いに現れます。
さて、数字はしっかりチェックされていますでしょうか?
*************************
ちょっと知りたい、聞いてみたい!
船井総合研究所 前田亮への無料経営相談はこちら↓
ryomaeda@funaisouken.co.jp
*************************
「競合店が自社の近くに出店してきた。
それによって件数が下がってしまった。
じゃあ自社も違う地域に出店しよう!!」
そういった思考回路で動いてしまう経営者の方は多いように思います。
確かに、施行件数が減るのは非常に厳しい。
商圏も広げれば施行件数の増加につながる可能性は有ります。
ただ、これは一時的なもの、特効薬のようなものであり、根本的には解決にはなりません。
なぜなら、同じ地域にまた競合店が出店してきてしまえば、また同じことが起きるからです。
しかも業績が右肩下がりの時に行うチャレンジは、失敗する可能性が大きいのです。
ですから、私は「競合店対策のために出店したいんです!」というお話には、相当良い条件でない限りGOサインは出しません。
出来ることは探せばいくらでも見つかります。右肩下がりの会社ほど、多く見つかるものです。
なぜなら本当にやることを全てやっていれば、競合店が来ただけではびくともしないからです。
出店を考える前にちょっと冷静に、今できることを見直してみてはいかがでしょうか。
それによって件数が下がってしまった。
じゃあ自社も違う地域に出店しよう!!」
そういった思考回路で動いてしまう経営者の方は多いように思います。
確かに、施行件数が減るのは非常に厳しい。
商圏も広げれば施行件数の増加につながる可能性は有ります。
ただ、これは一時的なもの、特効薬のようなものであり、根本的には解決にはなりません。
なぜなら、同じ地域にまた競合店が出店してきてしまえば、また同じことが起きるからです。
しかも業績が右肩下がりの時に行うチャレンジは、失敗する可能性が大きいのです。
ですから、私は「競合店対策のために出店したいんです!」というお話には、相当良い条件でない限りGOサインは出しません。
出来ることは探せばいくらでも見つかります。右肩下がりの会社ほど、多く見つかるものです。
なぜなら本当にやることを全てやっていれば、競合店が来ただけではびくともしないからです。
出店を考える前にちょっと冷静に、今できることを見直してみてはいかがでしょうか。
私はサッカーをやっていたこともあってスポーツが好きです。
意外とスポーツを見ていると経営に生かせることがあるんです。
サッカーにしろ、野球にしろ、強いチームには「勝ちパターン」があるものです。
じっくり守ってからのカウンターが得意なチーム、サイドからの徹底的な攻めが売りのチーム、そしてゴール前のパスワークで相手を崩すチームなど、”色”があるチームほど、強いということが多いのです。
これは企業にも同じことだと思います。
要は自社の”勝ちパターン”が確立されている会社ほど、業績がいいように感じます。
何を使って集客し、どのツールを使って会員化し、どんなものを使ってフォローをするのか。
施行後は何日後にお礼状を書き、何日後にご訪問するのか。
そういったルールが決まっており、それが徹底されている会社ほど業績がいいのです。
逆に、周りがやっているからという理由で、チラシを入れてみたり、セミナーを開催してみたりすると失敗に終わり、「なんだセミナーなんて効果ないじゃん」ということになるのです。
私の支援先では、チラシの効果も上がっています。
セミナーもしっかりと集客、施行件数アップにつながっています。
そのやり方、自社の勝ちパターンを確立することで、着実に会社は強くなり、業績も上がっていくのです。
意外とスポーツを見ていると経営に生かせることがあるんです。
サッカーにしろ、野球にしろ、強いチームには「勝ちパターン」があるものです。
じっくり守ってからのカウンターが得意なチーム、サイドからの徹底的な攻めが売りのチーム、そしてゴール前のパスワークで相手を崩すチームなど、”色”があるチームほど、強いということが多いのです。
これは企業にも同じことだと思います。
要は自社の”勝ちパターン”が確立されている会社ほど、業績がいいように感じます。
何を使って集客し、どのツールを使って会員化し、どんなものを使ってフォローをするのか。
施行後は何日後にお礼状を書き、何日後にご訪問するのか。
そういったルールが決まっており、それが徹底されている会社ほど業績がいいのです。
逆に、周りがやっているからという理由で、チラシを入れてみたり、セミナーを開催してみたりすると失敗に終わり、「なんだセミナーなんて効果ないじゃん」ということになるのです。
私の支援先では、チラシの効果も上がっています。
セミナーもしっかりと集客、施行件数アップにつながっています。
そのやり方、自社の勝ちパターンを確立することで、着実に会社は強くなり、業績も上がっていくのです。
葬儀の業界において、”生産性”を見られている会社はどのくらいあるでしょうか。
葬儀の件数はチェックしていても、なかなか売上、もっといえば生産性まで見られる会社は少ないのではないでしょうか。
私の支援先に、生産性を見直したことによって業績を急激に伸ばした会社があります。
ちなみに生産性とは、売上を人員で割った数字のことです。パート人員は0.5人として数えます。
例えば、社員8人、パート4人の会社で、一ヶ月の売上が2000万円の場合、
生産性は2000万円÷10人=200万円という数字になります。
この生産性ですが、TKCの経営指標によると業界の平均値は約120万円、優良企業でも約180万円という数字です。
私が新しくお付き合いを始めたA社というところでは、この生産性が約280万円でした。
これを現在では、約240万円まで落としています。結果として業績は150%と急成長を遂げました。
生産性という指標は、当然高ければよいのですが、高すぎるとそれはそれで問題がある場合もあります。
この会社でいえば、280万円という数字は、非常に高いのですが、その分社員への負荷もものすごいものでした。
それは結果として、お客様へのアフターフォローや商品価値の低下につながるのです。
生産性を意図的に下げることで、仕事に余裕が生まれ、その分を商品価値向上、お客様とのコミュニケーションにまわすことで、良い結果を生んだのです。
ちなみに業界平均はあるのですが、私が全国を廻ってみて思う最適な数字は、月次生産性約250万円という数字だと考えています。
葬儀の件数はチェックしていても、なかなか売上、もっといえば生産性まで見られる会社は少ないのではないでしょうか。
私の支援先に、生産性を見直したことによって業績を急激に伸ばした会社があります。
ちなみに生産性とは、売上を人員で割った数字のことです。パート人員は0.5人として数えます。
例えば、社員8人、パート4人の会社で、一ヶ月の売上が2000万円の場合、
生産性は2000万円÷10人=200万円という数字になります。
この生産性ですが、TKCの経営指標によると業界の平均値は約120万円、優良企業でも約180万円という数字です。
私が新しくお付き合いを始めたA社というところでは、この生産性が約280万円でした。
これを現在では、約240万円まで落としています。結果として業績は150%と急成長を遂げました。
生産性という指標は、当然高ければよいのですが、高すぎるとそれはそれで問題がある場合もあります。
この会社でいえば、280万円という数字は、非常に高いのですが、その分社員への負荷もものすごいものでした。
それは結果として、お客様へのアフターフォローや商品価値の低下につながるのです。
生産性を意図的に下げることで、仕事に余裕が生まれ、その分を商品価値向上、お客様とのコミュニケーションにまわすことで、良い結果を生んだのです。
ちなみに業界平均はあるのですが、私が全国を廻ってみて思う最適な数字は、月次生産性約250万円という数字だと考えています。











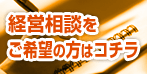





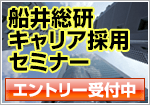
 詳細はバナーをクリック>>>
詳細はバナーをクリック>>>




