1975年、イーグルス4枚目のスタジオ・アルバム、ONE OF THESE NIGHTS(呪われた夜)が発売された、全米1位。
このアルバムによって、イーグルスはついにアメリカでトップのロック・バンドに上り詰めた。
シングル・カットされたタイトル曲、ONE OF THESE NIGHTSは印象的なベース・ラインとギターのカッティングから始まるファンキーなR&Bの曲調にウエストコースト・ミュージックらしいコーラスが絡むというそれまでのイーグルスのイメージを一新させるような曲であった。
イーグルスと言えば、カントリー・ロックやバラードに美しいコーラスというイメージがあったので、最初この楽曲を聴いたときは正直馴染めなかったのだが、何回も聴くうちにハマってしまい、よくカラオケで歌ったものである。年を取りまたカラオケも長い間ご無沙汰なので、この歌の高音のパートはもう歌えないだろう。
この曲以外にも、いつものイーグルスと言える、LYIN’EYES(偽りの瞳)やTAKE IT TO THE LIMITなどのヒット曲や、プログレ・カントリーとでも言えるようなインスト・ナンバーのJOURNEY OF THE SORCERERなど聴きどころ満載である。
このアルバムをもって、オリジナル・メンバーの一人、バーニー・リードンが脱退する。何が脱退の原因なのかは当事者でしか知る術はないが、若い頃は各人の自己主張も強く、また人生の経験も中途半端であるがゆえ、お互い物事を達観した上での行動が出来ずバンド内でのいざこざが起こってしまうのだろう。
長い年月が過ぎ、2013年にHISTORY OF THE EAGLESというドキュメンタリー・フイルムを製作し、そのサポートとしてワールド・ツアーを開催、2013と14そして15年と3年にまたがって世界各地を回り、今年の7月にツアーが終了した。
なんと、おなじみであるグレン・フレイ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュそしてティモシー・シュミットからなる4名のメンバーにバーニーも加わっているではないか!
やっぱり年をとると、お互い分かり合える時がやって来るのである。
めでたし、めでたし。
ちなみに、HOTEL CARIFORNIA製作後脱退したランディー・メイズナーは、体調不良のため参加出来なかったみたいだが、ドン・フェルダーに関しては彼に対してツアー参加のオファーを出さなかったようだ。
ここまで関係悪化するって、いったいどういうこと?
Eagles - One Of These Nights
博士:ネットからのダウン・ロードやレンタル・ショップで借りたCDをPCに取り込んだり、またユー・チューブの音源で満足という人もいるから、音楽ファンが半減したということにはならないが、毎年減少傾向という統計結果を見ると、趣味の多様化が進み、わざわざCDを買って楽しむという人口が減ってきているのは確かだと思う。
助手:シングルのほうは、2014年の 生産は約5550万枚で、その内訳は邦楽が5480万枚で洋楽のシングルはほとんど出されていないので70万枚程度とのことです。2005年と比べますと、約15%減少です。
博士:アルバムと比べそれほど減少していないのは、やっぱり某アイドル・グループのおかげじゃのう~ なにしろシングルを出すたびにミリオン・セラーじゃからのう~
昔懐かしい赤丸急上昇なんて言葉を出す前に、発売と同時にあっさりとシングル・チャート1位を獲得し翌週からは1位から陥落という現象が起こるのは、ガチのファンが特典付きの数種類のバージョンの初回限定盤をネットのサイトから大量予約購入をするからじゃのう~
この手の商法の良し悪しについて、いろいろ議論はあると思うが、少なくとも彼女たちの頑張りで、業界は一息ついているのじゃと思う。
残念なのは、90年代に数多くあったミリオン・セラーを叩き出すミュージシャンが2000年を過ぎてほとんどいなくなったことじゃ。
60-70年代にヒットしたロックは未だにリマスターなどされて再発されている。同様に現在のミュージシャンも頑張って、 将来に歌い継がれるようなビッグ・ヒットを次々と出して欲しいものじゃ。
助手:博士! たまにはいいこと言いますね。今日何かいいことあったんですか?
博士:実はのう、今日街を歩いていると、ペット・ボトルの飲料が80円で売っている自販機を見つけたのじゃ! もちろん、2流のメーカーの商品だったり、賞味期限が近づいている商品だったからかもしれんが?
それでも、自販機に入れて冷やすなどして経費が結構かかっているのに、80円で売るとは、一体原価って幾らなのか?
今まで一番安かったのは、100円じゃったからのう~ 感激ものじゃ。
売れ筋のCDの価格もこうならんかのう? そうすれば、ミリオン達成も夢で無くなるのじゃが。
ジャケ裏で両親が心配するのをよそに、普通の玩具では飽き足らない少年は老人がかざす宝石の美しさにぐいぐいと引き込まれて行く様子が描かれている。

現代の子供は、少子化のため両親が一人当たりの子供にお金を使う額が増えていて、そのため他の子供と横並びではあるが結構高額な遊び道具を手に入れ物質的にある程度満たされているように思えるし、TVやインターネットからもたらされる多くの情報によって結構大人顔負けに現実的になっていることから、何かに対して盲目的に惹きつけられることは少なくなったのではないかと思う。もう少し素朴さがあってもいいのではないかと思う今日この頃。
さて再編後のMOODY BLUES6枚目のアルバムとなるEVERY GOOD BOY DESRVES FAVOUR(邦題は童夢)1971年の発売(全英/全米 1/2位)。彼らはプログレ・ロックにカテゴライズされている。
じゃあ、プログレ・ロックとは?
- 独創的もしくは芸術的なコンセプトを持って1枚のアルバムを作る
- 長尺かつ変拍子と使った複雑な構成の楽曲がある
- 演奏を重視、ボーカルも演奏の一部と考える
- クラッシック、ジャズ、現代音楽などに既存のロック・サウンドを融合
- シンセサイザーやメロトロンなど新しい楽器を使用
などと思いつき、MOODY BLUESもその範疇に入るのだが、1971年当時の他のプログレ・バンドとは少し趣が違うように感じる。
1971年といえば、
KING CRIMSONのISLAND(4枚目)、全英/全米 30/76位
PINK FLOYDの MIDDLE(6枚目)、全英/全米 3/70位
YESの 3RD ALBUM(3枚目)、全英/全米 7/4とFRAGILE(4枚目)、全英/全米 7/4位
GENESISのNURSERY CRYME(3枚目)、全英 39位
ELPのTARKUS(2枚目)、全英/全米1/9位とPICTURE AT AN EXHIBITION(LIVE)全英/全米3/10位
MOODY BLUESの楽曲の歌詞は尖った内容のものが多いが、上記のバンドとは異なる、親しみやすく素朴なメロディーを持ったソフト・ロック系のサウンドが違いを出していたのだと思う。
私が初めて聴いた時と同じ年齢の現代の子供たちが、この音楽を聴いたらどのように感じるのか非常に気になる。
時代は変わったけれど、どう感じとるのかな~
The Moody Blues -- Story in Your Eyes (with lyrics)
第一弾として、東芝EMIの企画をアメリカのキャピトルが纏め上げたビートルズのロック・サウンド主体の曲を集めた2枚組のコンピ盤、ROCK N ROLL MUSIC が発売され、既発曲ばかりの寄せ集めだったのにもかかわらず、 アメリカ・チャート2位と大ヒットとなった。
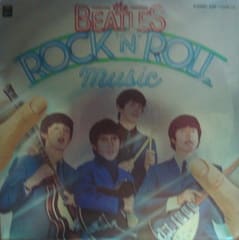
ROCK N ROLL MUSIC、日本盤はピカピカと銀色に輝くジャケットだが、写真に写そうとすると反射するのでなかなかうまく撮れない。
翌年、同じく2匹目のドジョウを狙って、東芝EMIがラブ・ソングというキーワードで企画した2枚組のコンピ盤、LOVE SONGSを制作。チャート的には24位と前作のような大ヒットとはならなかったが、それでも2000年の時点で、アメリカでの累積セールスが300万枚を記録した。
既出の曲であっても、テーマに沿って選曲された曲をうまく並べ替えることで、それまでのオリジナル盤や赤・青のベスト盤とはまた違った曲のイメージを感じ、新鮮さが生まれたのだろう。これらのコンピ盤は、オリジナル・アルバムの収録曲と別ミックスのものを採用しているケースもあり、マニアであれば少しだけ微妙な違いを感じ取ることが出来る。
しかしながら、デジタル・サウンド時代になり、現在では2009年にリマスターされた音源を持っていれば、コンピュータに取り込み同じシークエンスで演奏することが可能なのである。微妙に違う当時と同じミックスの楽曲を味わいたいとか、 レコードのジャケットなどに興味のあるマニア以外には、この手のコンピ・アルバムは用済みになったと思いきや、21世紀になってもさらなるコンピ・アルバムが制作され続けている。
2000年に発売されたコンピ盤、BEATLES 1はチャート・ナンバー1を獲得したシングルを寄せ集めたものだが、CDの16ビットデジタルからさらに進化した24ビットのハイレゾ・デジタルのリマスタリングが施され、それを売りにして発売されこれも全米チャート1位に輝く。
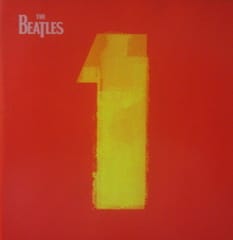
BEATLES 1 CD盤
さらに、今年の11月にBLUE-RAYもしくは DVDのフォーマットにビデオと楽曲を収録した新しいBEATLES 1が出る。映像は最新技術によって修正され、音源も5.1CHのマルチ・トラックに変換されている。
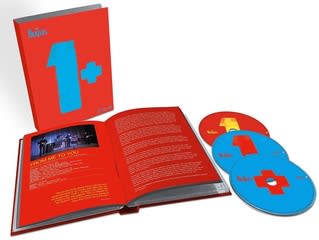
BEATLES 1 BLUE RAY +CD盤
サッカーの代表チームで、試合中にあるプレイヤーがミスを犯すと、なぜこの選手を代表チームのレギュラーとして使い続けるのか?なんて議論がよく起こるのだが、それはその選手に取って代わる実力を持った次世代の選手が見当たらないからであろう。
同様に、ビートルズの残した楽曲が偉大であり、レコード会社としてはビートルズに取って代わる存在が現れない限り、今後とも手を替え品を替えて延々と続いていくのであろう。普通の商売では、他社の先をいく新しい事業を立ち上げると、昔なら3-5年はそれで優位性を保てたのだが、情報化の進んだ現在ではもしその新しい事業が成功でもすれば、他社の追従によりあっと言う間に追いつかれることとなる。
50年前の音源で、今でも大きな商売が成り立つビートルズが羨ましい限りである。
ラブ・ソング収録のI WILL をどうぞ。
The Beatles - I Will
アメリカの60年代-70年代のサウンドを求めて、2003年のアメリカのロス・アンジェルスでファースト・アルバムが収録あれ、2003年発売されたアルバム、SO MUCH FOR THE CITYは母国あるランドで1位を獲得また英国でも3位にランクされた。
アイルランド出身のインディー・ロック・バンドということでU2のようなロック系のサウンドと思いきや、アメリカのフォークやカントリーをベースにした感じのサウンドである。
ではウエストコースト系の明るいフォークロックのようなものか?と言うとそれとも少し違う。同系統のアメリカン・バンドにはない、少し明るさを抑えたような不思議な感じを受ける。
大手のバージン・レコードから出たCDなので日本でも発売されたのではないかと思うのだが、当時海外に在留していた時にこのCDを買ったので、日本で当時どのような評価があったのかはわからない。 多分、地味なサウンドなので、日本ではあまり受けなかったのではないかと推測する。
今も昔も、若者は大志を抱き、彼らのプロミス・ランドとして一度はアメリカを目指す。それが、将来の成功に繋がるのかはたまた失望し帰国するのかは、誰も前もって予測は出来ない。
海外に行ったからすごいとか偉いとかは言わないが、日本人の若い人は最近海外志向を持った人が少なくなったように聞く。どのような理由かは定かではないが、言葉もよく通じない国に行って苦労するよりは、日本で住んだ方が随分と楽に生きていけるとでも思われているのかもしれない。
しかし、少しの間海外に出て外から日本の姿を眺めるのも一考である。今まで日本では、当たり前のことが彼の地では通じないことも。そして改めて日本人として日本に生まれてなんと良かったのかなんて初めて思うかもしれない。
例えば、国民健康保険に加入していれば、日本では医療費などに於いて非常に安く恵まれている。彼の地で、病気にかかり少しの間病院に入院し、退院の手続きの際高額の請求書を見て飛び上がったり、スペシャリストと呼ばれる専門医などにかかると、これまた高額の請求書をもらう羽目になる。日本で簡単な数千円単位の歯科での治療も数万円もかかることになる。
THE THRILLSの場合、セカンド・アルバムを2005年に再びアメリカで録音しファーストと同等の成功をアイルランドと英国で収めるのだが、 2007年にカナダで録音された彼らのサードは、受けが悪くその後解散に至る。アメリカ録音による独自のサウンドで一旦成功は掴みかけたが、それを継続していくことにはならなかった。
なかなか厳しい世界である。
The Thrills - Santa Cruz (You're Not That Far)
通常アルバムのプロモーションとして、先行シングルを出し、場を盛り上げたところに、セカンド・シングルとアルバムを一気に投入し売り上げ拡大を図る。
前回ファースト・シングルとしてカットされたSHE DID ITは23位と健闘したわけだが、セカンド・シングルでアルバムの目玉であったTHE BOAT AGAINT THE CURRENTが88位と振るわず、アルバム売り上げ上昇につながるブースターの役割を立たせなかったことが、アルバム売り上げ不振の原因だったと思う。
やはり、シングルはアルバム収録の楽曲と異なりラジオ・フレンドリーでなければならない。そう言った意味で、セカンド・シングルだったTHE BOAT AGAINT THE CURRENTはAMラジオでオン・エヤーされるには、少し冗長で重すぎるサウンドであったのでは…
というわけで翌年の1978年に出されたサード・アルバム、CHANGE OF HEARTは文字通り、以前とは方向性が違うアルバムとなった。レコード会社のプッシュからか、シングル・ヒット狙いのためラジオ・フレンドリーを意識して曲も3分程度の長さで、また全体的に比較的軽いアレンジで各楽曲が制作された。
リード・シングルのCHANGE HEARTは親しみのあるメロディーを用いたミッド・テンポの曲で19位と大健闘したわけだが、セカンド・シングルはモータウン・サウンドのヒットをカバーであったBABY I NEED YOUR LOVIN’で、それ はファースト同様の方程式で制作されたのだが、振るわず62位。サード・シングルはなんとチャート・インしなかった。またアルバムも137位と大幅に沈んだ。
一体何が?
シングル・ヒットを狙いすぎ、全体的にスリックなイメージなったため、エリックの持ち味であった時にはオーバー・プロデュース気味のサウンドやねちっこさが消えてしまったことが問題なのか? それとも時代が求めていたものとサード・アルバムの音作りが若干ずれていたのか?
思いもよらなかった、セカンドとサード・アルバムの不発により、今後のエリックの音作りの方向性はさらなる混迷を深めるのであった。
続く…
しかし、
安心してください。腕利きのウエスト・コースト系のセッション・ミュージシャンに囲まれて制作された演奏は素晴らしいの一言です。
ERIC CARMEN Change Of Heart
また、年をとるにつれてあまり複雑なストーリーも敬遠するように成り、新作もしくは準新作の単純明快なアクション物を好むように成り、テレビの映画番組にあまり興味を示さなくなった。
とは言え、贔屓の役者が主演である場合は、ストーリーに関係なく観てみようかということもある。個人的贔屓のレオナルド・デカプリオとトビー・マグワイヤ(スパイダー・マンの人)による、2013年リメイクの“華麗なるギャッビー”が昨晩深夜に放映されていたので、アクション物ではないが、鑑賞することと相成った。
トビー扮するギャッビーの友人が、ギャッビーの伝記をまとめ終えたところ(伝記の題名をTHE GREAT GABBYと書き換えた場面)で映画はTHE ENDとなるわけだが、その少し前の場面でTHE BOAT AGAINT THE CURRENT(逆流に向かってボートを漕ぎ出す)という言葉が出てきた。
これは、本日アップする予定だったエリック・カルメンのソロ2作目のタイトルではないかと思い出した。ネットで調べてみると、フィッツジェラルドが1925年に出した小説THE GREAT GABBY(華麗なるギャッビー)からエリックが借りた物だというような事がわかった。 1977年に買ったレコードのライナー(朝妻一郎氏執筆)にはその事が記されていなく、つい先ほど観た映画から38年を経てわかったのだ。偶然とはいえ、少し驚く。
2作目のソロ・アルバム、THE BOAT AGAINT THE CURRENT(邦題、雄々しき翼)は、全米45位となり、タイトル曲のTHE BOAT AGAINT THE CURRENTとSHE DID ITは シングル・カットされ、それぞれ88位と23位であった。
このアルバムは、当初エルトン・ジョンのプロデュース有名なガス・ダッジョンを起用して英国で録音されるとの事だったが、いろいろとプロデューサーと衝突があったのか、オリジナルのプランを変更し最終的には自身でプロデュースする事になりアメリカで完成した。セルフ・プロデュースされた納得のいくエリックの自信作であったのだが、残念ながらチャート的には前作と比べると振るわなかった。
シングル・カットされた楽曲を検証してみると、
THE BOAT AGAINT THE CURRENTは前作のALL BY MYSELFとよく似たエリックのヒットの方程式に沿って書かれた、美しくダイナミックなスローバラードの佳曲であったが、少しアレンジに力が入りすぎた(少し大袈裟すぎた)のか、AMラジオでオンエヤーされ気軽に聴くタイプの曲ではないような気がした。そのためチャート下位に低迷したのでは…
また、反対にSHE DID ITは、ビーチ・ボーイズのブルース・ジョンストンをコーラス・アレンジャーとして迎え、ビーチ・ボーイズ・スタイルのコーラスを従えたアメリカ受けする楽しい楽曲に仕上がったのが、21位のヒットに繋がったと思われる。コーラスを加えたことによって、当初のデモ音源とは全く異なった楽しい曲に生まれ変わった。
そういえば、ブルース・ジョンストンは、このアルバムの数年前に、エルトンのカリブというアルバムの中の楽曲、DON’T LET THE SUN GO DOWN ON ME(僕の瞳に小さな太陽)でもコーラス・アレンジメントを担当している。これも偶然?
そして、ロンドンでの録音の名残かどうか、幾らかの曲のドラムはエルトン・バンドのナイジェル・オルソンによって叩かれ、またポール・バックマスターもオーケストラのアレンジャーとして参加している。彼らが参加した曲を聴くと、ガスはエルトンの2作目から4作目のスタジオ・アルバムのようなサウンドを狙っていたような気もする。
しかしながら、プロデューサーの言う事を聞いて制作し、それがいつも成功するとは限らない。実際、クリス・レアのデビュー時、第二のエルトンを目論みガスを起用したが成功には至らなかった。
ヒット狙いで著名なプロデューサーを起用したり、ヒットの方程式に当てはめて練りに練った楽曲を出しても、必ずしもヒットするものではない。前もって計算に入れていなかった、なんらかの偶然が時にヒットをもたらすこともある。
音楽の制作とはなかなか奥の深いものである。
Eric Carmen - Boats Against The Current
Eric Carmen - She Dit It
1975年、 元ラズベリーズの中心メンバーであった、エリック・カルメンが自身の名前をアルバムタイトルに冠した、ソロ・デビュー・アルバムを紹介しよう。
ラズベリー時代のレコードのライナーを読むと、彼は好きなミュージシャンとして、ビートルズ、ストーンズ、ビーチ・ボーイズ、バーズ、ラフマニノフそしてプレスリーらを挙げている。なんでも、クリーブランド音楽学院に在籍した当時は、ラフマニノフとプレスリーを研究したとなっている。
なるほど、このアルバムに収録されている曲は過去に影響を受けたアーティストの香りが大いに感じられ、そしてエリック独特のハイトーンの声と独特のこってりした節回しで歌い上げている。
アルバムは、全米21位となり、ラフマニノフの影響をもろに受けたALL BY MYSELFとNEVER GONNA FALL IN LOVE AGAINはシングル・カットされ、それぞれ2位と11位に輝いた。前出のSUNRISEも34位と健闘した。
AORという言葉がアメリカで70年代に出てきた。当初はAUDIO ORIENTED ROCKと音を重視するロックと定義されたみたいだが、後にADULT ORIENTED ROCKすなわち大人向けのロックと解釈が変わった。
その大人向けロックというと、草分け的存在は、ブラス・ロックの雄、シカゴで、1973年にアルバムCHICAGO VIに於いて、シングル向けにカットされたJUST YOU N’ MEやFEELN’ STRONG EVERY DAYなど今までと異なるソフトでポップ・ソングな楽曲が当てはまるだろう。

アルバム全体を通してAORと解釈出来るのは、このアルバムあたりぐらいからではないだろうか? 翌年の1976年には同様な扱いでボズ・スキャッグスがSILK DEGREESを出し、トトやクリストファー・クリスなどが続く。そして80年代には、多くのミュージシャンがこのカテゴリーで楽曲を出しAOR全盛時代を形成していくのである。
つい最近まで、ロック小僧と言われた俺が、AORを聴きそして語るなんて、俺も随分大人に成ったもんだ… フッ(ため息)
何、かっこつけてんの! 後期高齢おっさんのくせに!
すみません。
ERIC CARMEN - Sunrise
1978年 トリプル・ギターの編成でハードなサウンドを展開したライブ・アルバム、BRING IT BACK ALIVE の後、2枚のスタジオ・アルバム、1978年にPLAYIN’ TO WIN(全米60位)と1979年にIN THE EYE OF THE STORM(全米55位)を出した。
その翌年に出したスタジオ・アルバムが、GOST RIDERSでチャートも全米25位と再び盛り返したのである。
デビュー・アルバムやセカンド・アルバムにあったアコースティック・ギターのバッキングに美しいコーラスという特徴を持ったウエスト・コースト系のサウンドは消え去り、ギターのキレがいいアップ・テンポな曲もバラードも南部フレーバーのロックやカントリー・サウンドに変化した。
シングル・カットされたGHOST RIDER IN THE SKYは1948年作られた古い西部劇のカーボーイ・スタイルのもので、多くのアーチストにカバーされた。メロディーを聴けばそういう曲があったなと思い起こされることであろう。
アウトローズのカバーは、トリプル・ギターによるハードなサウンドで、全米31位と中ヒットした。アレンジ次第で古い名曲も生まれ変わり、リバイバル・ヒットするのである。 また、1978年のレオ・セイヤーが歌ってヒットした、I CAN’T STOP LOVING YOU(BILLY NICHOLLAS作)もアウトローズらしさを出してカバーしている。
この後も、スタジオやライブ・アルバムを出し続けていくわけだが、このアルバム以降はチャートの上位を獲得することなくなった。そしてその後、メンバー・チェンジを繰り返して活動を継続し、なんと2012年に18年ぶりの新譜を出しているようだ。
南部出身のバンドは本当にタフである。
The Outlaws - Ghost Riders in the Sky
The Outlaws - I Can't Stop Loving You
博士:お父さんのモノマネをしてみたのじゃ。最近保険のコマーシャルでよく見かけるからのう。
助手:そういえば、喜多郎氏は、70年代に和製プログレバンド、ファーイスト・ファミリー・バンドでキーボードを弾いていましたね。1975年のファースト・アルバムのタイトルが“地球空洞説”だったと思いますが…
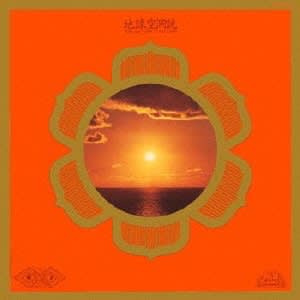
ファースト・アルバム “地球空洞説”
博士:70年代には、海外でもサウンドが受け入れられることを念頭にしたバンドがいろいろと登場し、和物プログレではファーイースト・ファミリー・バンドやコスモス・ファクトリーなんてのがあったのう。しかし、当時は和物のプログレまではとても手が回らんかったわい。
わしはCCRの5枚目のアルバムのタイトルをずっとコスモス・ファクトリーと思っておったよ。実際は一字違いのコスモズ・ファクトリー(コスモの製作所という感じか?)だったのじゃが。

コスモス・ファクトリーのアルバム
助手:喜多郎氏はその後ソロ・デビューしNHKの番組シルク・ロードのサントラを担当し日本では一躍有名になりましたね。80年中頃にアメリカに進出して、1987年のTHE KIGHT OF THE SPIRITからのシングルTHE FIELDがグラミー賞にノミネートされて以来、2014年までに出したアルバム計16作が連続してノミネートされているのは凄いですね。
博士:1993年にオリーバー・ストーン監督の“天と地”という映画のサントラも担当し翌年ゴールデン・グローブ賞を受賞しておる。部門がヒーリング・ミュージックと少し地味なため、アメリカでは結構人気があるのに、日本では大々的な報道はされていないのが残念じゃ。

HEAVEN & EARTH (天と地)サントラ盤
助手: ライブでは、和太鼓を使ったりエレキやシンセの重厚なソロパートもあるのでヒーリング・ミュージックとは言え結構迫力がありますね。
博士:今回は、2000年に発表され、2001年のグラミー賞を見事獲得した、THINKING OF YOU でも聴いてもらえればと思うのじゃが。LIVE IN U.S.A.もお勧めじゃ。

LIVE IN U.S.A.
シンセにより笛もしくは口笛に近い音色で懐かしの日本や南米アンデスを思い起こす素朴な主旋律をなぞっていったり、また得意の宇宙をイメージしたサウンドがこのアルバムには盛り込まれている。
静かな部屋で、音を少し絞って聴くとヒーリング効果覿面じゃ。
助手:ところで、この“き、き、”シリーズいつまで続くのですかね?
ちょっと飽きてきた感じが…
博士:そうかのう? 自分では面白いと思ったのじゃが? 秋が来たから飽きたということじゃろうか?
つまらないダジャレや語呂合わせは無視して、タイトル曲のTHINKING OF YOU聴いてみてください。心が洗われます。
Kitaro - Thinking of you
最近は、ボックス・セットでの旧譜の再発の花盛り。5枚組のペラ紙ジャケ・ボックスという 形で出されている廉価盤もあるのだが、スーパー・デラックスという、最上級の仕様で構成されてた再発盤なども近年よく見受けられる。
主なところでは、ポール・マッカートニーやレッド・ツェペリンの一連のリマスター・シリーズ、ディランのブートレグ・シリーズ、2期ディープ・パープルの40周年記念盤、ストーンズのスティッキー・フィンガーそれにビートルズの映像のボックスなどなど、数えたら本当に多くのアーティストがその手の高額商品を出している。
価格的には、国内盤では最低1万円から3万円程度となり、全ての主なアーティストを対象として音源を集めているコレクターであれば、かなりの出費となるであろう。
と言うわけで、スーパー・デラックス盤を構成している音源に特に新鮮味を感じなければ、一般のファンは通常盤の購入で落ち着いている。
先日大枚を叩いてクイーンのボックスを買ってしまった。何で、通販サイトの購入のクリックを押してしまったのだろうか? 個人的に考えられるのは、広告の写真にあったカラー・レコードに目が奪われたのだと思う。バラ売りのレコードは全て黒盤で、ボックス・セットの盤は非常にカラフルで、どうしても欲しいと言う欲求が湧き出てそれを止められなかったのだろう。しかしながら、カラー・レコードやピクチャー・レコードなるものは、盤上の傷の有無を発見しにくく、そのレコードで収録曲を 繰り返して何度も聴くという代物ではなく、やっぱり観賞用であろう。
もし、ショップにいって財布の中の現金から支払うこととなると、そのあたりの考えも浮かんできて多分購入することを躊躇するのではないかと思う。常時、腹巻の中に数百万の現金を入れて出歩るけるくらいの資金力があれば、また別の話となるのではあるが。
例外もあるが、ビートルズのレコードのみが、中古品であれ今だにそこそこの価格でオークションや中古レコード店で取引され、コンディションの良い初回盤や特殊な限定盤などは、数万円から時に数十万円の価格がつく。
果たして、現在続々と発売されているスーパー・デラックスなる限定の商品に将来付加価値は付くのであろうか? たとえ付いたとしても、40-50年の間コンディションの良い状態で保管し、当時発売されたほとんどの商品が廃棄などされマーケットにあまり出てこない状況でない限り難しいのでは? 但し40-50年後の話となると、私自身は、この世に存在していないだろうから、考えてもあまり意味のないことではある。
と言うわけで、趣味の世界とは言え、一般人では購入に使える資金も限度があるので、やはり音楽を聴くということに主体を置いて購入の決断するべきではないか思っていたところ、なんとディランがまたもや最新のブートレグ・シリーズを出すというようなニュースが飛び込んできた。
なんと今回は、1965-66年のアウト・テーク、すなわちBRINGING IT ALL BACK HOME、HIGHWAY 61 REVISITEDとBLOND ON BLONDなどのアルバムを出したロック・サウンドへの移行期の頃のもので構成されている。
今回の最上級の仕様の商品は、ウルトラと名付けられたCD18枚とシングル・レコード9枚にハードカバーの本がつく豪華なもので、CD6枚のデラックス・エディションと通常の2枚組さらに3枚組のレコード・バージョンもあるとのこと。
人気絶頂期にお金を貯めこんだ著名なミュージシャンは、過去の作品を必要以上に再発しなくとも、悠々自適の生活を送れるのだろうが、版権を持っているレコード会社は、そうはいかない。CDが売れない今の時代、会社存続のためあの手この手で再発を続けていくことになるのであろう。生活がかかっているので、仕方のないことではあるが。
博士:このタイミングでこれを出してくるとは… CD18枚組は論外じゃが、予算的にも6枚組でも難しいのう。
助手:博士! 今回の場合、我々としては2枚組の通常盤で十分と思います。“デラックス・エディションのCD3には、ライク・ア・ローリング・ストーンの現存する音源を術と収録され(約20曲分) 制作過程が明らかにされる”などと関連サイトに記載されていました。
博士:何!ディスク全てが ライク・ア・ローリング・ストーンになっておるのか? これほどの数を連続して聴けば、ライク・ア・ローリング・ストーンではなく、本当にア・ローリング・ストーンなっちゃうかも知れんのう。
昨日“恐るべし通販のクリック…”なんて書きましたが、インターネットの発達とともに、通販も爆発的な成長を遂げましたね。以前主流だった電話での注文による通販では、やり取りの記録が手元に残らないので、注文がちゃんと通っているかどうか、若干不安になりますからね。
自身の周りを見ても、CDやレコード、文房具、書籍、工具やオーディオ機器など通販を利用しているって言うか、最近では、近所のショップで在庫のないものや試着しないとわからないような衣類や靴などを除けば、ほとんどのものを通販で購入しています。
近所にあったCDショップがつい最近まで孤軍奮闘っていうか結構頑張っていたようですが、いつの間にかなくなってしまったし、大型のCDの実店舗となると、電車を乗り継いでたどり着くのに約一時間弱かかりますからね。
オーディオ機器なんかも、専門店で機能などを調べて、買うのは通販となっています。重量のあるアンプなんかが玄関口で受け取れるのは便利ですね。
以前、大手の電化製品の量販店で、通販の価格と同じにしてくれれば購入すると交渉した事があるのですが、競争相手の実店舗が出している価格であればなんとか検討はするが、通販の価格に合わせるのは無理と言われた事から、通販での購入が始まりました。
もちろん、通販では実店舗がない形態をとっているショップが多いため、価格が安くともクレームが起きた時の対応が悪いなどのリスクもあります。例えば送金したのに在庫がなく、ほったらかしにされる場合も結構あるようので、口コミなどで評判の良い業者を調べておくのは必須です。
まあ便利ではあるけど、購入の決定がマウスのワン・クリックでいとも簡単に行われるのは、少し問題があるような。
決済が現金であれば、当然財布に現金がなければ、購入できないと言うブレーキがかかるのですが、クレジット・カード決済となると、手持ちがなくとも銀行口座自動引き落としとなり、支払いの感覚がなくブレーキがかからないのが実情です。
決済のクリックを行う手前に、ワン・クッションとしてキャンセル・クリックなる画面をサイト上に設定し、そこでキャンセルしないと決定すれば初めて決済のクリックの画面にたどり着くなどの策を講じてもらえれば、購入の決断をもう少し冷静に判断出来るのでは?
そうなれば、“やっちまった~”と言う後悔から“悲しみのふりかけご飯おかず無し”に至ると言う残念な状況を避けられるかもしれない。
というわけで、今日はこちらも”恐るべしファースト・アルバム…”、クイーンの“戦慄の女王”を“やっちまった~”のボックス・セットから。
全英/全米チャートが24位/83位とクイーンとしては低空飛行で、さらに当時英国の音楽評論家から“BUCKET OF URINE(しょんべん桶)”と酷評されたにもかかわらず、両国でゴールド・ティスクの認定を受けそこそこの人気を獲得。めまぐるしく変わる曲調や美しいメロディーなど最初から最後まで一気に聴かせます。
米盤、 ハリウッドレーベル
当時、日本ではアメリカのワーナー系(エレクトラ・レーベル)から販売さたピンクのジャケット
ボックス・セットは英盤のジャケットで、EMIから販売され紫色
通販のサイトでクリックの連発するのではなく当ブログにアクセスするクリックを連発していただけば、励みとなり自身の“やっちまった~”感も多少薄まるのではないかと勝手なことを…(汗)
Queen - Liar



















