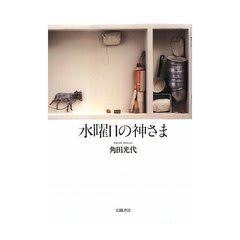いくつかの短編とエッセイによって構成された一冊。
本当に、この人は巧い小説を書くものだ、と改めて思い知らされた。まったくもって短編というにも短い、掌編の中に胸中を焦がす、というか、心の隙間をいじらしくさせられる話がいくつも連ねてあった。
そして旅を中心にしたエッセイ。旅行記とはまた違う、作者の内面を何気なくこぼしたような旅エッセイはなんだか凄い作家さんが近しくなったような感じがして微笑ましかった。なにより、最後の自著『悪人』についての章などは非常に興味深くあった。
だが、前半部にあまりにも良質な章編集があったがために、後半部のエッセイではいささか本音が出すぎているのか(いやまあ、そりゃエッセイなんだから本音を書くのだろうけど)一冊の本としてはまとまりが悪いような気もしたことは否めない。
しばしばこの作家は「お洒落作家」の代名詞として取り沙汰されたりもするが、特に鼻持ちならない言葉や表現を遣ったりするわけではない。それでいて「なんだか洒落ている」と匂わせるのは、やっぱり作者本人が洒落ているからだろうか? とも思っていたが、エッセイを読むかぎりではそうでもなさそうだ。ただ、生きること、書くことに対して自分なりの余裕を持っている人なのだろうな、そういところから滲み出るものがあるのだろうな、そんなことを感じられたエッセイはよかった。
それなので、好い意味で「ヘタクソなエッセイ」は身近に感じられるのである。
もちろん、小説は一級品であることに間違いはない。
さしでがましくもあるが、次作はエッセイはエッセイ、小説は小説、の一冊で出したほうが良いと思われる。
本当に、この人は巧い小説を書くものだ、と改めて思い知らされた。まったくもって短編というにも短い、掌編の中に胸中を焦がす、というか、心の隙間をいじらしくさせられる話がいくつも連ねてあった。
そして旅を中心にしたエッセイ。旅行記とはまた違う、作者の内面を何気なくこぼしたような旅エッセイはなんだか凄い作家さんが近しくなったような感じがして微笑ましかった。なにより、最後の自著『悪人』についての章などは非常に興味深くあった。
だが、前半部にあまりにも良質な章編集があったがために、後半部のエッセイではいささか本音が出すぎているのか(いやまあ、そりゃエッセイなんだから本音を書くのだろうけど)一冊の本としてはまとまりが悪いような気もしたことは否めない。
しばしばこの作家は「お洒落作家」の代名詞として取り沙汰されたりもするが、特に鼻持ちならない言葉や表現を遣ったりするわけではない。それでいて「なんだか洒落ている」と匂わせるのは、やっぱり作者本人が洒落ているからだろうか? とも思っていたが、エッセイを読むかぎりではそうでもなさそうだ。ただ、生きること、書くことに対して自分なりの余裕を持っている人なのだろうな、そういところから滲み出るものがあるのだろうな、そんなことを感じられたエッセイはよかった。
それなので、好い意味で「ヘタクソなエッセイ」は身近に感じられるのである。
もちろん、小説は一級品であることに間違いはない。
さしでがましくもあるが、次作はエッセイはエッセイ、小説は小説、の一冊で出したほうが良いと思われる。