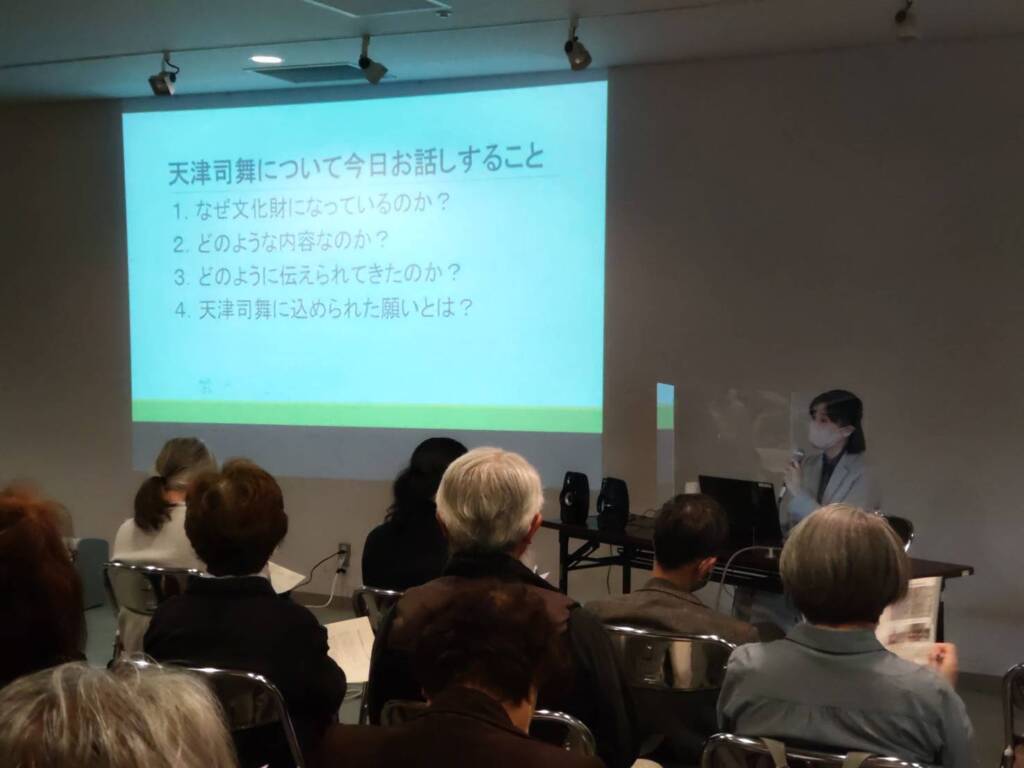ずっとお天気が崩れる予報でしたが、本日はおかげさまで昼までは天気も回復し、
時折日差しもありましたが、午後からは一転して雨空に。
気温の上昇とともに桜の開花も一段と進み、午前中は各所で春の景色を
カメラで撮影されている姿が見られました。
甲府盆地内の桜も7〜9分咲きで、もう満開を待つばかり。
武田神社周辺は土日に満開になると思われますが、あいにくの天気予報です。

そして、盆地東部の果樹地帯では、桃の花も徐々に咲き始めていまして、
毎年恒例の桜と桃の花で染まる甲府盆地のピンクの絨毯は、
来週から4月最初の土日が見頃かと。


春の甲府盆地は桜と桃で2度花見が楽しめます。
春休みとなり、お子様を連れたご家族の姿もちらほらと見受けられ、
「楽しかった」と、お子さんからお声がけいただき、展示のことについて話し合いながら
お帰りになるご家族の姿を見送り、気軽に歴史を学ぶ場を運営する側としては、
最高の褒め言葉をいただいた気分でした。
「楽しかった」の意味は、きっと知らなかったことや新しいことがわかった、という
発見の楽しさだったのだと思います。
展示内容は、これからも期待に応えられるよう精進してまいります。
そして、運営が官から民へと移行するまで残すところあと2日。
いよいよ最後の土日を迎えます。
平成31年3月20日の週まで諸々工事が残り、4月5日の開館に向けて準備期間も
10日あったか、なかったか、のようなドタバタした状態で開館を迎えました。
甲府市でも歴史資料館のような施設は初の運営だったこともあり、
準備不足で至らない点が多く、ご不便やご迷惑をおかけしたと思います。
アンケートなども行い、指摘事項を改善しつつ、展示なども可能なかぎり充実を図り、
さあ、これからという令和2年になって新型コロナウイルス感染症による
世界的なパンデミックの影響で、信玄ミュージアムもその年度の3月は臨時休館に。
それから今まで試行錯誤を繰り返し、新型コロナ感染症と付き合いながら
ここまで運営してまいりました。
今年度は臨時休館のない通年開館の予定でしたが、最後に運営引き継ぎのため
5日間臨時休館いたします。
とうとう通年開館を経験しないまま、民営へ移行となったことは残念ですが、
行政ではやりたくてもできないことがたくさんありますので、
今後に期待したいところです。
開館から4年となりますが、様々な出来事や出会いもありました。
今週末までで運営が切り替わることもあり、これまでお付き合いいただいた方々からは
労いや惜別のお言葉を頂戴し、また、ご多忙の折、東北や関西から時間を作って
はるばる訪ねて来ていただいた方もいました。
再会したところでゆっくりお話もしたいところでしたが、春休みも始まり、
コロナ対策緩和で迎える行楽シーズンとあって来館者も多く、
慌ただしい対応で本当に心苦しく、大変申し訳なかったのですが、
遠方から訪ねて来ていただいただけでも嬉しく、心よりお礼と感謝を申し上げます。
本当にありがとうございました。
運営は変わりますが、引き続き信玄ミュージアムを応援してくださいますよう
お願い申し上げます。