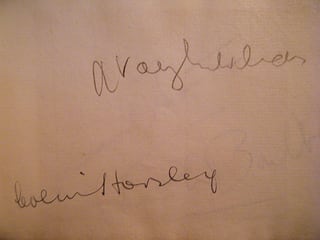<ラヴェル晩年の傑作。ダフニスの頃を思わせるリリカルな旋律と明快な新古典的楽想を持ち、同時期の「左手」よりも親しみやすく、万人を受け容れる喜遊性に満ちている。これですら(曲想のあけすけな明るさに対する好き嫌いを別とすれば)気に入らないのならラヴェルにそもそも縁が無いのかもしれない。どちらかといえば不作といわれる20年代、その終わりとともに「ラヴェルが戻ってきた」と感じさせる作である・・・これが「左手」と共に最後の大輪となってしまうのだが。諸所の技巧的な問題点など指摘されようが(ニコルス著渋谷訳「ラヴェル」泰流社刊参照)、一般的な聴衆にとってどうでもよいことで、特に2楽章アダージオ・アッサイの淡々とした、諦めにも似た感傷は、繊細な表現の巧い演奏家・・・フランソワなど・・・の演奏で聞くと、いてもたってもいられなくなる。本当に堪らないものがある。軽く透明で、情緒など微塵も混じえぬ演奏ほど、深く染み込むようにずっしりと、魂を揺さぶってくる。一方 終楽章の律動的で余りにあっさりきっぱりとしたすっきりプレストは(あきらかなリズム構成は「ゴジラ」に剽窃されたといわれる名リズム)、高雅なフランセというような雰囲気で、それゆえいくぶん皮肉めいてはいるけれども、ジャズなどの軽音楽的要素を巧みに織り込みながら(1楽章のブルースもそうだが)、ひたすらの運動性をもって終幕を盛り上げる。引き締まった筋肉質な音楽、しかしプロコフィエフほど肉感的ではなく寧ろ武道格闘家のような「一見優男的」音楽。壮絶な闘いも高度に洗練されると美的色感を帯びて来るように、ここにはめまぐるしい極度の技巧を乗り越えた上にたとえようも無く美しい夢幻が広がっている。全編明るく眩い光に満ちているがゆえ・・・このあと作曲家が歩んだ壮絶な死への道のりが、余りに切なく、哀れに思われてならない。「左手」を作曲家晩年の傑作とする向きも多いようだが、ラヴェルらしい「複雑だが煩雑ではない」明快な美を求めるなら、くぐもった同曲よりもこのト長調を選ぶべきだろう。>
ロン(P)
伝ラヴェル指揮パリ交響楽団(実際はフレイタス・ブランコ指揮作曲家監修)(EMI/PEARL他)/
◎ツイピーヌ指揮パリ音楽院管弦楽団(EMI)
先ずは献呈者にして大姉御ロン女史の演奏を挙げざるをえまい。今は新旧共にCDで聞ける。前者は貴重な同時代の演奏記録としてのみ価値を得る、じつに雑音に満ちた演奏(とくにバックオケの音の分離が悪すぎる)ゆえ、あくまで参考としておく。ただ脂の乗りきったロン女史の指の冴えが光っている。(ちなみに現在この演奏は、ラヴェル立ち会いのもとに当時フランスなどで活躍していたポルトガル人フレイタス・ブランコが振ったものとされている。EMIでCD復刻されるさいに正式に発表された)
最晩年の演奏とはいえ、後者にもまだまだ往年の壮絶な技巧の衰えない様が伺える。ロンはヴィニェスやメイエルを思わせる押せ押せ前のめりのスタイルを持った技巧派演奏家だったようだが(ミケランジェリの無機的スタイルともまた違う、熱い(南国風?)スタイル)、ここでは幾分穏やかなテンポ設定で細かい解釈表現を織り交ぜた堂に入った演奏となっている。耳ざとい向きはいろいろと綻びを聞き出すであろうが、まあ聞いてみて欲しい。録音は・・・ちょっと大目に見てください。
(3楽章のみ)
◎コンドラシン指揮モスクワ・フィル(モスクワ音楽院大ホール百周年記念盤)1955/4/12live
ラヴェルに対して姉御的存在だったのがロン。古いブランコ盤でのロンは雑音の多い中でも際立って巧い。逆にロンが最晩年に収録した盤はややオケに難がある。ところでここではコンドラシンの力量をまずもって明らかにする。コンドラシンの素晴らしいコントロールとモスクワ・フィルの巧さをもって非常に耳心地が良い音楽となっている。終楽章だけというのがいかにも残念。ロンはさすがにちょっと老いた感もあるが、聞ける。
ペルルミュテール(P)
ホーレンシュタイン指揮コンセール・コロンヌ (ACCORD,VOX他)1962
ホーレンシュタインの指揮が余りに硬くて野暮。コロンヌも反応が悪すぎる。とてもプロとはおもえないアンサンブル・・・作曲家の一番弟子といってもいいであろうペルルミュテールの唯一の盤としては・・・余りに・・・(泣)ペルルミュテールの紡ぎ出す微妙なニュアンス表現のみを「頭の中で」選別して聴いてください。それは素晴らしいリリカルな世界です。ホーレンシュタインの武骨とは真逆!録音は余り良くない。最初ライヴ演奏かと思った。
ニコレ・アンリオ=シュヴァイツアー(P)
ミュンシュ指揮
パリ音楽院管弦楽団(london)1949/5/31
原盤起因のノイズはともかく、演奏はたどたどしいと言わざるを。指の回らないアンリオに合わせてオケを抑えるというやり方は管楽ソロのミスを誘発。ガーシュイン再構築みたいなこの曲、ミケランジェリ位じゃないと遊べない。音程がどうもズレている。ピアノの音程がズレるわけないので、原盤起因か。ラヴェルは音同士が衝突しかねないバランスの難しい重ね方をすることがある。こういうズレ方をすると単なる不協和音にきこえてしまう。
ORTF(ina配信)1966/12/4(11/22?)live
録音は良好なステレオ。聴衆反応も激しい。ただ、特に一楽章のオケがカッチリしておらず、ラヴェル特有の「細工」が瓦解しかかる場面がしばしば聴かれる。ライヴならこんなものかもしれないが同曲を得意としたコンビにしては毎度ながらアバウトな印象が残る。アンリオは強い調子であまり起伏やニュアンスを作らない。
○シカゴ交響楽団("0""0""0"classics:CD-R)1966LIVE
このソリストは戦時中はレジスタンスとしてミュンシュと行動を共にし(歿後に至るまで)非常に親密で、幾度と無くタッグを組んでこの曲をやっていたが、その中では割合と落ち着いたほうの演奏で、スピードもやや緩い。しかしそれ以前に録音が悪すぎ。高音がぜんぜん聞こえてこないのに、低音はガンガン響いてきて、ソリストが高音をまるで誤魔化して弾いているように聴こえるのが辛い。ただ、強く明瞭なタッチは十分楽しめ、細かいニュアンスを込めることへの拘りがよく聞こえて面白い。ああ、巧いな、と思うフレージングがいくつかある。それだからスピードが緩くても楽しめるのだ。パラパラ胡麻を撒くような芸風のロンがけっこう直感的にやっている「部分」を、意識して誇張しているようにも思える。音が悪いので、よーく聴いてみてください。シカゴ響はこころなしか振るわない。なんとなくちぐはぐな感触だけ残るのは録音のせいだけだろうか。差し引き○。
○(ペルルミュテール?)(P)ミュンシュ指揮シカゴ交響楽団(DA:CDーR)1966/7LIVE
ピッチ高っ!最初たどたどしくてメロメロ、ミュンシュは大きく伸び縮み、とどうしようかと困惑してしまうが、テンポは余り上げられないものの1楽章の最後にはかなり解釈を入れてきて、激しいタッチで意外なほど熱気をもって終わる。エッジが立った分離の激しいステレオ録音ゆえ、冒頭よりソリストをも含む弱音表現が聞き取り辛い。音質がニュアンスを捉えきれず2楽章はリリシズムの聞こえ具合にやや不満も残った。ロマンティック過ぎるかもしれない。その意味ではリアリテ溢れる表現主義者ミュンシュと見解の一致がありそうだ。この録音に○をつけたのは終楽章いきなりの攻撃性で、オケがついていかなかったり技術的に墓穴を掘ったようなところも出てくるものの、内容のないところが持ち味とも言えるこの曲の運動性の要求には応えている。起伏の付けすぎのような印象もなくもないが、音が割合無個性なので臭みはない。表記上ペルルミュテールになっているがラジオアナウンス内容と解釈から明らかに誤りである。従って既出盤("0""0""0"classics:CDーR)と同一の可能性極めて大。 (※感想は前記の2年以上後のものです)
ボストン交響楽団(RCA)1957/11/25・CD
旧録だがステレオ。これが妙に、と言っては何だか魅力のある演奏で、もちろんスタジオ録音だからミスは無いのだが時折瞬間立ち止まるような堅さは、ペルルミュテール/ホーレンシュタイン盤を彷彿とさせるのだ。音はもっと硬質で色が無く無理して強く打鍵しているような荒さがあり詩情を比べるのもおかしいのだけれど、それでもこの演奏は魅力がある。マルグリート・ロンからヴラド・ペルルミュテールに至る同曲演奏の一つの流れの上にいる。私の悪い耳から言えば「ハッキリしている」からわかりやすいのだろう。柔らかさがないのが同曲には向いているのだ。それでも二楽章~誰がやっても詩情漂うのだが~はこの人にしては、結構感傷的というか、よく起伏がつき印象深い。ミュンシュはぴたりとつけ、これもロンやペルルミュテールのバック同様何かを付加することはない(ホーレンシュタインはマイナスしている感もあるが)。この演奏は推せます。ニコレ・アンリオについては別記したが自分で検索する上で引っかかりやすくするのと、同じ人であることを強調し統一感を持たせるため、わざわざ結婚前後で名前表記を変えず、シュヴァイツァーまで記載しています。本ブログ(まとめブログ)ではこのようにわざと表記をいじったり、検索用に文中で名前表記を幾つも使ったり(モントゥー、モントゥのように)してます。
ボストン交響楽団(RCA)1958/3/24・CD
仕方ないといえばそうなのだがソリストとオケがどうしても細かい部分でかみ合っていない。この曲ではほとんどの人の演奏(録音)がそうなので仕方ないといえばそれまでなのだが、ソリストが思いっきりアグレッシブに出てきている1楽章では、オケがむしろ後ろ向きの縦ノリのテンポをとりバランスが微妙に危うい感じがする。それでもロンの晩年盤によく似たかんじもあり、この楽章は(ほとんどの録音が成功していない中)かなり成功しているとはいえるだろう。2楽章は音色に深みはないが表現がなかなかに情緒的で美しい。テンポどりが絶妙である。主知的な部分と主情的な部分のバランスをどう保って、結論としてどうテンポ設定をし、どう揺らすかが鍵となるが、ここはソリストがまずもって巧いといっていい。3楽章はやや遅い感じがする。ミュンシュにこのソリストとあれば猛烈なスピードが期待されるところ、ライヴ盤でもそうなのだが今ひとつ客観的なテンポ設定にきこえてしまう。スポーティな楽章である、猛烈なスピードのまま弾き切って素っ気無く切り落としておしまい、というところが今ひとつどっちつかずな感じもする。まあ、でも無理は言わないで○だけつけておこう。
○ボストン交響楽団(WHRA)1958/3/15live・CD
晩年なじみの組み合わせだがこの録音が新発掘なのかどうかわからない。印象としては適度に派手でなかなか楽しめるが技術的なことやライヴなりの瑕疵を気にする向きには、1楽章始めのほうのオケのばらけぐあいや生硬なテンポ設定に一部ソロミス、3楽章にはオケは素晴らしく一気呵成に攻めるもののソロミスがかなり目立つ、ということを言っておかねばならない。ロンの表現に沿ったような解釈だが、ちょっと若い。2楽章を頂点として織り交ざるイマジネイティブな情景が晩年ラヴェルには珍しく、どの演奏でもそれなりに印象深く感じられるものだが、ミュンシュの音彩が実に素晴らしい。むせ返るようでもある。ピアノソロも細かい粒をたてた美麗で繊細な、抑制された印象派ふうの表現が印象的。総じてライヴなりに、であり、音はこのてのものにしてはいいがモノラル。○。
パリ管弦楽団(ANGEL/EMI他)1968/9パリ・CD
ステレオだが古ぼけたノイズが載るけして良好ではないもの(私はLPからリマスターCDまで持っているが全般を見通しても70年代も近い頃の標準的なスタジオ録音の中で上位には置けない。LPではライヴかと思ったほど。原音からのノイズ除去勝負だろう)。相対的に言って抑制的な表現で、遅いインテンポで確かめるように進めていく。そのぶん演奏精度は高く、このオケの母体となる団体の(団員が大幅に入れ替わっているのでそれは無いとは言われているがなお)伝統であろう情緒的とでも言うのか、力強い表現とあいまって、ミュンシュのものとしては最も一般的に勧められる。だが壮年期の突進し暴れまくるミュンシュらしさの欠片もないので、そこはどうかというところ。ソリストはかつてない精度で演じているがどこかデリカシーがない、音色が一本調子だ。私にはこの「白鳥の歌」の一枚が、新生楽団の首席として指揮台に立ったミュンシュがしかし板につく表現まで至らなかった「その真価を発揮できないまま」急逝してしまった、生硬な記録として聴こえてしまうのだがどうだろうか。
このソリストも巧いです。ミュンシュ・ラストレコーディングでCD化もしている。アース・パレー盤の感じだが、総じて一枚上手におもう。(※前記の13年以上前の感想です)
○ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィル(NICKSON)1953/11/29LIVE
ソリストが面白い。ミスタッチもあるけど大まかには強靭なタッチでよく指が回り、聞きごたえの有る音になっている。さらにけっこう即興的に揺らしてくるからオケが慌てる。解釈に意外性があり、とても面白い。3楽章ではあまりの高速にオケがついていけずすっぽり落ちてしまったりずれてしまったり、とても人に勧められるような演奏ではないが、面白さを買って○つけときます。
冒頭から異常な迫力で突き進むソリストにオケが完全にズレるという事態。管楽器ミスだらけ。味も何もなく両端楽章のスピードはライブならではの感興を呼んでいる。
(結婚前のニコレ・アンリオでもわかりやすさを優先してここでは「シュヴァイツァー」の名字をつけています) (※前記の12年以上後の感想です)
ミケランジェリ(P)
グラチス指揮フィルハーモニア管弦楽団(EMI)1957/3/
○サンゾーノ指揮トリノ放送交響楽団(ARKADIA)1952/2/1ライヴ
ミケランジェリも晩年のラヴェルに賛美されたピアニストで、カサドシュのタイプ。異常な指の魔術師だが大抵それこそ情(印象)の薄い透明な音色の鋼鉄演奏ぶり。ここでは少しルバートを駆使して演奏を盛り立てるが音色はいかんともしがたい。ライヴの方が熱気を感じるし、より集中力の高い演奏に思うが録音悪し。ピアノにマイクが近すぎる!良く知られたステレオ初期の正式録音は、割合とロマンティックな解釈が光る。細かいニュアンス解釈の妙があるが厚ぼったいオケ・・・また補記します。
マルケヴィッチ指揮聖チチェリア音楽院管弦楽団(tahra,ina)1952/5/28シャンゼリゼ劇場live・CD
粒だったリズム良い演奏ぶりが魅力。表現のくまどりがはっきりしていて少々エキセントリックと感じる向きもあるかもしれないが。あ、オケがです。ソリストもこの演奏家にしてはいつになくダイナミズムが感じられヨイ。オケの乱れなど何処吹く風、素晴らしくドライヴ感溢れる演奏ぶりで楽しめる。ところで技術的な問題が特に速い3楽章に多く見受けられる。豪快に崩壊しているのが痛い。あ、オケがです。それら以前の問題として録音がリマスタリングのせいかややぼけてしまっており高音が聞き取りづらい箇所が有る。ソリストが俊敏で冴えまくっているだけにもったいない。総じては無印だ。
収録音量が小さすぎなのはともかく、オケがついてってない。事故多発。ミケランジェリは醒めた音だがニュアンスには富んでいてテクニックも完璧。速いパセージでオケを置いてきぼりにするのはオケが悪い指揮者が悪い。(※前記の12年以上後の感想です)
○ルンプフ指揮NHK交響楽団(KING/NHK)1965/4/3東京文化会館live・CD
N響は何度もこのてのライブ音源をシリーズないしボックス化しているが今回は二度めのLPボックスに含まれていたものを含むシリーズ、その中の一枚。全盛期のミケランジェリというだけで大いに期待されるものだが技術的に難のあるドイツ寄りのオケであった楽団との取り合わせの妙も。一楽章は遅い。まるでオケにあわせるように、確かめるようなテンポの上でこの曲に秘められたラベルの独創的な書法を明らかにえぐって見せていく。こんなテンポでは指がもたつきかねないがミケランジェリの技術は確かだ。ラベルが称賛したピアニズムはラベル好みの即物性が際立ち、この曲でもともすると感情のない機械のようなスピードオンリーの演奏をしたりもしているが、腹を開いて音構造を示しながら弾き進めるさまが意外に楽しかった。二楽章はホルンソロに大ミスで台なし。昔なら正規音盤化しなかったかも。三楽章はスピードが戻り鮮やかなミケランジェリの指の踊りを楽しむのみ。オケもまあまあ。○。
チェリビダッケ指揮
○ミュンヒェン・フィル("0""0""0"classics:CD-R)1992/5live
この組み合わせは映像もある。チェリの透明な造形はラヴェルの音楽とよくあっており、意外にも速さを維持して流麗なところをみせている。ミケランジェリも気持ち良く演奏しているようだが、腕の衰えがみられるところがある。あれほどバリバリストイックに弾いていく人が、けっこうゆっくりとしたテンポに落として弾いてしまったりしている。この組み合わせは非常によいが、過去の記録に比べるとどうなのだろう。録音のよさで○ひとつつけておく。
◎ロンドン交響楽団(VIP:CD-R)?1LIVE
ミケランジェリの詩情溢れる表現が冴え渡る2楽章が絶品。速い楽章もテクニックに微妙な解釈もからめてまったく臆することがない。チェリ/ロンドンは金管などにやや鈍い表現が聞かれるがおおむねそつなくこなしている。ロンドン響の機能性の高さ、とくに木管楽器の巧さに拍手。やはりチェリの安定した音楽作りはしっかりした聴感をあたえ、下手にロマンティックな奏者がやるとグズグズになるラヴェルの繊細なテクスチュアがしっかり組みあがって聞き易い。これを聞きながら私はロンの新盤を思い出していた。ロンも衰えた
とはいえそれを上回る指先の香気をもって聴くものを陶然とさせた。この一寸聞き解釈の特徴が聞こえ辛い演奏、何度も聴くうちに何か同時代の作曲家に対する共感ある仕草がごく細かいコンマ何秒の打鍵のズレに現われているようで、深みにはまっていくような感傷を受けた。ミケランジェリはもっとバリバリ弾く事もできたはずだが、それをしていないことこそが素晴らしい。幼い頃ラヴェルに賞賛されたというピアニスト、これは名演である。ブラヴォー拍手盛大。録音年月日不明。
◎ブランカール(P)アンセルメ指揮スイス・ロマンド管弦楽団(DECCA)
モノラル時代の名盤、遂にCD化。(これも名演)プロコフィエフの6番と並んで愛聴していただけに、ほんとうに嬉しい(半分悔しい)復刻だ。アンセルメの瑞々しい音感と明瞭なリズム処理に聴くものの気持ちも浮き立つ。すこぶる安定したテンポに乗る軽やかな足取りは、決して気まぐれに動かないだけに尚更、ブランカールの確かな手腕とともに(目立ったところは無いものの底はかとなく味の有るタッチのピアノ)、理想的な音風景を形作る。オケはけして巧くない(全般しっかりした音程感には欠ける(しかしギリギリセーフなところで踏みとどまってはいる)し、第一、アンセルメ後の状態を思い出してみて欲しい)。なのにこれだけ聞かせる演奏になると思うと、アンセルメの力量はやっぱり大した物だったのだと思う。アンセルメの揺れの少ない解釈はそれほど無機的なものでもなく(録音のせいか新しいステレオ盤はそう聞こえてしまうきらいがあるが)、何より音色(管弦楽の総体的音響)への隅々にいたる繊細な配慮が、周到な準備を経て、計算ずくのスコア(解釈)と絶妙なバランスを保って、それが完璧精妙にすぎるために、冷血に聞こえてしまうこともある。もっと単純に、テンポがゆっくりめで微細には揺れないこと、感情的な表現を抑え目にしていること(周到な準備や計算をホゴにしてしまうから当然そうなるわけだ)が今一つのめりこませない、好かないという向きも多いだろう。無論アンセルメも全てが全て良いとはいえないが、ダフニスをはじめラヴェルは相性ぴったり、 名演揃いだ。複雑にからみあった個々の楽器がそれぞれちゃんと適正な役割のもとに正確に組み合わされ、全く単一のアンサンブルの ”結晶”となって耳に届く。ソロピアノの走句とソロ管楽器の絡み合いなど傾聴してみるとよい。こんなにしっかりとした「アンサンブル」を行っている演奏は稀だろう。規範たる演奏ともいえる。ブランカールはやや単調だが美しく透明感の有る音をかなでているが、ソフトなタッチが2楽章では強みとなりその美質を遺憾無く発揮する。技巧的問題は皆無で指は晩年のロンよりもよく回る。
この組み合わせは「左手」も名演で、中間部の熱気溢れる雰囲気(ペットの強奏から!)はアンセルメが得意としたロシア音楽を思わせる。こういう曲では前述の「冷血ぶり」も影を潜める。両手に比べ、やや”濁った”曲想だから敢えてそうしたのだ、と思う。
○ウーセ(P)ケーゲル指揮ライプツィヒ放送交響楽団(WEITBLICK)1974/3/27,28・CD
冒頭ピッコロが異常に高いピッチで入ってくるのにびっくり。耳を疑ううちになんとなくつじつまがあってくるが、録音のせいかほんとにずれていたのか?まあライプツィヒ放響だからこんなこともあるだろう。ウーセが巧い。粒立ってコロコロ転げる音楽が素晴らしい。とにかく指がよく回る。この曲のライヴで殆どテンポを乱さない演奏というのを初めて聴いた気がする。冷徹なほど変化しない、水の流れるような演奏ぶりは、ケーゲルの冷徹な音とじつにマッチしている。何度でも聞ける演奏だ。ソリストもオケもまったく危なげないから安心して聞ける。2楽章にもう少し情緒が欲しかったが1、3楽章の俊敏さはそれを補って余りある。録音が茫洋としているのが少し残念。それと3楽章のとんでもない事故が(誰がミスしているかは聴いてのお楽しみ)。○。
○ホーランダー(P)ルドルフ指揮シンシナティ交響楽団(MELUSINE)1965live・LP
ソリストがバリ弾きで(ミスタッチもあるけど)凄まじいの一言。一方オケはカスカス。ぼろぼろ。もうまったく渡り合えていない。アマチュアのようだ。このソリストを聴くだけでも価値はあるが、終楽章などどうしたものか、という疲労感漂う高速演奏なのでした。○。
カッチェン(P)ケルテス指揮ロンドン交響楽団(DECCA)
特異な演奏だ。ケルテスはロマンティックな方法論に従い交響曲の如き重厚な構造物を創り出す。面白いが違和感あり。カッチェンは巧いがケルテスの硬く重厚な音の一部と化している。ロンドンもそれほどうまくないが、ケルテスの硬質で分厚い曲作りによるところが大きいだろう。曲に慣れたすれっからしか楽しむ類の盤。
○ワイセンベルク(P)小澤指揮パリ管弦楽団(SERAPHIM)CD
正直録音があまりよくないのだが、演奏は立派である。このソリストには機関銃のようなテクを見せ付けるイメージがあったのだが、この演奏では意外と感傷的。とくに2楽章は深く心を打つ表現で、私は自分の葬式にはこれを流して欲しいな、とさえ思った。1、3楽章もテクニック+αのきめ細やかな感情が盛り込まれており、凡百の演奏家を寄せ付けないものがある。ただ録音のせいかちょっと弱々しく感じるところもなきにしもあらず(決してテクニックが足りていないわけではないが)。それよりオケが不振だ。杓子定規で心が無い。一部木管の音程は悪いし、何か非常に落ち着いていて、敏捷に動くソリストに付いていかない(付いていけないわけではない)。響きも一様に鈍重だ。この高度なバトンテクを誇る指揮者にしてはいささか振るわない。ソリストだけに○をあげておく。
ツァーク(P)
○スヴェトラーノフ指揮ソヴィエト国立交響楽団(MELODIYA)1960'?
個性派指揮者の伴奏指揮というのは案外普通だったりするものだが、これも意外なくらいラヴェルだったりして、デフォルメを求めると拍子抜けする。ソリスト、オケ共にミスが聞かれたりするが、音楽そのものは悪くない。オケ、ソリスト共に音色が単調なのはちょっと痛いが、良い意味でも悪い意味でもスリリングなアンサンブルを聞かせる1楽章はそれなりに楽しめる。2楽章は真面目。最後の余韻GOOD。3楽章いきなりの快速にちょっと驚くが、なかなか健闘する。オケが持ち味を発揮できていない感もあるが、この曲では仕方ないか。総じて○。ライヴみたいな演奏精度は気にはなる。
コンドラシン指揮レニングラード交響楽団(放送(CD-R化?))1963/1/10(20?)live
もう最初から無茶苦茶。オケのソリストが落ちまくりでガタガタ、ツァークもミス連発で何の曲やってんだかわからないほどひどい一楽章。二楽章はツァークのぶっきらぼうさが曲のとつとつとした情景にあってきて、三楽章は機関銃のような演奏様式が(あいかわらずニュアンスは無いしテンポは暴走だしミスもあるが)曲とシンクロしてくる。しかしここでオケの弱さがまたも露呈。怖がって前に出ようとしない管楽ソリストとか、もうなんていうか。二軍オケですよ。ツァークのぶっきらぼうさはもう早く終わりたいと思ってるとしか思えない。無印。
○クロード・カサドシュ(P)デルヴォー指揮パリ音楽院管弦楽団(CND)LP
パキパキした演奏で内容は浅いがわかりやすく楽しめる(左手ともども)。オケもやりやすそうだ。このドライヴ感、疾走感は並ではない。細部のニュアンスはともかく力強く手慣れた巧いソリストで旋律の勘どころを全て押さえている。単純だけど単調にはならないのだ。録音もモノラル末期だけあってデルヴォの意志的で立体的な音作りをかなり精緻に捉らえている。また自然なのがこの指揮者の上手いところ。三楽章のブラスがやや不調だが音色にかんしても非常に感傷的で美しく直截なテンポの上にしっかりハマっているのがよい。また念押しするような引きずる感覚がなく自然に融和しているのも出色。変な解釈は無いのに娯楽性を構成する必要なだけの一音一音を若々しいスピード感を損なわずにクリアにしっかり聞かせていて心地よい。ラヴェルがこれでいいのか?いいんです。個人的にしっくりくる。さすがに二楽章は全く深みがなくただ弾いているだけの感は否めないが、少なくとも親父さんのスピードだけの無味乾燥な独特のスタイルとはかけ離れた(ロベール氏は両手は録音してないが)血の通った感じは強くあり、好意的に聞いてしまう。とにかく軽く聞き飛ばせる難しくない録音なので初心者向き。ソリスト指揮者オケの相性がいい、これだけは確かだ。◎に近い○!クロード氏巧いよ。
○サンカン(P)デルヴォー指揮バーデン・バーデン南西ドイツ放送管弦楽団(club france他)1964/10/3-6・CD
正統的なラヴェルの協奏曲の演奏と言えるだろう。デルヴォーらしい作為がちょっと見え隠れするところもあるけれども、そこがアクセントとなって巧くまとまっている。演奏的には十全といってよく、サンカン先生の解釈の絶妙な「寸止め」は、ロマンティックにならず無機質にもならず、つまりヴィトゲンシュタインにもならずミケランジェリにもならず巧い事バランスを保っている。音色が明るく単調だが楽器のせいかもしれない。そこを繊細なタッチとテンポ変化でカバーしている。特に単純であるがゆえに難しい2楽章の表現は、ギリギリ感傷を煽りながらもラヴェルの厳しい視線をつねに意識しているかのようにそこに溺れないで乗り切っている(デルヴォは溺れる傾向がある)。規範的だろう。ペルルミュテールやフェヴリエよりはロン婦人に近いか。なかなかだが、強い印象を残すわけではない。規範ということで○。
◎(※同一盤の数年後の感想)
こういう音色表現はラヴェル特有の表現で、テンポ操作や音量変化、アーティキュレーション付けといった部分では一切解釈的なものを排除するかわりに、タッチとニュアンスだけで音楽の起伏を作ってゆく。フランス派ならでは、逆に言うとセンスだけを問われるようなものでここまで完成された表現を会得するのは誰しも難しいかもしれない。ソリストもオケも理想的なラヴェルを表現しているが、それを説明するのが難しいという、微妙なところにあるので、◎をもって何が言いたいかを示しておく。ステレオの好録音。
◎ワイエンベルグ(P)ブール指揮シャンゼリゼ劇場管弦楽団(DUCRET THOMSON/EMI)
EMIのバジェット盤で出たが不良品だったためすぐに店頭回収になったワイエンベルグの演奏です(のち再発)。私のLPは非常に状態が悪い。けれどもこの曲における鮮やかな色彩性、感傷性、ブールが客観的な立場から厳しく音楽を律しているにもかかわらずそこから溢れ出る香気、熱気は並大抵のものではない。ミケランジェリのような即物スタイルの演奏を多く聴いてきたせいかとくにそう感じる。ワイエンベルグの音楽はテンポを決して崩さないながらもその音量音色によって非常に多彩な表情を見せ、いかにもラヴェルらしい詩情を掻き立てられるものがある。2楽章の感傷性はワイエンベルグのみならず木管を始めとするオケ側も共感を込めて、優しく、哀しく演奏している。ブールの現代音楽指揮者らしい正確さへの希求が、ここでは音楽そのものの秘めた感傷性と全く離反せずに共存し融和しあっている。弦の音色も懐かしい。この2楽章があまりにスバラシイので他の楽章の演奏ぶりを忘れてしまった。とにかくゴマを撒くようにぱらぱらと鍵盤を鳴らし無理も狂いもなくやってのけるスタイル(まあうるさい事を言えば全般にタッチが繊細なため全ての音を鳴らしきれていない場面もあるにはあるのだが、遅くても弾けてない演奏の多い・中、これだけ表現できれば十分でしょう)。テンポが若干遅いため醒めた客観性を感じるが、3楽章などオケとソロのスリリングなアンサンブルには手に汗握る。こんなに構造的にかかれた曲だったのか、と改めて認識させられるが、そんなことを考えているうちにあっというまにエンディング。これは名演だ。◎。
○バーンスタイン(P、指揮)
ロンドン・フィル(HISTORY他)1946/1/7・CD
まー、よく指が回ります。といっても指が回るだけではだめで、ニュアンスが大事。その点この演奏はやや単純なもののように思える。激しいタッチの両端楽章よりも寧ろ思い入れたっぷりに歌わせる2楽章が美しい。この楽章は人類が考えうるすべてのルバートを尽くしていると言ってもいい。この人ののちの指揮にも言えることだが、作曲家としての感覚が曲の潜在的な抒情味を引き出し尽くしている。そのあざとさを受け容れられるかどうかは聴く人の趣味によるだろう。その点では両端楽章は単純なスポーツ感覚を追求してい るから万人に受け容れられる素質があるかもしれない。とにかく指は回るので○。もっともよく聞くとゴマカシっぽいところもあるのだが。ヒストリーの復刻は残響付けすぎ。元の音がよくわからない。オケはやや鋭さが足りないがしっかり表現しきっている。
VPO(DG)LIVE・CD
酷い。管が酷い。バンスタの音色が酷い。3楽章でバンスタの指が回ら無ければ間違いなく無印の演奏である。冒頭のパッパカパカパカが既にド崩壊していて酷いが、とにかくブラスが全くラヴェル向きではなく機敏さが無い。バンスタもバンスタでこんなに無味乾燥した2楽章もないもんだ。この曲で2楽章をこんなにニュアンスもへったくれもなく演奏した記録を私は知らない。タッチも何も無い。音色を速さでカバーしたせいか終楽章最後ブラボーが飛ぶが、若い頃から比べて明らかに劣化したバンスタのピアノは特筆すべきだろう。その得意とした指揮解釈とは真逆。
フランソワ(P)
◎クリュイタンス指揮パリ音楽院管弦楽団(EMI)1959ステレオ
いわずと知れた名盤だが、1楽章など聞くと分かるとおり、バックオケは決して巧くはない。これはオケ(木管等ソロ楽器)にとってかなりの難曲だけれども、クリュイタンスは演奏の瑕疵をそのまま録音に残すような指揮者ではないと思うし、多分フランソワの調子を優先してオケの出来は二の次に考えられていたのではないか。フランソワの類希な即興的天才は、特に2楽章の味わい深い表現に結晶している。この人が一旦ノってしまったら、どんなに恣意的表現であってもそれらしく、必然性をもって迫って来るから不思議。ショパンを思わせるロマンティックな「ズラし」やルバートが、ラヴェルでここまで透明感を損なわずに表現できる演奏家というのは、史上この人を除いてはいまい。気まぐれな技巧を持つフランソワ、ここでは持てる力を全面的に発揮している。 3楽章など他の追随を許さぬ指の冴え、揺るがぬ繊細な音色感に脱毛。独特の解釈がめまぐるしい中にも随所に織り交ざり、あれ、あれと思ううちに、「ホー」と目を丸くするしかなくなる演奏だ。3楽章はオケも頑張っていて、フランソワと融合し、共に大きな世界を形作っている。
プリッチャード指揮ORTF(EMI他)1964/12/22live・DVD/BD
EMIから膨大な数の「名演奏家シリーズ」の一枚としてDVD化されていたが(フランソワ版は二枚)、EMIの権利が他へ流れた結果、わずか3,4枚のブルーレイにオマケ付きでまとめられた。そのピアニスト編の一部として現役。白黒モノラル、画質も良くないが、あんな高いところからよくまあ打鍵できるなあ、左手がカマキリ拳法状態で交差、といったフランソワ独特のスタイルを楽しむことができる。はっきり言って軋みっぱなしでフランソワは走ったり端折ったり、でも強靭に押し進めてきわめてハッキリしたラヴェルを打ち出してくる。なぜかイギリスの指揮者という映像だが指揮者の奮闘ぶりよりむしろ何か焦りすら感じずに平然とズレたりするオケが面白い。いや事故ばかり論ったらしょうがない、二楽章の即物ぶりはともかく音色は明快なフランスのそれ、フランソワが同曲を得意としていたのはわかるし、ライヴとしては十分な精度は保っていると思うし、マッチョラヴェルを好むなら観て損はない。
アース(P)パレー指揮ORTF(DG)
パレーとアースの一本調子スタイルが見事にマッチ。余りの押せ押せムードに、音の強さと反比例の内容的な軽さを感じてしまった。でも運動性という点では終楽章など面白く聞ける。
ルフェーヴル(P)
パレー指揮ORTF(SOLSTICE)
パレーはミュンシュのくぐもりを取り去って、どぎつさを薄めたような剛直系指揮者だ。ミュンシュと同じく作曲家存命のころからラヴェル演奏会を振っていたオーソリティであるが、そのスタイルは少なくとも「ニュアンス系」ではない。この演奏はORTFの木管(クラなど)の音が「ボー」というかんじでかなり違和感を覚える。感傷性を排したオルガン的発声、これもTPOで使い分けるべきであるが、フルートの音色が余りに美しい(デュフレーヌ?)だけに一層耳につく。アンゲルブレシュトなら超絶な舵取りで聞かせてしまうかもしれないが、パレーの豪速球はいたずらに耳に奇異感を残すのみだった。悪いところばかり書いているようだが、ルフェーヴルの演奏はリリカルなもので、若干テンポが穏か過ぎるきらいもあるが、2楽章など結構聞ける。アース盤とは対照的だ。
○オーベルソン指揮ベロミュンスター放送管弦楽団(coup d'archet、DRS2放送)1959/8/24・CD
ルフェーヴルが光りまくっている。とにかく打鍵が強く、しかし女性的な柔らかい表現で聴く者を魅了する。しょうじき巧い。ロンに似ているかもしれない。2楽章は少し音がはっきりしすぎているかもしれないが、そういう解釈としては楽しめる。オケにはたどたどしいところもあるがおおむねしっかりと表現している。2楽章の詠嘆までしっかり聞こえるのはうれしい。録音はやや茫洋としておりモノラルなのが弱みか。○。まあ、よくよく聴くとマイクがピアノに異様に近いだけで、ただただ強靭な、味の無い演奏に聴こえるような気もする。
○マガロフ(P)マルケヴィッチ指揮ベルリン・フィル(DA:CD-R)1974live
「この面子が揃ったにしては」僅かに瑕疵はあるものの、非常に充実感のある演奏。ラヴェルに充実感という言葉は似合わないがロン最盛期はこうだっただろうなあというマガロフの腕、パラパラそつなくも繊細明瞭で高精度なピアニズム(ラヴェル自身に好まれたピアニストはみなこんなかんじ)、録音もよくマルケも前進的なテンポと的確なリズムで(マルケのフランスものの中欧オケライヴは素晴らしい、VPOとの「海」はARKADIAの不良盤以降耳にできていないがどこか出さないものか)緊密なアンサンブルを維持している。厳しく真面目だったとも言われる演奏家で際立った特徴は指摘しかねるが、ラヴェルのコンチェルトはいいものであればあるほど個性が見出せなくなるものでもある。そういう作曲家であったのだから。そういえばピアニストと指揮者は一応同郷か。エアチェックレベルの録音と個人的好みで○にとどめておく。
○園田高弘(P)ブール指揮バーデン・バーデン南西ドイツ放送交響楽団(EVICA,日本クラウン/SWR)1965/12/13・CD
入りからびっくりしたのだ、あ、ロンの音だ、と。フランスの至宝と呼ばれたマルグリット・ロン女史(ロン・ティボー・コンクールのロンね)の、明快だがどこかロマンティックな軟らかい色のある音。タッチが似ているのか。ライナーにもあるとおり園田氏はブールより、「直伝」と言われたロン女史の解釈(じっさいにはラヴェルは最盛期の女史に容易に口出しできなかったとも言われる)とは異なる、譜面にあるとおり「だけ」の演奏をするように強いられたという。しかし器楽演奏というものは指揮者や作曲家の考えるものとは違う部分がある。統制のきかない部分は確かに残る。これは「ドナウエッシンゲンのブール」の世界に園田氏が埋没させられてしまったのではない、素晴らしい技術的センスと鋭敏な反射的能力を駆使した園田氏が、ブールが思い描く「客観即物主義的な音楽観」を損なわず、かつ(無自覚のようだが)自らのほうに見事に融合させている。寧ろその性向的にブールでよかったという結果論も言える(晩年のロン女史のような「突っ走り」は無いが、フランソワのようにスピード感が失われることも決して無い)。
両端楽章においてはこの盤の表題になっている「若き日」とはいえ、浅あさしい技巧家ぶりは無い。2楽章は最も繊細な感覚が要求されるがここで古典的構成感とロマン派的旋律性の狭間に確固としたテンポで柔らかく奏される絶妙な音楽は、より直伝に近いと言われたスタイルを持っていた(しかしこの曲は時期的に直伝ではない)ペルルミュテールに似ているかもしれない。
ブールのラヴェルはロスバウトより色が無く、音は軽やかでも揺ぎ無い構造物となる。だが遅さや重さというのは感じない。巧緻な設計のなせるわざだろう。全く別種の指揮者とはいえ同じ指向も感じさせるケーゲルのムラある芸風とは違い、スコアを固持はするものの、ギリギリ「どちらにも振り切らない」ことにより晩年ラヴェルのロマンティシズムを失わず、あっさりもしすぎない魅力的な演奏を仕立てる。ライヴではこうもいかなかったかもしれないがブールのライヴに精度の低いものは知らない。少なくとも同じ即物的傾向の強い透明なラヴェルを得意としたベルティーニの無味乾燥とは違うものではある。うーん、これは知られざる名演だが、一般的ではない。何故だろうか。○。
○アルゲリッチ(P)ベルティーニ指揮ケルン放送交響楽団(CAPRICCIO)1985/12/7live・CD
まず新しいものでは滅多に入り込める演奏に出くわさない難曲だがアルゲリッチの表現力は素晴らしい。野暮ったいロシアスタイルでも鋼鉄機械の現代スタイルでもない、やはりフランス派の表現に近い非常に繊細でしかも変化に富んだ粋っぷりである。オケも若干響きが重いが録音がいい。滅多にこの人の演奏でハマる演奏がないのだが流石こだわりのあらわれた余人を寄せ付けないピアニズムでした。ライヴなりの荒さも録音かホールが吸収。○。