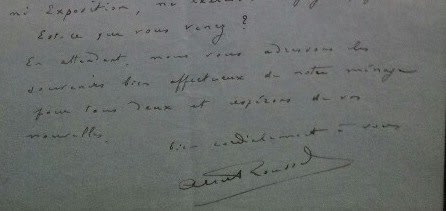<連作歌曲集と言うには余りに意味深い大曲。交響曲とするのが一般的だが、室内楽的に絡み合う薄い響きは8番までとは全く異質のもの。ベトゲの“超訳”により蘇った李白らの詩文が、マーラー流滅びゆく世界に巻き取られていくさまは圧巻。確実に完成された曲としては最後の作品で、最高傑作とする向きも。自身は終に振る事ができず、続く9番共々弟子にして友人ワルターに託された。全曲の半分を占める終曲「告別」に傾聴!“永遠に”、、、>

ワルター指揮
<言わずと知れた初演者による演奏。ロマンティックなマーラー。>
○ニューヨーク・フィル、エレーナ・ニコライ(Msp)スヴァンホルム(T)(NOTES他)1953ニューヨークlive・CD
これは何度かCDが出ていたと思うが、私の手元の盤はかなり質が悪く、レコード盤からモノラルで録音し直されたものと思われる。だがそのせいか狭い音場にハチキレンばかりの音楽がぐわっと飛び出してくるような迫力があり、寧ろ聴き易い(個人的には余りに聴き易いので◎にしたいくらいだ)。演奏は信じられないほど瑕疵の無いもので、歌手二人にしてもどこにもマイナス点が見付からない。しいて言えば中間楽章で間違えたらしき拍手がパラパラ入りかけているところくらいか。ワルターの解釈はまるでこの曲がワルターのために書かれたかのように板についており、この盤に限らないが、たぶん一回聞くと他が聞けなくなるくらい迫真性が有る。中間楽章の速いパッセージで歌手がテンポに追い付いていけず音程を崩したりするなどワルター盤であっても瑕疵のある録音はあるが、この演奏ではそういう危うさが全く無いから大した物である。「告別」にはもっと陰影があってもいい気がするがその幸福感はワルターの本質からくるものであり、諦念も至福に変えるワルターならではのものか。最後のエーヴィッヒまで、固唾を飲んで聴いてしまう演奏です。いい演奏。
◎ニューヨーク・フィル、フォレスター、ルイス(M&A)1960/4/16live・CD
ワルターの音楽は「呼吸」している。
吸っては吐き、吸っては吐く。時に深く、時に息せき切って、音楽は進む。これは恐らく初演者最良の「大地」のライヴ記録だ。オペラティックと評さるルイスの「酔えるもの」は心の深層に轟く諦めと宣告の歌だ。つづく歌もまた荒野をうつろう放浪者の気分に満ちている。
個人的にフォレスターの「告別」がとても気に入っている。抑制の効いたくぐもった声が、なぐさめの言葉となり語りかけてくる。幼き頃に聴いた遠い母の子守歌。時折管弦楽によって表現される抑えられない複雑な感情の渦。ハープとオーボエの響きは、遠い牧場の声となる。これはサウンドスケープだ。アイヴズの思い描いた世界に先行し、より高度に純化された俗謡の世界。想い出はやがて旋回し更に遠く溯っていく。暗い苦悩と幻想はいつしか記憶の奥底に沈殿した純粋な生への憧れを謡う。天上の聖母の声が、途切れ途切れのヴァイオリンと木管の僅かにたゆたう霧の中で、やがて春を迎え芽生える草ぐさを夢見て横たわる身体を包み込む。
大地に横たわる、わたしは死ぬのである。
惑いは低く不吉なフレーズによって復活する。痛む足を引き摺り、底の無い炭坑へ向かう骸骨の列に加わる悪夢に身が竦む。しかし・・・穴の底から最後に現れるのは美しく輝く「永遠」だ。永遠の生という「死」を、むかえ入れる準備は出来た。母なる大地の高らかに謡う永遠の歌は、ハープの調べにのって、風のように私を運び、あの高く澄んだ空の彼方へ連れ去ってゆく。遠く、見えなくなるまで。
秀作。マーラー畢生の作品、「告別」。
これが私の決定盤だ。
ニューヨーク・フィル、ミラー、ヘフリカ゛ー 1960/4/18,25・CD
○ウィーン・フィル、トルボルク(A)クルマン(T)(PEARL他)1936/5/24・CD
トルボルク(イ)の歌唱に尽きるだろう。特に終楽章「告別」の歌唱は絶唱と言ってよく、生臭さもドライさも無く、ただここには歌がある。私の盤が劣化してしまい最後が雑音まみれなのでなんとも後味が悪かったが、それでもそこに至る過程でのいい意味で安定し曲調に沿った真摯な歌唱ぶりが耳を傾けさせるに十分であった。録音が悪いためオケの美質はあまり際立ってこないが、後年のワルターとは違う覇気に満ちたところが聞かれる。颯爽としたというかとにかくドライで、この人が初演を託されたのか・・・と少し不思議な心持ちになるが、案外そういうスタイルがマーラーの想定していたものなのかもしれない。となるとこの曲はやっぱり連作歌曲集と考えるのが正しいのか?・・・などとごにょごにょ考えながらもいつのまにか聴きとおしてしまう演奏ではあります。正直ワルターの大地の中では余りお勧め度は高くないが、今出ている盤だともう少しましな音で聞けるかもしれないという希望込みで○をつけておく。
○ウィーン・フィル、フェリアー(Msp)パツァーク(T)(DECCA)1952/5・CD
○ウィーン・フィル、フェリアー(Msp)パツァーク(T)(TAHRA/harmonia mundi)1952/5/17live・CD
驚愕の盤である。私はこの存在すら知らなかった。全く同じメンツによるスタジオ録音(decca)はかねてより名盤で知られたものだが、これはほぼ同時期の実況録音である。録音状態は余り良いとはいえない(とくに前半楽章)。また、歌唱が大きすぎて管弦楽がやや小さく聞こえるのもマイナス要因だ。しかしここにはスタジオ録音のおすまし顔ではない、生の演奏家たちの呼吸が感じられる。パツァークの詠唱はやや開放的にすぎるように感じたが、フェリアーのとくに終楽章「告別」の詠唱は絶唱といってもいいくらいに素晴らしい。最後長調に転調したところのニュアンス表現の繊細さには脱帽。一方オケもライブならではのとちりやばらけ等もなく、スタジオ盤以上に緊張感をもって演奏している。表現がじつに板についていて、これほど情熱的であるにも関わらず、全く無理が無い。とにかく、「大地」好きなら聞いてみて損はあるまい。ちなみに高価なうえ不良品続発で悪名高いANDANTEの演奏はライヴではなくスタジオ録音の音源に拍手や雑音を挿入した偽演であるそうだ。(下記)
ウィーン・フィル、フェリアー(Msp)パツァーク(T)(ANDaNTE)1952/5/17live(?)・CD
これをここに切り出して書いたのは、某レコード店店員への抗議の意味がある。アンダンテで出たこの「大地の歌」は、最初デッカの有名なスタジオ録音に拍手を重ねただけの偽演という説が出て、物議をかもした。しかしそのレコード店員によると、アンダンテの版元に問い合わせた所、あくまで17日のライヴで初出だと言い張っていたらしい。しかし17日ライヴといえば既にターラから出ている(前記)。それと同じなのではないか、と店員に問うたところ、パツァークがミスっているところがあり、ターラ盤とはあきらかに違うという(ターラの日付誤りということなのか?)。寧ろデッカ録音に似ているので前述のような説が出たのだ、と。その店員を信じ、二度と買うもんかと思っていた高価なアンダンテの当盤を買ってしまったわけである。しかし、うちに帰って比較聴取してみたところ、はっきりいって、まったく同じなのである。音質がよくなっていればまだしも、ほとんど差がない。店員のいう事を信じて、ということでここでは別項にあげておくが、私の耳が正しければ、これはまったくの同じ演奏である。それにしてもレコード店員はレコード評論家のようにあてにならないものだ。同盤には復活と4番が併録されているが、どちらも(CBS、DG)既出のものである。初出と言い切れるのは、4番の録音と同時に録音された数曲の歌曲で、歌唱は4番と同じギューデンだ。これだけがせめてもの救いだった。でも、あー、腹が立つ・・・
後記:某雑誌で、この盤はデッカ盤に拍手等を挿入したものだと断言してあった。どちらでもあんまり変わらないからどっちでもいいのだが、このレーベル、信用ガタ落ち。ちなみにこの盤、一枚他のセットのCDが間違って入っていた。サイアク。
○ウィーン・フィル、フェリアー(Msp)パツァーク(T)(andromedia)1952/5/18(?)live・CD
この音源はandanteが偽者を出したあとtahraが正規に復刻したものを何度も焼きなおしていろんなマイナーレーベルが出していた、その一番最近の復刻で音がいいというフレコミだったが石丸の店員は「いやー・・・かわんないす」といっていた。それ以前にレーベル表記上の収録月日が一日ずれているため、資料として入手。ワルターは元々リアルな肌触りの生々しいマーラーをやるけど(作曲家じきじきの委託初演者とはいえ同時代者から見ても「ユダヤ的にすぎる」と言われていた)、透徹した「大地の歌」という楽曲ではとくに違和感を感じることも多い。このEU盤は最近の廉価リマスター盤の他聞に漏れず、輪郭のきつい骨ばったのリマスタリングで、もっとやわらかい音がほしいと思った。でもたぶん普通の人は聞きやすいと思うだろう。大地の歌に浸るには、やっぱ新しい録音にかぎるんですが。イマかなり厭世的な気分なので、ドイツ語による漢詩表現が薄幸の電話交換手キャサリン・フェリアーの万感籠もった声と、ウィーン流儀の弦楽器のアクの強いフレージングとあいまって奇怪な中宇の気分を盛り立てられる。穏やかな気分で消え入る死の世界なのに、この生命力は・・・とかおもってしまうけど、ワルターもけしてこのあと長くないんだよなあ。
~Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
○ウィーン・フィル、フェリアー(Msp)パツァーク(T)(VPR)1949/8/21ザルツブルグ音楽祭live・CD
モーツァルトの40番と一緒に演奏された抜粋、即ち歌曲として演奏されたもの。だから録音も声だけが生々しくオケはやや音が遠くて悪い。若々しく張りのあるパツァークの声が素晴らしいし、インタビューも収録されているフェリアも闊達な歌と喋りでのちの不幸な死を微塵も感じさせない。まるで電話交換手のように闊達に喋る。歌を味わうものとして特筆できる、両者雄弁さを発揮した録音で、交響曲としては肝心の両端楽章が抜けているのだから土台評価できない。歌好きなら。依然溌剌としたワルターのライヴ芸風が楽しめる側面もあるが、とにかく時代がらまあまあの音質できける自主制作盤として、マニアなら。確かに交響曲じゃないものとしてワルターの大地の歌が聴けるというのは面白くはある。やはりベツモノなのだ、と各曲に明確な性格付けがなされ統一性を持たせようとしていないところに感じることが出来る。 中間楽章でのパツァークの安定した、でも崩した歌唱にも傾聴。個人的にdecca録音にむしろ似てるきもするけど。
~Ⅴ抜粋、Ⅵ抜粋
○ウィーン・フィル、フェリアー(Ms)ピアース(T)(PEARL)1947/9/11放送live・CD
SPエアチェックの板起こしらしく、両楽章冒頭から四分前後で切れている。ワルターの、後年のバーンスタインを思わせる独特の伸縮するロマンチシズムがオケの身体的共感により音楽に昇華している様子がとくに顕著で、全曲聴きたかったが仕方ない。ピアースの晴朗な歌唱が印象的だが、このCD自体はフェリアの小品集。○。
※2004年以前の記事です(一部2006,2007,2011)