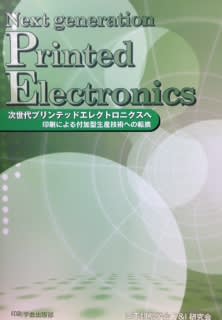「未来を破壊する」-厳しい印刷市場の進路を示す「新しい常識」-

・著者;ジョー・ウェブ博士/リチャード・ロマノ
・発行;㈲エー・エム・コンサルタント
・体裁;A5判/140ページ
米国で出版された書籍『Disrupting the Future』の日本語版(部分訳)。原著のなかで著者のウエブ博士(コンサルタント)とロマノ氏(著作者・記者)が記述した印刷市場の現状分析結果とそれに基づく提言が、現在の日本市場においても印刷会社が業態変革を実践するのに非常に有益だと考え、日本での刊行となった。
「われわれは、技術や革新を通じて未来を破壊することを学ばなければならない」で始まる本書は、前書きに続く①印刷産業の失われた年月、②宇宙の法則が変化した日、③変化するメディアミックス、④新しい印刷ビジネスをつくるために必要なブロック、⑤我々が言うように、やってみよう――の5章で構成され、最後に「大量破壊のための武器」というタイトルでまとめられている。姿勢を正してページをめくっていただかないといけない、読み応えのある重厚な、かつ刺激的な内容となっている。右から左へと読み流したままだと、本書から未来へ向かう進路を得ることはできないだろう。
ここでは「まとめ」のなかから要点を紹介し、印刷サービスのあり方、顧客支援の重要性、課題解決の方法を戦略的に思考する“コツ”を説く本書の趣旨をお伝えしたい。
「自社のマーケティングやコミュニケーションの目的のために、新しいメディアやソーシャルメディアをどのように使うことができるのかについて考え始めること。あなたの顧客について、印刷物以外のマーケティングやコミュニケーションの計画に対して、どのような支援が可能か考え始めること。現在の顧客から1社か2社を選び、彼らの印刷物をより大きなマルチチャンネルのキャンペーンに広げる方法について考えること。印刷以外のグラフィックコミュニケーションの専門家と、あなた自身の新しいメディアの取り組みをアウトソーシングするためのネットワークを開拓すること……」

・著者;ジョー・ウェブ博士/リチャード・ロマノ
・発行;㈲エー・エム・コンサルタント
・体裁;A5判/140ページ
米国で出版された書籍『Disrupting the Future』の日本語版(部分訳)。原著のなかで著者のウエブ博士(コンサルタント)とロマノ氏(著作者・記者)が記述した印刷市場の現状分析結果とそれに基づく提言が、現在の日本市場においても印刷会社が業態変革を実践するのに非常に有益だと考え、日本での刊行となった。
「われわれは、技術や革新を通じて未来を破壊することを学ばなければならない」で始まる本書は、前書きに続く①印刷産業の失われた年月、②宇宙の法則が変化した日、③変化するメディアミックス、④新しい印刷ビジネスをつくるために必要なブロック、⑤我々が言うように、やってみよう――の5章で構成され、最後に「大量破壊のための武器」というタイトルでまとめられている。姿勢を正してページをめくっていただかないといけない、読み応えのある重厚な、かつ刺激的な内容となっている。右から左へと読み流したままだと、本書から未来へ向かう進路を得ることはできないだろう。
ここでは「まとめ」のなかから要点を紹介し、印刷サービスのあり方、顧客支援の重要性、課題解決の方法を戦略的に思考する“コツ”を説く本書の趣旨をお伝えしたい。
「自社のマーケティングやコミュニケーションの目的のために、新しいメディアやソーシャルメディアをどのように使うことができるのかについて考え始めること。あなたの顧客について、印刷物以外のマーケティングやコミュニケーションの計画に対して、どのような支援が可能か考え始めること。現在の顧客から1社か2社を選び、彼らの印刷物をより大きなマルチチャンネルのキャンペーンに広げる方法について考えること。印刷以外のグラフィックコミュニケーションの専門家と、あなた自身の新しいメディアの取り組みをアウトソーシングするためのネットワークを開拓すること……」