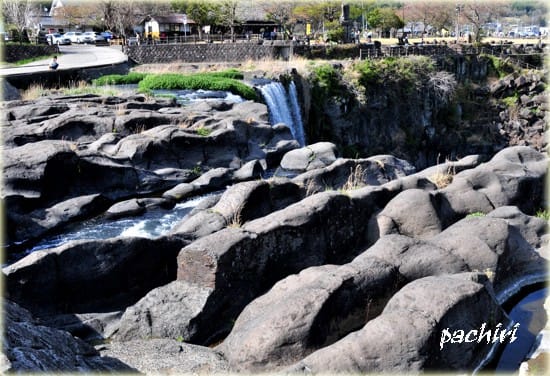|
毎年親類グループ(8名)で小旅行に行きます |

天草キリシタン館
本渡の高台にある殉教公園に所在していて「天草・島原の乱」を中心としたキリシタン史が
展示してあります。H22年7月にリニューアルされ、バリアフリーも随所に施されていました
ご覧のように駐車場からのエントランスはエスカレーターです

天草四朗像
何を指しているのでしょうか

入館すると正面に石像と”くまモン”がお出迎えです
作者と偶然会うことができました。本渡の写真家です
了承を頂いて掲載します

エキゾチックですね
夜は灯されるのでしょう。ここから本渡の町が一望できます

国指定重要文化財「祗園橋」
多脚式アーチ型石橋です。この付近は天草の乱の激戦地だったとのことで
毎年10月第四日曜に殉教祭が催されます

本渡歴史民俗資料館へ
天草の歴史と民族展示です

二階へ行くと。懐かしき裕ちゃんの映画ポスターが
天草秋季特別展 「天草ー映画の時代」の一枚です。この他沢山のポスターがありました
昭和30年代には天草には40を超える映画館があったそうです
その歴史と天草で撮影された映画の紹介は12月28日まで。入館無料です

映写機

寅さんの映画が上映されていました
一映画にフイルム数巻あり、途中で取り換えねばなりません
残念ながらチョイ見でした

1950年代の電気洗濯機。手回しで絞ります
”三種の神器”白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫の一つです
これで奥様業は大いに楽になりましたね

帰りに寄った維和島の展望所から
大矢野島から維和島へ架かる西大維橋が見えます

これは東大維橋
維和島に渡るにはこの二つの橋を渡りますが、道幅が狭いのが難点

「藍のあまくさ村」の天草四朗像
キリシタン館の像とはえらい違いです。健康優良児風
そのはず、ここは海産物のお土産店なのです
今夜のお酒の肴として、名物の竹輪を買いました
(C)2006-2012 Pachiri Allrights Reserved.