朝日新聞土曜版【特集】いいね!探訪記の12月25日
「東京国立博物館で結婚式の前撮りをするカップル」
という記事がありました。
そしてそのプレゼント,たった10人・・・
あたった!

プレゼント応募の時のアンケート
私が書いたのはこちら(Wordに保存していました。)
Q11. 今回の「いいね!探訪記」のご感想をお聞かせください
いつも拝見しています。
介護等で,家をあけにくい私が日本中いろんな所,(それもガイドブックには載っていないような)を見ることができます。
さて,東京国立博物館は,歴史好きの私には,行ってみたいところのベスト10に入る所です。
(関西の人間なので,京都国立や奈良国立は行ったことがありますが)
でも,博物館が「前撮りスポット」とは驚きです。
実は,昨年(今年だったかな?)と東京国立博物館監修の「洛中洛外図屏風 舟木本」をネット買いました。
普通に書籍として売っているので,とても小さいのですが,屏風として(?)部屋に飾っています。
新聞のプレゼントは申し込んだことがないのですが,今回はぜひ!と申し込みました。
尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」・・・缶入りクッキーお願いします。
そしてなんと,当選!
新聞社の担当の方が,印刷された「プレゼント当選のお知らせ」の下に,
「・・・今秋には,東博で150周年記念の国宝展があるので,
「洛中洛外図」も見られると思います。・・・」と書いてくださっていました。
うれしいですね。
きっと行くことは無理だろうけど,
プレゼントが当たったことも,このコメントも。
尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」も「洛中洛外図屏風 舟木本」も
本物ではないけれど,
小さいけれど,
大切に部屋に飾ります。
PS.
2022/1/15 13:48神戸新聞NEXT
【速報】兵庫県のコロナ感染者、過去最多の見通し
兵庫県で15日、新たに確認された新型コロナウイルスの感染者が、
昨年8月18日の1088人を上回り、過去最多となる見通しであることが関係者への取材で分かった。
大阪府 新型コロナ 感染確認3000人大幅超 過去最多の見通し
2022年1月15日 13時06分 (NHK NEWS WEB)
「東京国立博物館で結婚式の前撮りをするカップル」
という記事がありました。
そしてそのプレゼント,たった10人・・・
あたった!

プレゼント応募の時のアンケート
私が書いたのはこちら(Wordに保存していました。)
Q11. 今回の「いいね!探訪記」のご感想をお聞かせください
いつも拝見しています。
介護等で,家をあけにくい私が日本中いろんな所,(それもガイドブックには載っていないような)を見ることができます。
さて,東京国立博物館は,歴史好きの私には,行ってみたいところのベスト10に入る所です。
(関西の人間なので,京都国立や奈良国立は行ったことがありますが)
でも,博物館が「前撮りスポット」とは驚きです。
実は,昨年(今年だったかな?)と東京国立博物館監修の「洛中洛外図屏風 舟木本」をネット買いました。
普通に書籍として売っているので,とても小さいのですが,屏風として(?)部屋に飾っています。
新聞のプレゼントは申し込んだことがないのですが,今回はぜひ!と申し込みました。
尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」・・・缶入りクッキーお願いします。
そしてなんと,当選!
新聞社の担当の方が,印刷された「プレゼント当選のお知らせ」の下に,
「・・・今秋には,東博で150周年記念の国宝展があるので,
「洛中洛外図」も見られると思います。・・・」と書いてくださっていました。
うれしいですね。
きっと行くことは無理だろうけど,
プレゼントが当たったことも,このコメントも。
尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」も「洛中洛外図屏風 舟木本」も
本物ではないけれど,
小さいけれど,
大切に部屋に飾ります。
PS.
2022/1/15 13:48神戸新聞NEXT
【速報】兵庫県のコロナ感染者、過去最多の見通し
兵庫県で15日、新たに確認された新型コロナウイルスの感染者が、
昨年8月18日の1088人を上回り、過去最多となる見通しであることが関係者への取材で分かった。
大阪府 新型コロナ 感染確認3000人大幅超 過去最多の見通し
2022年1月15日 13時06分 (NHK NEWS WEB)










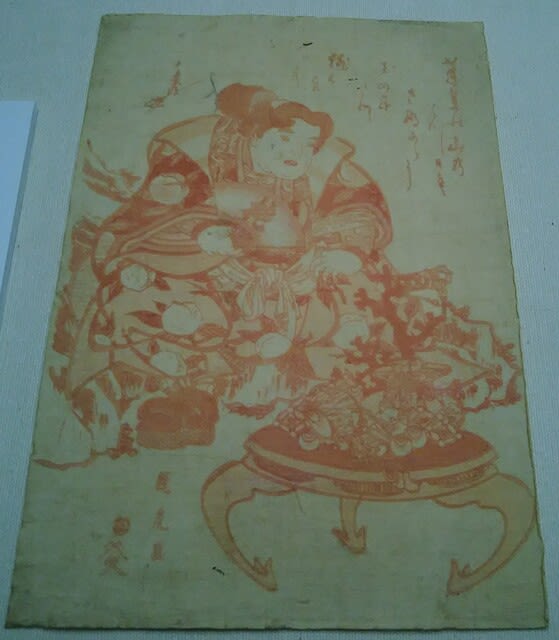
 またこんな季節です。
またこんな季節です。


