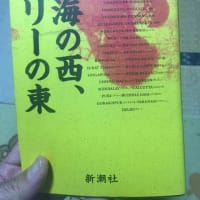ひさしぶりに、本当にひさしぶりにブログを更新する。前に投降したのは、3月だったようだ。ひとこと、ふたことの更新だったが。
あれからずいぶんいろんなことがあった。今日も、支離滅裂に、あちらこちらに話を飛ばせて、好きなように書き綴っていこうと思う。
今日、ひさびさに記事を書いてみようと思ったのは、ある本を読んだこと(正確には読み始めたばかりだが)がきっかけだ。その本は、『「死」とは何か』というタイトルで、イェール大学で、23年間この表題の講義を行っているシェリー・ケーガン教授が書いたものだ。
今月の初めに、本を5、6冊買った時の中の1冊だ。他の本を目当てに、地元の本屋に行って、入り口の片隅で視界に入った本だ。
よく、そうして、本屋でちらっと見たり、手に取ってみて、すぐに購入を決める本がある。えてして、そういう直観的な選び方をした本は間違いがない。必ず、自分にとって必要な本であることが多い。
たまに都会に行くこともあるが、都会地の大きな本屋でも、数知れぬ大量の本の中で、そうやって見つけた「自分にとっての必要な本」というのも結構ある。いや、「今の自分にとって」と言ったほうが正しいかもしれない。
去年ぐらいから、公私ともにストレスが多かったようで、今年の3月についに身体のほうが警告を発した。
持病の不整脈の発作が起き、連続するようになったのだ。とは言っても、仕事や生活をやめるわけにはいかないので、普通に働いたり、遊んだりしていた。
で、3月にあった卓球の試合(笑)の途中に具合が悪くなり、棄権して帰宅し、そのまま病院の休日診療を受けた。その時はそれでなんとか回復したが、これではいけないということで、4月に本格的な治療を受けた。アブレーションという不整脈(心房細動)の治療だ。
5年前に1度受けて、今回が2回目だ。そのために仕事も1週間ほど休ませてもらった。治療は成功し、危機は脱したようだったが、なにせ、心臓周りを電気治療するのだから、体には負担がかかるし、私もそれほど若くはない(笑)。
治療は成功したものの、いまひとつ元気が出ない。というか、体力が落ちていて、踏ん張りがきかない。ともすれば、不整脈の発作が出そうで、無理が出来ない状態がつづいていた。
治療を受けてから3か月ぐらいは、発作も出やすいので気をつけないといけないらしいが、実際に軽いのは何度か出ていたと思う。5年前の最初の治療では、見事に調子がよくなったが、今回は年齢のせいもあるかもしれないが、そうはいかないようだった。
身体も体重が落ちてしまって、とくに首回りや、胸などは肉が落ちてしまって、不整脈と治療のためだけではないのではないか、ほかに悪い病気があるのではないか、などと疑う日々が続いた。
発作が起きるのを誘発するため、アルコールも極力控えることにして、なんと晩酌をやめた! もう一回打っておこう、!(笑)。ただ、会合や人との付き合いで、飲まざるを得ないときは(笑)、その限りではなく、ジョッキなら3杯までは、自らに許している(この言い方カッコイー)。
ともかく、そんなことで、半世紀生きてきたこの歳で、かなり「死」というものを意識した感覚がある。そのためもあって、本屋で、この本(やっと戻ってきた(笑))が目についたのかもしれない。
すごく面白い本だ。タイトルは恐ろしいが、純粋に「死」というものについて、学問的に考察している。講義の内容を著した内容だから、とてもまとまっていて、わかりやすい。
私はTEDなどが好きで、大学の講義やそれに関連したスピーチを観たり読んだりするのも好きだ。
学生の頃、講義をさぼってばかりいたが、本当に面白い講義は好んで聴いていた。つまらない講義が多い中でも面白い講義はあるし、興味深い先生方もいた。学問というか、学ぶということに関しては、嫌いではないほうだ。その、私がなぜ大学の講義をさぼり、まともに卒業しなかったのか、という話題についてはまた別の機会で語ろう(笑)。
話を戻して、この本は今読み始めたばかりだが、非常に面白い本だ。時々、こういう会心のヒットに出会うので、読書というものはやめられない。この前、本屋で「読書する習慣を持つ人だけが到達できること」というような名前の本があったが、あれはまさにこのことだと思う。読書の醍醐味だ。
それはともかく、この本は、「死」というものについて、とてもわかりやすく、論理的、学問的にアプローチを繰り広げていて、実に興味深い。内容については、個々に中身を読んでもらうしないが、カバーに書いてある見出しが、この著書の魅力を伝えている。
○死とは何か
○人は、死ぬとどうなるのか
○死への「正しい接し方」―本当に恐れたり、絶望したりすべきものなのか
・・・etc。
そしてもう一つ、添えてある言葉、「人は、必ず死ぬ。だからこそ、どう生きるべきか」。
最近、やっと身体の調子が復調気配がある。さきほど、言ったように、晩酌をやめてアルコールをほとんど抜き、夜はなるべく早く寝て、最近では徒歩で大回りして仕事に行くようにしたり、卓球を真面目に練習したり(笑)、そんなことをしているうちに、復調を感じてきつつある。
3月に記事でひとこと更新したように、「生きているってすばらしい」のだ。
一昨日か、我ながら、馬鹿ではないかというようなことをした。仕事の帰りに、(徒歩通勤の帰り道に)、地元の益田川の土手を歩いていると、「月見橋まで3キロ」と表示された看板があったのだ。月見橋は、益田川のもっとも下流にかかっている橋だ。私は橋が好きで、1年ぐらい前に、バイクで益田川にかかっている橋をすべて回るというプチツーリングをしたことがある(笑)。
3キロか、ちょっと行ってみるかな。天気もよく、暑くも寒くもないウォーキングにちょうどいい気候だったので、その気になってしまった。
3キロ下流の月見橋まで行き、ついでにそれを過ぎて益田川の河口の海岸まで行った! 6時過ぎに出発して7時過ぎぐらい。帰りも1時間かかって、家に帰ったのは、日も暮れた8時過ぎだった(笑)。
実に思い付きの、馬鹿みたいな行動だが、面白かった。もとより、山歩きが好きなので、歩くのはあまり苦ではないし。半世紀生きいて、初めて、土手を歩いて益田川の河口まで行き、日本海を見た。まさに南日本海人の真骨頂だ!
そんなささやかな、子供みたいな冒険をして、気づいたのは、今日、今を感じて、面白いことにチャレンジしたり、集中したりすれば、楽しいことはいくらでもあるということ。
少し前に5、6冊本を買った中に、もうひとつ『自分を休ませる練習』という本があって、その中に、「中今を生きる」という概念があって、なるほどなあと感心した。まさに、その感覚だった。
今現在を生きる。中今を生きる。
急に話が飛ぶのが、このブログのいいところだが、体調が良くなりつつ、卓球の方も地道に(?)練習していて、復調してきた。(ここからは卓球を知っている人しかわからないかもしれないが、まあ、書いてしまうのだ。)
ラバーの片側を表ソフトに変えた。4月のブダペストの世界選手権で2位に活躍した、スウェーデンのファルク・マティアス選手の影響されたわけではない。前から少しずつ考えていたのだ。両面裏のドライブマンでは、なかなか通用しない。少し個性的な戦型を考えて、そういう選手にならなければ、とつねづね思っていたのだ。
治療後、練習に復帰してから、1ヵ月ちょっと、フォア表の戦型の選手として、これからチャレンジしていくつもりだ!
卓球を知らない人たち、ごめん。<(_ _)>(笑)。
というわけで(なにがというわけなのかは知らないが)、南日本海人、大きな谷を切り抜けて、復調気配なのである。
皆のものも、がんばろうな(かなりな高みからの上から目線で申し訳ない(笑))。
人生を生きよう! 「中今を生きる」のだ☆。
生きているって素晴らしい(笑)。
ごはんが食べられて、仕事が出来て、たいせつな人たちと過ごせて、ほんとうにほんとうに素晴らしい。
くどいようだが、卓球もできる(笑)。
じゃねー☆
あれからずいぶんいろんなことがあった。今日も、支離滅裂に、あちらこちらに話を飛ばせて、好きなように書き綴っていこうと思う。
今日、ひさびさに記事を書いてみようと思ったのは、ある本を読んだこと(正確には読み始めたばかりだが)がきっかけだ。その本は、『「死」とは何か』というタイトルで、イェール大学で、23年間この表題の講義を行っているシェリー・ケーガン教授が書いたものだ。
今月の初めに、本を5、6冊買った時の中の1冊だ。他の本を目当てに、地元の本屋に行って、入り口の片隅で視界に入った本だ。
よく、そうして、本屋でちらっと見たり、手に取ってみて、すぐに購入を決める本がある。えてして、そういう直観的な選び方をした本は間違いがない。必ず、自分にとって必要な本であることが多い。
たまに都会に行くこともあるが、都会地の大きな本屋でも、数知れぬ大量の本の中で、そうやって見つけた「自分にとっての必要な本」というのも結構ある。いや、「今の自分にとって」と言ったほうが正しいかもしれない。
去年ぐらいから、公私ともにストレスが多かったようで、今年の3月についに身体のほうが警告を発した。
持病の不整脈の発作が起き、連続するようになったのだ。とは言っても、仕事や生活をやめるわけにはいかないので、普通に働いたり、遊んだりしていた。
で、3月にあった卓球の試合(笑)の途中に具合が悪くなり、棄権して帰宅し、そのまま病院の休日診療を受けた。その時はそれでなんとか回復したが、これではいけないということで、4月に本格的な治療を受けた。アブレーションという不整脈(心房細動)の治療だ。
5年前に1度受けて、今回が2回目だ。そのために仕事も1週間ほど休ませてもらった。治療は成功し、危機は脱したようだったが、なにせ、心臓周りを電気治療するのだから、体には負担がかかるし、私もそれほど若くはない(笑)。
治療は成功したものの、いまひとつ元気が出ない。というか、体力が落ちていて、踏ん張りがきかない。ともすれば、不整脈の発作が出そうで、無理が出来ない状態がつづいていた。
治療を受けてから3か月ぐらいは、発作も出やすいので気をつけないといけないらしいが、実際に軽いのは何度か出ていたと思う。5年前の最初の治療では、見事に調子がよくなったが、今回は年齢のせいもあるかもしれないが、そうはいかないようだった。
身体も体重が落ちてしまって、とくに首回りや、胸などは肉が落ちてしまって、不整脈と治療のためだけではないのではないか、ほかに悪い病気があるのではないか、などと疑う日々が続いた。
発作が起きるのを誘発するため、アルコールも極力控えることにして、なんと晩酌をやめた! もう一回打っておこう、!(笑)。ただ、会合や人との付き合いで、飲まざるを得ないときは(笑)、その限りではなく、ジョッキなら3杯までは、自らに許している(この言い方カッコイー)。
ともかく、そんなことで、半世紀生きてきたこの歳で、かなり「死」というものを意識した感覚がある。そのためもあって、本屋で、この本(やっと戻ってきた(笑))が目についたのかもしれない。
すごく面白い本だ。タイトルは恐ろしいが、純粋に「死」というものについて、学問的に考察している。講義の内容を著した内容だから、とてもまとまっていて、わかりやすい。
私はTEDなどが好きで、大学の講義やそれに関連したスピーチを観たり読んだりするのも好きだ。
学生の頃、講義をさぼってばかりいたが、本当に面白い講義は好んで聴いていた。つまらない講義が多い中でも面白い講義はあるし、興味深い先生方もいた。学問というか、学ぶということに関しては、嫌いではないほうだ。その、私がなぜ大学の講義をさぼり、まともに卒業しなかったのか、という話題についてはまた別の機会で語ろう(笑)。
話を戻して、この本は今読み始めたばかりだが、非常に面白い本だ。時々、こういう会心のヒットに出会うので、読書というものはやめられない。この前、本屋で「読書する習慣を持つ人だけが到達できること」というような名前の本があったが、あれはまさにこのことだと思う。読書の醍醐味だ。
それはともかく、この本は、「死」というものについて、とてもわかりやすく、論理的、学問的にアプローチを繰り広げていて、実に興味深い。内容については、個々に中身を読んでもらうしないが、カバーに書いてある見出しが、この著書の魅力を伝えている。
○死とは何か
○人は、死ぬとどうなるのか
○死への「正しい接し方」―本当に恐れたり、絶望したりすべきものなのか
・・・etc。
そしてもう一つ、添えてある言葉、「人は、必ず死ぬ。だからこそ、どう生きるべきか」。
最近、やっと身体の調子が復調気配がある。さきほど、言ったように、晩酌をやめてアルコールをほとんど抜き、夜はなるべく早く寝て、最近では徒歩で大回りして仕事に行くようにしたり、卓球を真面目に練習したり(笑)、そんなことをしているうちに、復調を感じてきつつある。
3月に記事でひとこと更新したように、「生きているってすばらしい」のだ。
一昨日か、我ながら、馬鹿ではないかというようなことをした。仕事の帰りに、(徒歩通勤の帰り道に)、地元の益田川の土手を歩いていると、「月見橋まで3キロ」と表示された看板があったのだ。月見橋は、益田川のもっとも下流にかかっている橋だ。私は橋が好きで、1年ぐらい前に、バイクで益田川にかかっている橋をすべて回るというプチツーリングをしたことがある(笑)。
3キロか、ちょっと行ってみるかな。天気もよく、暑くも寒くもないウォーキングにちょうどいい気候だったので、その気になってしまった。
3キロ下流の月見橋まで行き、ついでにそれを過ぎて益田川の河口の海岸まで行った! 6時過ぎに出発して7時過ぎぐらい。帰りも1時間かかって、家に帰ったのは、日も暮れた8時過ぎだった(笑)。
実に思い付きの、馬鹿みたいな行動だが、面白かった。もとより、山歩きが好きなので、歩くのはあまり苦ではないし。半世紀生きいて、初めて、土手を歩いて益田川の河口まで行き、日本海を見た。まさに南日本海人の真骨頂だ!
そんなささやかな、子供みたいな冒険をして、気づいたのは、今日、今を感じて、面白いことにチャレンジしたり、集中したりすれば、楽しいことはいくらでもあるということ。
少し前に5、6冊本を買った中に、もうひとつ『自分を休ませる練習』という本があって、その中に、「中今を生きる」という概念があって、なるほどなあと感心した。まさに、その感覚だった。
今現在を生きる。中今を生きる。
急に話が飛ぶのが、このブログのいいところだが、体調が良くなりつつ、卓球の方も地道に(?)練習していて、復調してきた。(ここからは卓球を知っている人しかわからないかもしれないが、まあ、書いてしまうのだ。)
ラバーの片側を表ソフトに変えた。4月のブダペストの世界選手権で2位に活躍した、スウェーデンのファルク・マティアス選手の影響されたわけではない。前から少しずつ考えていたのだ。両面裏のドライブマンでは、なかなか通用しない。少し個性的な戦型を考えて、そういう選手にならなければ、とつねづね思っていたのだ。
治療後、練習に復帰してから、1ヵ月ちょっと、フォア表の戦型の選手として、これからチャレンジしていくつもりだ!
卓球を知らない人たち、ごめん。<(_ _)>(笑)。
というわけで(なにがというわけなのかは知らないが)、南日本海人、大きな谷を切り抜けて、復調気配なのである。
皆のものも、がんばろうな(かなりな高みからの上から目線で申し訳ない(笑))。
人生を生きよう! 「中今を生きる」のだ☆。
生きているって素晴らしい(笑)。
ごはんが食べられて、仕事が出来て、たいせつな人たちと過ごせて、ほんとうにほんとうに素晴らしい。
くどいようだが、卓球もできる(笑)。
じゃねー☆