PHA-1の話を書いていて思い出したのですが、PHA-1を購入時に「絶対に変わるから買った方が良いですよ、お客さん!」と店員さんに勧められるがままに購入したiPhoneとPHA-1を接続するためのケーブルには本当に驚かされました。「そもそも電気の信号(しかもデジタル)を送るだけなんだから、そんなに変わる訳なくない?」とかなり疑っていたのですが、実際に他のケーブルに変えると何故かまったく違う音になるのです。一体何故こんなことが起こるのでしょう? 迷信のようにしか思っていなかったことを身をもって体験すると、驚きを通り越して感動すら覚えますよ。
なので、久々にPHA-1を取り出して使ってみることにしたときも、ケーブルだけは同じメーカーの製品にしてみました。
コロナ禍で自宅にいることが多くなったことも影響してか、音楽を聴く時間が徐々に長くなってきました。であればより良い音で聴きたいという欲が出てくるというもの。そんなとき、かなり昔に買ったSONYのPHA-1を引き出しで眠らせていることを思い出しました。
買った当時はiPhoneはiPhoneでもiPhone 4Sとかの時代なので、iPhone側のコネクタ形状が今とは異なります。ケーブルだけLightning - USBのものを買い足して、手持ちのiPhone 11 ProにPHA-1をつなげてみることにしました。
流す曲はApple Musicの音源ですし、使っている機器もいつものイヤホンとiPhone。そこにPHA-1が加わっただけなのですが、やはり音の印象は結構違うものになりますね。一つ機器を足すだけでいつも通りの音楽が一転してとても楽しいものになりました。PHA-1はかなり古い機種なので、中古品であればわりと安価に手に入ると思いますし、中古品は気が引けるのであればONKYOのDAC-HA200等も試してみたら良いかも知れません。
以前中古で買ったストラトキャスターがいつの頃かひどくビビるようになってしまいました。初めて弦交換をしたときがきっかけかも知れません。今にして思えば、購入時に張られていた弦よりも細いゲージの弦を張ってしまった気がします。
初めは弦の張り方が悪かったのかと思い、何度か弦交換をしてみましたがまったく改善しません。弦高を高くしようと思い立ったものの、何故かこういう時に限って六角レンチが見付かりません。やっとの思いで六角レンチを探し出したら、メートル規格のもので手持ちのギターにあわないという...何だか嫌になってきて一瞬PACIFICAでも買ってしまおうかとも考えました。
ただ、機材ばっかり増えても上達する訳でもないし、PACIFICAを買ったところで、そもそもストラトキャスターのビビリ問題は何ら解決しません。気を取り直してインチ規格の六角レンチを購入し、弦高とオクターブチューニングを直してみることにしました。
いざやってみるとこれが劇的に効果がありました。あれ程悩まされていたビビリなどどこ吹く風で、以前より鳴りも良くなった気すらします。道具は大切にメンテナンスをしながら使い続けるべきだと学んだ一件となりました。
 | So Far So Good |
| クリエーター情報なし | |
| A&M |
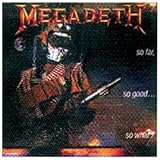 | So Far So Good So What |
| クリエーター情報なし | |
| Capitol |
似たようなジャケットです。
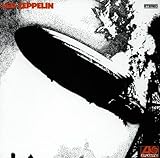 | Led Zeppelin |
| クリエーター情報なし | |
| Atlantic / Wea |
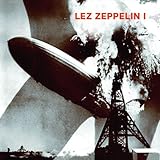 | Lez Zeppelin I |
| クリエーター情報なし | |
| Pie Records |
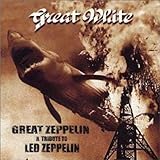 | Great Zeppelin: Tribute to Led Zeppelin |
| クリエーター情報なし | |
| Cleopatra |
アルバムの内容としてはお馴染みのFreak Kitchen節炸裂で、期待を裏切りません。それだけに入手難だけはどうにかして欲しいものです。
 | Land of the Freaks |
| クリエーター情報なし | |
| Roadrunner |
きっかけは今年になって生とテレビの両方で同氏の演奏を聴いたことでした。どうほめて良いか分からないくらい、半端なく上手でした。ほとんどJazzに興味のなかった僕でも真面目に聴き始めてみようかなと思うほど、印象的な出会いになりました。
テレビで音楽番組が減ってきていることもあって、国内のミュージシャンを見聞きする機会が減っています。僕が知らないだけのことで、まだまだ素晴らしい才能が本邦にも沢山潜んでいるのですね。
 | The Best |
| クリエーター情報なし | |
| SMJ |
このニューアルバムもさることながら、アルバム発表後の武道館でのパフォーマンスも素晴らしかったです。震災や原発事故の悪夢が記憶にまだ新しい時期とあって来日自体を延期・キャンセルする海外タレントが多い中で、わざわざ来日し、仙台公演もこなし、ショーの中でわざわざ日本のファン向けの曲まで作って演奏している彼らを観ていたら、はからずも涙が止まらなくなってしまいました。ハードロックのショーを観て泣けるなんて、これが最初で最後かも知れません。
意識の高いバンドに敬意を払うべく、彼らのアルバムセールスに貢献するための小銭を払ってみました。
 | ホワット・イフ・・・(初回限定盤)(DVD付) |
| クリエーター情報なし | |
| WHDエンタテインメント |
今更ながら今年に入ってオートワウというジャンルのアタッチメントがあることに気付きました。正確に言えば、子供の頃から「オートワウ」という単語は聞いたことはあったと思うものの、まったく意識したことがなかったというのが正しいでしょうか。Youtube等でデモ演奏などを見ていると結構楽しそうなエフェクターではありませんか。しかも何といっても自分で操作しなくて良いので不器用な僕でも使えそうです。
当初は無難にBOSSのAW-3を買おうかとも思ったのですが、Webであれこれ眺めているうちにMXR M-120 AUTO Q
これまた便利なエフェクターですね。特別なことは何もしなくてもただ弾いているだけでワウ特有のトーンが出てくれます。両手と足を同時に動かせそうにない方であってもワウを諦めるにはまだ早過ぎますよ。
# ただ、残念ながらMXR M-120 AUTO Q
 | BOSS ダイナミック・ワウDynamic Wah AW-3(T) |
| クリエーター情報なし | |
| BOSS(ボス) |
それから早くも9ヶ月以上の時が流れ、今年も残すところあと3日です。ネガティブに過去を振り返るのも非生産的ですし、3月以降買った品々が僕を幾許か支えてくれたことも事実です。そこで今年巡り会えた逸品について、気を取り直して少しご紹介していきたいと思います。
コンプレッサーと言えばギターエフェクターのカタログを眺めたときに最も地味に感ぜられるペダルの一つではないでしょうか。コンプレッサーの機能説明を読んでも、「歪みもの」のように音色が劇的に変わる訳でもなさそうですし、音が圧縮されるので特徴のない音色になってしまうのではないかとずっと思っていました。ところが去年のことです。雑誌でエフェクター関連の記事を立て続けに眺めていたところ、ブルース系・ジャズ系のギタリストのペダルボードに何故か必ずコンプレッサーが入っているのです。実はコンプレッサーをかませるとちょっと上手く聞こえてしまうのではないかと短絡的に思うに至りました。
早速購入するコンプレッサー選びをはじめます。定番はMXRのDYNA COMP2かBOSSのCS-3でしょう。ただ、あまりに定番過ぎても面白くないので最近名前を聞くようになったstrymonのOB.1を購入することにしました。
結論から申し上げると、このペダルは絶対に買って損しない逸品です。ものの本で読むコンプレッサーの原理がどのように影響するのかさっぱりよく分からない程、このペダルを通した音は非常に上手く演奏できているかのように聞こえます。またブースター機能も思いの外効果的で、非力なストラトで太い原音を作ることも出来ます。エフェクターとしてはやや高い価格設定ですが、十分のその価値がある製品ですよ。
あえて欠点を探せば2点あげられます。1つはエフェクターのゴム足がピップエレキバンのように製品に同梱されており、ゴム足を自分でペダルに貼り付けなければならないことです。不器用な僕は貼る位置を少しずらしてしまい、さい先の悪いスタートを切ることになりました。2点目は電池交換の際にいちいちネジを回して裏蓋を外さなければならないことです。電池交換の頻度は演奏時間によって異なるでしょうから、人によっては気にならないかも知れませんが。
最近文章をまともに書いてないこともあってか、何ともまとまりのない文章で失礼しました。ただし、この記事のクオリティとOB.1のクオリティはまったく関連しませんので、躊躇なくOB.1をお買い求め下さい。
 | strymon OB.1【Optical Compressor & Clean Boost】 |
| クリエーター情報なし | |
| strymon |
しかし突然の訃報には本当に驚きました。何か病気だったというような話も聞いたことがないし、薬物のイメージもないミュージシャンだったので尚更です。数少ない「職人芸のギタリスト」の名演が聞けないかと思うと本当に残念です。素晴らしいミュージシャンでした。
最高の音楽を今まで本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。
 | スティル・ガット・ザ・ブルース |
| クリエーター情報なし | |
| EMIミュージック・ジャパン |

















