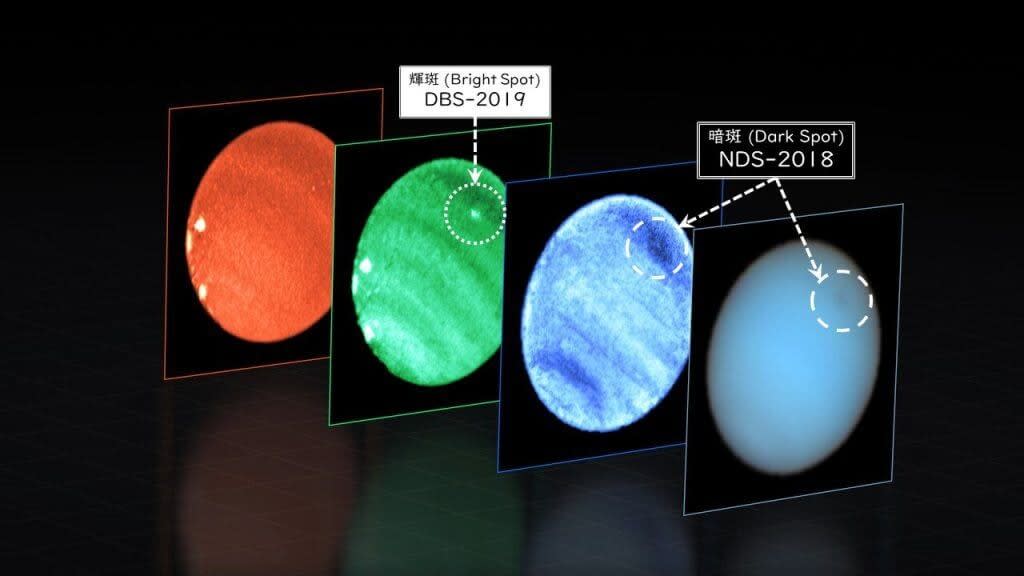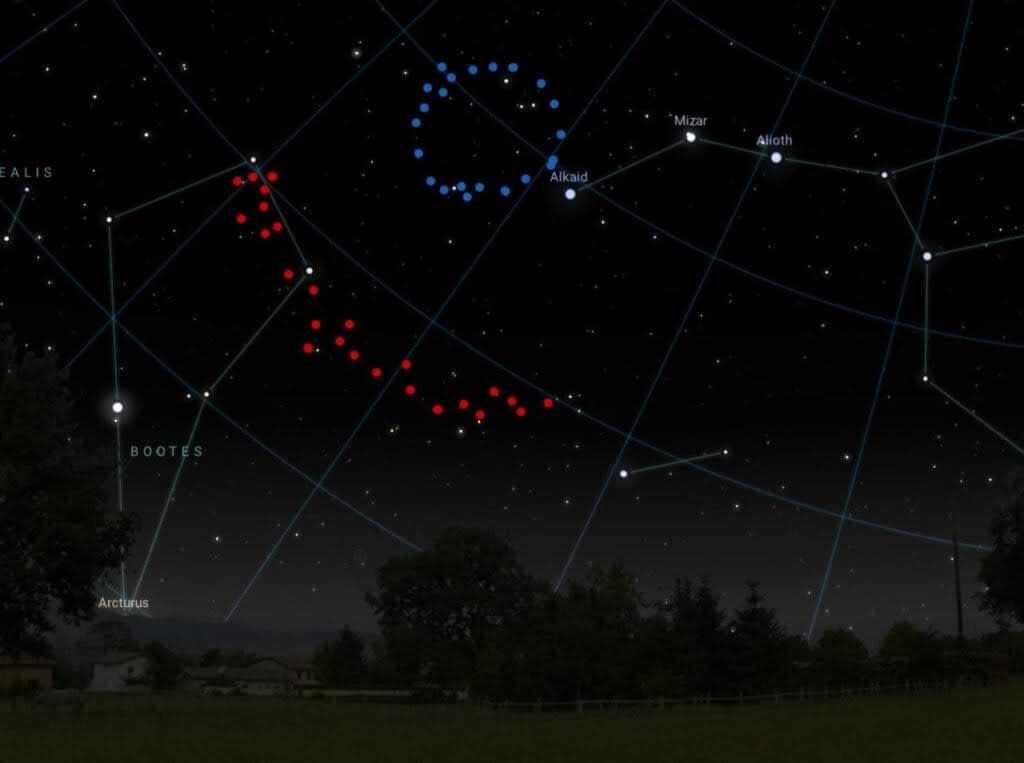NASAのジェット推進研究所“JPL”が、惑星探査機“ボイジャー1号(Voyager 1)”のデータ転送に関する問題に引き続き取り組んでいることをX(旧Twitter)に投稿しています。
1977年に打ち上げられたNASAの“ボイジャー1号”は、10年以上も星間空間を飛行している探査機です。
星間空間とは、銀河内の各々の恒星と恒星の間に広がる空間。
太陽風勢力圏といった各恒星の影響が及ぶ空間は惑星間空間、各銀河の間の空間は銀河間空間と言い区別されています。
“ボイジャー1号”は2012年に星間空間に到達し、“ボイジャー2号”は2018年に太陽風と星間物質がぶつかり合う境界“ヘリオポーズ”を通過し、星間空間に達しています。
“ボイジャー1号”では、2022年と2023年に相次いでコンピュータ関連の問題が発生し、観測データの送信に問題が発生していました。
ジェット推進研究所によれば、“ボイジャー1号”との通信は引き続き可能なものの、地球から非常に離れた場所を航行しているので、問題の解決には時間がかかるとのこと。
現在、“ボイジャー1号”が航行しているのは地球から240億キロ以上も離れた星間空間。
通信によるコマンドが届くのに22時間以上もかかってしまうそうです。
NASAでは、この老探査機の寿命を少しでも伸ばすために様々な取り組みが行われています。
最近では、スラスターの動作を修正するコマンドの送信がありました。
スラスターは、主に探査機の通信用のアンテナを地球に向けるために使われています。
スラスター内では、外部の燃料ラインより25倍も細いチューブを推進剤が通ることになります。
ただ、スラスターの点火のたびに、そのチューブ内には、ごくわずかの残留物が残ってしまうんですねー
打ち上げから46年が経過し、一部のチューブでは残留物の蓄積が顕著になっているものもあります。
そこで、ボイジャーミッションの技術者が考えたのは、残留物の蓄積を遅らせるため、スラスターを噴射する前のアンテナと地球との間の角度のズレの許容範囲を、わずかに広げることでした。
これにより、スラスターの噴射頻度を減らすことができる訳です。
許容角度が大きくなると、気になるのは科学データの一部がときおり失われる可能性があること。
でも、今後のミッション全体としては、“ボイジャー”がこの先より多くのデータを送信することができると、ミッションチームは結論付けています。
寿命をはるかに超え46年間にも渡ってミッションを継続している“ボイジャー1号”。
いろいろと問題が発生するのは仕方がないとして、人類史上最も遠方を航行する探査機として、まだまだ頑張ってほしいですね。
こちらの記事もどうぞ
1977年に打ち上げられたNASAの“ボイジャー1号”は、10年以上も星間空間を飛行している探査機です。
星間空間とは、銀河内の各々の恒星と恒星の間に広がる空間。
太陽風勢力圏といった各恒星の影響が及ぶ空間は惑星間空間、各銀河の間の空間は銀河間空間と言い区別されています。
“ボイジャー1号”は2012年に星間空間に到達し、“ボイジャー2号”は2018年に太陽風と星間物質がぶつかり合う境界“ヘリオポーズ”を通過し、星間空間に達しています。
“ボイジャー1号”では、2022年と2023年に相次いでコンピュータ関連の問題が発生し、観測データの送信に問題が発生していました。
|
| JPL公式Xアカウントのツイートより |
現在、“ボイジャー1号”が航行しているのは地球から240億キロ以上も離れた星間空間。
通信によるコマンドが届くのに22時間以上もかかってしまうそうです。
NASAでは、この老探査機の寿命を少しでも伸ばすために様々な取り組みが行われています。
最近では、スラスターの動作を修正するコマンドの送信がありました。
スラスターは、主に探査機の通信用のアンテナを地球に向けるために使われています。
スラスター内では、外部の燃料ラインより25倍も細いチューブを推進剤が通ることになります。
ただ、スラスターの点火のたびに、そのチューブ内には、ごくわずかの残留物が残ってしまうんですねー
打ち上げから46年が経過し、一部のチューブでは残留物の蓄積が顕著になっているものもあります。
そこで、ボイジャーミッションの技術者が考えたのは、残留物の蓄積を遅らせるため、スラスターを噴射する前のアンテナと地球との間の角度のズレの許容範囲を、わずかに広げることでした。
これにより、スラスターの噴射頻度を減らすことができる訳です。
許容角度が大きくなると、気になるのは科学データの一部がときおり失われる可能性があること。
でも、今後のミッション全体としては、“ボイジャー”がこの先より多くのデータを送信することができると、ミッションチームは結論付けています。
寿命をはるかに超え46年間にも渡ってミッションを継続している“ボイジャー1号”。
いろいろと問題が発生するのは仕方がないとして、人類史上最も遠方を航行する探査機として、まだまだ頑張ってほしいですね。
 |
| 星間空間を航行するNASAの惑星探査機“ボイジャー”のイメージ図。(Credit: NASA/JPL-Caltech) |
こちらの記事もどうぞ